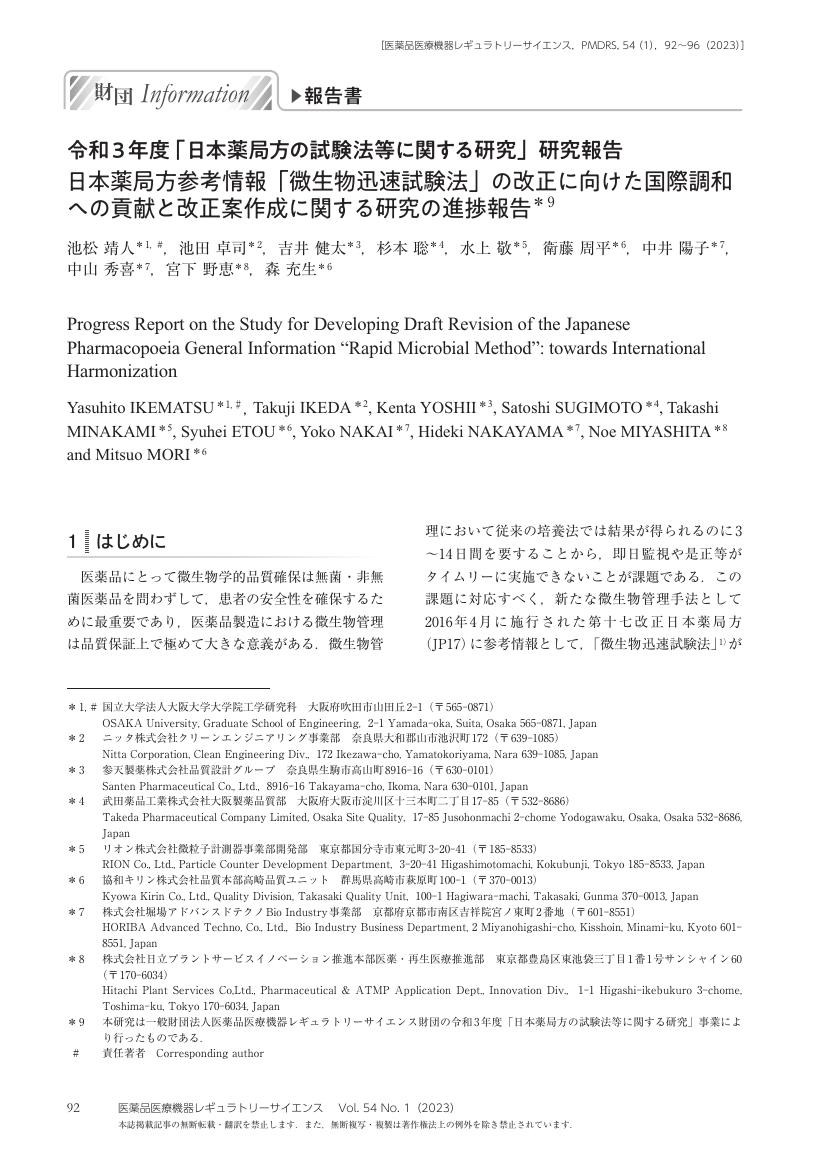- 著者
- 池松 靖人 池田 卓司 吉井 健太 杉本 聡 水上 敬 衛藤 周平 中井 陽子 中山 秀喜 宮下 野恵 森 充生
- 出版者
- 一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団
- 雑誌
- 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス (ISSN:18846076)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.92-96, 2023 (Released:2023-03-10)
1 0 0 0 OA 不登校の訪問臨床における訪問者の役割と課題
- 著者
- 吉井 健治 Kenji YOSHII
- 出版者
- 鳴門教育大学地域連携センター
- 雑誌
- 鳴門教育大学学校教育研究紀要 = Bulletin of Center for Collaboration in Community Naruto University of Education (ISSN:18806864)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.137-146, 2022-02
本論文の目的は,不登校の訪問臨床における訪問者の役割と課題について明らかにすることである。訪問者には多様な役割がある。これらの役割のうちで最も重要なのは,訪問者が子どもたちとの人間関係づくりを行う心理発達的役割である。筆者は,訪問者の心理発達的役割の基本的な要因として8つを説明した。また,訪問者が抱えている3つのタイプの課題(悩み),つまり,訪問者の役割上の悩み,訪問者の心理面の悩み,訪問の構造に関する悩みについて述べた。最後に,大学院生の訪問者の経験と成長,そして研修とスーパーヴィジョンについて述べた。
1 0 0 0 電気刺激法による牛の精液採取について
- 著者
- 吉井 健五郎 石川 康哲 近松 典子
- 出版者
- 北海道家畜人工授精師協会
- 雑誌
- 繁殖技術 (ISSN:00177520)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.p32-34, 1990-09
- 著者
- 小谷 清子 高畑 彩友美 瀬古 千佳子 吉井 健悟 東 あかね
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.105-115, 2022-04-01 (Released:2022-05-24)
- 参考文献数
- 50
【目的】地域の若年期からの循環器病予防をめざして,乳児の父母の推定1日尿中食塩排泄量(以下,食塩排泄量)および尿中Na/K比を評価し,食習慣との関連を明らかにすること。【方法】2015年10月から1年間の,京都府内3市町の全ての乳児前期健診対象児393人の父369人,母386人,計755人を対象とした。早朝第1尿から食塩排泄量と尿中Na/K比を算出した。自記式食習慣調査は食物摂取頻度と減塩意識の13項目で,これらと食塩排泄量および尿中Na/K比との関連について,単変量解析と多変量解析を行った。解析対象は,父166人(年齢中央値34.0),母200人(同32.0),計366人(解析率48.5%)であった。【結果】食塩排泄量(g/日)(中央値)は父10.2,母9.9,尿中Na/K比(mEq比)(中央値)は父4.0,母3.9であった。多変量解析の結果,食塩排泄量と食物摂取頻度については有意な関連がなく,減塩意識ありとの関連は父のオッズ比0.83(95%信頼区間0.44~1.60),母のオッズ比0.55(0.28~1.09)であった。尿中Na/K比と食物摂取頻度については母において有意な関連は認めなかった。父において果物摂取と有意な正の関連を認めたが,その解釈は困難であった。【結論】乳児の父母の食塩排泄量と尿中Na/K比を評価し,これらと食物摂取頻度や減塩意識に有意な関連を認めなかった。
- 著者
- 吉井 健一郎 志和地 弘信 入江 憲治 豊原 秀和
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業研究 (ISSN:18828434)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.81-87, 2012
インディカイネのプカールンドゥール品種はカンボジアのバッタンバン州の主力品種であるが,直播き栽培において播種後に水田が湛水すると苗立ちが悪くなることが知られている.これまでの研究において,プカールンドゥール品種の苗立ち不良は第一義的に溶存酸素量の不足によって起きていると考えられたことから,溶存酸素量と苗立ちとの関係について調べた.水だけを入れたポットに種子を播くと播種数が多くなるほど溶存酸素量が低下し,苗立ちが見られなくなった.しかし,ポットに空気を供給すると,苗立ち不良になる播種数のポットの苗立ちは改善した.そこで,溶存酸素量とプカールンドゥール品種の生長との関係を調べたところ,鞘葉は溶存酸素量にかかわらず伸長するが,溶存酸素量が2 mgl<sup>-1</sup>以下では本葉と根の伸長が阻害された.これらのことから,プカールンドゥール品種の苗立ちに必要な溶存酸素量は3 mgl<sup>-1</sup>以上と考えられた.水田土壌の溶存酸素の低下には土壌中の微生物が関与していると考えられている.そこで,種子をコサイドおよびカスミンボルドー剤で処理をして湛水した水田土壌中に播種したところ,いずれのボルドー剤処理においても苗立ちが改善した.ボルドー剤処理は水田土壌表面水中の溶存酸素量と水田土壌中の酸化還元電位の低下を抑制したことから,土壌中の微生物の活動を抑えたものと考えられた.ボルドー剤による種子処理は直播栽培による苗立ち不良の改善に期待される.
1 0 0 0 OA カウンセリングの基本的技法 : 相手のこころに近づく聴き方十二の技
- 著者
- 吉井 健治 Kenji YOSHII
- 出版者
- 鳴門教育大学
- 雑誌
- 鳴門教育大学研究紀要 = Research bulletin of Naruto University of Education (ISSN:18807194)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.41-51, 2015-03-13
In the counseling and the educational counseling, it is important that a counselor and the teacher understand how children, young people and parents experience and feel. Next, a counselor and the teacher solve the problem in cooperation with children, young people and parents. Then, 12 skills of listening to get closer to the feeling of the partner are proposed and explained in this article. These are basic technique of counseling. These are derived from author’s clinical experience as counselor during approximately 25 years. These 12 skills are not based on a specific psychotherapy theory, but are mixed various psychotherapy theories.
- 著者
- 梅垣 明美 大友 智 上田 憲嗣 深田 直宏 吉井 健人 宮尾 夏姫
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.367-381, 2018-06-10 (Released:2018-06-20)
- 参考文献数
- 43
In school education, it is important to encourage students to improve their social skills. Umegaki et al. (2016b) have developed an instructional model known as the Acquisition of Social Knowledge in Sport (ASKS) Model for facilitating improvement in social skills in the context of physical education. They consider that the ASKS Model with heterogeneous team organization would improve social skills that would be applicable to daily life outside of physical education classes and help students to maintain these social skills. However, no previous study has examined whether the ASKS Model would be effective for homogeneously organized teams. Therefore, the present study was designed to examine the type of team organization that would be most effective for the ASKS Model by comparing physical education classes with the ASKS Model based on homogeneous teams and heterogeneous teams. The study focused on physical education classes for male students in the second year of junior high school. The classes included those without the ASKS Model, those with the ASKS Model based on homogeneous teams, and those with the ASKS Model based on heterogeneous teams. A formative evaluation of friendship-building and the KiSS-18 questionnaire on paper were administered before and after each class. The study confirmed 2 points: First, the ASKS Model appeared to be effective when heterogeneous teams were organized. Second, the effectiveness was suggested to be improved when heterogeneity of motor skills was maintained, rather than heterogeneity of social skills.
1 0 0 0 OA 50kg級技術実証衛星「ひばり」-形状可変姿勢制御と重力波対応天体観測-
- 著者
- 俵 京佑 針田 聖平 河尻 翔太 松下 将典 吉井 健敏 太田 佳 古賀 将哉 渡邉 輔祐太 菊谷 侑平 林 雄希 小池 毅彦 新谷 勇介 谷津 陽一 河合 誠之 松永 三郎 Tawara Kyosuke Harita Shohei Kawajiri Shota Matsushita Masanori Yoshii Taketoshi Ohta Kei Koga Masaya Watanabe Futa Kikuya Yuhei Hayashi Yuki Koike Takehiko Shintani Yusuke Yatsu Yoichi Kawai Nobuyuki Matunaga Saburo
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)
- 雑誌
- 第17回宇宙科学シンポジウム 講演集 = Proceedings of the 17th Space Science Symposium
- 巻号頁・発行日
- 2017-01
第17回宇宙科学シンポジウム (2017年1月5日-6日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県
1 0 0 0 IR 体言の並立について
- 著者
- 吉井 健
- 雑誌
- 文学史研究 (ISSN:03899772)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.47-56, 1989-12
1 0 0 0 IR 不登校の予防のための子ども理解と支援
- 著者
- 吉井 健治
- 出版者
- 鳴門教育大学地域連携センター
- 雑誌
- 鳴門教育大学学校教育研究紀要 (ISSN:18806864)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.127-134, 2016
不登校の予防は現代的な教育課題の1つである。本論文で筆者は,不登校の予防において子ども及び支援者に何が必要とされているのかを考察した。まず,不登校の予防における一次予防(未然防止),二次予防(早期発見・早期対応),三次予防(重症化の防止)を説明した。次に,不登校の予防のために子どもに必要とされていることとして「学校の楽しさ」と「こころの栄養素」の2点を指摘した。Kohut,H.の自己心理学理論を適用するならば,こころの栄養素(自己対象)は,自信(鏡映自己対象),希望(理想化自己対象),仲間(分身自己対象)から構成されている。最後に,不登校の予防のために支援者に必要な関わり方として「調節(アジャストメント)」という概念を提唱した。The prevention of non attendance at school is one of the modern educational problems. In this article, I considered about what was required to children and their supporters in the prevention of non attendance at school. At first I explained the primary prevention, the secondary prevention, and the tertiary prevention. Then, I pointed out two points of "pleasure of the school" and "the nutrient of the heart", which were required to children in the prevention of non attendance at school. If I apply psychoanalitic selfpsychology theory, the nutrient of the heart (selfobject) consists of the confidence (mirroring selfobject), the hope(idealized selfobject), and the friend (alterego selfobject). Finally I proposed a concept called "adjustment" as the way of relationship which were required to their supporters in the prevention of non attendance at school.
1 0 0 0 OA 学校教育構造と不登校問題 : 「なかま」による癒しと成長
- 著者
- 吉井 健治
- 出版者
- 熊本学園大学社会関係学会
- 雑誌
- 社会関係研究 = The Study of social relations (ISSN:13410237)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.1-22, 1998-12-15
- 著者
- 吉田 成志 吉井 健一 松本 英昭 大貫 淳 曽禰 元隆
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D-I, 情報・システム, I-コンピュータ (ISSN:09151915)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.1, pp.11-20, 1997-01-25
- 被引用文献数
- 1
マルチDSPシステムは, 高速性と汎用性を備えた計算機として国際的に注目を浴びているが, マルチDSPシステムに演算処理を行わせる上での問題点として, DSP間のデータ通信によるシステム稼動率の低下が挙げられる. 稼動率の低下を防ぐためには, ハードウェア設計段階においてデータ通信時間を考慮したタスクスケジューリングをさまざまな相互結合網に対して行い, 演算処理に最適な相互結合網および並列アルゴリズムを十分に検討しなければならない. そこでデータ通信時間をあらかじめ正確に把握するためのシミュレーション方法が不可欠となる. 本論文では, マルチDSPシステムに演算処理を行わせた場合に生じるデータ通信の正確な時間を, アセンブラプログラムのインストラクションサイクル数から作成した数式を用いて求める方法について示す. 本手法を用いることにより, 使用するDSPの種類, プログラマ, DSP間の接続方式およびハードウェアシステムの仮装・実装にかかわらず正確な通信時間を理論的に求められる. 演算処理の例として行列積算と連立1次方程式の求解を取り上げた結果, 最適なトポロジーを選択することが数式によりシミュレーション上で容易に可能となることを示した.
- 著者
- 吉井 健悟 有田 清三郎 田中 章太郎 宮脇 貴久
- 出版者
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会
- 雑誌
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会大会講演論文集 : BMFSA
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.100-101, 2001-10-27
Recently the number of tuberculosis at Osaka City is increasing to the high level in the world. It is important to make clear the mechanism of the trial of the tuberculosis spread model. In this paper, we propose a mathematical model for the tuberculosis spread model in Osaka using the distance based on the data of 27 indexes of the management table of Osaka's tuberculosis. From the analytical results based on our model, it is suggested that tuberculosis spread model in Osaka has the central area and it is spread to the seaside.