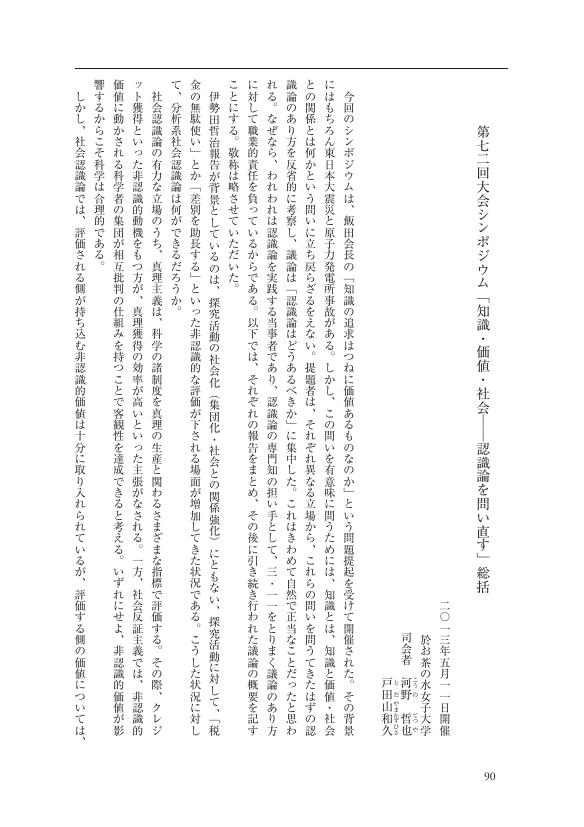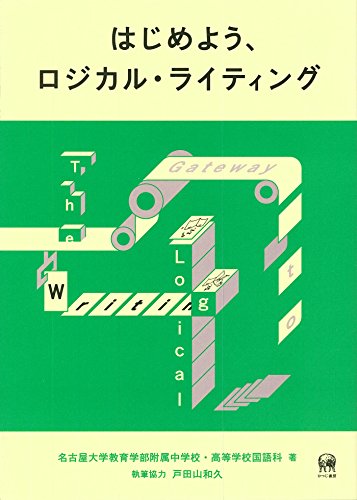70 0 0 0 OA 感情って科学の概念なんだろうか
- 著者
- 戸田山 和久
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- エモーション・スタディーズ (ISSN:21897425)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.91-104, 2021-03-10 (Released:2021-03-12)
64 0 0 0 OA 一物理学者とのチャット
- 著者
- 谷村 省吾 TANIMURA Shogo 戸田山 和久 TODAYAMA Kazuhisa
- 巻号頁・発行日
- 2020-12-03
2020年9月30日に名古屋大学出版会と本屋B&Bの共催で行われた対談イベント「自由意志の哲学ぅ?オレが求めている自由はそんなんじゃねえ!」において対談の視聴者から寄せられた質問・コメントに対する回答集。イベントの趣旨は、ダニエル・デネット著、戸田山和久訳の書籍『自由の余地』(名古屋大学出版会)の刊行記念。戸田山和久氏によるコメントも所収。リポジトリ投稿2020年12月3日。総ページ数47.
32 0 0 0 OA 第七二回大会シンポジウム「知識・価値・社会――認識論を問い直す」総括
- 著者
- 河野 哲也 戸田山 和久
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.65, pp.90-93, 2014-04-01 (Released:2016-06-30)
22 0 0 0 OA 非専門家の問いの特徴は何か? それは専門家の眼にどう映るか?
- 著者
- 齋藤 芳子 戸田山 和久
- 出版者
- 北海道大学 高等教育推進機構 高等教育研究部 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)
- 雑誌
- 科学技術コミュニケーション (ISSN:18818390)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.3-15, 2011-12
Questions raised by lay persons in relation with the Universe were investigated to clarify what they want to know and which aspects of the questions tend to embarrass experts trying to answer them. The seventy percent of questions are about the whole Universe or celestial bodies. In terms of the whole Universe, the beginning, the end, the edge, and the difference from everyday space are the frequently asked. Throughout the raised questions, the mechanisms, origins, and futures are featured rather than definitions or status. Experts are confused when they find questions unexpected or hard to answer. The unexpected questions are based on everyday experiences or misunderstandings, and the questioners point out contradictions among the information through logical extrapolation. The hard questions are with less considerations on whether they are answerable by science. Some of them are neglecting how science is done or what does science target for, while the others are scientific but difficult to answer with the current status of science. The results imply that embarrassing questions from lay persons are the important opportunities to deepen the two-way science communication.
16 0 0 0 OA 神経科学の誤信念の修正は講義を通じて可能か?
- 著者
- 八田 武志 八田 武俊 戸田山 和久 唐沢 穣
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.41-46, 2011 (Released:2011-06-30)
- 参考文献数
- 14
The present study examined whether false beliefs on neuroscience among college students can be corrected by the class lecture of neuropsychology. On the basis of a within subjects experimental design, a 21-item questionnaire was administered to 30 female students from a school of psychology during the first class meeting in a semester as the pre-test and at the final class meeting as the post-test. The participants were asked to judge whether each statement was correct or wrong and evaluate the confidence in their response on a 5-point Likert-type scale. The comparison between the pre- and post-tests with respect to the overall correct response rate showed a significant effect. However, further analyses for separate questionnaire items showed that the majority of items did not show any significant change individually between the pre- and post-tests, with only two exceptional items showing the effect. Therefore, it seems reasonable to conclude that the present results suggest the following. That is, although the class lecture of neuro-psychology discussed issues such as the methodology in scientific research, limitations of brain imaging, and refutation of false information in textbooks concerning the right versus left brains, it nevertheless remained to be a difficult task to reduce the misconception of false scientific information among students by lectures in classrooms. We also emphasized the responsibility that mass media is a powerful source of misunderstanding in the scientific knowledge among the general public.
12 0 0 0 OA 認知科学のなかで哲学に何ができるかを考え直してみた
- 著者
- 戸田山 和久
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.685-687, 2010 (Released:2011-06-06)
6 0 0 0 OA 書評
- 著者
- 戸田山 和久他
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.139-149, 1997-11-10 (Released:2009-05-29)
5 0 0 0 OA 科学哲学のラディカルな自然化
- 著者
- 戸田山 和久
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.29-43, 1999-05-15 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
To naturalize philosophy of science radically and thoroughly, we must re-examine the ontological character (not ontological commitment) of theories and ask how theories are realized in this physical world. Paul M. Churchland dare to answer to this question and claims that a theory is a partition across activation space which is realized by a specific pattern of synaptic weights in a brain. He also tries to justify some Feyerabendian strategies for doing science well in terms of neurocomputational functions of our brains. In this paper, Churchland's project to naturalize philosophy of science is defended against some criticisms. Then, a minor deficiency of his theory is pointed out and a way-out is suggested.
5 0 0 0 OA 神経科学情報に関する誤信念の浸透度とその修正可能性について
- 著者
- 八田 武志 八田 武俊 戸田山 和久 唐沢 穣
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.155-161, 2010 (Released:2010-12-29)
- 参考文献数
- 10
In Study 1, the degrees of penetration and familiarity of false belief on neuroscience, especially brain imaging, among students were surveyed using a questionnaire technique. A total number of 485 students from medical school, school of nurse sciences, school of psychology, and school of informatics were given 20 items and they were requested to evaluate authenticity of the items and familiarity was rated. The results suggested that as familiarity increased, the tendency for participants to regard the item was correct. In Study 2, the question whether false belief on neuroscience can be modified by a usual class lecture was examined. Degrees of the authenticity evaluation and the familiarity of false information between student groups who took the class of neuropsychology and who did not take the class were compared. Results showed a significant difference in many items between the two groups and suggested a possibility of modifiability even by a class lecture.
3 0 0 0 実験哲学は概念分析の何を破壊するのか
- 著者
- 戸田山 和久
- 出版者
- 岩手哲学会
- 雑誌
- フィロソフィア・イワテ (ISSN:13483846)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.41-55, 2014-11
3 0 0 0 大学初年次学生の分野別科学のイメージ--天文学のイメージの特異性
2 0 0 0 OA 置き換え理論,そしてラッセルの数学の哲学についてまだわかっていないこと
- 著者
- 戸田山 和久
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.1-19, 2003-12-30 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
There seems to be a consensus among philosophers who are interested in Russell's early philosophy of mathematics. They hold that we can best understand the process of its development on the assumption that Russell kept trying to reconcile a type-theoretical solution to the paradoxes with the doctrine of univocality of being. This assumption have worked well in so far as to reconstruct the history of Russell's endearvor from Principles of Mathematics (1903) through the invention of substitutional theory (1905-7). Taking Principia Mathematica (1910) into consideration, however, this assumption seems to fail. There are many questions left unanswerable concerning the relation between PM and his former position. In this paper, I will survey some of the recent findings in the Russell Archives and Gregory Landini's works based on these findings, and clarify the relevance they could have to the "unanswered questions" mentioned above.
2 0 0 0 OA 大学職員のためのレポート作成指導法講座
- 著者
- 戸田山 和久
- 巻号頁・発行日
- 2014-09-25
文部科学省平成26年度「大学間連携共同教育推進事業 学都いしかわ・課題解決型グローカル人材育成システムの構築「図書館機能強化プログラム」講演会「『論文の教室』の著者による 大学職員のためのレポート作成指導法講座」(平成26年9月25日)での発表資料
2 0 0 0 OA 「普遍生物学」であるために人工生命研究は何をせねばならないか
- 著者
- 戸田山 和久
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.57-71, 2000-11-25 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 20
This paper aims:1) to re-place and re-estimate A-Life in the tradition of universal biology which goes back to Erwin Schrodinger's memorable lecture "What is Life?";2) to clarify the role which the principle of 'multirealizabitily of life' and the idea of 'strong A-Life' played in justification of A-Life as a form of universal biology;3) to show that clinging to the ideal of storng A-Life is not only unnecessary but harmful for A-Lifers to build a universal biology.
- 著者
- 河野 哲也 戸田山 和久
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.65, pp.90-93, 2014
2 0 0 0 シンギュラリティと人類の生存に関する総合的研究
本研究は、人類よりも知的な人工システムが技術的に可能になる日であるとされるシンギュラリティを巡り、その技術予測としての妥当性、そこで用いられる「人類よりも知的」の意味を明らかにし、その基礎作業の上で、なんらかの意味でのシンギュラリティが起こりうるという仮定にもとづき、予防的にシンギュラリティに人類はどのように対処すべきかを検討し、提言することを目指す。平成29年度は、シンギュラリティの「哲学的問題」として(1)知能爆発の可能性(必然性?)を論証する回帰的議論は果たして妥当か。(2)知性・知能とは何か。そもそも機械はどのような心的能力をもちうるか。(3)知能爆発の結果、倫理や価値(真・善・美)はどうなるのか。(4)シンギュラリティ後の世界において、われわれ人間はどんな役割を果たせるのかという問題群を取り出した。また、これまでに「シンギュラリティ」について書かれた言説について包括的なサーベイを行い、技術予測、シンギュラリティ概念、知性の概念、コンピュータ観、人間観等にかかわる基礎的概念について、著者によって大きく異なることを見出し、それを整理し、「シンギュラリティ」についてどのように論じるべきかというメタ的・方法論的なことがらについて結論を得た。それは、研究代表者により『人工知能学大事典』の「シンギュラリティ」の項目執筆というかたちで発表された。その他、シンギュラリティについて考察するのに関わりをもつ副次的概念や問題(とりわけ機械が犯した失敗についての責任の所在、機械は責任主体になりうるかという問題)について、研究成果を得て、さまざまな媒体で発表した。
2 0 0 0 OA 一般書における科学コミュニケーションの分析
- 著者
- 唐沢 かおり 戸田山 和久
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.117-123, 2013 (Released:2013-12-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
本研究は、福島第一原発事故後、間もない時期に出版された、一般読者向けの書籍5冊を対象として、その内容を分析し、科学コミュニケーションが科学的事実や科学者組織について、詳細な科学的知識を持たない人たちに伝達する際の問題点を議論したものである。まず焦点を当てたのが、現在、科学的に正しい見解が定まっていないと思われる、低線量放射線による被ばくの危険性に関する議論、および、危険閾についてのガイドラインを提出している組織である「ICRP」(International Commission on Radiological Protection)の信頼性を操作するような記述である。そこでは、科学的な論争における重要な論争点が提示されておらず、また、執筆者の立場により、ICRPの信頼性を高めたり貶めたりするような記述が恣意的になされていることが明らかとなった。このように、科学的論争を、科学的事実に関する議論の場ではなく、関与する科学者や組織の信頼性の問題としてフレームして、読者を説得する手法について、本論文は「信頼性戦争(Credibility war)」方略と名付け、その問題点を、科学的事実への理解が欠如した読者を安易に特定の立場に誘導してしまうこと、また、読者が確証バイアスによりその立場を堅持する結果につながりやすいことにあると指摘した。続いて、科学コミュニケーションのスタイルとして、「知識的に優位な立場の科学者」が、「知識が欠如した一般市民」に「教え授ける」という「欠如モデル」による説得レトリックの存在を指摘した。さらにその問題点として、このモデルがトピックに対しての自我関与がそれほど高くない一般大衆(つまりは、福島第一原発事故の直接被害を受けない層)により強く機能する可能性と、心理的リアクタンスの喚起により、コミュニケーション内容の理解が妨げられる可能性を指摘した。最後に、新しくみられる科学コミュニケーションの一例として、中川(2011)に着目し、一般市民が自らの行動を選択する責任を保持していることを前提にした科学コミュニケーションのあり方の可能性について議論した。そのうえで、放射線被ばくの健康への直接的結果だけではなく、それがもたらす社会的帰結がもたらす影響も総合的に評価したうえで、リスクを評価せねばならないという状況認識の重要性、またリスクを背負う人自身が、リスク評価を行う必要を前提とした科学コミュニケーションが今後求められることを論じた。
2 0 0 0 はじめよう、ロジカル・ライティング
- 著者
- 名古屋大学教育学部附属中学校 [名古屋大学教育学部附属]高等学校国語科著 戸田山和久執筆協力
- 出版者
- ひつじ書房
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- 戸田山 和久
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 思想 (ISSN:03862755)
- 巻号頁・発行日
- no.948, pp.63-92, 2003-04
2 0 0 0 OA 科学技術コミュニケーションの著されかた
- 著者
- 齋藤 芳子 戸田山 和久
- 出版者
- 研究・技術計画学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.68-71, 2010-10-09
一般講演要旨