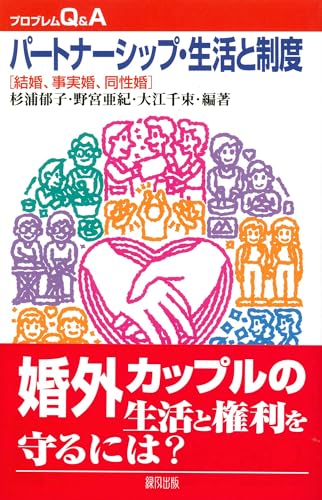- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 中央大学出版部
- 雑誌
- 中央大学社会科学研究所年報 (ISSN:13432125)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.143-158, 2003
7 0 0 0 IR 女性カップルの生活実態に関する調査分析 法的保障ニーズを探るために
- 著者
- 杉浦 郁子 釜野 さおり 柳原 良江
- 出版者
- 日本性教育協会
- 雑誌
- 日本=性研究会議会報
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.30-54, 2008-11
7 0 0 0 OA 偽書というフェイク : 芥川龍之介、谷崎潤一郎、そして石川淳
- 著者
- 杉浦 晋
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.187-197, 2022
偽書は、事実(ファクト)もしくは現実(リアル)と虚構(フィクション)とのあいだに位置づけられる、もう一つの虚構(フェイク)であり、独特の事実=現実らしさ(リアリティ)を虚構(フィクション)に与える。芥川龍之介「奉教人の死」、谷崎潤一郎「春琴抄」、石川淳「喜寿童女」といった偽書の趣向に基づく近代以降の小説は、現実を拒絶して虚構に向かう指向とあわせて、近代以前の諸テクストによって自らを根拠づけようとする、いわばインターテクスチュアリティへの指向を有する。森鷗外の歴史小説や史伝はその先例とみなされ、たとえば「喜寿童女」は「渋江抽斎」にならった可能性がある。偽書をめぐる考察は、文学の想像力の本質にかかわる。
7 0 0 0 OA 鶴田幸恵著『性同一性障害のエスノグラフィ性現象の社会学』
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.357-359, 2010-12-31 (Released:2012-03-01)
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 三輪書店
- 雑誌
- 地域リハビリテーション (ISSN:18805523)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.11, pp.1090-1093, 2008-11
7 0 0 0 IR 日本におけるレズビアン・フェミニズムの活動--1970年代後半の黎明期における
- 著者
- 杉浦 郁子 SUGIURA Ikuko
- 出版者
- 東海ジェンダー研究所
- 雑誌
- ジェンダ-研究 (ISSN:13449419)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.143-170, 2008-12
7 0 0 0 医療訴訟における高齢者が死亡した場合の慰謝料に関する一考察
- 著者
- 杉浦 徳宏
- 出版者
- 判例時報社
- 雑誌
- 判例時報 (ISSN:04385888)
- 巻号頁・発行日
- no.2402, pp.136-141, 2019-06-11
7 0 0 0 OA 中心地理論とナチ・ドイツの編入東部地域における中心集落再配置計画
- 著者
- 杉浦 芳夫
- 出版者
- 日本都市地理学会
- 雑誌
- 都市地理学 (ISSN:18809499)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.1-33, 2015 (Released:2019-04-07)
- 参考文献数
- 127
- 被引用文献数
- 2
本稿は,ナチ・ドイツによるポーランド西部の編入東部地域における中心集落再配置計画最終案と中心地理論との関係について考察した.1941 年頃,Christaller は,編入東部地域の中心集落再配置計画という課題に対し,オリジナルな中心地理論に変更を加えた混合中心地階層の考え方に基づいて計画案を作成したが,最終計画案に直接盛り込まれることはなかった.編入東部地域における中心集落再配置計画案策定の重責を担うドイツ民族性強化帝国委員会の都市建設部門・空間計画部門の統括責任者であったUmlauf によって作成されたものが,最終計画案となった.この最終計画案はChristaller の計画案とは中心集落の規模階層ならびに配置の点で全く異なるものであった.両者の違いは,農村的色彩を残し,一部はポーランド風の集落景観を呈する,規模の小さい都市集落の,中心集落ネットワークへの積極的組み込みの如何によるものであった.しかしながら,最終計画案における集落階層構成が入れ子構造をなしている点は,集落の勢力圏の形が円形と六角形という違いはあるとしても,Christaller の計画案の集落階層構成が入れ子構造をなしている点と共通しており,そこに最終計画案に対する中心地理論ないしは混合中心地階層の考え方の影響を観て取ることができるのである.
7 0 0 0 パートナーシップ・生活と制度 : 結婚、事実婚、同性婚
- 著者
- 杉浦郁子 野宮亜紀 大江千束編著
- 出版者
- 緑風出版
- 巻号頁・発行日
- 2007
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- Japan Society of Family Sociology
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.148-160, 2013
- 被引用文献数
- 2
本稿では,性別違和感のある人々の経験の多様性が顕在化したことを背景に,「性同一性障害であること」の基準として「周囲の理解」が参照されるようになった可能性を指摘する.また「性同一性障害」がそのように理解されるようになったとき,性別違和感のある子とその親にどんな経験をもたらしうるのかを考察する.<br>まず,1980年代後半から90年代前半に生まれた若者へのインタビュー・データを用いて,「周囲の理解」という診断基準が出現したプロセスについて分析する.次いで,「性同一性障害」の治療を進めようとする20代の事例を取り上げ,医師も患者も「親の理解」を重視していることを示す.そのうえで,親との関係調整の努力を要請する「性同一性障害」という概念が,親子にどのような経験を呼び込むのかを論じる.
7 0 0 0 OA 森山至貴著『「ゲイコミュニティ」の社会学』
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.729-730, 2013 (Released:2015-03-31)
6 0 0 0 OA チェルノブイリ事故後の環境影響
- 著者
- 杉浦 紳之
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.419-425, 2011 (Released:2019-09-06)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
6 0 0 0 OA 「性」の構築 「性同一性障害」医療化の行方
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.73-90,222, 2002-02-28 (Released:2016-11-02)
Since Saitama Medical University applied to carry out a sex reassignment surgery (so called "sex change surgery") in 1995, medicalization of "gender identity disorder" is actively encouraged in Japan. There has been a corresponding increase in number of treatises on this mental disorder published by specialists. By analyzing those professional discourses, I will illustrate how a domain of "the sexual" is socially constructed. The social constructionism has argued two important views: First, objects are produced in and through a series of linguistic practices of signification; second, some knowledge is cited/referred when the practices are intelligible. The question of how "the sexual" is constructed will not be limited to the work of showing the particular way of construction of "the sexual." I will also show how and what kind of knowledge is cited in the constructing process. Having learned constructionism from Judith Butler, this paper keeps the interest of describing gaps and fissures that are produced in the very process of the constructing practices. Those gaps and fissures are observed as logical discontinuity, and are taken as the possibility to change the hegemonic meaning of "the sexual." I hold the attention of its changeablity because I am anxious that the construct of "the sexual" by professionals becomes standard and legitimate knowledge. Examining carefully the practices, we will find cited knowledge there operates against not only other "sexual minorities" but also transsexuals themselves.
6 0 0 0 OA 「女性同性愛」言説をめぐる歴史的研究の展開と課題
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 和光大学現代人間学部
- 雑誌
- 和光大学現代人間学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Human Studies (ISSN:18827292)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.7-26, 2015-03-13
近代以降の日本社会は「女同士の親密な関係」「女を愛する女」に対してどのような意味を与えてきたのだろうか。「女性同性愛」言説の変容をたどる研究成果を「性欲」の視点から整理することが本論文の目的である。ここで「性欲」の視点とは、大正期に定着してから現在まで様々な仕方で構築されてきた「性欲」という領域が、女性同性愛に関する言説をどのように枠づけてきたのか、反対に、女性同性愛に関する言説が「性欲」をどのように枠づけてきたのか、という視点のことをいう。したがって、本論文が注目するのは、「性欲」が女同士の親密性をめぐる経験や理解の仕方に関わっていることを示し得ているような研究成果である。この「性欲」の視点を軸にして、「女性同性愛」言説をめぐる歴史研究の現在における到達点と今後の課題を明らかにしたい。
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- アジア女性資料センタ-
- 雑誌
- 女たちの21世紀
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.26-29, 2004-02
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 「現代社会理論研究」編集委員会事務局
- 雑誌
- 現代社会理論研究 (ISSN:09197710)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.93-104, 1998
6 0 0 0 OA 車両の固有振動数を用いた車両重量推定に関する基礎検討
- 著者
- 杉町 敏之 須田 義大 阿部 朋明 鈴木 彰一 牧野 浩志 鯉渕 正裕 杉浦 孝明
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.149-151, 2015-03-01 (Released:2015-03-30)
- 参考文献数
- 4
本研究では,道路の劣化に与える影響が大きい過積載トラックの対策のため,重量変化により生じる車両の固有振動数変化に着目し,次世代交通システムで応用可能な重量推定法に関する基礎検討を行う.具体的には,重量ごとに変化する車両の固有振動数に着目し,この値を走行車両上で計測することにより過積載を検出するシステムの実現を目指す.そのための検討として本稿では2 軸車両を対象とし,積載重量に対する固有振動数の変化を解析する.また,個体差や経年変化に対する検討として,重心位置の変化に対する固有振動数への影響に影響について検討を行った.
- 著者
- 杉浦 良樹 太田 益弘 平野 昌弘 石川 英男 浜口 正規 背戸 好廣 伊藤 龍彦 天野 智康 日下部 行宏 村上 逸則
- 出版者
- 公益社団法人日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術學會雜誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, 1989-02-01
- 著者
- 柳澤 博紀 杉浦 琢
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.15-23, 2020-01-31 (Released:2020-10-23)
- 参考文献数
- 15
チック症状に対する行動療法として、ハビット・リバーサル(Habit Reversal: HR)の有効性が示されているが、音声チックや重症度の高い症例の蓄積が少ないと国内外で指摘されている。本研究では叫び声様の重度音声チック症状を抱えたクライエント(Cl.)に対してHRを含んだ行動療法を実施し、客観的行動指標を用いたうえで単一症例研究法により効果を検証した。Cl.は40代女性、入院後約1カ月の服薬治療も著効なく行動療法を開始した。ベースラインでは1日5時間の測定を4日行い、叫び声の頻度は1日平均93.5回であった。介入は各回約15分程度心理士と共に咳払いを用いた競合反応訓練を練習すること、および同様の練習を日常的に実施する宿題であった。介入は25日間で10回実施した。介入開始後叫び声の頻度は大幅に減少し、約4週で叫び声は生起しなくなりCl.は退院した。介入実施後3年経過後も症状の再発は見られていない。重度音声チック症状に対するHRの有効性が示唆された。