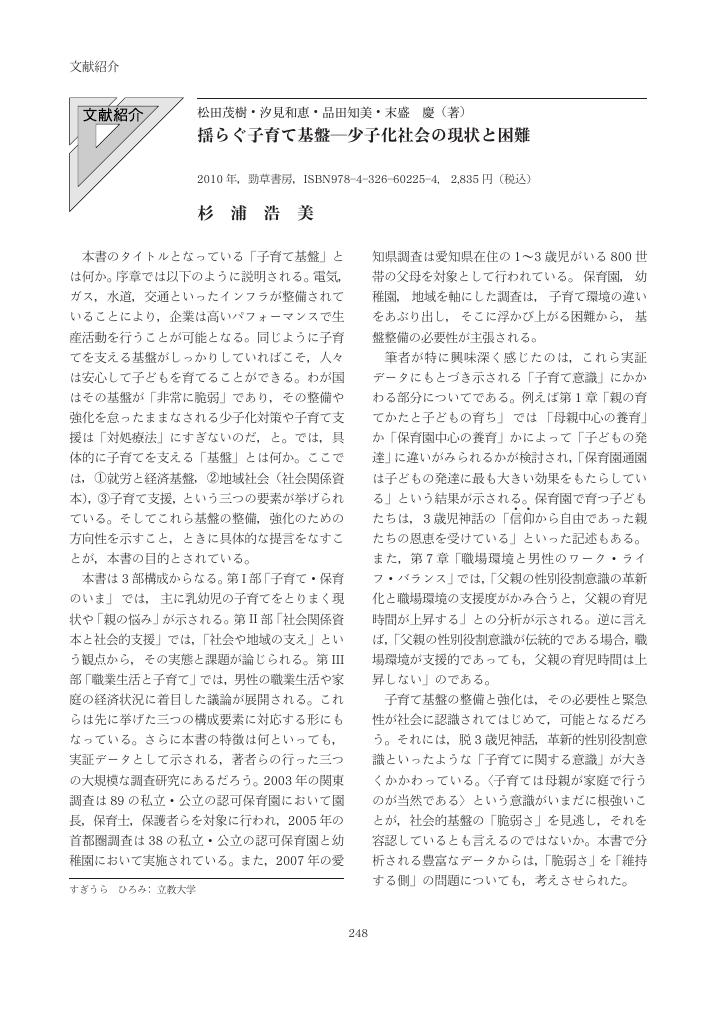- 著者
- 水野 基樹 川田 裕次郎 飯田 玲依 山本 真己 東 慎治 上野 朋子 山田 泰行 杉浦 幸 田中 純夫 Motoki Mizuno Yujiro Kawata Rei Iida masaki Yamamoto Shinji Higashi Tomoko Ueno Yasuyuki Yamada Miyuki Sgiura Sumio Tanaka 千葉経済大学短期大学部非常勤講師 CHIBA KEIZAI COLLEGE Part-time Lecturer
- 出版者
- 千葉経済大学短期大学部
- 雑誌
- 千葉経済大学短期大学部研究紀要 = Bulletin of Chiba Keizai College (ISSN:13498312)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.51-61,
The psychology of motivation is a broad and loosely defined field. Furthermore, motivation is a basic psychological process. Few would deny that it is the most important focus of the micro organizational behavior. Traditionally, psychologists have not totally agreed on how to classify the various human motives, but they acknowledge that some motives are unlearned physiologically based. For that reason, it is difficult to comprehend a framework of motive concepts which can predict human behavior. Therefore, the purpose of this paper was to review the motive concept suggested by McClelland(1987), who is most closely associated with the study of achievement motive. Specifically, first we summarized up the measurement and concepts of motive, such as "measures of human motive dispositions", "achievement motive", "power needs", "affiliative motive" and "avoidance motive". In addition, we critically reviewed and discussed them in terms of the definitions of concepts. In conclusion, although we could grasp the implications of each motive concept, there were some ambiguities regarding McClelland's motive concepts. Thus, more elaborate conceptual regulation and detailed explanation of the connections to the concepts seem necessary in order to clarify the notion of motive concepts, because there are a number of motives which lie in a gray area from the viewpoint of human motivation described by McClelland.
3 0 0 0 OA トンパ文字の構造原理とビジュアル・コミュニケーションデザインに関する研究
- 著者
- 黄 國賓 杉浦 康平 赤崎 正一 今村 文彦 荒木 優子 山之内 誠 さくま はな 曽和 英子 Kuo-pin HUANG Kohei SUGIURA Shoichi AKAZAKI Fumihiko IMAMURA Yuko ARAKI Makoto YAMANOUCHI Hana SAKUMA Eiko SOWA
- 雑誌
- 芸術工学2014
- 巻号頁・発行日
- 2014-11-25
本研究は中国雲南省の麗江地区を基軸に、トンパ文字とその特異な造形、宗教的背景を明らかにし、トンパ文字の構造原理と新たなビジュアル・コミュニケーションツールを開発するための基盤研究を確立する。本研究はトンパ文字の造字原理の考察をはじめ、現地でのフィールドワーク調査、トンパ文字を再デザインする仕組み、また、先例の視覚言語の表現や漢字の構造をも分析の視野にいれ、トンパ文字の表現の可能性について研究を行った。その結果、以下の結論を得た。すなわち、トンパ文字は象形文字であるため判読がしやすく、時間軸、空間軸、動詞などの記号を組み合わせれば、トンパ文字としての視覚言語のシステムを構築する可能性が高いと示唆した。一方、文字としての記述、伝達の機能が欠け、覚えにくいということが最大の欠点であり、漢字の変遷原理を探究すれば、書きやすく、覚えやすいトンパ文字が作られると考えられる。
3 0 0 0 OA 新人看護師を支援するプリセプター育成のための研修コースの開発と効果の測定
- 著者
- 杉浦 真由美 向後 千春
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:21896453)
- 巻号頁・発行日
- pp.40063, (Released:2016-12-28)
3 0 0 0 OA 野生ニホンザルを取り巻く社会問題と餌付けに関する意識調査
- 著者
- 田中 俊明 揚妻 直樹 杉浦 秀樹 鈴木 滋
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.123-132, 1995 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 12
The purpose of the present survey was to investigate the awareness of the public on the problems arising from provisioning. The social problems of provisioned wild Japanese macaques happens throughout Japan including Yakushima Island in Kagoshima Prefecture. A questionnaire was given to residents in Yakushima and to tourists visiting. Responses were obtained from 438 people. The results may be summarized as follows: (a) The majority of people questioned were aware of some of the social problems in wild Japanese macaques caused by provisioning. (b) Many people gave wild monkeys food for reasons of amusement and in the belief that it improved their situation. This questionnaire revealed that the public understood some of the issues described above but their actions appeared to contradict this. Consequently there is a need to develop a better understanding on the influence of man particularly in regard to feeding.
3 0 0 0 OA 神経障害性疼痛モデルにおける神経分泌能解析~痛覚過敏への末梢神経機能の関与
3 0 0 0 研修症例 場面緘黙の少年との心理療法過程
- 著者
- 杉浦 浩代
- 出版者
- 日本精神分析学会
- 雑誌
- 精神分析研究 = The Japanese journal of psycho-analysis (ISSN:05824443)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.509-513, 2015-11
3 0 0 0 OA 諸葛亮
- 著者
- 杉浦重剛, 猪狩又蔵 著
- 出版者
- 博文館
- 巻号頁・発行日
- 1913
3 0 0 0 フラクタル次元による茶室空間の美の分析
- 著者
- 佐藤 祐介 新宮 清志 杉浦 巌
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本ファジィ学会誌 (ISSN:0915647X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.5, pp.104-109, 2000-10-15
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 5
茶室は、その空間内部のあらゆる場に於いて、秩序と無秩序の混在が織りなす複雑な構成となっている。茶室の美は、その複雑さに起因しているのではないだろうか。本論文では、茶室空間に施されたデザインに内在する複雑さを定量的に示す方法として、フラクタル幾何学におけるフラクタル次元の利用を提案している。その際、まず始めにサンプルとして取り挙げたそれぞれの茶室空間に施されたデザインから、実際にフラクタル次元を測定する方法を示す。さらに、算出されたフラクタル次元による比較・考察を行い、茶室空間における美的考察の新しい観点として"リズム"の分析について言及すると共に、デザインを数学的に解析する際の道具としてのフラクタル次元の有効性を示す。本論におけるフラクタル次元の算出方法は、以下に示す手順を踏む。(1)対象となる形態のディテールをグリッド化する(2)グリッドを空間的変動曲線として表す(3)作成した空間的変動曲線から、スケール変換解析よりH指数を測定する(4)測定されたH指数から、フラクタル次元を求める
3 0 0 0 OA アドルフ・アッピアとエミール・ジャック=ダルクローズ
- 著者
- 杉浦 康則
- 出版者
- 北海道大学ドイツ語学・文学研究会
- 雑誌
- 独語独文学研究年報 (ISSN:13480413)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.48-68, 2006-12
3 0 0 0 OA コトの物理学
- 著者
- 樺島 祥介 杉浦正康
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:07272997)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.1, pp.1-33, 2008-10-20
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
3 0 0 0 OA 回復期退院時の移動手段が車椅子となった脳卒中患者に求められる自宅復帰条件
- 著者
- 杉浦 徹 櫻井 宏明 杉浦 令人 岩田 研二 木村 圭佑 坂本 己津恵 松本 隆史 金田 嘉清
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.5, pp.779-783, 2014 (Released:2014-10-30)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
〔目的〕回復期リハビリテーション病棟退院時に移動手段が車椅子となった脳卒中患者に求められる自宅復帰条件を検討すること.〔対象〕移動手段が車椅子の脳卒中患者で,転帰先が自宅もしくは施設・療養病床となった68名とした.〔方法〕自宅群(28名)と施設群(40名)を群間比較し,ロジスティック回帰分析にて転帰先因子を抽出した.また,入院時に家族が想定した転帰先と実際の転帰先の関係を分析した.〔結果〕ロジスティック回帰分析では「食事」と「トイレ動作」が転帰先因子として抽出された.また,入院時の転帰先意向は最終的な転帰先に反映される傾向がみられた.〔結語〕移動手段が車椅子での自宅復帰条件には「食事」と「トイレ動作」が求められ,患者の家族とは入院当初から自宅復帰に向けた展望の共有が重要となる.
3 0 0 0 OA 第一言語としての日本語発達指標の開発と言語発達障害への適用
- 著者
- 宮田 Susanne 伊藤 恵子 大伴 潔 白井 英俊 杉浦 正利 平川 眞規子 MACWHINNEY Brian OSHIMA-TAKANE Yuriko SHIRAI Yasuhiro 村木 恭子 西澤 弘行 辰巳 朝子 椿田 ジェシカ
- 出版者
- 愛知淑徳大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2006
1歳から5歳までの日本語を獲得する子どもの縦断発話データに基づき発達指標DSSJ(Developmental Sentence Scoring for Japanese)を開発し、この日本語の発達指標を84人の子どもの横断データ(2歳~5歳)にあてはめ、標準化に向けて調整を行った.DSSJはWWW上のCHILDES国際発話データベースの解析プログラムCLANの一部として一般公開されている.
3 0 0 0 OA 共通1次試験総合得点に対する分布のあてはめII
- 著者
- 杉浦 成昭
- 出版者
- 応用統計学会
- 雑誌
- 応用統計学 (ISSN:02850370)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.39-52, 1981-08-31 (Released:2009-06-12)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 2
昭和55年度共通1次試験総合得点の分布は,杉浦[8]によりJohnson systemのSB分布がよく適合することが示された.昭和54,56年度について同様に調べるとSB分布ではなく,負のWeibull分布を負の方にトランケートした分布が良く適合することがわかった.昭和56年度についてはBeta分布も同じ位よく適合するので分布の両すその階級をそれぞれ2分し自由度を2増して調べるとトランケートWei-bull分布よりもBeta分布がよく適合することがわかった.
- 著者
- 杉浦 榮三
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- 新聞学評論 (ISSN:04886550)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.132-135, 1957-01-30
3 0 0 0 OA 松田茂樹・汐見和恵・品田知美・末盛 慶(著)揺らぐ子育て基盤—少子化社会の現状と困難
- 著者
- 杉浦 浩美
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.248-248, 2010-10-30 (Released:2011-10-30)
3 0 0 0 OA J・D・サリンジャーと東洋思想の諸相 : 短篇「テディ」をめぐって
- 著者
- 杉浦 銀策
- 出版者
- 駒澤大学
- 雑誌
- 駒澤大學文學部研究紀要 (ISSN:04523636)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.125-180, 1999-03
- 著者
- 杉浦 隆之
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.11, pp.1077-1081, 2003-11-01 (Released:2018-08-26)
- 参考文献数
- 13
2 0 0 0 OA 神経発達症児における血清亜鉛値の検討
- 著者
- 井之上 寿美 河野 芳美 河野 千佳 白木 恭子 塩田 睦記 雨宮 馨 中村 由紀子 杉浦 信子 小沢 愉理 北 洋輔 小沢 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.356-358, 2022 (Released:2022-10-13)
- 参考文献数
- 10
神経発達症児の血清亜鉛値について健常児の参照値と比較検討した.血清亜鉛値を測定した学齢期の神経発達症児63名(男児49名,女児14名)を患者群とし,先行研究において年齢分布が一致する380名の健常児のデータを用いて解析を行った.その結果,患者群のうち19名(30%)が亜鉛欠乏症,また39名(62%)が潜在性亜鉛欠乏,亜鉛値正常は5名(8%)であり,血清亜鉛値は健常児の参照値と比較して有意に低値であった(p<0.001).患者群の診断内訳では,ADHD(36名,54%)と自閉スペクトラム症(22名,39%)の2疾患が大部分を占めたものの,血清亜鉛値は疾患間で有意な差はなく(p=0.32),性差も認められなかった(p=0.95).神経発達症児は亜鉛欠乏傾向にあると考えられ,疾患や性別による血清亜鉛値の明らかな違いはなかった.