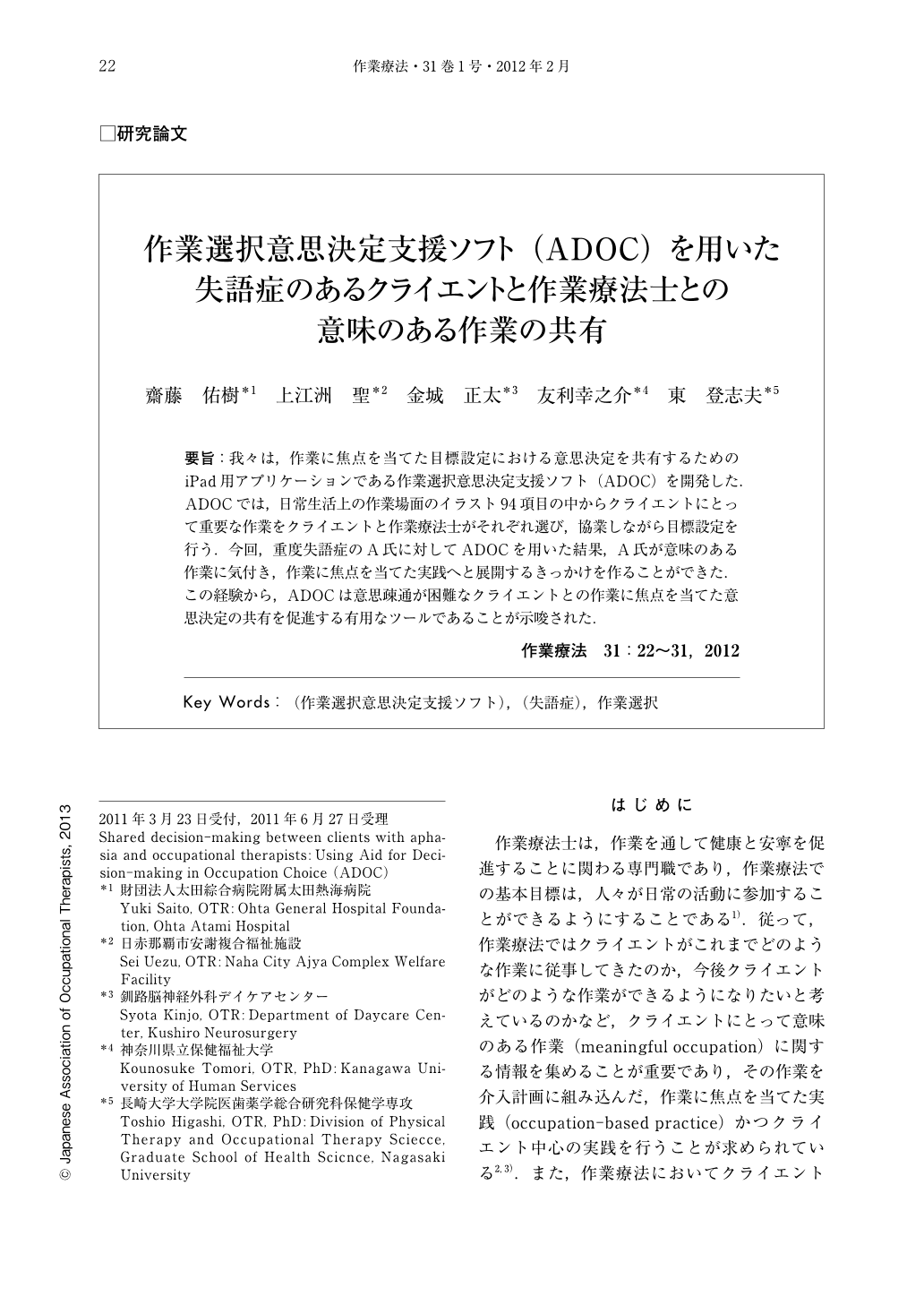- 著者
- 齋藤 佑樹 上江洲 聖 金城 正太 友利 幸之介 東 登志夫
- 出版者
- 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.22-31, 2012-02-15
- 被引用文献数
- 2
要旨:我々は,作業に焦点を当てた目標設定における意思決定を共有するためのiPad用アプリケーションである作業選択意思決定支援ソフト(ADOC)を開発した.ADOCでは,日常生活上の作業場面のイラスト94項目の中からクライエントにとって重要な作業をクライエントと作業療法士がそれぞれ選び,協業しながら目標設定を行う.今回,重度失語症のA氏に対してADOCを用いた結果,A氏が意味のある作業に気付き,作業に焦点を当てた実践へと展開するきっかけを作ることができた.この経験から,ADOCは意思疎通が困難なクライエントとの作業に焦点を当てた意思決定の共有を促進する有用なツールであることが示唆された.
6 0 0 0 OA 身体柔軟性と関節弛緩性における性差および関係性
- 著者
- 古後 晴基 村田 潤 東 登志夫
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.189-193, 2015-01-30 (Released:2015-03-04)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3 4
[目的]本研究は,身体柔軟性と関節弛緩性において性差および関係性について検証した。[対象と方法]大学2年生の健常人42名(男性28名,女性14名)を対象とした。身体柔軟性および関節弛緩性スコアを評価した。身体柔軟性の評価は,指足尖間距離,指床間距離,膝床間距離,および中指-中指間距離の測定とした。[結果]身体柔軟性および関節弛緩性スコアの測定値を性別間で比較したところ,関節弛緩性スコアにおいて性差を認めた。身体柔軟性の測定値と関節弛緩性スコアとの関連を分析したところ,関節弛緩性スコアと有意な相関を示した身体柔軟性の測定項目はなかった。身体柔軟性の各測定項目間において,指足尖間距離と指床間距離に極めて強い相関関係が示され,指床間距離と膝床間距離に弱い相関関係が示された。[結語]女性は男性に比べ関節弛緩性が高いことが示唆された。本研究における身体柔軟性評価の指標と関節弛緩性評価の指標は関連がないことが示唆された。
3 0 0 0 OA 我が国の作業療法士による研究活動の現状と課題
- 著者
- 東 登志夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.136-141, 2020-04-15 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 6
作業療法士を取り巻く情勢の変化に対応するため,作業療法のエビデンス構築に向けた研究活動の活性化が急務となっている.本稿では,それらの情勢に触れた上で,我が国の作業療法士による研究活動の現状と,日本作業療法士協会が発刊している学術誌に掲載された論文や,作業療法に関係した国際誌の分析結果等をもとに,いくつかの課題を列挙した.そして,それらを改善するための方策として,日本作業療法士協会員各位が現状の作業療法を取り巻く情勢に危機感を持ち,現在の自分の状況からワンステップ上の目標に向けて行動を起こすことを提言した.
- 著者
- 古関 友美 永井 善大 山西 葉子 友利 幸之介 東 登志夫
- 出版者
- 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.385-395, 2009-08-15
- 参考文献数
- 27
- 著者
- 金城 正太 友利 幸之介 大友 貴子 山田 勝雄 東 登志夫
- 出版者
- 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.578-584, 2009-10-15
- 著者
- 壱岐尾 優太 佐賀里 昭 中野 治郎 近藤 康隆 小田 太史 大賀 智史 長谷川 隆史 東 登志夫
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.331-338, 2020 (Released:2020-12-21)
- 参考文献数
- 33
【目的】化学療法誘発性末梢神経障害(CIPN)を呈したがん患者の痺れおよび疼痛に対する破局的思考と,自覚症状,上肢機能,生活障害との関連を調べること.【方法】上肢にCIPNを認めた造血器腫瘍および消化器がん患者の破局的思考(PCS:合計得点,反芻,無力感,拡大視),痺れおよび疼痛に対する自覚症状,上肢機能,生活障害を評価し,Spearmanの順位相関係数を求めた.【結果】破局的思考と生活障害との間に有意な相関関係を認め,上肢機能との間には有意な相関関係は認めなかった.PCSの下位項目別では,反芻のみ自覚症状と有意な相関関係を認めた.【結論】上肢にCIPNを認めたがん患者の生活改善のためには,機能面に対する評価やアプローチだけでは不十分な場合があり,破局的思考などの認知的側面に対する評価やアプローチも考慮する必要がある.
2 0 0 0 OA 外傷性頚部痛と非外傷性頚部痛では能力障害に関与する因子が異なる
- 著者
- 山下 裕 西上 智彦 古後 晴基 壬生 彰 田中 克宜 東 登志夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.H2-198_2, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに、目的】頚部痛患者において,単に筋や関節由来だけでなく,様々な要因が能力障害に関与することが明らかになっている.外傷性頚部痛は非外傷性頚部痛よりも,臨床症状がより重度であることが報告されているが,それぞれの能力障害に関与する要因は未だ明らかではない.近年,他害的な外傷や痛みに伴う不公平感を定量するInjustice Experience Questionnaire(IEQ)や,頚部の身体知覚異常を包括的に評価するFremantle Neck Awareness Questionnaire(FreNAQ)といった新たな疼痛関連指標が開発されているが,外傷性,非外傷性頚部痛それぞれの能力障害にどのように関与するか明らかでない.本研究の目的は,外傷性と非外傷性頚部痛の疼痛関連因子の比較及びそれぞれの能力障害に影響する因子を検討することである.【方法】対象は, 頚部痛患者119名(外傷性頚部痛患者74名,非外傷性頚部痛患者45名)とした.評価項目として,疼痛期間,安静時・運動時痛,能力障害はNeck Disability Index (NDI),不公平感は IEQ,身体知覚異常はFreNAQ,破局的思考は短縮版Pain Catastrophizing Scale(PCS6),運動恐怖感は短縮版Tampa scale for Kinesiophobia(TSK11),うつ症状はPatient Health Questionnaire(PHQ2)を調査した.統計解析は,Mann-Whitney U検定を用いて外傷性頚部痛と非外傷性頚部痛における各評価項目の差を比較検討した.さらに,NDIを従属変数とした重回帰分析を用いて,外傷性頚部痛,非外傷性頚部痛におけるそれぞれの関連因子を抽出した.【結果】2群間比較の結果,疼痛期間において有意な差を認めたが[外傷性頚部痛: 30日(0−10800日); 非外傷性頚部痛: 300日( 2−7200日),p<0.001],その他の項目に有意な差は認められなかった.重回帰分析の結果,NDIと有意な関連が認められた項目として,外傷性頚部痛ではIEQ(β=0.31, p =0.03)と運動時痛(β=0.17, p =0.01),非外傷性頚部痛においてはFreNAQ(β=0.79, p =0.002)のみが抽出された.【結論(考察も含む)】本研究の結果から,外傷性頚部痛患者と非外傷性頚部痛患者において,能力障害に影響を与える因子が異なる可能性が示された.したがって,外傷性頚部痛患者では不公平感を軽減する介入が必要であり,非外傷性頚部痛患者においては身体知覚異常を正常化する介入が必要である可能性が示唆された.【倫理的配慮,説明と同意】対象者には研究の主旨と内容を口頭および書面で説明し,同意を得て研究を実施した.なお本研究は西九州大学倫理委員会の承認を得ている(承認番号:H30 − 2).
1 0 0 0 OA 眼動脈の走行異常により術中大出血を来した慢性副鼻腔炎の1例
- 著者
- 末田 尚之 梅野 悠太 杉山 喜一 上野 哲子 福崎 勉 中川 尚志 福田 健治 東 登志夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会
- 雑誌
- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.463-467, 2016-02-28 (Released:2016-04-06)
- 参考文献数
- 12
内視鏡下鼻内副鼻腔手術の合併症での動脈性出血の責任血管として内頸動脈,前・後篩骨動脈や蝶口蓋動脈は良く知られている。今回,非常にまれと考えられる眼動脈の走行異常に伴う出血を経験した。症例は71歳男性。慢性副鼻腔炎に対する手術操作時に篩骨洞内を走行する眼動脈を損傷した。通常の止血術では出血のコントロールがつかず,血管造影下での塞栓術を行った。この時,3D-造影CTと眼動脈3D-DSAを併施することでより的確に出血部位が同定され塞栓処置を行うことが可能であった。術後,一時的に眼窩内出血と眼瞼浮腫により視力低下を来したが,経過とともに視力は術前の状態にまで回復した。現在,術後9か月が経過するが視力障害等は認めていない。
- 著者
- 山田 美穂 津川 潤 新居 浩平 井上 律郎 坪井 義夫 東 登志夫
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.10, pp.801-804, 2022 (Released:2022-10-22)
- 参考文献数
- 8
症例は79歳男性.一過性の右片麻痺を繰り返すため当科に紹介入院した.神経学的に異常はなく,血液検査で腎機能障害を認めた.少量の造影剤で左内頸動脈撮影のみを行い,左内頸動脈分岐部にNASCET 86%の狭窄を認めた.血管内治療を行う方針となったが,造影剤による腎機能悪化が危惧されたため,診断脳血管撮影時に取得した3Dイメージのfusion画像を使用し,B-modeエコーなどを併用しcarotid artery stenting(CAS)を行った.治療後は良好な拡張が得られ,神経症状の再発なく経過している.3Dイメージを用いることで造影剤を使用せず血管内治療を安全に行うことができた.
- 著者
- 永井 善大 東 登志夫 石橋 仁宏 古関 友美 三代 貴康
- 出版者
- 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.29-35, 2010-02-15
1 0 0 0 OA 痛みに対する破局的思考が強い脊椎圧迫骨折患者への成功体験を強調した介入:症例報告
- 著者
- 長谷川 隆史 佐熊 晃太 西 啓太 小無田 彰仁 東 登志夫
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.137-141, 2021 (Released:2021-02-24)
- 参考文献数
- 17
[目的]本研究の目的は,痛みに対する破局的思考が強い脊椎圧迫骨折患者への有効な介入方法を検討することである.[対象と方法]対象は脊椎圧迫骨折と診断され,当院に入院した高齢男性であった.成功体験を強調した介入を行い,痛みの程度(NRS),痛みに対する破局的思考(PCS),不安抑うつ状態(HADS),日常生活動作能力(mFIM),活動量を評価した.[結果]入院時PCSの合計点は44点と高値を示したが,成功体験を強調した介入を実施することで,32点に改善し,その他の痛み関連因子も改善し,mFIMも37点改善した.[結語]痛みが強い脊椎圧迫骨折患者に対し,入院早期から多職種協働で成功体験を強調した介入を実施することで,PCSを改善させ,痛みの遷延化を防止できる可能性が示唆された.
- 著者
- 山下 裕 古後 晴基 西上 智彦 東 登志夫
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.101-106, 2018-10-16 (Released:2018-10-19)
- 参考文献数
- 32
【目的】慢性頸部痛患者における破局的思考や運動恐怖感が能力障害に関連する因子かどうか検討した。【方法】3ヶ月以上頸部痛を有する外来患者99名(外傷性35名,非外傷性64名)を対象とした。評価項目は,Neck Disability Index(NDI),安静時・運動時疼痛強度,疼痛持続期間,破局的思考,運動恐怖感とした。Mann-Whitney U 検定を用いて発症起点の有無における評価項目を比較した。また,Stepwise 法による重回帰分析を用いてNDI に関連する項目を検討した。【結果】外傷性頸部痛患者と比較して非外傷性頸部痛患者は年齢,疼痛持続期間において有意に高値を示したが,その他の項目に有意な差は認められなかった。NDI と関連する項目は,破局的思考と安静時・運動時疼痛強度であった。【結論】慢性頸部痛患者においては,外傷性か非外傷性に関わらず破局的思考が能力障害に関連することが明らかとなった。
1 0 0 0 運動学習過程と筋機能特異性に関わる皮質運動野の興奮性変化
- 著者
- 菅原 憲一 田辺 茂雄 東 登志夫 鶴見 隆正 笠井 達哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.A3P2129, 2009
【目的】運動学習過程で大脳皮質運動野は極めて柔軟な可塑性を示すことはよく知られている.しかし、運動学習効率と各筋の特異性に関わる運動野の詳細な知見は得られていない.今回、トラッキング課題による運動学習過程が皮質運動野の興奮性に及ぼす影響を学習経過と筋機能特異性を中心に経頭蓋磁気刺激(TMS)による運動誘発電位(MEP)を指標に検討した.<BR>【方法】対象は健常成人13名(年齢21-30歳)とした.被験者に実験の目的を十分に説明し,書面による同意を得て行った.なお、所属大学の倫理委員会の承認を得て行った.<BR>被検者は安楽な椅子座位で正面のコンピュータモニター上に提示指標が示される.提示波形は3秒間のrest、4秒間に渡る1つの正弦波形、3秒間の一つの三角波形から構成される(全10秒).運動課題はこの提示指標に対して机上のフォーストランスデューサーを母指と示指でピンチし、モニター上に同期して表れるフォースと連動したドット(ドット)を提示指標にできるだけ正確にあわせることとした.提示指標の最大出力は最大ピンチ力の30%程度とし、ドットはモニターの左から右へ10秒間でsweepするものとした.練習課題は全部で7セッションを行った.1セッションは10回の試行から成る.練習課題の前にcontrol課題としてテスト試行(test)を5回行い、各練習セッション後5回のテスト試行を行うものとした.練習課題は提示指標とドットをリアルタイムに見ることができる.しかし、testではsweep開始から3秒後に提示指標とドットが消失し遂行状況は視覚では捕えられなくなる.TMSはこの指標が消失する時点に同期して行われた.MEPは、第1背側骨間筋(FDI)、母指球筋(thenar)、橈側手根屈筋(FCR),そして橈側手根伸筋(ECR)の4筋からTMS(Magstim社製;Magstim-200)によるMEPを同時に導出した.MEP記録は刺激強度をMEP閾値の1.1~1.3倍,各testでMEPを5回記録した.また、各4筋の5%最大ピンチ時の筋活動量(RMS)、提示指標と実施軌道の誤差面積を測定した.データ処理はいずれもcontrolに対する比を算出し分析検討(ANOVA, post hoc test: 5%水準)を行った.<BR>【結果と考察】誤差面積と各筋RMSは、controlと比較すると、各訓練セッションで有意に減少した(P<0.05).FCRとECRは練習後、MEPの変化は認められないものの、7セッション後ではFDIの有意な増加が示された(P<0.05).しかし、thenarでは7セッション後に有意な減少を示した(P<0.05).以上の結果、パフォーマンスの向上に併せて大脳皮質運動野の運動学習による変化は全般の一様な変化ではなく、その学習課題に用いられる各筋の特異性に依存していることが示唆された.
1 0 0 0 OA 等尺性収縮時における肘関節角度が肘関節屈筋群の 筋疲労と筋出力に及ぼす影響
- 著者
- 東 登志夫 鶴崎 俊哉 船瀬 広三 沖田 実 岩永 竜一郎 野口 義夫
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.121-125, 2004 (Released:2004-06-12)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2 3
等尺性収縮時における肘関節角度が肘関節屈筋群の疲労度合いと筋出力に及ぼす影響について検討した。被験者は,健常成人9名とし,被験者全員に対してインフォームド・コンセントを得た。被験者には座位をとらせ,肩関節は0度とし,肩関節,骨盤及び大腿部をベルトにて固定した。肘関節の肢位は,肘屈曲30, 60, 90, 120度の4条件に設定した。実験は,まず最大随意収縮時(maximum voluntary contraction;MVC)の筋出力値を筋力測定装置を用いて計測した。次に被験者に視覚的フィードバックを行いながら,等尺性収縮にて各条件の50%MVCを60秒間以上保持させ,上腕二頭筋と腕橈骨筋から表面筋電図を計測した。筋疲労の指標には,表面筋電図の自己回帰パワースペクトル解析による周波数中央値を用いた。周波数中央値は,60秒間のデータを10秒ごとの6区間にわけ,それぞれの区間における周波数中央値を算出した。その結果,1)最大筋出力が得られたのは,90度であった,2)周波数中央値は,時間経過とともに減少し,その減少度合いは肘関節の屈曲角度が大きくなる程大きい傾向にあった。これらの結果より,最大筋出力が得られる肘関節角度と疲労しにくい角度は異なることが示唆された。従ってセラピストが,運動肢位を決定する際には,その点を十分考慮する必要があると思われる。
1 0 0 0 OA 浮腫における圧痕深度計測法の妥当性および圧痕性浮腫の判別
- 著者
- 古後 晴基 村田 潤 東 登志夫 村田 伸 鳥山 海樹 山下 裕 今村 純平
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.29-33, 2016-04-30 (Released:2016-07-29)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,浮腫における圧痕深度計測法の妥当性と圧痕性浮腫の判別が可能な評価法であるかを明らかにすることである。22名44肢の浮腫有と診断された患者と,30名60肢の地域在住の健常高齢者を対象とした。被験者の足底を床面に付けた端座位とし,第3中足骨骨頭の足背部の圧痕深度をエデゲー?にて計測した。また,同一部位の皮下軟部組織厚を超音波画像診断装置にて計測した。統計解析には,圧痕深度値と皮下軟部組織厚値をPearson の相関係数にて分析した。また,圧痕深度値は,対応のないt 検定を用いて患者と健常者間で比較した。その結果,圧痕深度値と皮下軟部組織厚値との間に,極めて強い相関関係を示した。また,患者群は健常者群と比較して圧痕深度値が有意に高値を示した。本研究より,圧痕深度計測法は妥当性ある評価法であり,圧痕性浮腫の有無を判別可能な評価法である可能性が認められ,圧痕性浮腫における有用な評価法であることが示唆された。
- 著者
- 齋藤 佑樹 友利 幸之介 東 登志夫
- 出版者
- 日本作業療法士協会 ; 1982-
- 雑誌
- 作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.55-63, 2013-02-15
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 IR 当院でのステント型血栓回収デバイスによる初期治療経験
- 著者
- 榎本 年孝 吉岡 努 高木 勇人 桑野 幸 喜友名 扶弥 平田 陽子 後藤 聖司 藤井 健一郎 継 仁 東 登志夫 井上 亨
- 出版者
- 9日本赤十字社医学会
- 雑誌
- 日赤医学 = The Japanese Red Cross medical journal (ISSN:03871215)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.467-472, 2015-09-01
- 著者
- 友利 幸之介 大野 勘太 東 登志夫
- 出版者
- 日本作業療法士協会 ; 1982-
- 雑誌
- 作業療法 = Japanese occupationai therapy researh : JOTR (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.94-102, 2014-04
1 0 0 0 OA メンタルプラクティスの効果的な実践方法の開発に向けた神経生理学的検討
メンタルプラクティス(MP)の実践においては対象者が運動イメージ(MI)を鮮明に想起していることが前提となるが, 1人称MIを想起することは容易ではない.そのため,効果的なMPを実践するには,この1人称MIの鮮明度を十分に確保する必要がある.本研究では対象者が1人称のMIを想起する際に,想起する課題に関する感覚情報を提示することで,1人称MIの鮮明度が強化されるという仮説を立て,大脳皮質運動野興奮性の変化と主観的なMI鮮明度評価の観点から検証した.その結果,動作に関連した聴覚情報や視覚情報の負荷した条件では対象者の主観的なMIの鮮明度を高め,またMI中の大脳皮質運動野の興奮性も高値を示した.