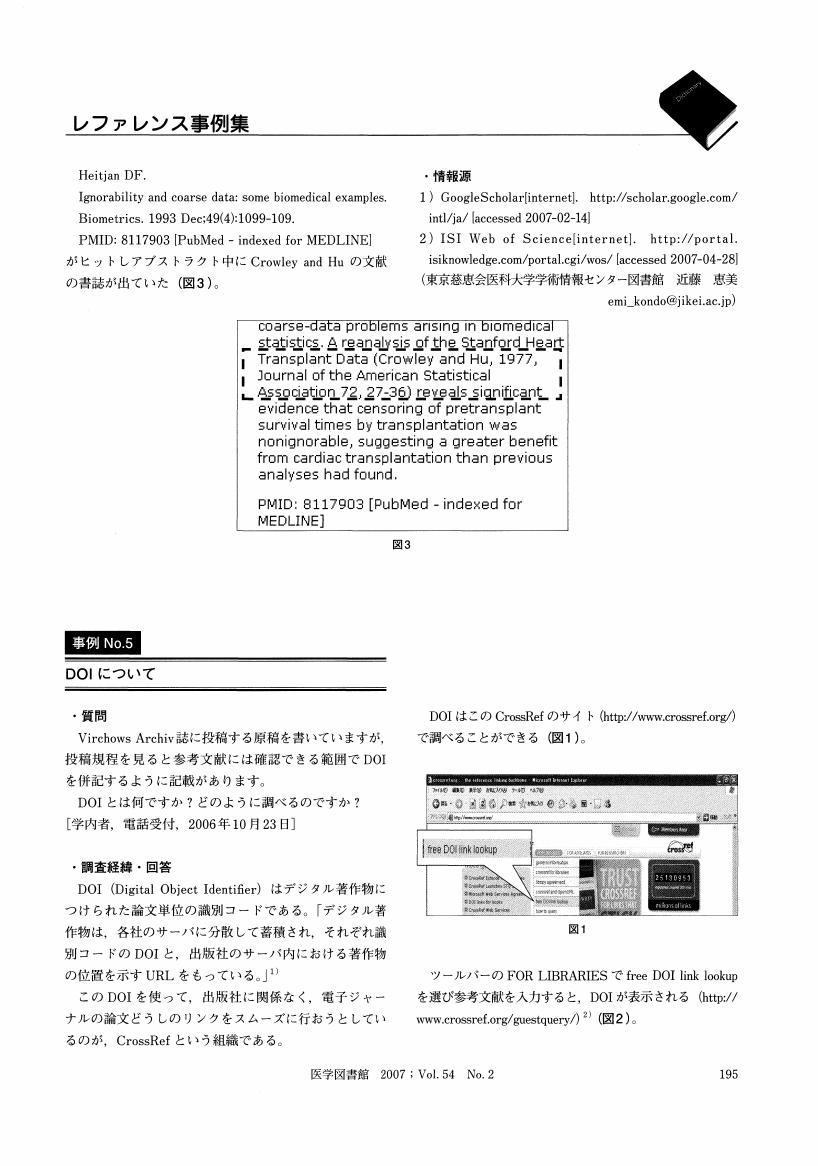1 0 0 0 OA 乳癌集団検診におけるコンタクト・サーモグラフィーの有用性と限界の検討
- 著者
- 清水 哲 横山 日出太郎 松川 博史 城島 標雄 有田 峯夫 須田 嵩 五島 英迪 松本 昭彦 田中 耕作 萩原 明 井出 研 近藤 庸人
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.7, pp.923-927, 1985-07-25 (Released:2009-02-20)
- 参考文献数
- 6
乳癌集団検診の二次検診において,コンタクトサーモグラフィーを,マンモグラフィー,エコーグラフィーと共に補助診断法として用い,その有用性,限界について検討を行なった.使用したサーモブレートは,イタリアFinpat社製 “Breast Thermo Detector” であり今回は特に,腫瘤部の温度の高低に注目して診断した.その結果,乳癌症例の正診率は全体で68%, T>2cmでは86%, T〓2cmでは38%であった.病理組織学的には,線維腺腫,乳腺のう胞腫との鑑別は容易であったが,乳腺症との鑑別は難しかった.したがって,コンタクトサーモグラフィーは乳癌の精密検査法としての利用価値は低いとおもわれた.しかし,触診の補助診断法として用いることにより,手軽で安価な検査法としての利用価値があるのではないかと考えられた.
1 0 0 0 OA 進学準備教育の研究-学習塾・家庭教師等に関する調査報告-
- 著者
- 近藤 大生 野垣 義行 原田 彰 高旗 正人
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.239-255, 1963-10-20
<Aim>__-: "Gakushujuku" and tutors outside the formal school system of Japan have been so widely used to prepare the adolescent for entrance examinations that they are now recognized as one of the major problems of socio educational significance. In Hiroshima where this survey was taken this phenomenon is most prevalent. It was the aim of this study to make clear the actual situation by analyzing the attitudes of the children, the parents and of the teachers in using "gakushujuku" and/or tutors. <Method>__-: This survey was taken in Hiroshima in December, 1962. To carry out our purpose, we questioned children (9 to 17 years of age), parents and teachers in primary and secondary schools totaling approximately 7,000. <Findings>__-: 1) Extent to which "gakushujuku" and tutors are utilized varies significantly with children's grade and sex, parents' occupation as well as schooling, income and level of education expected of the children. 2) About thirty per cent of the parents who utilize them for their children point out the successfully passing of entrance examinations as the prime motive 3) About half of the teachers whom we questioned regard this phenomenon as one of the serious socio-educational problems. 4) Many parents, if not most, look upon "gakushujuku" and tutors as a means of ensuring higher education for their children. *Gakushujuku" is a small private informal school where children go to do their homework and prepare themselves for entrance examinations.
1 0 0 0 タマガイ類の捕食活動の進化学的研究
1.“生きている化石"モクレンタマガイの解剖学的研究を行った結果、この巻貝は原始的な神経系をもち、多くの点で淡水性のリンゴガイ科の巻貝に近縁であることが明らかとなった。また、モクレンタマガイは肉食性ではなく、植物食であったことが明らかとなった。この発見により、タマガイ類は白亜紀中頃に出現し、従来三畳紀から知られているモクレンタマガイ類とは類縁が薄く、しかもそれらは他の貝類に穿孔して捕食しなかったと考えられる。その結果、タマガイ類とその捕食痕の化石記録は調和的となり、従来のタマガイ類の捕食の起源についての2説のうち、白亜紀中期起源説が正しいことがわかった。2.タマガイ類の捕食痕を調査した結果、それらの中には他の原因で似たような穴ができることがわかった。1つはカサガイ類による棲い痕で、白亜紀のアンモナイトの殼表面に多く見つかった。これらは小型のカサガイ類が殼表面の1ヶ所に定住する為、その部分が殼形と同じ形に凹むためにできたと思われる。穴はタマガイ類の不完全な捕食痕のようにパラボラ形で中央がやや凸となるが、形は大きくやや不規則な点などで区別ができる。従来、モササウルスの噛み痕といわれているプラセンチセラス属アンモナイトの穴も同じ起源と考えられる。その他、無生物的にタマガイ類の捕食痕に似た穴ができることもわかった。3.巻貝各種のタマガイ類の捕食痕を調査した結果、殼形により捕食の様式が異なる1例を見出した。これは巻貝の殼形態が長く伸長することが捕食から身を守る適応形態となっていることである。つまり、殼の伸長度と捕食痕の数の頻度を調べた結果、殼形が長くなると捕食痕数も増加することがわかった。従来捕食痕をもつ個体の頻度で捕食圧を推定した研究例は再評価する必要がでてきた。
- 著者
- 近藤 良三
- 出版者
- 日本電気
- 雑誌
- NEC技報 (ISSN:02854139)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.p59-65, 1986-01
1 0 0 0 Fractional facial rejuvenation
- 著者
- 山下 理絵 松尾 由紀 近藤 謙司
- 出版者
- オプトロニクス社
- 雑誌
- Medical photonics
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.46-51,9, 2015-01
1 0 0 0 IR フィボナッチ数列と複素力学系
- 著者
- 川部健 近藤芳朗
- 出版者
- 津山工業高等専門学校
- 雑誌
- 津山工業高等専門学校紀要 (ISSN:02877066)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.25-33, 2000-01-04
1 0 0 0 OA 神社仏閣江戸名所百人一首
1 0 0 0 OA 物理近説
- 著者
- 飯盛挺造, 近藤耕蔵 編
- 出版者
- 飯盛挺造[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1908
1 0 0 0 OA 九州の地名
- 著者
- 近藤 忠
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.31-41,83, 1950-04-30 (Released:2009-04-28)
Place names are so closely connected with topography that it is very interesting to investigate them by means of the maps.Place name of “Tsuru” …… Many of them are found in Kyushu especially. There are 258 names on the topographical map of 1/50, 000. Originally it means an alluvial plain on the river. When number of settlements was a few, simple name of “Tsuru” can be distinguished from each other. But as the plain has developed, other words were added to “Tsuru” to distinguish itself from others. These surfaced-words were “ue” (upper) “naka” (middle) and “shimo” (lower) (18% of the whole added word), “higashi” (east) “minami” (south), “nishi” (west) and “kita” (north) (3%), “dai” (greater) “ko” (smaller) (6%), name of plantation (12%), name of animal (rare), those words referring to topography (slope, between the rivers, river, cape, hill). They are found mainly in Oita and Miyazaki Prefecture and also in Fukuoka, Kumamoto and Kagoshima Prefecture. That is, they are found in the central part of Kyushu especially on the eastern side of it, facing to the Bungo Straight.Place name of “Koba” …… It means the cultivated land in the forest. There are 147 names on the topographical map of 1/50, 000. In Tsushima Isl, the mountain agriculture is called “Kobazukuri” (burning cultivation) and it makes us infer that this place name is related to the mountain agriculture in Kyushu before Meiji Era. Like the place name of “Tsuru”, in general, an additional word was connected with “Koba” to make a compound word. They are distributed in a group in eastern Kyushu. But its predominant area is differrent from that of “Tsuru”. The place name of “Tsurukoba” is found also in the southern Kumamoto prefecture, connecting with the area of “Tsuru”.Place name of “Muta” …… 125 names on the 1/50, 000 topographical map. They are distributed in Saga Prefecture, the Tsukushi Plain, the Kumamoto Plain and southern part of Kyushu, that is, between the “Tsuru” area and the “Koba” area in both districts. It means a marshland originally, but at present time those places do not always keep the original characteristic of this name. Additional words are “upper”, “middle” and “lower” and “east”, “south”, “west” and “north”, which are found at the same percent (9%) of the total. Here the place name of “Tsuru” and “Koba” are also mixed, but they scarecely added “east”, “south”, “west” and “north” as the additional words. This is because the place name of “Muta” is much found on the largest plains in Kyushu stretching eastwards from north of the Ariake Bay where water ways are diversed and formed net -like landscape.
1 0 0 0 「考古背景」法からみる殷周境界問題 : 王朝交替と「もの」・現象
- 著者
- 近藤 はる香
- 出版者
- 日本中国考古学会
- 雑誌
- 中国考古学 = Chinese archaeology (ISSN:13490249)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.69-84, 2014-12
1 0 0 0 OA ムガル朝時代のインド洋と日本
- 著者
- 近藤 治
- 出版者
- 追手門学院大学
- 雑誌
- 追手門学院大学文学部紀要 (ISSN:03898695)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.137-153, 1994-06-30
1 0 0 0 OA 選択公理
- 著者
- 近藤 基吉
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.13-27, 1965-07-20 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 28
- 著者
- 宇川 諒 今谷 潤也 森谷 史朗 近藤 秀則 林 正典
- 出版者
- 中部日本整形外科災害外科学会
- 雑誌
- 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 (ISSN:00089443)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.1367-1368, 2013-11-01 (Released:2014-01-31)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 修正主義をこえて(史学会第一〇〇回記念大会講演要旨)
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人史学会
- 雑誌
- 史學雜誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.12, pp.1986-1988, 2002-12-20
- 著者
- 近藤 孝弘
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.187-199, 2014-06-30
歴史教育を論じる際に、国民国家とグローバリゼーションを対立的にのみ捉えるのは不適切である。前者は後者を軸に展開した近代史の中で発展を遂げたのであり、歴史教育には既に両者間の緊張を含む深い結びつきが刻印されている。世界の変容を踏まえ、従来の形に修正を重ねつつ民主国家を担う政治的市民を育成するという課題に取り組んできたドイツの例は、歴史教育の課題について長期的視野から再考する必要性を訴えている。
1 0 0 0 IR 算数・数学教育の目標としての「算数・数学の力」の構造化に関する研究
- 著者
- 長崎 栄三 国宗 進 太田 伸也 五十嵐 一博 滝井 章 近藤 裕 熊倉 啓之 長尾 篤志 吉川 成夫 久保 良宏 上田 雅也 牛場 正則 日下 勝豊 塩野 友美 島崎 晃 島田 功 榛葉 伸吾 西村 圭一 早川 健 藤森 章弘 牧野 宏 松元 新一郎 望月 美樹 森 照明 藤村 和男 半田 進 家田 晴行 松田 泉 浅沼 健一 小俣 弘子 清水 壽典 村越 新 安部 浩一 飯嶌 一博 久永 靖史 山根 浩孝 山口 啓
- 出版者
- 公益社団法人日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.4, pp.11-21, 2008-04-01
- 被引用文献数
- 5
算数・数学教育における新たな目標として「算数・数学の力」を考えた.算数・数学の力とは,算数・数学のあらゆる活動に関わるはたらきで,大きく「算数・数学を生み出す力」,「算数・数学を使う力」,「算数・数学で表す力」,「算数・数学で考え合う力」の4つの力で構成される.初めに,我が国の算数・数学科の教育課程の史的分析,算数・数学のカリキュラムの国際比較,算数・数学教科書の研究,数学的な考え方・問題解法の史的分析,社会の算数・数学教育に関する意識の分析を行った.その上で,算数・数学教育の目的・目標に算数・数学の力を位置付けた.そこでは,算数・数学教育の目標を概念理解と能力習得とで均衡を図った.そして,算数・数学の力を,算数・数学的内容との一体化,算数的活動・数学的活動の重視などの原則の下で構造化し,その質の高まりを具体化するための算数・数学の力の水準の重要性を指摘した.
1 0 0 0 賀茂真淵と菅江真澄 : 三河植田家をめぐって
- 著者
- 近藤 金助 林 常孟 松下 〓
- 出版者
- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.354-361, 1927
以上論述した事柄を要約すれば次のやうである<br> 1. 私等はRice-glutelin No. 1.及びNo. 2.に就て其の最適雪出點に及ぼすNaCH<sub>3</sub>COO, NaCl, KCl及びLiClの影響に就きて研究した<br> 2. 其の結果によれば是等の鹽類の存在はRice-glutelinの最適雪出點を等しく酸性の側に變移せしめるそして其の程度は鹽類の濃度によつて一定しない醋酸曹達に就ても同樣であるこのことはMichaelis氏の所論とは一致しないのみならず最適雪出は完全雪出を意味しない<br> 3. 私等はこの事實を此等鹽類より由来する正負兩イオンの蛋白質イオン化力の優劣の差によつて説明し得た但しこの力は鹽類の種類と濃度及び蛋白質の種類によつて特殊なものである<br> 4. 從つて難溶性蛋白質の見かけ上の等電點は試用する鹽類の種類及び濃度によつて不同でてると私等は思ふ
1 0 0 0 OA DOIについて
- 著者
- 近藤 恵美
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本医学図書館協会
- 雑誌
- 医学図書館 (ISSN:04452429)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.195-196, 2007-06-20 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 3