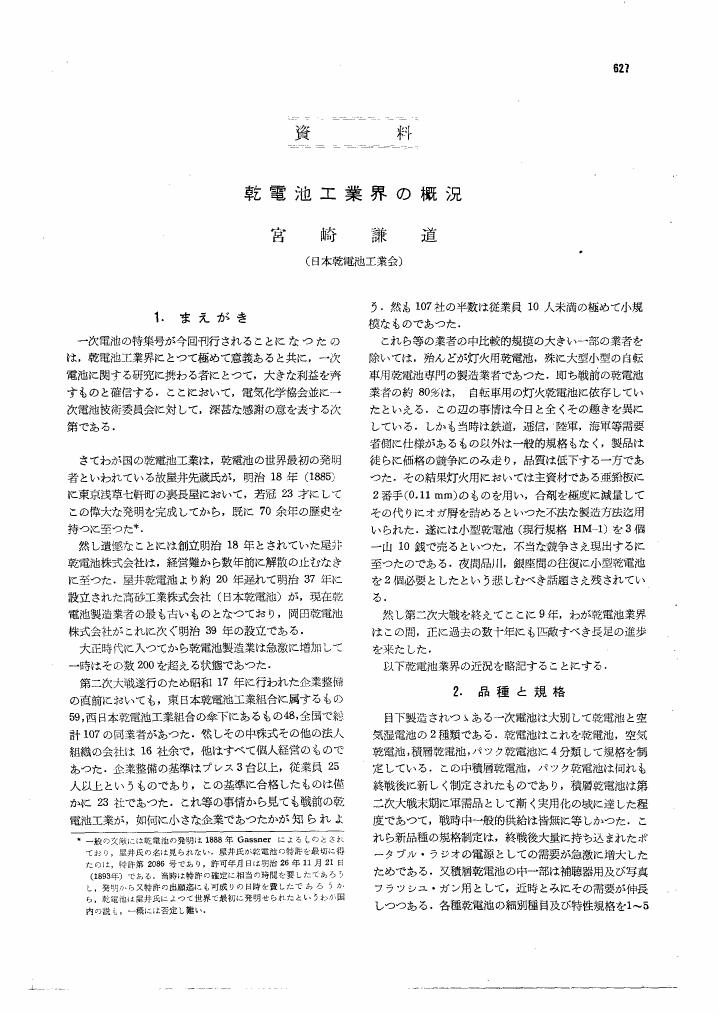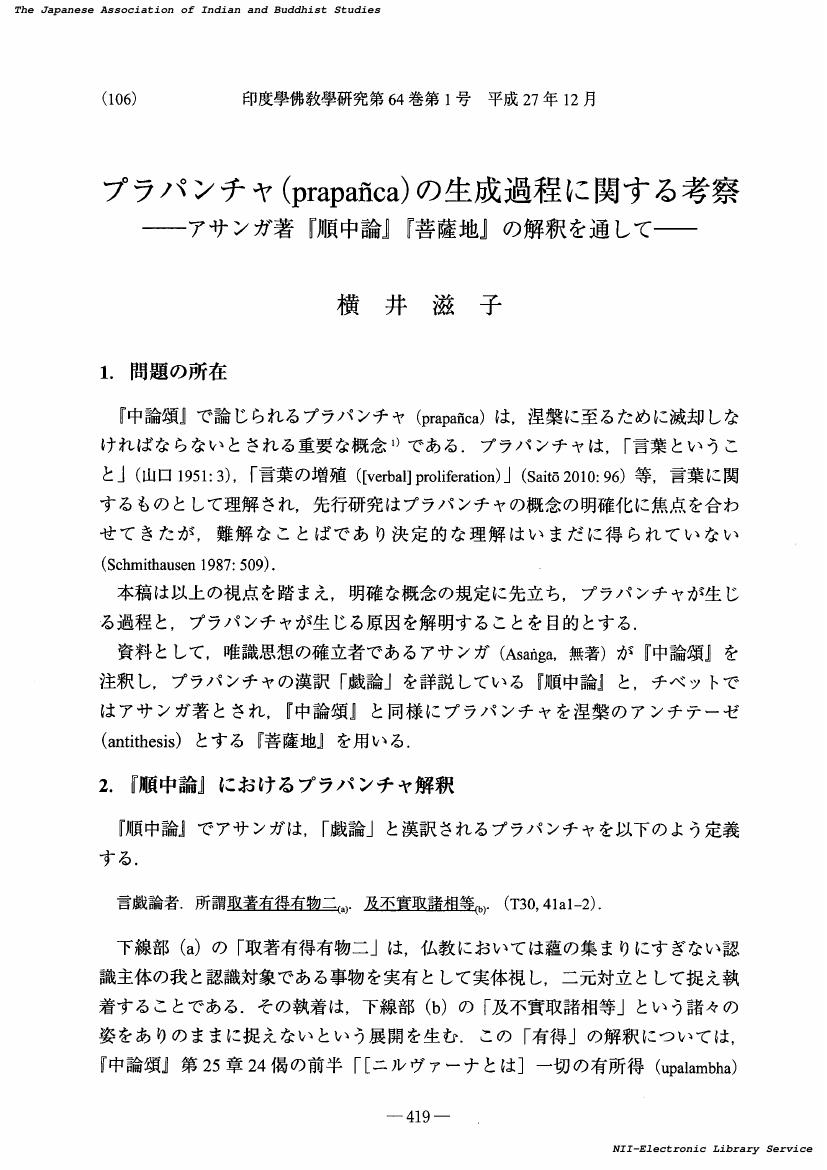1 0 0 0 IR 訳注晋書刑法志-11(完)-
- 著者
- 内田 智雄
- 出版者
- 同志社法學會
- 雑誌
- 同志社法学 (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.49-75, 1961-10
資料
- 著者
- 戸田浩
- 雑誌
- C MAGAZINE
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, pp.38-68, 2001
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 井上篤太郎翁
- 著者
- 井上篤太郎翁伝記刊行会 編
- 出版者
- 井上篤太郎翁伝記刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1953
1 0 0 0 OA 応天門の変と『伴大納言絵巻』 : 記録と記憶の間
- 著者
- 仁藤 智子
- 出版者
- 国士舘大学日本史学会
- 雑誌
- 国士舘史学 = Kokushikan-Shigaku
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.1-39, 2015-03-20
1 0 0 0 OA 嚥下時に前腕を置く机の高さが舌骨上筋群の筋活動に与える影響
- 著者
- 鈴木 哲 小田 佳奈枝 高木 由季 大槻 桂右 渡邉 進
- 出版者
- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.25-30, 2011-04-30 (Released:2020-06-25)
- 参考文献数
- 14
【目的】嚥下時に前腕を置く机の高さが舌骨上筋群の筋活動に与える影響を検討し,嚥下時の姿勢調節に関する基礎的な情報を得ることを目的とした.【方法】健常者10 名を対象に,机無し条件(両上肢下垂位)と,前腕を机上に置いた机有り条件A(差尺が座高の3 分の1 の高さ),机有り条件B(座高の3 分の1 に15 cm 加えた高さ)の3 条件で,全粥(5 g)を嚥下させ,その際の舌骨上筋群の表面筋電図,主観的飲みにくさ,肩甲帯挙上角度を測定した.舌骨上筋群の表面筋電図から,嚥下時の筋活動時間,筋活動積分値,嚥下開始から最大筋活動までの時間を算出した.各机有り条件の各評価・測定項目は,机無し条件を基準に正規化し,机無し条件からの変化率(% 筋活動時間,% 筋活動積分値,% 最大筋活動までの時間,% 主観的飲みにくさ)を算出した.机無し条件と2 種類の高さの机有り条件間における各評価・測定項目の比較,2 種類の高さの机有り条件間における肩甲帯挙上角度の比較,および各評価・測定項目の机無し条件からの変化率の比較には,Wilcoxon の符号付き順位和検定を使用し検討した.【結果】机無し条件と比べ,机有り条件A では,舌骨上筋群の筋活動時間,最大筋活動までの時間は有意に短く,筋活動積分値,主観的飲みにくさは有意に低かったが,机有り条件B では有意な差はみられなかった.机有り条件A における肩甲帯挙上角度は,机有り条件B と比べ,有意に高かった.机有り条件Aにおける%筋活動時間,%最大筋活動までの時間,%筋活動積分値,%主観的飲みにくさは,机有り条件B に比べ,有意に低かった.【結論】本研究結果から,嚥下時に前腕を置く机の高さは,舌骨上筋群の筋活動に影響を与えることが示唆された.頸部や体幹の姿勢調節に加えて,前腕を置く机の高さを適切に調節することは,嚥下時の姿勢調節のひとつとして有用となる可能性があると考えられた.
1 0 0 0 OA 飼料カブにおける計量育種に関する実験的研究
- 著者
- 福岡 壽夫
- 出版者
- 農林省北陸農業試験場
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.127-215, 1982 (Released:2011-03-05)
1 0 0 0 カタハリグモの生活史および隠れ帯二型の出現頻度の季節変化
- 著者
- 渡部 健
- 出版者
- 日本蜘蛛学会
- 雑誌
- Acta arachnologica : organ of the Arachnological Society of Eastern Asia (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1-12, 2000-07-31
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA R.シュタイナーの子ども観 -発達と気質の側面から-
- 著者
- 鈴木 そよ子
- 雑誌
- 国際経営フォーラム (ISSN:09158235)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.121-140, 2018-12-25
自由ヴァルドルフ学校は、1919年にドイツのシュトゥットガルトにおいて設立された。2017年現在では、1092校を数える。本稿では、ヴァルドルフ学校の指導者ルドルフ・シュタイナーの子ども観のうち、発達の段階と課題、そして、気質の観点からそれぞれの特徴と働きかけ方について考察する。 シュタイナーは、子どもの発達段階を3期に分けて捉えている。 第一期:誕生から歯の生え替わる時期まで(およそ0 ~ 7歳) 第二期:歯の生え替わる時期から性的成熟期まで(およそ7 ~ 14歳) 第三期:性的成熟期以降(およそ14~ 21歳) シュタイナーの発達観によれば、第一期には想像力を豊かにすること、第二期には訓練された想像力の基盤に立って、感情・意志などの心的諸力を豊かにすることが十分なされて初めて、第三期に入ったのち、悟性概念を用いた的確な思考・判断が可能になるのである。 また、シュタイナーは、気質学の観点から子どもを把握するが、多血質、憂鬱質、粘液質、胆汁質の四気質が個々の性格を構成していると捉える。教師に求められた、子ども理解及び子どもへの働きかけ方は3点にまとめられる。 第一点は、四気質の特徴を把握すること。 第二点は、教師自身が子どもの中で、優位を占めている気質を受け入れることによって、気質の短所を長所に変えていくこと。第三点は、教師自身の働きかけと並行して、子どもたち同士の影響力・同化力を十分に活かすためのグループ作りを工夫すること。
1 0 0 0 OA 乾電池工業界の概況
- 著者
- 宮崎 謙道
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- 電氣化學 (ISSN:03669440)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.11, pp.627-631, 1954-11-05 (Released:2019-11-15)
1 0 0 0 OA プラパンチャ(prapanca)の生成過程に関する考察
- 著者
- 横井 滋子
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.419-416, 2015-12-20 (Released:2017-09-01)
1 0 0 0 OA アルミニウム合金の電食
- 著者
- 東海林 喜雄
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 金属表面技術 現場パンフレット (ISSN:03685527)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.11, pp.72-75, 1964-11-15 (Released:2009-10-07)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 子規の和歌・俳句と漢文學
- 著者
- 仁枝 忠
- 出版者
- National Institute of Technology, Tsuyama College
- 雑誌
- 津山工業高等専門学校紀要 = Bulletin of Tsuyama National College of Technology (ISSN:02877066)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.15-44, 1969-03-29
1 0 0 0 OA 片頭痛の有無が与える模様の好みと印象
- 著者
- 藏野 夏海 小山 慎一
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 巻号頁・発行日
- pp.530, 2019 (Released:2019-06-27)
本研究では、片頭痛の有無にかかわらず人々の間で視覚的パターンの好みと印象評価を比較した。 片頭痛を持つ人々は親子牡丹唐草や荒波のパターンを好んだが、片頭痛を持たない人々はストライプや格子のような幾何学的パターンを好む傾向にあった。 印象評価では、片頭痛の人は幾何学模様の方が目が痛く感じたと報告している。 生活環境では、感覚の多様性を考慮し、インテリアデザインの模様パターンを慎重に選択する必要がある。
1 0 0 0 IR 職業運転手における脳卒中後の復職状況の調査
- 著者
- 川上 敬士 渡辺 容子 小林 康孝
- 出版者
- 新田塚学園福井医療短期大学
- 雑誌
- 福井医療科学雑誌 (ISSN:24240176)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.10-13, 2019
【目的】脳卒中に罹患した職業運転手の復職状況を把握すること.【対象と方法】対象は2015年から2018年までに脳卒中罹患のため当院に入院または通院し,自動車運転評価を実施した患者のうち,脳卒中罹患前に職業運転を行っていた7名.カルテからの基本情報抽出と,本人または家族へ電話にて退院後の復職状況を調査した.【結果】7名中6名が復職しており,うち2名は原職復帰し,4名は配置転換していた.産業医の関わりがあったのは1名のみであり,他6名は企業の上司による技術確認で職業運転再開の可否が決定されていた.そのため,対応には企業毎にばらつきがみられた.また,発症から1年以内に運転業務を再開した3名中2名が脳出血再発を起こしていた.【考察】現在の日本では,職業運転手の復職に際し明確な判断基準がないため企業毎に対応せざるを得ない状況である.今後,職業運転の再開に対する明確な判断基準を構築していく必要があると考える.
1 0 0 0 就労年齢で発症した脳卒中患者の復職状況
- 著者
- 佐々木 誓子 岡部 孝生 岡田 耕平
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.E1104, 2007
【はじめに】<BR> 本邦における脳卒中患者の平均復職率は約30%とされる。しかし、脳卒中患者の復職率は、地域により社会情勢及び医療状況が異なるため、国別はもちろん国内においても地域格差がある。そこで今回、当院における復職状況を把握することを目的にアンケート調査とカルテより後方視的に調査を行った。<BR>【対象】<BR> 対象は2001年1月~2005年12月までの過去5年間に当院を退院した脳卒中患者のうち、退院時年齢が60歳以下の256名(男性187名、女性69名、年齢は53.0±6.1歳)とした。<BR>【方法】<BR> まず、予め作成した調査用紙を用いて復職に関するアンケート調査を郵送法により行った。次に、対象者の入院カルテより1)診断名、2)障害側、3)Brunnstrom stsge(Br-Stage:下肢)、4)感覚障害の有無(下肢)、5) 高次脳機能障害の有無、6)歩行自立度(屋内)、7)Barthel index(BI) の7項目について抽出した。なお、今回は各項目とも退院時のものを採択した。アンケート回収後、対象者を復職群と非復職群の2群に分け、前述 した7項目について、カイ2乗検定、対応のないT検定を用い比較検討した。<BR>【結果】<BR> 有効回答数は114名(有効回答率=46%)であった。その中で、発症前に就労していなかった者12名を除外した102名中の復職者は43名(42%)であった。まず、1)診断名は復職群が脳出血20名、脳梗塞26名、クモ膜下出血4名、非復職群は脳出血37名、脳梗塞26名、クモ膜下出血8名となり有意差は認めなかった。2)障害側は、復職群が右片麻痺17名、左片麻痺20名、その他5名、非復職群は右片麻痺24名、左片麻痺24名、その他12名となり有意差は認めなかった。3)Br-stageは、復職群がI・II 2名(5%)、III・IV 6名(14%)、V・VI 34名(81%)、非復職群はI・II 5名(8%)、III・IV 35名(58%)、V・VI 20名(33%)となり有意差を認めた(p<.05)。4)感覚障害は、復職群が正常23名、鈍麻19名、脱失0名、不明0名、非復職群は正常22名、鈍麻33名、脱失1名、不明4名と有意差は認めなかった。5)高次脳機能障害は復職群で高次脳障害を認めた者6名(14%)、認めなかった者36名(86%)、非復職群で認めた者33名(55%)、認めなかった者27名(45%)となり有意差を認めた(p<.01)。6)歩行自立度は復職群自立40名、介助2名、非復職群自立46名、介助14名となり退院時に有意差は認めなかった。7)BIに関して復職群は98.0±6.2点、非復職群87.8±22.5点となり有意差を認めた(p<.01)。<BR>【考察】<BR> 今回の結果は脳卒中患者の復職率が42%と、本邦の平均値より高い結果であった。復職に至ったものは、身体機能面はもちろん移動だけでなく日常生活動作等の能力面においても能力が高い者が復職していることが考えられた。<BR>
1 0 0 0 脳卒中の職業復帰:―予後予測の観点から―
- 著者
- 杉本 香苗 佐伯 覚
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.10, pp.858-864, 2018
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 相原 彩⾹ ⾕村 厚⼦
- 出版者
- 日本保健科学学会
- 雑誌
- 日本保健科学学会誌 (ISSN:18800211)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.24, 2018
【⽬的】回復期病院に⼊院中の脳卒中患者を対象に⾯接を実施し,退院後⽣活に関する認識の要因を検討した1 事例を取り上げ報告する.【⽅法】回復期病院に⼊院し,⾃宅退院予定の50 歳代男性の初発脳卒中患者に対し,退院後⽣活の認識について半構造化⾯接を3 回実施した.データ分析には複線経路等⾄性モデル(Trajectory Equifinality model:以下TEM)を⽤い、退院後⽣活の認識を等⾄点として描いた.得られたデータを試作的なTEM 図として描き可視化し,2 回⽬以降の⾯接で対象者に呈⽰した.筆頭筆者の解釈に誤りがないか,不明確な内容や疑問点を対象者と確認・修正することでデータの信頼性を担保し,TEM 図を完成させた.【結果】対象者の語りから,Ⅰ期「社会と距離を置く」Ⅱ期「⼀度は改善を実感するが復職への不安が募る」Ⅲ期「外泊により退院後⽣活のイメージが具体的に湧く」Ⅳ期「障害を受け⼊れ付き合っていく」のⅠ〜Ⅳに区分されたTEM図が描けた.【考察】脳卒中患者の退院後⽣活の認識に関わる要因をTEM図で描くことで,⼼⾝機能の回復だけを⽬的とした⽀援を提案するのではなく,その⼈の社会との関わりや思いの変化の時期を理解し捉えた上で⽀援を提供する重要性,さらにその⼈が経験する出来事の気持ちの変化や受け⽌め⽅を捉え働きかけることが,退院後⽣活の認識を促進し,障害と向き合うことに繋がると考えられた.
1 0 0 0 勧修寺大法房実任における法流授受と年譜
- 著者
- 増山 賢俊
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.105-121, 2015