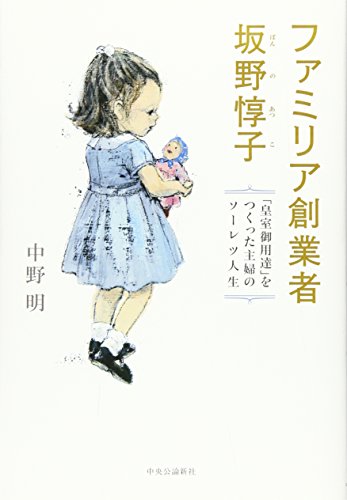- 著者
- 木村 真二 藤田 健太 石隈 慎一郎 白岩 真弥 豊田 英里 浦川 聖太郎 佐藤 文衛 伊藤 洋一 時政 典孝 向井 正
- 出版者
- 日本惑星科学会
- 雑誌
- 日本惑星科学会秋季講演会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.88-88, 2005
1995年に初めて我々の太陽以外の恒星の周りを回る惑星、太陽系外惑星が発見されて以来、その数は現在までに160個に達している。太陽系外惑星の検出方法はいくつかあるが代表的なものとしては、ドップラーシフト法とトランジット法がある。我々はすばる望遠鏡でのドップラーシフト法による観測から視線速度に変化の見られる天体を、西はりま60cm望遠鏡を用いて観測し、トランジットの検出を試みている。今回は、西はりまでの観測においてトランジット検出に十分な測光精度を得られたことを報告し、さらにいくつかの天体の観測・解析結果を示す。
- 著者
- 竹内 拓 Velusamy Thangasamy Lin Douglas N. C.
- 出版者
- 日本惑星科学会
- 雑誌
- 日本惑星科学会秋季講演会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp.54-54, 2004
高精度位置天文学によって星のふらつきを検出することにより系外惑星を発見することが、可能となりつつある。NASAの計画する位置天文衛星(SIM)は、150pc彼方にある原始惑星さえも発見できると期待されている。しかし、原始惑星には原始惑星系円盤も伴っていると考えられ、円盤からの光が位置測定の障害となる可能性がある。円盤がどの程度の影響をもたらすか見積もり、それが無視できる程度であることを示した。
2 0 0 0 OA アリストテレス自然学に対するビールーニーの疑問
- 著者
- 鈴木 孝典
- 出版者
- 東海大学
- 雑誌
- 総合教育センター紀要 (ISSN:13473727)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.43-57, 2004-03-30
2 0 0 0 ドイツ的給付行政論の問題性:福祉と治安 序説
- 著者
- 高田 敏
- 出版者
- The Japanese Association of Sociology of Law
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.1969, no.21, pp.50-82,218, 1969
Inhaltsübersicht<br>1. Die Fragestellung<br>a) Peitsche und Zuckerbrot.<br>b) Der Gegenstand dieses Aufsatzes.<br>2. Die Entstehung der Theorie der Leistungsverwaltung<br>a) Der Dualismus der Verwaltung im bürgerlich-liberalen Rechtsstaat: die hoheitliche Verwaltung und die fiskalische Verwaltung.-Die Teilung der hoheitlichen Verwaltung in die obrigkeitliche Verwaltung bzw. die Eingriffsverwaltung und die schlicht-hoheitliche Verwaltung unter der Weimarer Verfassung.<br>b) Ernst Forsthoffs "Die Verwaltung als Leistungstäger" vom 1938.<br>c) Die Problematik der Forsthoff'schen Theorie der Leistungsverwaltung.<br>3. Die Entwicklung der Theorien der Leistungsverwaltung nach dem 2. Weltkrieg<br>a) Die Wandlung der Forsthoff'schen Theorie der Leistungsverwaltung.<br>b) Der Begriff der Leistungsverwaltung.<br>c) Der Sozialstaatsgedanke als Grundlage der Theorie der Leistungsverwaltung.<br>4. Die Leistungen und die öffentliche Sicherheit<br>a) Die Leistungsverwaltung und die Sicherheitspolitik in einigen Sozialstaatstheorien.<br>b) Die Problematik der Theorie der Leistungsverwaltung. Die Rollen, die die Theorien der Leistungsverwaltung spielen.-Die Problematik des Begriffs der Leistungsverwaltung.-Die Probleme der Rechtsdogmatik um das sog. Leistungsverwaltungsrecht.
- 著者
- Utaroh Motosugi Diego Hernando Curtis Wiens Peter Bannas Scott. B Reeder
- 出版者
- 日本磁気共鳴医学会
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2016-0081, (Released:2017-02-13)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 9
Purpose: To determine whether high signal-to-noise ratio (SNR) acquisitions improve the repeatability of liver proton density fat fraction (PDFF) measurements using confounder-corrected chemical shift-encoded magnetic resonance (MR) imaging (CSE-MRI).Materials and Methods: Eleven fat-water phantoms were scanned with 8 different protocols with varying SNR. After repositioning the phantoms, the same scans were repeated to evaluate the test-retest repeatability. Next, an in vivo study was performed with 20 volunteers and 28 patients scheduled for liver magnetic resonance imaging (MRI). Two CSE-MRI protocols with standard- and high-SNR were repeated to assess test-retest repeatability. MR spectroscopy (MRS)-based PDFF was acquired as a standard of reference. The standard deviation (SD) of the difference (Δ) of PDFF measured in the two repeated scans was defined to ascertain repeatability. The correlation between PDFF of CSE-MRI and MRS was calculated to assess accuracy. The SD of Δ and correlation coefficients of the two protocols (standard- and high-SNR) were compared using F-test and t-test, respectively. Two reconstruction algorithms (complex-based and magnitude-based) were used for both the phantom and in vivo experiments.Results: The phantom study demonstrated that higher SNR improved the repeatability for both complex- and magnitude-based reconstruction. Similarly, the in vivo study demonstrated that the repeatability of the high-SNR protocol (SD of Δ = 0.53 for complex- and = 0.85 for magnitude-based fit) was significantly higher than using the standard-SNR protocol (0.77 for complex, P < 0.001; and 0.94 for magnitude-based fit, P = 0.003). No significant difference was observed in the accuracy between standard- and high-SNR protocols.Conclusion: Higher SNR improves the repeatability of fat quantification using confounder-corrected CSE-MRI.
- 著者
- 岸 俊光
- 出版者
- 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科出版・編集委員会
- 雑誌
- アジア太平洋研究科論集 (ISSN:13466348)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.21-39, 2015-09
2 0 0 0 OA 小児領域の理学療法について
- 著者
- 齋藤 悟子 齋藤 翔吾 八重樫 淑子 佐藤 房郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.28-35, 2016 (Released:2016-04-21)
- 参考文献数
- 9
2011年に日本理学療法士協会より理学療法診療ガイドライン第1版が公表され,小児領域では脳性麻痺の理学療法について掲載された。しかし,日本の救命医療の進歩により,小児領域の理学療法では,脳性麻痺のみならず,発達遅滞,視覚障害,聴力障害,てんかん,注意欠如や多動性障害,呼吸器障害など対象は多様となる。また,様々な理由により長期入院となる児や,退院後も在宅酸素療法,気管切開,人工呼吸器,経管栄養などの医療的管理を継続しなければならない児が問題となっている。さらに当院は,2013年に小児がん拠点病院に指定され,小児がんの子どもに対するリハビリテーションニーズが高まっている。小児領域のリハビリテーションは,長期にわたることが少なくないため,理学療法士は身体面のみならず心理的サポートを担う役割が求められ,児を取り巻く環境すべてを考慮し,関わる人すべてと協働し,専門分野の枠組みを超えて,協働体制を確立していく必要がある。また,小児領域の理学療法は,個別性が求められ画一的な介入が困難な側面がある。介入の妥当性について,科学的根拠を示すことが困難であるが,それに向き合って行くことが私たちの責務である。「小児期」についての考え方は様々であるが,今回は当院小児科入院した子どもを対象とした。その中から,発展的に介入しているNICUに入院した早産児や低出生体重児やハイリスク児と,小児がんの子どもに対する理学療法士の取り組みを中心に紹介する。
2 0 0 0 IR 書評 カトーの『農業論』について
- 著者
- 川越 俊彦
- 出版者
- 成蹊大学経済学部学会
- 雑誌
- 成蹊大学経済学部論集 (ISSN:03888843)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.109-112, 2013-12
2 0 0 0 IR 文学が描いた優生手術--ハンセン病患者は「断種」をいかに描いてきたか?
- 著者
- 荒井 裕樹
- 出版者
- 東京大学グローバルCOEプログラム「死生学の展開と組織化」
- 雑誌
- 死生学研究 (ISSN:18826024)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.127-151, 2010-03
論文 ArticlesIn modern Japanese history, eugenic ideas were manifested at their most extreme in sanatoria for the treatment of Hansen's Disease (leprosy). There, "There are no means to support children," and "it's a pity for the child" were given as reasons for the sterilization, abortion, and other eugenic surgeries that had long been performed on the patients. <改行> Putting peremptory, forced eugenic surgeries aside, I take as my topic the cases where patients themselves chose to accept (or had no choice but to accept) the eugenic surgeries. When faced with the serious decision of a eugenic surgery, what logic did patients use to manage their wavering feelings, and persuade themselves to have it done? <改行> In this article I read literary works written by former patients, examining the process through which they accepted the eugenic surgery and the course of their mind. After the war, the importance of the problem of eugenic surgery was often an important theme in patient literature. I believe these works of literature are an important resource for thinking about the above problem.
2 0 0 0 OA 気体中の水晶振動子のインピーダンスと周波数の圧力依存性の比較
- 著者
- 黒河 明 北條 久男 小林 太吉
- 出版者
- 一般社団法人 日本真空学会
- 雑誌
- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.196-198, 2011 (Released:2011-05-17)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
The vibrating quartz oscillator in the viscous-flow gas was observed to compare the pressure (P) dependence between the impedance change (ΔZ) and the frequency change (ΔF). We obtained the ΔZ and the ΔF for Ar, O2, and Ne gases. Among Ar and O2 both the ΔZs and the ΔFs had no intersection with each other. However, Ne gas had the intersections with Ar gas with the ΔZ(P) and with O2 for the ΔF(P). The phenomenon was caused by the Ne property which Ne has smaller mass but larger viscosity compared with Ar and O2. The ΔZ-ΔF property showed that the property of each gas lied in the viscosity descending order, i.e., Ne, Ar, O2. The measurement of (ΔZ, ΔF) property could give the viscosity related information.
2 0 0 0 OA 三次元データに基づく文化財研究と新展示手法の開発-興福寺 国宝阿修羅像を中心に-
- 著者
- 今津 節生 岩佐 光晴 丸山 士郎 浅見 龍介 楠井 隆志 神庭 伸幸 和田 浩 鳥越 俊行 金子 啓明 山崎 隆之 矢野 健一郎 成瀬 正和
- 出版者
- 独立行政法人国立文化財機構九州国立博物館
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2012-04-01
本研究は興福寺の許可を得てX線CT調査で得た国宝 阿修羅像をはじめとする十大弟子像4躯、八部衆像5躯の高精細三次元デーを美術史・工芸史・修復技術・文化財科学・博物館学の専門知識を集めて解析した。私達はX線CTによって得られた三次元画像を観察して議論を進めた。その結果、1270年あまり前に製作された脱活乾漆像の構造や技法、過去の修復履歴などを明らかにした。本研究の結果、阿修羅像の心木は虫食が無い良好な状態であることを確認した。また、鎌倉時代と明治時代の修理の痕跡も把握した。さらに三次元データから阿修羅像の塑土原型像を復元することに成功した。また、最終年度に本研究の成果をまとめた報告書を製作した。
バリ(インドネシア)とラオスにおいては、公的教育機関や私的サークルにおける一対多の舞踊伝承形態を、従来の師と弟子といった一対一の関係の教授形態と比較し、民族舞踊を中心とした伝統芸能の伝承システムの変化について考察した。バリでは、30代から70代の6名の女性舞踊家へのインタヴュー内容を比較検討し、各世代の女性舞踊家の舞踊習得過程を明らかにした上で、民族舞踊の伝承システムの現代的変容が伝統文化に与えた影響について考察した。ラオスでは、国立音楽舞踊学校の現状を調査し、卒業生たちの舞踊家としての将来が、今後の観光業の発展に支配さていることを明らかにした。しかしながら、現時点では、バリでみられるような新しい観光文化の創出には至っておらず、現状では近隣諸国における観光産業の模倣としてのラーマーヤナ復活にとどまっている。日本では、東美濃地域の農村歌舞伎と奥三河花祭りの伝承の現状を調べた。農村歌舞伎は、戦中戦後の中断をはさんで、近年、盛んに演じられるようになっているが、かつて村人の最大の娯楽のひとつであった歌舞伎が、過疎化・少子化の進む現状にあって、行政から地域活性化の機能を担わされていることがわかる。また、奥三河の花祭りでは、過疎化の進む地域を超えて、地域外の伝統芸能に関心を抱く人々によっても伝承され、その一部の人々は実際に祭礼を支えていることが確認された。農村歌舞伎、花祭りのいずれもが、学校教育との関係を築き上げ、教育の一環として地域の伝統を伝承していこうと試みている。日本と、バリ・ラオスにおける民族舞踊伝承の現状における相違は、前者が地域に伝わる伝統芸能をもっぱら地域活性化のために活用しようとしているのに対して、後者は同じく地域の活性化を目的としてはいても、それが現金収入を得るためといった個人的な目的のための手段としても捉えられている傾向が強い点にある。
2 0 0 0 北原白秋と松下俊子--その投獄事件をめぐって
- 著者
- 鈴木 一郎
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 文学 (ISSN:03894029)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, 1961-02
2 0 0 0 OA 冬季の実生活におけるミストサウナ入浴が睡眠に及ぼす影響
- 著者
- 吉田 郁美 竹森 利和 山崎 政人 道広 和美 都築 和代 裏出 良博 吉田 政樹
- 出版者
- 人間-生活環境系学会
- 雑誌
- 人間と生活環境 (ISSN:13407694)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.101-106, 2012-11
ミストサウナ入浴が睡眠に与える影響を把握することを目的に、冬季の実生活において被験者実験を実施した。実験は、被験者の自宅において就寝約1.5時間前に40℃10分間の通常入浴とミストサウナ入浴をそれぞれ10日間ずつ連続して実施した。浴室の設定温度、寝室の温湿度ならびに入浴前後の舌下温を10日間測定・記録した。また、1日の活動量(活動量計)、夜間就寝時の脳波(携帯型1チャンネル脳波計)を計測し、睡眠後の眠気(KSS調査票)や温冷感、目覚めの感覚等を記録した。睡眠効率、入眠潜時、および覚醒指数については条件間に有意な差はなかったが、第一周期デルタパワーについてはミストサウナ入浴の方が通常入浴よりも有意に高かった。入浴による舌下温の上昇度についても通常入浴よりミストサウナ入浴の方が有意に高かった。寝室温・湿度に両条件間の差は無かったが、被験者の申告結果からは、ミストサウナ入浴の場合、就床前はより暖かく感じ、起床時には目覚めの爽央感が得られるとの評価が有意に高かった。
2 0 0 0 戦後日本における社会保障制度の研究
戦後日本における社会保障制度の研究を、毎月二つずつ主題をさだめ、研究代表者の統括のもとで、研究分担者二人がそれぞれの研究をおこない、代表者、分担者全員参加の研究会でこれを発表し、討論をしてもらい、まとめてきた。今年度の毎月の主題はつぎのとおりであった。4月、近代国家の形成と内務省の行政/『厚生省50年史』の作成について。5月、内務省の衛生行政/『厚生省50年史』の作成について(2)。6月、内務省の社会行政、労働行政、社会保険行政/社会保障研究の諸論点。7月、厚生省の創設と厚生行政/戦時体制下の厚生行政。9月、戦時下の衛生行政と社会行政/施設内文化の研究。10月、戦時下の労働行政と社会保険行政/『厚生省50年史』の編集について。11月、戦後復興期の厚生行政/『厚生省50年史』の編集について(2)。12月、戦後復興期の衛生行政/占領政策と福祉政策。1月、戦後復興期の社会福祉行政/社会福祉史の研究方法について。2月、戦後復興期の社会保険行政/老人ホーム像の多様性と統一性。3月、高度成長期の厚生行政(予定)。以上をつうじて、総力戦体制がわが国の福祉国家体制の厚型をつくったこと、明治以後の内務行政と敗戦以後の厚生行政に一部共通する型が認められること、衛生、労働、社会保険、社会福祉の四分野の進展に顕著なタイム・ラグがあることなどがあきらかになり、それぞれの検討が進みつつある。
2 0 0 0 IR 戦国期豪商の存在形態と大友氏
2 0 0 0 OA 玄界灘の戦国豪商点描 : その栄光と没落
- 著者
- 丸山 雍成
- 出版者
- 交通史学会
- 雑誌
- 交通史研究 (ISSN:09137300)
- 巻号頁・発行日
- no.75, pp.23-48, 2011-09-30
- 著者
- 武市 祥司 野上 貴章
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育研究講演会講演論文集 第62回年次大会(平成26年度) (ISSN:21898928)
- 巻号頁・発行日
- pp.218-219, 2014-08-08 (Released:2016-12-28)