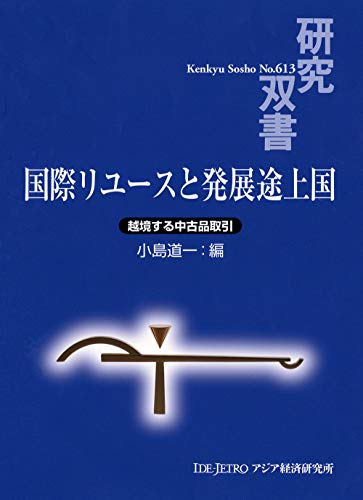2 0 0 0 OA 幼児の自己制御を育む父子遊びの発達力動理論──介入プレイ観察による力動理論の構成──
- 著者
- 荻本 快
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. I-A 教育研究 = Educational Studies (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.81-88, 2014-03-31
父親と幼児によるRough-and-Tumble Play(RTP:乱闘遊び)は,幼児が自らの攻撃性を制御する能力の発達に寄与することが示唆されてきた。本論は,父子のRTPに関する幼児の発達理論に基づき,介入プレイ観察法による事例検討をもとに理論的考察を行うことで,父子のRTPにおける幼児の自己制御の発達要件について,その変数間関係を考察した。その結果,RTPにおいて優位性を保つ父親が攻撃性を制御する態度と行為を示し,それを幼児が模倣することで,攻撃性の制御の内在化を促進する父子の協調が生じることが見出された。そして,幼児の攻撃性の制御が安定化する過程で,RTP中に幼児が自らの限界を超えようと挑戦することと,それに対する父親からの賞賛と誇りの表現によって幼児の父親への同一視が強化されることが考察された。
2 0 0 0 OA 「ふたりきょうだい」における対人魅力の検討
- 著者
- 中嶋 佳苗 磯崎 三喜年
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. I-A 教育研究 = Educational Studies (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.61-69, 2014-03-31
本研究は,「ふたりきょうだい」に焦点をあて,「きょうだい」関係における対人魅力の検討を行った。研究1では,日本の大学生96名を対象にきょうだいにおける対人魅力尺度を作成し,研究2では,研究1で作成した尺度を用いて性格の社会的望ましさと類似性がきょうだいの魅力に与える影響を検討した。研究1より,きょうだいにおける対人魅力尺度は「交流因子」「信頼因子」「誇り因子」の3因子全15項目の構造であり,高い信頼性があることが示された。研究2では,先行研究より,性格の社会的望ましさの方が性格の類似性よりもきょうだいの魅力に与える影響が大きいという仮説をたて検討を行った。その結果,仮説を支持する結果が得られ,きょうだい関係においても類似性の効果よりも社会的望ましさの効果の方が魅力判断における影響が大きいという,これまでの知見と一致する結果が得られた。
2 0 0 0 OA 「ひきこもり」と役を演じる感覚に関する一考察 -「遊び」の概念を手がかりに-
- 著者
- 森崎 志麻
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.45-57, 2014-03-31
Taking the narratives of two interviewees who experienced "hikikomori" (social withdrawal) as materials, the aim of this thesis is to examine why the sense of playing a role is important to "hikikomori" people and also to Japanese society that contains "hikikomori" issues. In order to examine these questions, the concepts of "play" by Henriot and Winnicott were studied. The mental situation of "hikikomori" can be thought of as a negative self-relationship such as excessive self-consciousness. To have the sense of playing a role of oneself means that one can create distance and play between self and another self playing the role of oneself, between self and other, and also between self and society, since "play" is paradoxical in that it allows one to be absorbed into one's role and to be conscious that one is playing a role at the same time. When one is playing between the two elements described as "transitional space, " one can be creative and a subjective self occurs in play. Also, "hikikomori" and Japanese society that has "hikikomori" issues have the two paradoxical moral values of individualistic ethics and interdependent ethics. It is suggested that the sense of playing a role can serve as a bridge between these two moral values.
2 0 0 0 ひきこもり経験と遂行機能の関連 : 気分障害の影響について
- 著者
- 新井 初雪
- 出版者
- 公益社団法人精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.7, pp.756-759, 2007-07-05
- 被引用文献数
- 3 3
2 0 0 0 OA 退屈さとの闘争,衝撃へのノスタルジー : W.ベンヤミンと村上龍をめぐって
- 著者
- Cassegard Carl
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 京都社会学年報 : KJS
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.75-91, 2001-12-25
In this article I investigate the relation of boredom to the experiences of "shock" and "nature" (or "naturalization") in Walter Benjamin and Murakami Ryu. Nature is the semblance of timeless givenness in a taken for granted order of things, whereas shock is the break-up of this natural order. Just as shock is an ambivalent experience - not only destructive but also liberating - so naturalization gives rise to conflicting strategies. In this article I seek to throw light on these strategies by focusing on the role of boredom, first in the "shocking" modernity depicted by Benjamin, then in the "naturalized" modernity in Murakami Ryu. Benjamin depicts modernity as a "hell" characterized by a "dialectic of the new and eversame" in which people develop a "heightened consciousness" that serves as a "protective shield" against the shocks of everyday life but which also leads to the disintegration of "aura". Benjamin describes the boredom that springs from the experience of a world drained of aura as "spleen". Spleen, in other words, is not a boredom that stems from the absence of shocks or of stimuli, but on the contrary a boredom that is fuelled by an excess of shocks. In this respect it is similar to the bored indifference of what Simmel calls the "blase attitude". Although Benjamin regards modernity as a "hell", he rejects the nostalgic attempt to resurrect the aura - as seen above all in fascism - since such an attempt would be caught in the "law that effort produces its opposite". Thus fascism is driven towards war, the greatest shock of all. Benjamin choses instead a strategy of "waiting", a "tactile" getting used to the shocks and the reification of the nightmare of modernity in order to discover the dialectics of awakening within it. The boredom seen in much contemporary fiction is of a fundamentally different kind, springing not from a shocking but a naturalized world. This boredom can be affirmed, as in Okazaki Kyoko, Yoshimoto Banana or Murakami Haruki. Murakami Ryu, however, "wages war on boredom" (Shimada Masahiko) in the attempt to resurrect the experience of shock. Although his fiction abounds in seemingly shocking or nauseating episodes, these shocks are never simply given as part of experience itself, as the shocks characteristic of the modernity depicted by Benjamin, but consciously produced in order to resist naturalization. The paradox of this attempt to resurrect shock, however, is analogous to that of resurrecting the aura : the effect produced is the opposite of the intended. Thus Murakami Ryu enables us to study how the efforts to combat naturalization themselves become naturalized, i. e. part of the boring everyday. In Murakami Haruki, we can see a diametrically opposed strategy resembling Benjamin's attitude of "waiting" and passively immersing oneself in the experience of the present-the one significant difference being that while this experience was shock for Benjamin it is rather naturalization for Murakami Haruki. If Murakami Haruki represents a basic acceptance of naturalization that still seems to be waiting for something new, then Murakami Ryu represents a basic revolt against naturalization that acknowledges its own futility. In the former, we see the mute expectation that new shocks will arise through his affirmation of nature. In the latter, the grim foreboding that he will get mired down in nature through his pursuit of shock.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経Linux (ISSN:13450182)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.12, pp.61-63, 2004-12
Linux上で動作する本格的な年賀状(はがき)作成ソフトがいよいよ登場する。Linuxディストリビューション「ターボリナックス ホーム」に同こんされる「筆ぐるめ」だ。発売前にいち早く試してみたが,年賀状作成ソフトとして十分満足できるものだ。
2 0 0 0 OA 全結合リカレントネットの応用可能性についての考察−オンライン文字認識を対象として−
- 著者
- 糟谷 勇児
- 出版者
- Waseda University
- 巻号頁・発行日
- 2004
リカレントネットはフィードバックを持つニューラルネットであり、全結合リカレントネットは、入力層へのフィードバックを除くあらゆる結合を許したモデルである。全結合リカレントネットは脳のモデルとして信頼性があり、人工知能等の分野での応用が期待できる。しかし全結合リカレントネットを応用した研究は少なく、パラメータの設定法や時系列認識における性能などの応用に関する情報が十分に得られていない。そこで本研究では全結合リカレントネットをオンライン文字認識に用いることで、全結合リカレントネットの応用上の注意点や応用可能性を探ることを目的とする。 今回作成した文字認識システムを東京農工大学中川研究室オンライン手書きデータベース「TUAT Nakagawa Lab.HANDS-kuchibue_d-7-06-10」の数字データ6人分300個で評価したところ、最大91%となる認識率を示すなど、全結合リカレントネットが時系列認識に有効であることがわかった。
- 著者
- Thomas M. Mongar
- 出版者
- Edwin Mellen Press
- 巻号頁・発行日
- 1994
2 0 0 0 国際リユースと発展途上国 : 越境する中古品取引
- 著者
- 小島道一編
- 出版者
- 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- 大矢 明彦
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.915, pp.109-112, 1997-11-10
プロ野球・横浜ベイスターズは18年ぶりに、セントラルリーグ2位でシーズンを終えました。しかし、監督を務めた私は辞めることになりました。「来年も横浜の監督として指揮をとりたかったか」と聞かれれば、それは続けたい気持ちが強くありました。シーズン終盤に球団から、「来年の契約はしない」と通告されたときには、頭の中が真っ白になった感じがしました。
2 0 0 0 OA ベイズ統計と統計物理 : 有限温度での情報処理
- 著者
- 伊庭 幸人
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.677-699, 1993-09-20
- 被引用文献数
- 1
ベイズ統計の"有限温度の情報処理'としての側面を物理の研究者向けに解説し、関連する自分の研究を紹介した。とくに、1.ベイズ統計の枠組と統計物理との類似。2.'有限温度'での推定の最良性。3.'自由エネルギー'の情報処理における重要性。4.有限温度での推定を行なうためのアルゴリズム。について述べた。付録では、spin glassにおけるNishimori lineとベイズ統計の関連について、hyper parameterの推定という観点から考察した。
2 0 0 0 OA ホワイトヘッドの有機体の哲学における永遠的客体という概念
- 著者
- 稲村 文
- 出版者
- 京都大学大学院文学研究科哲学研究室
- 雑誌
- 京都大学文学部哲学研究室紀要 : Prospectus
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.63-70, 2010-03
2 0 0 0 IR 書評 又吉栄喜『漁師と歌姫』
- 著者
- 浜川 智久仁
- 出版者
- 沖縄大学地域研究所
- 雑誌
- 地域研究 (ISSN:18812082)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.139-143, 2010-03
2 0 0 0 IR 『にごりえ』を読む:「泣きての後の冷笑」を視界に
- 著者
- 木村 勲
- 出版者
- 神戸松蔭女子学院大学
- 雑誌
- 神戸松蔭女子学院大学研究紀要. 文学部篇 (ISSN:21863830)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-30, 2013-03-05
『にごりえ』は樋口一葉が二四歳半での死の前年に書いた作品。ひとたびは自分の店を構えた男・源七が酌婦・お力に迷って零落し、尽くす妻・お初と一児を捨てて破局にいたるというもの。源七のもとを去るときのお力の言葉が「たとへ何のやうな貧苦の中でも二人双つて育てる子は長者の暮しといひまする、別れゝば片親、何につけても不憫なは此子と思ひなさらぬか、あゝ腸が腐た人……」だ。男の無責任さと、捨てられた母子とくに母の健気さとを、酌婦を介在にした悲劇として読まれてきた。しかし一葉は時間的・空間的(そして心理的)に巧みな仕掛けをして、一読の印象とは違う世界を織り込んでいた。「冷笑がある」と突いたのが斎藤緑雨だ。毒舌で文壇から嫌われていた彼と、一葉は死ぬ前の半年間、親交した。頻繁な来訪を心待ちして「微笑」んで聞く――そんな最後の日々が日記に詳細に書かれた。作品と日記と制作過程を示す残骸(未定稿)を比較し、思想史的背景も考慮に入れて作品分析を行う。
2 0 0 0 OA 人形の家 : ノラ
- 著者
- ヘンリック・イブセン 著
- 出版者
- 春江堂書店
- 巻号頁・発行日
- 1914
2 0 0 0 OA Y系高温超伝導線材の低交流損失・大電流容量化に関する研究
2 0 0 0 極域アイスコアに記録された地球環境変動
- 著者
- 藤井 理行
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地學雜誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.3, pp.445-459, 2005-12-25
- 被引用文献数
- 4
This paper describes past climate and environmental changes during the past 101 to 105 year time scale obtained by recent studies on ice cores from Arctic and Antarctica. Shallow ice cores from Greenland and Svalbard show clear North Atlantic Oscillation (NAO) signals and explosive volcanic activities in the Northern Hemisphere and the equatorial regions. A deep ice core drilled to 2503 m at Dome Fuji, Antarctica covers the past 320 ka, which includes 3 glacial-interglacial cycles with Milankovitch cycles of about 20, 40, and 100 ka. Major chemical compositions and microparticle flux show high concentrations in glacials and low concentrations in interglain high-middle latitudes during glacial-interglacial cycles. The Dome Fuji deep ice core contains 25 visible tephra layers. An analysis of the chemical compositions shows the possible source volcanoes in and around the Antarctica.
2 0 0 0 モザイクとニューラルネットを用いた顔画像の認識
- 著者
- 小杉 信
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-情報処理 (ISSN:09151923)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.6, pp.1132-1139, 1993-06-25
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 69
顔画像のモザイクパターンとニューラルネットを組み合わせた顔の認識法を提案する.顔画像の場合,顔の輪郭や目・鼻・口などの形状,ならびにこれらの位置関係が顔の重要な特徴であるが,顔は陰影が柔らかで正確な形状抽出が困難であり,更に,互いによく似ているため,従来,多人数の顔の認識はほぼ不可能であった.そこで,線分形状ではなく顔の濃淡情報に注目し,顔画像の中心部を12×12に粗くモザイク化し,これをニューラルネット(3層BPN)に入力して多人数の識別を試みた.この結果,学習後の中間層の各ユニットは,モザイク画像の各所から濃淡情報をきめ細かく集めることにより,互いに共通の特徴をもつ顔画像,例えば男女,を自動的に分類した.また,100人の上半身動画像から得た各人一つの正面向き平常顔を学習後,同じ録画像から任意にサンプルした平常顔ならびに微笑顔をテストし100%の認識率を得た.更に,学習の対象外,すなわち,見知らぬ顔に対しては,「その他検出」専用の出力ユニットを設けることにより,見知らぬ顔に対するエラー率を約1/2に低減することができた.