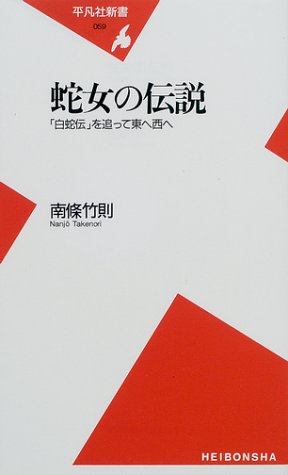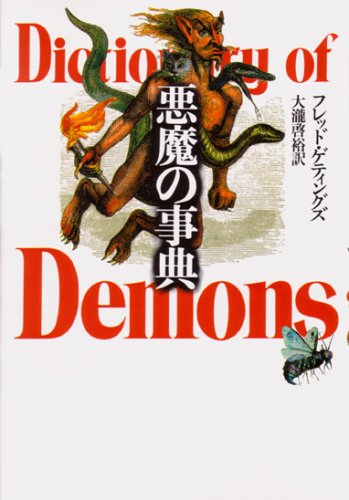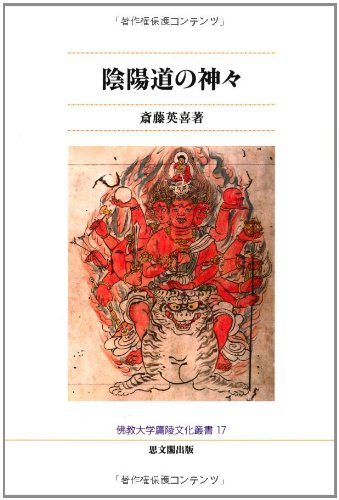- 著者
- 林 正巳 實 清隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.97-101, 1979
Most of Japanese municipalities, which were incorporated first in 1899, have experienced annexation or consolidation. However, there are municipalities which have not been annexed by adjacent large municipalities. This symposium was intended to focus on the problems of such non-annexed small corporate units. In order to handle the problems, we must pay attention not only to their geographical location, but also totheir administrative, financial and historical background.<br> This symposium was carried on by two chairmen, four commentators, and ten speakers. Chariman: Osamu NISHIKAWA (Univ. of Tokyo) and Yoshio WATANABE (Tokyo Metropolitan Univ.), Commentators: Shoichi YOKOYAMA (Univ. of Ehime), Hideo TSUKADA (Univ. of Nara), Yasuo MASAI (Univ. of Tsukuba), and Naoki YOSHIZU (Univ. of Nagoya). We got the following ten reports.<br> 1. FUKUHARA, H.: Case Study of Waki-cho Bordering Hiroshima and Yamaguchi Prefecture.<br> 2. HIGAKI M.: Case Study of Yoshitomi-cho Adjacent to Nakotsu City, Ohita Prefecture.<br> 3. SAEKI, I.: Case Study of Fuchu-machi Adjacent to Hiroshima City, Hiroshima Prefecture.<br> 4. IDO, S.: Historical Approaches to Several Non-annexed <i>Muras</i> in Shiga Prefecture.<br> 5. SAKAGUCHI, K. MIZUYAMA, T. and KOTANI, M.: Case Study of Iwataki-cho, Kyoto Prefecture.<br> 6. YOKOTA, T.: Case Study of Kasugai-cho, Yamaguchi Prefecture.<br> 7. CHIBA, T.: Minami-kawahara-mura, Saitama Prefecture.<br> 8. OHISHI, T.: Demographical Approach to the Distribution of Non-annexed Municipalities.<br> 9. OGURI, H.: On the Changes in Communities with the Consolidation of Local Government.<br> 10. MIIDA, K.: Case Study of Some Non-annexed Small Corporate Units. Discussions were focused on the following points.<br> 1. Merits and demerits of the non-annexed municipalities<br> 2. Management and control of the budget of the municipalities<br> 3. Community sentiment and non-annexed municipalities<br> 4. Moderate scale of local government<br> 5. Connection with other local governments in terms of consolidation.
1 0 0 0 OA 日欧の歴史的乾ドックの形状から見た日本の煉瓦積み乾ドックの固有性
- 著者
- 若村 国夫 ワカムラ クニオ Kunio Wakamura
- 雑誌
- 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.131-148, 2009
1 0 0 0 IR 英語教材開発と社会言語学
- 著者
- 森戸 由久 Yoshihisa MORITO
- 出版者
- 創価女子短期大学紀要委員会
- 雑誌
- 創価女子短期大学紀要 (ISSN:09116834)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.3-11, 2008-12
1 0 0 0 外傷学における頭部外傷の位置づけ
- 著者
- 横田 裕行
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.102-109, 2020
1 0 0 0 IR 「悪魔(サタン)とヴェネチアの古き神々」-下-ある文学的常数の発展
- 著者
- Pabst Walter 田村 和彦
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学人文科学研究 (ISSN:02862700)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.p107-124, 1982-04
1 0 0 0 IR ロレンスの魔女
- 著者
- 高島 葉子
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 人文研究 (ISSN:04913329)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.11, pp.835-850, 1996
はじめに : ヨーロッパにキリスト教が広まるとともに, 土着の異教の神々の多くは悪魔に転落させられ, 排除されていった。「大いなるパン神は死せり」という言葉どおり, パン神も悪魔として追放された。……
1 0 0 0 蛇女の伝説 : 「白蛇伝」を追って東へ西へ
1 0 0 0 悪魔の事典
- 著者
- フレッド・ゲティングズ著 大瀧啓裕訳
- 出版者
- 青土社
- 巻号頁・発行日
- 1992
- 著者
- 田村 和彦 Kazuhiko Tamura
- 雑誌
- 桃山学院大学人文科学研究 = THE JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, St. Andrew's University (ISSN:02862700)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.107-124, 1982-04-30
1 0 0 0 光重合型直接裏装材"エポレックス・リベース"の適合性と補強効果
- 著者
- 早川 巌 松本 竹男 仲地 理 安江 透 石塚 等 増原 英一
- 出版者
- 一般社団法人日本歯科理工学会
- 雑誌
- 歯科材料・器械 (ISSN:02865858)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.59-63, 1987-01-25
- 被引用文献数
- 1
不適合義歯の裏装法には, 常温重合レジンを用いる直接法と加熱重合レジンによる間接法とがある.前者は, 簡便で適合性もよいが, モノマーの刺激や重合時の発熱が患者に不快感を与え, さらに物性的にも問題がある.一方, 後者は, 裏装材の物性は優れているが裏装操作が煩雑で, かつ重合時の加熱によって義歯床に変形が生じるため適合性にも問題がある."エポレックス・リベース"は, これら従来の裏装材に付随した問題点を解決する目的で開発された光重合型直接裏装材である.すでに本材料の理工学的性質, 生物学的安全性などについては検討され, 裏装材として十分実用性があることが判明しているので, ここでは, 硬いが幾分脆いという本材料を義歯床レジンに張り合せた場合に, どの程度の補強効果があるかを検索した.また, 裏装後の適合性についても加熱重合レジンおよび常温重合レジンを使用した場合と比較検討した.その結果, 適合性については, 本材料は加熱重合レジンよりはるかに良好で, 常温重合レジンに相当するものであった.補強効果については, 両者を積層することにより塑性変形量が増大して靱性が著しく向上し, 本材料を用いた裏装義歯は, 従来の床用材料のもつ脆性を克服し, 義歯自体の耐久性をも高められる可能性があることが示唆された.
- 著者
- 小林 節雄 根本 俊和
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.71-77, 1975
- 著者
- 鈴木 一馨 Suzuki Ikkei
- 出版者
- 駒澤史学会
- 雑誌
- 駒沢史学 (ISSN:04506928)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.74-95, 2003-11
1 0 0 0 OA 児童虐待への刑事法的介入と理論的背景
- 著者
- 三枝 有
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.45, 2012 (Released:2017-11-01)
1 0 0 0 IR 精神障害者福祉から見る成年後見制度と監督義務者責任問題 : 日中比較を交えつつ
- 著者
- 曹 正陽
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法政ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.111-136, 2015
- 著者
- 林原 めぐみ 鈴木 慶太 藤井 雅弘 渡辺 裕 伊藤 篤
- 出版者
- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会
- 雑誌
- 情報科学技術フォーラム講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.555-556, 2008-08-20
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1924年10月23日, 1924-10-23
1 0 0 0 OA フランス議会における国政調査制度
- 著者
- 濱野雄太
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.851, 2021-11
- 著者
- WILLIAMS CL
- 雑誌
- Circulation
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.143-160, 2002
- 被引用文献数
- 2 518
1 0 0 0 アドラー心理学から見た大学等における合理的配慮とその支援
- 著者
- 長田 岳大
- 出版者
- 日本アドラー心理学会事務局
- 雑誌
- アドレリアン = The Adlerian (ISSN:09181490)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.3-14, 2021-10