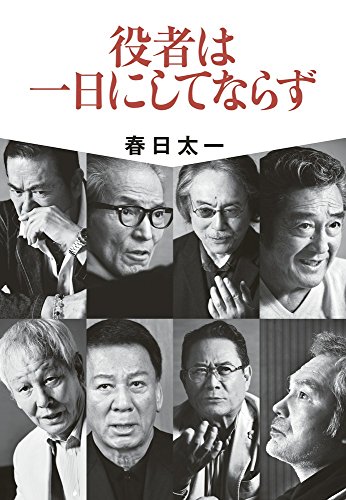1 0 0 0 IR 三重県尾鷲湾から得られたマサカリテングハギの三重県初記録および日本における3個体目の記録
- 著者
- 髙橋 夢加 木村 清志
- 出版者
- 鹿児島県自然環境保全協会
- 雑誌
- Nature of Kagoshima = カゴシマネイチャー : an annual magazine for naturalists (ISSN:18827551)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.159-162, 2020
1 0 0 0 OA フタロシアニン顔料の最近の開発動向
- 著者
- 大倉 研
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.10, pp.687-698, 1996-10-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 東京文理大英文科の閉学-福原麟太郎を中心に-
- 著者
- 祐本 寿男
- 出版者
- 日本英語教育史学会
- 雑誌
- 日本英語教育史研究 (ISSN:0916006X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.45-63_1, 2001-05-10 (Released:2012-10-29)
1 0 0 0 古墳時代木棺の用材選択に関する研究
- 著者
- 岡林 孝作
- 出版者
- 奈良県立橿原考古学研究所
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2003
本研究では、遺物論的視点に立った古墳時代木棺研究の一つの試みとして、その製作材料である木材の樹種に注目した検討をおこなった。具体的には、古墳等から出土した遺存木棺材の木材科学的な樹種同定作業を進め、資料を蓄積するとともに、木材科学的な同定により樹種が判明した出土木棺材の調査例を全国的に集成し、用材選択の地域性・階層性と時期的変化を分析した。資料収集の結果、全国で165例の樹種同定例を集成した。針葉樹が91%、広葉樹が9%で、針葉樹が圧倒的に多い。なかでもコウヤマキの使用が突出しており、全体の51%を占めるが、その分布域が近畿地方を中心として西は岡山県から東は愛知県にかけての太平洋側の地域にほぼ限定されることが顕著な顕著な地域的傾向として認められる。その他の樹種としては、スギ、ヒノキがやや多く、カヤ、サワラと続くが、コウヤマキにみられるような明確な使用の選択性は認められない。近畿地方を中心とした地域では、前期〜中期にはコウヤマキの使用率が90%に近い高率を示す。コウヤマキの使用率は後期になると80%程度になり、6世紀末〜7世紀初頭頃を境にして選択的な使用はみられなくなる。この状況の要因は、コウヤマキ材の大量消費による資源の枯渇であったと考えられる。後期におけるコウヤマキ材の不足状態は、木棺自体の小型化や、部材の軽薄化、細長い板の接ぎ合わせ行為などから裏付けられる。コウヤマキ材の選択的使用地域の枠組みが古墳時代を通じて変化せず、その使用のあり方に一定の階層性も反映していることから、古墳時代にはコウヤマキ材を供給する何らかの木材移送システムが存在していた可能性が高い。また、6〜7世紀にはコウヤマキの自生しない朝鮮半島南部の百済王陵へ棺材としてのコウヤマキ材の供給もおこなわれており、そうしたシステムへの王権の関与を示唆する事実として興味深い。
1 0 0 0 OA 内航フェリーへの空気潤滑システムの適用と実運航データに基づく実海域における省エネ効果検証
- 著者
- 溝上 宗二 黒岩 良太
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本船舶海洋工学会論文集 (ISSN:18803717)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.1-9, 2019 (Released:2019-09-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
The authors verified an energy saving effect of an air lubrication system for the domestic service ferry which was one of slender body ships. The energy saving effect was evaluated by the engine output reduction rate of system ON and OFF at speed-trial test. As the result, a net energy saving effect of about 3.7% was confirmed.After that, long-term voyage monitoring had been conducted since the ship was in service. At the same time, monitoring had been conducted about same type of sister ship without air lubrication system, in service on the same route.The investigation result of the energy saving effect by comparison of fuel consumption of both ships, a net effect of about 3.13% was confirmed. According to these results, the effectiveness of an air lubrication system for slender body ships was proved; therefore, scope of an air lubrication system as energy saving system of ships had expanded.
1 0 0 0 障害者スポーツの現場から
- 著者
- 三浦 祐助 斎藤 禎彦 廣道 純
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 = Bulletin of the Japanese Society of Prosthetic and Orthotic Education, Research and Development (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.36-38, 2003-01-01
1 0 0 0 IR 民意とメディア : 「辺野古」県民投票に関する新聞報道を事例として
- 著者
- 吉岡 至
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.65-92, 2021-03-31
2019年2月24日、沖縄で実施された県民投票は辺野古沿岸への普天間飛行場移設・新基地建設のための「埋め立て」の賛否を問うもので、沖縄の民意をあらためて示す一つの重要な機会であった。本稿は沖縄の地方新聞である『沖縄タイムス』と『琉球新報』が県民投票をめぐる争点や沖縄の民意をどのように伝えたのか、その報道の特徴を明らかにすることを目的としている。報道内容の分析を通じて、2つの側面― 県民投票に関する「全県実施」の可能性と「反対」の民意を強調していることを、その特徴として指摘した。
1 0 0 0 OA GRDC (世界河川流量データセンター) とそのデータについて
1 0 0 0 統計的生命価値と規制政策評価
- 著者
- 古川 俊一 磯崎 肇
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本評価学会
- 雑誌
- 日本評価研究 (ISSN:13466151)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.53-65, 2004
政策の評価を行うに当たっては、基本的な原単位の数値が確定されている必要がある。生命価値はその最たるものであり、規制評価が政策評価の中で、主要なものとされているにもかかわらず、十分な研究蓄積に乏しい。本論文では、リスク工学の考えも応用し、第1に、死亡事故のリスクに対する「統計的生命価値」の推定モデルを探求する。第2に、自動車購入時に、使用者が評価しているリスクから「統計的生命価値」を推定する。第3に、その結果を現在我が国で主として用いられている逸失利益をベースとした人命の価値と比較し、費用便益分析においての取り扱いを考察する。道路建設等の分野における約3, 000万円という従来の人命の価値は、今回分析の結果示された「統計的生命価値」8~10億円や、質問法をベースにした場合の我が国における「統計的生命価値」において妥当な数値との指摘のある数億円と大きな格差がある。もし生命価値が、一桁高い評価を受けることになれば、規制政策等の評価結果が大きく変更される可能性がある。
1 0 0 0 OA 鉄鋼業圧延部門等の工場間分業 : 川崎製鉄の立地について
- 著者
- 中島 清
- 出版者
- 横浜市立大学学術研究会
- 雑誌
- 横浜市立大学論叢. 人文科学系列 (ISSN:09117717)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.11-62, 2016-01-29
1 0 0 0 役者は一日にしてならず
1 0 0 0 IR ゴールデンキウイ(Hort16 A種)のゼラチンゼリー形成と食味特性
- 著者
- 柳沢 幸江 ヤナギサワ ユキエ Yukie YANAGISAWA
- 雑誌
- 和洋女子大学紀要. 家政系編
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.193-202, 2003-03-31
ゴールデンキウイはキウイ特有のプロテーゼ活性が極めて低いことから、従来のグリーンキウイと比較してのゼラチンゼリー形成を検討した。ゴールデンキウイの果実の食味特性は、従来のグリーンキウイと比べてpHと糖度には有意差はなかったものの、甘味と酸味のバランスがよくえぐみが少なかった。ゼリー形成では、グリーンキウイを用いた果汁ゼリーでは果汁濃度1.5%までしかゼリー形成しなかったのに対して、ゴールデンキウイでは、果汁濃度が50%でもゼリー形成が充分可能であり、ゼリー形成に対する作用は双方に約40倍の差が認められた。また、果肉ゼリーの場合でもゴールデンキウイを50%添加してもゼリー形成が可能であった。官能評価の結果、果汁・果肉ゼリーとも30%程度の添加が、テクスチャー・味の両面から好まれた。
- 著者
- 山本 文陸郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- 中央獸醫會雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.1-19, 1931
1 0 0 0 OA 前十字靱帯の力学特性
- 著者
- 林 和彦 白崎 芳夫 池田 洋教 立石 哲也 下條 仁士 宮永 豊
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会
- 雑誌
- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.26-32, 2003-06-30 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 12
The mechanical properties of the anterior cruciate ligament (ACL) were investigated. The method of a versatile clamp was designed to holding the femur-ACL-tibia complex (FATC). Twelve porcine FACT specimens were tested at angle 30° and the parallel direction of the ACL. The static tensile and stress relaxation tests were performed with an Instron-type universal testing machine. Differences in stress-strain behavior at the two (slow and fast) deformation rates. The ACL AM (anteromedial) bundle exhibited significant distribution of the deformation at the two deformation rates. Good agreement is obtained using Y. C. Fung's QLV (quasi-linear viscoelastic) theory relationship between theoretical and experimental data.
1 0 0 0 職業構造の変化と男女間賃金格差の実証研究
1 0 0 0 IR 「差異の寄生者」としての個人--ルーマンを読む
- 著者
- 村上 淳一
- 出版者
- 桐蔭法学会
- 雑誌
- 桐蔭法学 (ISSN:13413791)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-26, 2000-07
医学的管理が充実している日本の高齢者であっても、認知症予備群から認知症へ移行する数は増加の一途である。一方、チェンマイ県での認知症罹患率は、日本の6分の1程度に留まっている。そこで本研究の目的は、タイ北部農村部とタイの都市部の高齢者、日本の北陸地方の農村部と都市部の高齢者の、認知機能面、身体機能面、社会生活面、栄養摂取面、精神心理面、保健行動面を評価し、その影響要因について、また、継続して3年間の認知機能経年変化値や脳血流量変化量を従属変数に、生活習慣や環境、社会背景を説明変数として何が認知機能の経年変化に影響を与えているかを比較検討することであった。日本側の農村部および都市部在住の高齢者の調査から、ミニメンタルステートテスト(MMSE)の値と言語流暢性課題と運動課題を同時に行う二重課題実施中の前頭前野の脳血流との間に有意な関連がみられ、近赤外分光法(NIRS)を使用した前頭前野血流変化量は認知機能低下の予測因子として重要な指標となり得ることが示唆された。また高齢者の宗教観および社会的孤立が認知機能に及ぼす影響についての調査結果から日本の都市部と農村部ではMMSEとMOCAの認知機能検査結果に違いはなかったが、農村部では信仰有りが有意に高く、「信仰の有無」、「高齢者のうつ」、「社会的孤立状態」は認知機能の経年変化の予測因子になり得ることが示唆された。一方、タイ,チェンマイ市内都市部と農村部の3か所の高齢者サロンに通所する高齢者へ、半構成的インタビューを中心に行った結果からは、「老いることの意味」について全員が「老い」をポジティブに受け止めていた。タイ高齢者の宗教心が老いへ向かう態度や日々の生活への態度にポジティブに関連している可能性があった。宗教的背景が他者とかかわる機会を持たせ、「人の役に立つ」ことを満たすために、高齢であっても孤立しない環境である可能性があった。
1 0 0 0 Монгол ардын хээ угалз
- 著者
- Батсүхийн Болд хянан тохиолдуулсан Л. Чуваамид
- 出版者
- Admon
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 OA 214 覚醒剤(l-methamphetamine)のラット胎仔発育に及ぼす影響
- 著者
- 尾崎,浩士
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科學會雜誌
- 巻号頁・発行日
- vol.43(Supplement), 1991-02-10