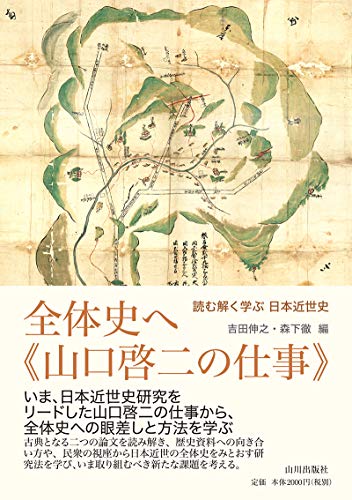- 著者
- 田中 直樹 小辻 俊通 大倉 実紗 小西 敏生
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.299, 2007
〈はじめに〉当院は病床数460床の地域中核病院であり、平成17年に臨床工学部門であるCE部が設立された。現在、臨床工学技士8名でME機器管理業務、血液浄化業務、循環器業務などを行っている。医療技術の進歩に伴い各種ME機器が導入され、業務拡大を求められるなか、効率的に業務を行うため、臨床工学技士業務支援システム(以下CE Office)を作成したので報告する。〈方法〉CE Officeは、データベースソフト「File Maker Pro」で作成し、サーバーとして「FileMaker Server 7」を設置した。クライアントは各部門に設置し、院内LAN上で接続し、どこからでも情報が閲覧、書き込みができる環境にした。また、各クライアントごとにアカウントとパスワードを設定し、セキュリティーを強化した。機能としては、掲示板として、メッセージ(申し送り)、勤務表、待機表の作成。ME機器管理では、バーコードを使った貸し出し返却システムや、機器管理台帳、メンテナンス計画。血液浄化では、透析記録用紙やサマリーの発行、検討会の資料作成。循環器では、心臓カテーテル検査、PCI、QCA、IVUSデータ管理や、物品管理などがある。又、メッセージを必ず見るように、掲示板を初期画面とし、そこから各部門のデータベースにアクセスできるようにした。〈結果〉院内LANを使用することにより、どこからでもアクセスでき、効率的に業務が行うことができた。掲示板を使用することで伝達が確実かつスムーズに行うことができた。ME機器管理では、貸し出し返却システムにバーコードを使用することで、容易に作業が行うことができ、誤記入がなくなり、データの信頼性が向上した。血液浄化では、患者データを透析記録用紙に反映することにより、転記ミスや記載漏れを少なくすることができた。循環器では、患者個別でデータをリアルタイム入力することができた。また、過去のデータ検索が容易になり、医師に迅速な情報提供がおこなえた。〈まとめ〉データベースを自作することにより、低コストでシステムを構築することができ、施設に即した情報だけを管理することができるので、効率的に業務を行うことができた。また、必要に応じてシステムを変更することができ、今後の業務改善につながると考えられる。
- 著者
- Hayato Yamana Sachiko Ono Akira Okada Taisuke Jo Hideo Yasunaga
- 出版者
- Japan Society for Occupational Health
- 雑誌
- Journal of Occupational Health (ISSN:13419145)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.e12183, 2020 (Released:2021-01-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3
Objectives: It is unclear whether mandatory health examination is effective for employees who are already being treated for chronic diseases. We focused on patients being treated for hypertension and evaluated the association between employer-based health examination attendance and diabetes treatment initiation.Methods: Using a database that stores health insurance claims and health examination results of subscribers enrolled in society-managed health insurance plans in Japan, we identified employees aged 40-59 years who were being treated for hypertension when starting diabetes treatment from April 2012 to December 2016. A case-crossover analysis was conducted using 90, 180, and 270 days prior to diabetes treatment initiation as reference points and 90 days after the mandatory health examination as the exposure period. We conducted a subgroup analysis by hemoglobin A1c (HbA1c) level and frequency of outpatient blood glucose testing before the mandatory health examination.Results: We identified 1464 individuals starting treatment for diabetes while on antihypertensive drugs. The overall odds ratio for starting diabetes treatment within 90 days of the health examination was 1.89 (95% confidence interval: 1.70-2.10). The subgroup analysis showed that this odds ratio increased as HbA1c level increased and as blood glucose testing frequency decreased.Conclusions: Among employees starting treatment for diabetes while being treated for hypertension, employer-based mandatory health examination attendance was associated with initiation of diabetes treatment. The health examinations may be functioning as a complement to screening in outpatient settings.
1 0 0 0 OA 2, 4, 6-トリニトロベンゼンスルホン酸ナトリウムによるアミノ基定量の改良法
- 著者
- 山科 孝雄 平田 博文
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- 油化学 (ISSN:18842003)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.441-443, 1987-06-20 (Released:2009-11-10)
- 参考文献数
- 4
The reactions of amino groups in amino acids and proteins with sodium 2, 4, 6-trinitrobenzenesulfonate (TNBS·Na) in the presence of sodium sulfite (Na2SO3) were studied at pH 10.1. Determination of the amino groups was performed by following the absorbance A (420 nm) of the Meisenheimer complex. A good linear relationship between A and the concentrations of amino compounds was observed. The reactions in a cuvette showed good agreement with those in the dark. Based on these observations, a modified method for determining amino groups by TNBS·Na in the presence of Na2SO3 is proposed, and several comments are described.
1 0 0 0 食事由来脂肪酸と皮膚炎症性疾患
- 著者
- 本田 哲也
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.1, pp.5-8, 2018-02-01 (Released:2018-06-04)
- 参考文献数
- 28
脂質は,糖質・たんぱく質と並ぶ三大栄養素の一つであり,多種の脂肪酸から構成される。脂肪酸は,細胞膜などの生体膜構成,エネルギー源,シグナル伝達などの機能を有し,生体恒常性維持に極めて重要な役割を果たしている。一方で,その過剰な摂取やアンバランスな摂取が,皮膚疾患を含めた様々な病態の悪化因子として注目されている。また,脂肪酸の中でも,オメガ 3 系脂肪酸やオメガ 6 系脂肪酸は食事からの摂取が必要な必須脂肪酸である。特にオメガ 3 系脂肪酸は抗炎症作用を有している可能性が多数報告されており,新たな創薬ターゲットとしても注目されている。食事由来脂肪酸の観点からの疾患の病態解明,および創薬展開が今後益々期待されている。
1 0 0 0 大学生における日本酒のイメージと嗜好
- 著者
- 五島 淑子 小野 佑輔 広津 理恵 石田 佳菜絵 前田 綾子 村尾 奈美 柏木 享
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.1006, 2009
<BR>【目的】近年日本酒の消費量が減少している。日本の食文化のひとつである日本酒について、将来の酒の消費量に影響を与える年齢層の大学生を対象に、日本酒に対するイメージと嗜好について調査を行い、若者に日本酒を普及させる方法を探る。<BR>【方法】(1)酒のイメージ調査 平成20年6月上旬~7月上旬、山口大学学生290名を対象に、SD法によるイメージ調査を行った。(2)実態調査 平成20年6月中旬から7月中旬、山口大学学生353名を対象に、日本酒の飲酒頻度、日本酒についての関心などについてアンケート調査を行った。(3)日本酒の試飲調査 平成20年12月10日~12日に、山口大学学生102名(20歳以上で試飲後運転をしない人)を対象に、山口大学教育学部食物調理科学教室で、4種類の日本酒(純米酒、地酒)から好きな酒を選ばせた。<BR>【結果】(1)大学生は、日本酒を「アルコール度数が高い」「男性的」「年配向き」「高級」「辛い」とイメージしていた。(2)お酒として一番に思い浮かべるのはビールついで日本酒であったが、最も好きな酒はカクテルついで梅酒、ビールであった。(3)日本酒を飲む頻度は「月1回以下」「飲まない」が6割以上を占めた。(4)「料理にあう日本酒」「日本酒の飲み方」「日本酒の種類」に関心が高かった。(5)日本酒離れが進む原因として、「においがきつい」「アルコール度が高い」「値段が高い」「近寄り難い」「辛い」ためと考えていた。(6)試飲調査の結果、純米大吟醸、発泡純米酒、アルコール度数の低い酒が好まれた。(7)若者に日本酒を普及させるためには、若者が好む種類の日本酒の販売、料理にあう酒や飲み方などについて情報の発信など、日本酒の知識と経験が重要だと考える。
- 著者
- 亀山 孝一郎
- 出版者
- フレグランスジャーナル社
- 雑誌
- フレグランスジャーナル (ISSN:02889803)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.8, pp.41-48, 1999-08
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 「高輪築堤」の保存を求める要望書
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.96-98, 2021-04
1 0 0 0 「高輪築堤」遺構の保存・公開の要望
1 0 0 0 ウワナベ古墳(宇和奈辺陵墓参考地)限定公開参加記
- 著者
- 鬼塚 知典
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.60-64, 2021-04
1 0 0 0 新刊案内 三宅紹宣著『幕末維新の政治過程』
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.86-88, 2021-04
- 著者
- 佐藤 麻里
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.56-59, 2021-04
- 著者
- 風間 洋
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.52-55, 2021-04
1 0 0 0 日本歴史学協会報告
- 著者
- 新井 浩文
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.46-51, 2021-04
- 著者
- 伊藤 哲平
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.24-45, 2021-04
1 0 0 0 『風土記』における国譲り・天孫降臨神話について
- 著者
- 舟久保 大輔
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.4-23, 2021-04
1 0 0 0 全体史へ《山口啓二の仕事》 : 読む解く学ぶ日本近世史
1 0 0 0 OA コリヤークのトナカイ遊牧
- 著者
- 大島 稔
- 出版者
- 北海道立北方民族博物館
- 雑誌
- 北の遊牧民-モンゴルからシベリアへ-
- 巻号頁・発行日
- pp.47-51, 2004-07-09
第19回特別展
1 0 0 0 OA 崩壊誘起土石流の数値実験及び別当崩れを対象とした事例研究
- 著者
- 汪 発武 高田 渉 松本 樹典
- 出版者
- 公益社団法人 地盤工学会
- 雑誌
- 地盤工学研究発表会 発表講演集 第39回地盤工学研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.2127-2128, 2004-03-05 (Released:2007-01-18)
崩壊誘起土石流の運動範囲予測は斜面防災の分野で重要な課題である。Sassa(1988)及びWang & Sassa (2002)によって提案された地すべり運動予測プログラムは計算結果の可視化機能などが加わり,実務適用可能の段階まで至っている。本報告は,簡単化した数値模型斜面を用いて,地形条件及び土質パラメータの影響を確認し,プログラムの有効性を確認した。さらに,崩壊土砂の衝撃による河床堆積物の流動化過程の数値実験を行った。これらに基づいて,1934年に発生した白山別当崩れを対象に,事例研究を行った。別当崩れは崩壊後,土石流となり,手取川に沿って,70kmも流下し,日本海まで達した大災害である。
1 0 0 0 IR 『フライハイト』紙に見られる革命観--1879-86年
- 著者
- 田中 ひかる
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 一橋論叢 (ISSN:00182818)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.2, pp.340-359, 1996-08
論文タイプ||論説
1 0 0 0 OA 道徳的知と行為のアポリアに抗して-自然主義・歴史主義・共同体主義からの批判とその可能性- : 松下良平著, 『知ることの力-心情主義の道徳教育を超えて-』, 勁草書房, 2002年刊行
- 著者
- 松下 晴彦
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.241-245, 2003-09-27 (Released:2017-08-10)