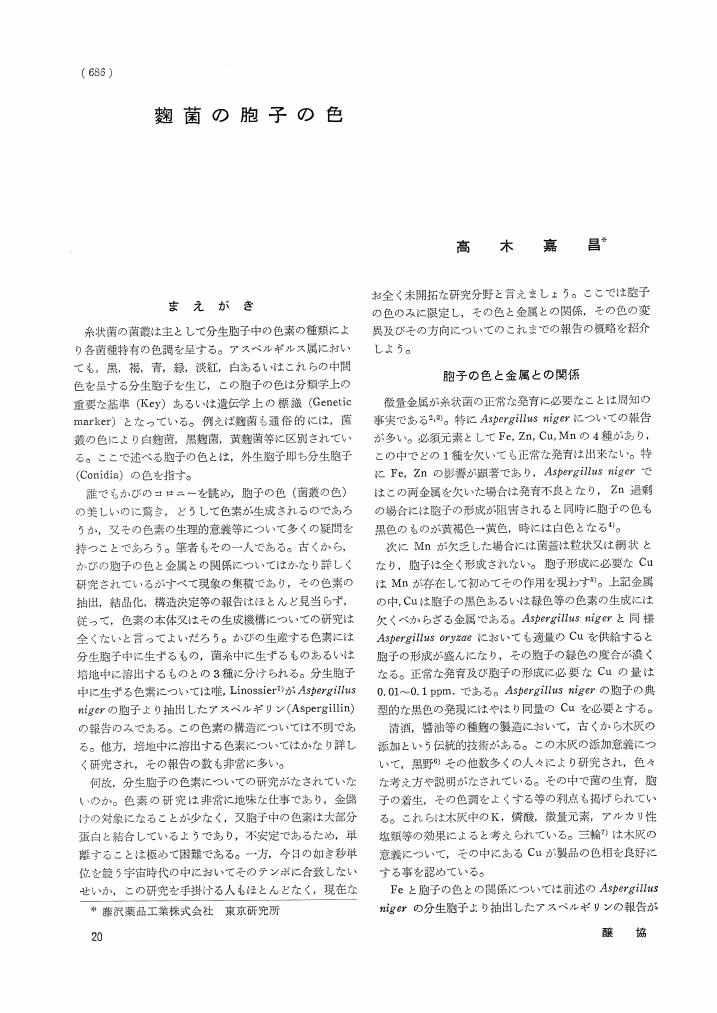1 0 0 0 OA 麹菌の胞子の色
- 著者
- 高木 嘉昌
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.8, pp.686-688, 1963-08-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 水産・海洋系学部・大学院の学生動向,教育の現状と連携の必要性
- 著者
- 梅澤 有 福田 秀樹 小針 統
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.3-10, 2017 (Released:2020-02-12)
- 参考文献数
- 17
地方の都道府県に立地する大学の多くは,18歳人口の減少と大学進学率の停滞によって,地元からの大学進学者の割合が低下し,大都市圏から多くの学生が集まるようになっている.学生は卒業後に出身地に戻って就職をすることも多いため,今後も続くこの傾向は,地方大学の人材育成方針にも影響を与えうる.一方で,卒業生が,水産・海洋系の専門を活かして,大学院への進学や,公的機関に就職するだけでなく,多様な民間企業へと就職していく現在,専門に特化した教育だけでなく,応用力,問題解決能力,語学を含むコミュニケーション能力等を持ち,多方面で活躍できる人材の育成が一つの鍵となっている.アクティブラーニングの活用,地域だけに特化しない総合的な水産・海洋教育,大学間連携と いった大学教育に加えて,地域の小学生から社会人を対象とした教育活動など,広範な視野をもった教育が,今後の水 産・海洋分野の発展には必要と考えられる.
1 0 0 0 OA 小腸アニサキス症により腸閉塞をきたした1切除例
- 著者
- 大島 稔 赤本 伸太郎 柿木 啓太郎 萩池 昌信 岡野 圭一 鈴木 康之
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.589-592, 2011-03-31 (Released:2011-05-10)
- 参考文献数
- 16
症例は30代,男性。刺身を食べた2日後より突然の腹痛を自覚し近医を受診し,加療目的で翌日当院に紹介,入院となった。来院時,激しい腹痛と反跳痛を認めたが筋性防御は認めず,単純撮影でイレウス像を呈していた。CTで腹水の貯留および小腸に限局した壁肥厚と炎症所見を認め,その部位より口側の小腸の拡張を認めた。内ヘルニアなどによる小腸の絞扼性イレウスの他に,画像所見より小腸アニサキス症を疑い,緊急手術を施行した。開腹所見で中等量の腹水を認め,回盲部から100cm口側の小腸壁に点状の発赤と浮腫,肥厚を認めた。同部をイレウスの原因と判断し,小腸部分切除術を施行した。切除腸管の粘膜内に刺入した線虫を認め,小腸アニサキス症と診断した。小腸アニサキス症はまれな疾患であり,一般的に術前診断は困難である。しかし,腸閉塞の鑑別疾患として絞扼性イレウスなどが考えられる場合は時期を逸することなく手術を検討することが重要である。
1 0 0 0 OA 帝国公証人条令(1512年)
- 著者
- 田口 正樹
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.6, pp.266-248, 2015-03-30
1 0 0 0 OA 日本新産鉱物情報(1997年)
- 著者
- 松原 聰
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 鉱物学雜誌 (ISSN:04541146)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.119-120, 1998-05-11 (Released:2009-08-11)
1 0 0 0 OA フッ化物入りペーストがチタンの耐食性に与える影響
- 著者
- 木村 英一郎 野村 智義 溝口 尚 吉成 正雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 雑誌
- 日本口腔インプラント学会誌 (ISSN:09146695)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.54-60, 2014-03-31 (Released:2014-04-20)
- 参考文献数
- 22
Fluoride-containing pastes for professional mechanical tooth cleaning (PMTC) have been frequently used during implant treatment. However, the influence of these pastes on the corrosion resistance of titanium implants is not well understood. The objective of this study was to clarify the influence of the pH of fluoride-containing paste on the corrosion resistance of commercially available pure titanium (cp-Ti). Commercially available PMTC pastes with neutral pH (6.8-7.4) and different fluorine concentration (400-980 ppm), acidulated phosphate fluoride (APF) paste (APF 9000A, fluorine concentration:9000 ppm, pH=3.7), and experimental acidic NaF paste (NaF900A, fluorine concentration:900 ppm, pH=4.0) were applied to polished cp-Ti disks (grade 2). After storing the specimens at 37℃ for 3 days in a humid atmosphere, the color difference was measured, and optical microscope and scanning electron microscope (SEM) observations of the Ti disks were performed. In addition, the amounts of Ti dissolved into the pastes were evaluated. Remarkable color differences were observed on the Ti disks coated with APF9000A and NaF900A pastes of ΔE*ab=12.0(±2.3) and 8.8(±1.4), respectively. In contrast, negligible color differences were observed on the other specimens with ΔE*ab ranging from 0.6 to 1.2. The optical microscopic and SEM observations revealed that the Ti disks coated with APF9000A and NaF900A pastes had roughened surface morphologies caused by pitting corrosion. In addition, noticeable amounts of Ti, 25.3(±6.2) and 8.6(±2.3) µg/cm2, from Ti disks coated with APF9000A and NaF900A pastes, respectively, were detected. Accordingly, the remarkable color differences of the APF9000A and NaF900A specimens were due to the roughening of the surface caused by corrosion of the Ti surface. These results indicate that fluoride-containing pastes with low pH may reduce the corrosion resistance of titanium, and so great care is required when using these fluoride-containing pastes for PMTC.
1 0 0 0 地質調査所における地下水 地下ガスによる地震予知研究の概要
- 著者
- 地震予知 地球化学的研究グループ
- 雑誌
- 地質ニュース
- 巻号頁・発行日
- vol.356, 1984
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 非等温場におけるMiscible Viscous Fingeringの実験的研究
- 著者
- 藤田 憲人 長津 雄一郎 加藤 禎人 多田 豊
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第38回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.197, 2006 (Released:2007-02-09)
1 0 0 0 OA ホソヘリカメムシとBurkholderiaの環境獲得型相利共生
- 著者
- 菊池 義智
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.3_219-3_222, 2014 (Released:2015-04-03)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 初期発生期におけるJNK シグナル伝達経路の多様な生理的役割
- 著者
- 浅岡 洋一
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.59-67, 2013-05-10 (Released:2013-06-21)
- 参考文献数
- 43
c-Jun N-terminal kinase(JNK)シグナル伝達経路は,細胞外からの様々なストレス刺激や発生プログラムなどの内因性シグナルを細胞核へ的確に伝達するための主要なシステムの1つである。JNKはMAPキナーゼファミリーに属するタンパク質リン酸化酵素であり,線虫から哺乳類に至る動物門で幅広く保存されている。JNKは上流の2種類の活性化因子であるMAPキナーゼキナーゼ(MKK)4とMKK7によってリン酸化を受けて活性化し,遺伝子発現を調節することにより多彩な細胞応答を誘導する。近年,MKK4とMKK7のそれぞれのノックアウトマウスを用いた解析から,これらが発生期の肝臓形成や脳形成に重要な役割を果たすことが明らかとなった。一方,JNKシグナルは器官形成期より早い時期の形態形成運動にも関与することが最近になって示され,初期胚のボディプラン形成におけるJNKの役割が注目を集めている。本稿では,MKK4とMKK7の生化学的特性について概説するとともに,各動物種の初期胚形成期における両キナーゼの生理機能を比較し,最後にJNKシグナルが形態形成運動を統御する分子機構の一端についてゼブラフィッシュの知見を中心に紹介する。
1 0 0 0 OA 「就労」の場で若者の「主体」を立ちあげる 支配的文化へのもうひとつの抗い方
- 著者
- 児美川 孝一郎
- 出版者
- 社会文化学会
- 雑誌
- 社会文化研究 (ISSN:18842097)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.49-61, 2012 (Released:2020-04-15)
- 著者
- 長田 有里子 金澤 潤一郎
- 出版者
- 全国大学保健管理協会
- 雑誌
- Campus health 公益社団法人全国大学保健管理協会機関誌 (ISSN:24329460)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.171-177, 2019-05
1 0 0 0 OA 我国における戦後既往最大流量の特徴
- 著者
- 中村 晋一郎 佐藤 裕和 沖 大幹
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.I_1453-I_1458, 2012 (Released:2013-03-26)
- 参考文献数
- 10
In this research, we gathered the Historical Maximum Discharge (HMD) of A class rivers in Japan after World War 2nd (1945) and classify these data into the topography-meteorological area. We used Creager curve for analyzing the regional characteristics of HMD. From this analysis, we explained the difference of the flood specific discharge among geographic regions. And we compared the historical maximum specific discharge between as of 1975 and 2009, so we could explain Creager curves in 3 region was updated and the flood specific discharge in most of river converged to Creager curve.
1 0 0 0 IR 就職活動場面における被援助志向性および友人からのサポート受容と精神的健康の関係
- 著者
- 藤野 真行
- 出版者
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科
- 雑誌
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 心理発達科学 (ISSN:13461729)
- 巻号頁・発行日
- no.66, 2020-01-31
1 0 0 0 IR 「生きる意味」について--フランクルの人間観
- 著者
- 香川 豊
- 出版者
- 甲南女子大学
- 雑誌
- 甲南女子大学研究紀要 人間科学編 (ISSN:13471228)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.9-17, 2002
Today we live in an age of crumbling traditions. Universal values are on the wane. That is why ever more people are caught in a feeling of aimlessness and emptiness. However, even if all human values should disappear, life holds a meaning for each and every individual. Man is responsible for giving the right answer to a question he is asked by life. In other words, Man is responsible for what to do, whom to love, and how to suffer, while Man's freedom is freedom to take a stand on whatever conditions might confront him, And taking a stand toward somatic and psychic phenomena implies opening a new dimension, the spiritual dimension. In this dimension, it is still possible to find a world beyond that of Man. According to Frankl's view, the question of an ultimate meaning for human suffering will find an answer in the spiritual dimension. But Man is incapable of understanding the ultimate meaning of human suffering because the ultimate meaning is no longer a matter of thinking but rather a matter of believing. Moreover, faith in the ultimate meaning is preceded by trust in God. But this relationship between God and human existence is ambiguous in Frankl. It is a problem with his viewpoint.
- 出版者
- [川越市立美術館]
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 OA オランダ領東インドにおける日本企業の進出・定着過程
20世紀におけるアジア地域の発展をミクロレベルで解明・把握するため,本研究では,両大戦間期から戦時期までのオランダ領東インドにおける日本企業の進出・定着過程を一次資料から検討する。本研究は,従来の統計資料や外交資料に基づく検討ではなく,海外に所蔵されている戦前期日本企業アーカイブの資料を利用して,具体的な企業・産業レベルの分析から,その変化を辿った。特に「環太平洋」という視点から,オランダ領東インドを取り巻く欧州―日本―中国―豪州―米国が,産業・貿易の各側面で相互にどのような関係(支配・従属・依存・補完)を構築していたのか,複眼的な視点から研究をまとめた。