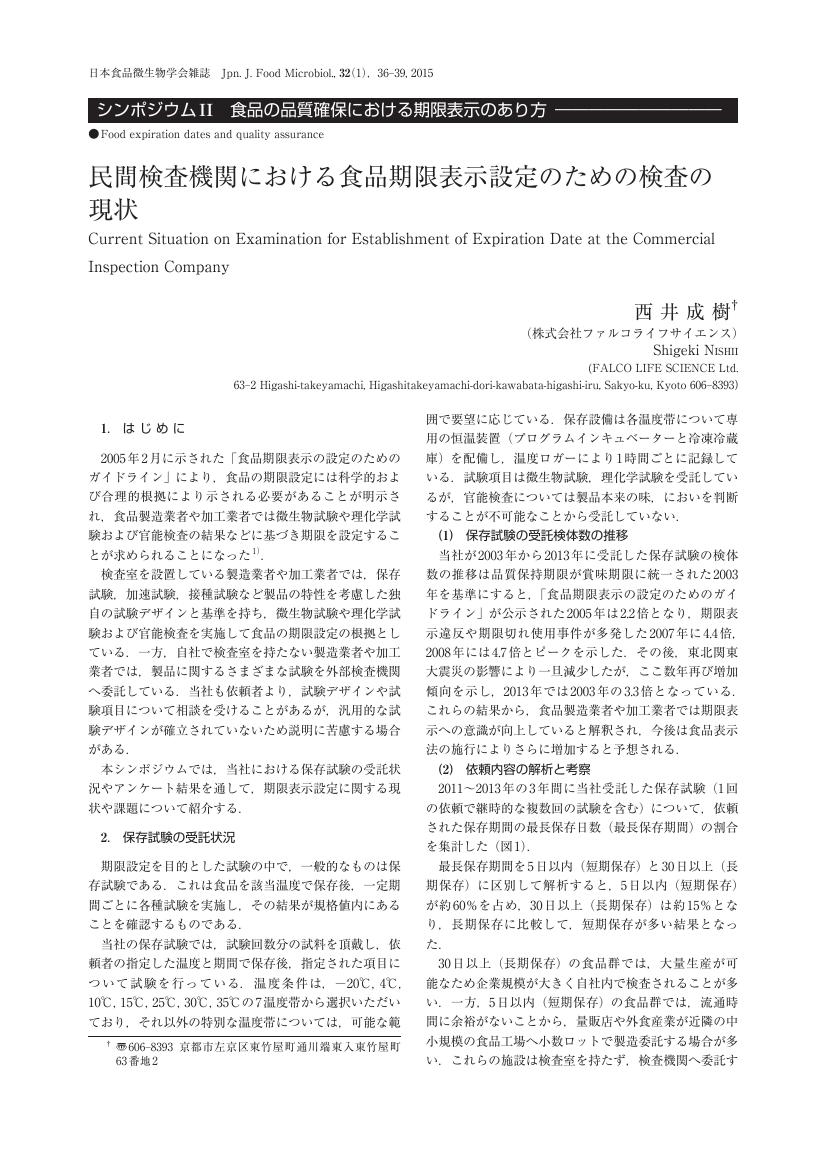1 0 0 0 OA 医療言説におけるゆらぐジェンダー概念と再帰的自己
- 著者
- 石井 由香理 イシイ ユカリ Yukari Ishii
- 雑誌
- Gender and Sexuality : Journal of the Center for Gender Studies, ICU
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.3-22, 2010-03-31
This paper considers the transitions in the "Guidelines for the diagnosis and treatmentof GID" , which was created by the Japanese Society of Psychiatry and Neurology. By analyzing the text of the guidelines, we observe that the current concept of gender has become less influential in representing a consistent identity model for society today.This is reflected in the following distinctions in the transitions of the guidelines in which there are five issues to be emphasized: First, gender identity is defined as being of multiple forms. Second, the approach to medical treatment is determined not only by an individual' s gender identity but also by his/ her life, world and value system. These factors explain the need for more diversity in medical treatment. Third, it is supposed that gender identity has coherence. Fourth, since diversity of gender is more emphasized, a patient's decision concerning treatment is more highly regarded than ever. And lastly, due to the extended scope of decision-making, the range of patients' self-responsibility for the risk is extended accordingly. It is evident from these guidelines that the concept of gender that has hitherto disciplined people has become weaker.However, this does not necessarily mean that society has become an ideal world.There are still various problems concerning the issue of transgenderism that must beconsidered.
1 0 0 0 OA シアニン色素とわが国の写真工業
- 著者
- 大庭 成一
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.152-160, 1994-06-25 (Released:2011-08-11)
- 著者
- 平 久美子 青山 美子
- 雑誌
- 臨床環境医学 : 日本臨床環境医学会会誌 = Japanese journal of clinical ecology (ISSN:09169407)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.114-123, 2006-12-30
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 衛生器具の配置と使用頻度に関する研究
- 著者
- 紀谷 文樹 市川 憲良
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文報告集 (ISSN:09108017)
- 巻号頁・発行日
- vol.359, pp.24-30, 1986-01-30 (Released:2017-12-25)
Many research works were carried out for the estimation of the number of fixtures. However, the method on t:he layout of the sanitary fixtures have not been clear theoretically. The results of the investigations for 6 buildings have shown that the frequency of usage of the sanitary fixtures were changed by the types of the layout. The results are shown as follows ; 1. There are many cases that the water closet and urinals are installed in the depth direction from the entrance. And the fixtures being near the entrance are generally used more than the others. 2. There are few difference of the frequency of usage for the fixtures being same distance from the entrance. 3. The case of the wash basin are installed in the same plane with the water closet and urinals, the wash basin being near those fixtures are used more than the others. 4. The case of the wash basin are installed in the rectangular or counter position of the water closet and urinals, there are a few difference of the frequency of usage, and the fixtures being near the exit are used some more than the others. Finally the authors discussed that those results infulenced for not only the layout of the fixtures but also planning of piping and maintenance.
1 0 0 0 OA 民間検査機関における食品期限表示設定のための検査の現状
- 著者
- 西井 成樹
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.36-39, 2015-03-31 (Released:2015-09-10)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 認知症における食行動異常と嗅覚・味覚の生理学的機能
- 著者
- 坂井 麻里子 西川 隆
- 出版者
- 日本神経心理学会
- 雑誌
- 神経心理学 (ISSN:09111085)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.167-176, 2017-09-25 (Released:2017-10-11)
- 参考文献数
- 51
認知症における食行動異常と嗅覚・味覚の生理学的機能との関連についての近年の知見を概説した.嗅覚障害に関してはいくつかの認知症性疾患に合併するという多くの報告がある.アルツハイマー病(AD)とレビー小体型認知症(DLB)ではしばしば著明な嗅覚障害を早期より認めるが,他の認知症性疾患では著明な障害はみられない.一方,味覚についてはいまだ少数の研究しか見あたらず,結果にも相違がみられる.著者らはADの基本4味覚(甘味・塩味・酸味・苦味)の検知・認知閾値を測定し,認知閾値は初期から上昇するが,検知閾値は遅れて上昇することを見出した.また,意味性認知症(SD)に関する予備的研究では,検知・認知閾値ともに初期から上昇した.これらの知見は特に嗜好の変化を呈するADとSDにおいて基礎的な味覚機能が食行動異常の背景にあることを推測させる.
1 0 0 0 OA 化粧料用粉体の表面処理による高機能化
- 著者
- 田中 巧
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.47-53, 2016-02-20 (Released:2016-05-20)
- 参考文献数
- 14
化粧料用の表面処理技術はここ約30年で飛躍的に発展してきた。耐水性・耐油性の向上による化粧崩れの防止,感触の改良,皮膚への付着性の向上,などを目的として行われてきた。本報では,とくに水にかかわる無機顔料粉体の表面処理の及ぼす特徴について述べる。とくに,水分散性の向上を図るカチオンポリマー,また,pH応答性能を有するアニオンポリマーでの表面処理顔料の特性について,結果を報告する。さらに,ポリアクリル酸エステル球状粒子の加水分解による表面改質で表面にカルボキシル基グループを導入することで,もともと疎水性であったポリアクリル酸エステル球状粒子を親水化するとともに,この粒子を水に分散させるとこの表面に未処理無機酸化物顔料粒子がきれいに付着して水に分散できることを見いだした。また,ジェミニ型化合物の表面処理では,界面活性剤なしで液状エマルジョン化できることも見いだしたので報告する。
1 0 0 0 OA 行政保健師の情報ネットワーク環境とICTの活用
- 著者
- 中谷 久恵 金藤 亜希子
- 出版者
- 一般社団法人 日本地域看護学会
- 雑誌
- 日本地域看護学会誌 (ISSN:13469657)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.64-70, 2018 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 16
目的:本研究の目的は,行政で働く保健師の職場と職場外での情報ネットワーク環境を把握し,ICT活用の現状を明らかにすることである.方法:調査対象者は670人の保健師であり,調査内容は属性,職場と職場外の情報ネットワーク環境と検索学習の実態,eラーニング利用の有無を調査した.調査は,無記名自記式で任意の調査票を配布し,研究者宛に個別に郵送で返送してもらった.結果:350人から回答があり,常勤317人を分析対象とした.職務上の個人専用パソコンは82.6%が保有し,職場外でネットにつながる私用機器は95.0%が所有していた.職務に関する職場内外での検索学習は92.7%が行っており,職務の個人専用パソコンを保有する保健師は検索学習の割合が高かった(p=0.004).eラーニングの学習は77.9%が希望しており,職場内外の情報ネットワーク環境や年齢区分での有意差はなかった.考察:保健師は,個人専用の情報通信機器を8割以上が保有し,インターネットを活用した職務の検索学習を9割以上が実施しており,ICTを活用している実態が明らかとなった.eラーニング利用は約8割が希望しており,保健師はICTを職務の利用に加えて,学習用のツールとしても関心を寄せていることが示された.
1 0 0 0 OA 国公立試験研究機関における有機物・肥料等の長期連用試験の現状について
- 著者
- 金森 哲夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.286-293, 2000-04-05 (Released:2017-06-28)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 秋田県における自殺の実態に関する調査結果の検討
- 著者
- 伏見 雅人 清水 徹男
- 出版者
- 日本精神神経学会
- 雑誌
- 精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica (ISSN:00332658)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.4, pp.367-372, 2009-04-25
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 足利家における笙と笙始儀
- 著者
- 石原 比伊呂
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.766, pp.16-31, 2012-03
1 0 0 0 OA これからの高齢者救急医療の方向性
- 著者
- 山下 寿 矢野 和美 古賀 仁士 爲廣 一仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.471-477, 2018-06-30 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 34
総務省の発表では,2015年の国勢調査で日本は世界最高の高齢化率である26.7%を示し,さらに進行することが予測されている。当院の2010〜2014年の高齢者救急の実態調査を行い,これからの方向性を検討した。高齢者の搬入時重症度は,調査期間を通じて外来帰宅・ICU入院・一般病棟入院・外来死亡の順であった。特徴は,ICU入院が高率であったことであり(28.6〜32.7%),その平均年齢は80±8歳であった。また病院到着時心肺停止例に関しては,救命率・社会復帰率・神経学的予後は非高齢者に比して有意に劣っており,一方では医療費には有意差は認めなかった。今後はフレイルに関する臨床データが蓄積され,高齢者各自に応じた適正医療の指針が示されれば,すべての高齢者に一律に最新の高度な救急集中治療を行う医療から,過剰医療・過少医療など不適切な医療が減少し,結果的に医療費削減につながる。