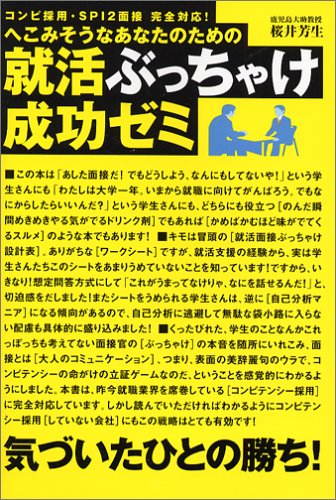1 0 0 0 『醜い韓国人』の著者論争に完全決着--加瀬英明氏が"敗北宣言"
1 0 0 0 OA 自閉症スペクトラム児と保護者の関係発達
- 著者
- 高橋 ゆう子
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究 (ISSN:21871930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.29, pp.581-590, 2019-01-01 (Released:2019-11-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
本論の目的は,RDI(対人関係発達指導法)の特徴と効果について,一家族の事例から検討することである.対象は,6 歳のASD 児とその両親で,約2 年間RDI に取り組み,その間,アセスメント(RDA)として親子のやりとりを3 回録画した.その映像は,関係性を捉える3 つの状態(共同注意,相互調整,間主観性)について評価された (Larkin, et al, 2010).また,日常生活における母子のやりとりを録画した63 場面について母親が振り返りとして記述した内容について,コンサルタントとともに分類を試み,その特徴を整理した.結果は次の通りである.まず,3 回のRDA から父親,母親とも共同注意,相互調整,間主観性のいずれにも変化がみられた.次に母親の記述については,その内容が肯定,否定,分析,課題,疑問の5 つのカテゴリーに分類でき,否定的な内容が減って肯定的なもの,子どもとの関係性に関する内容が増えた.以上から,RDI が親子の関係性の変容に影響することが推測された.そして,情緒的意欲的関係性に焦点をあてた育て直しをねらったRDI の特徴と課題について考察を行った.
1 0 0 0 OA 粘弾性流体のレオロジーの基礎
- 著者
- 鈴木 洋
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.47-51, 2011-02-20 (Released:2011-05-20)
- 参考文献数
- 11
インクなど(含色材流体)の塗布プロセスを考えるうえで,流体の流動特性について知ることは重要である。インクの多くは色素微粒子が溶媒(分散媒)に懸濁された状態(サスペンジョン)であり,一般に通常知られている水や空気のような単純な粘度特性を示さない。乾式である場合にも同様である。また媒体によっては粘弾性という特殊な性質を示す場合があり,この場合にはより複雑な流動特性が発現する。ここではこれら特殊な流体を取り扱うレオロジーに基づき,かかる複雑流体の基礎的な流動特性について解説する。
- 著者
- 朽木 量
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.591-614, 2000-05
問題の所在I 民俗学・石造美術史・文献史学における近世石工の研究 (1) 「渡りの石工」と「村の石工」 (2) 奈良における近世石工研究II 木津地域周辺の鉄石製墓標の消長 (1) 木津郷にみられる墓標型式と石材の分類 (2) 木津郷周辺の墓標から見た鉄石使用の地域的傾向III 鉄石採石の歴史的背景結語研究ノート
1 0 0 0 IR 鎌倉期における石造美術をめぐる若干の問題
- 著者
- 浅子 勝二郎
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.1-35, 1967-03
On a dry river-beach of the upper stream of the Narawa river (成羽川) in Bicchucho (備中町), Okayama prefecture, there is a monument called "Kasagami no Mojiiwa" (笠神の文字岩). It was set up in memory of the opening of the water way which had been completed in 1307. The details of its construction are engraved on that monument. According to it, I would like to call attention to a stone mason, named Ingyokei (伊行径) who took part in the construction of the water way. He was a descendant of Ingyomatsu (伊行末), a famous mason of the Sung dynasty who had come to Japan and made a contribution to the reconstruction of Todaiji (東大寺). We can find nine stone monuments which are regarded as Ingyokei's works. He started his work in Bicchu and afterward went to Kinki where he left some of his works. In order to study Ingyokei's works, it would be well to classify them into two groups, namely the works produced in Bicchu and the works produced when he left Bicchu. In the same period when Ingyokei was working actively in Bicchu, an anonymous mason who had some relation with Ninsho (忍性), the priest of Saidaiji (西大寺) in Nara, was producing some excellent stone objects in the districts of Hakone and Kamakura. In this article I wish to find out the currents of cultural influence between the western and the eastern parts of Japan during the Kamakura period with special reference to the aforesaid stone objects.
1 0 0 0 IR <紹介>川勝政太郞著 石造美術
- 著者
- 中村 直勝
- 出版者
- 史學硏究會 (京都帝國大學文學部内)
- 雑誌
- 史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.451-452, 1939-04-01
1 0 0 0 紀伊高野山奥之院石造美術調査記 (第一)
- 著者
- 天岸 正男
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1956, no.36, pp.58-72, 1956
1 0 0 0 砂岩製石造遺物における銘文の風化傾向と銘文の取得方法について
- 著者
- 上椙 英之 上椙 真之
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. 人文科学とコンピュータ研究会報告
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.2, pp.1-2, 2014-07-26
砂岩製の石造遺物は風化が早く,日々剥落・摩耗で文字情報が失われている.本論文では,この砂岩製の石造遺物の風化傾向を踏まえた上で,文字情報の取得のための画像処理方法を検討した.
1 0 0 0 石造遺物銘文取得のためのデータベース開発
- 著者
- 上椙 英之 上椙 真之 多仁 照廣
- 雑誌
- じんもんこん2012論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.7, pp.179-184, 2012-11-10
1 0 0 0 OA 灸法の学理
- 著者
- 木下和三郎 編
- 出版者
- 日本理科医学院出版部
- 巻号頁・発行日
- 1935
1 0 0 0 IR 〈表紙写真解説〉舞楽面〈新鳥蘇〉(奈良・春日大社)
- 著者
- 稲本 泰生
- 出版者
- 奈良国立博物館
- 雑誌
- 奈良国立博物館だより
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.[6], 2007-10
1 0 0 0 舞楽と能--追っかけの話
- 著者
- 上田 成之助
- 出版者
- 関西交通経済研究センター
- 雑誌
- 関交研 (ISSN:13499920)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.13-16, 2006
- 著者
- 西部 忠
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.22-35, 2015-04-20 (Released:2017-04-25)
The present paper shows, by using different models of scientific research and methodology, that economics and economy coevolve because there exists a bidirectional causal relation between them, and that Keynes, Hayek and Marx all knew its unique implications for economic policy of the government and economic thought of the public even in different views. We focus on Marx's historical materialism (HM) and his model for coevolution of economics and economy that comprises HM as pre-theory, and advocate the necessity of transforming HM into historical knowledgism (HK) in the 21st century of post-industrial society. Finally we present the framework of evolutionary economics in view of HK and explain its implication for theory and policy.
- 著者
- Satoru Mitsuboshi Naoki Tsuruma Kazuya Watanabe Shigehiro Takahashi Atsuko Ito Manami Nakashita Mitsuyuki Suzuki Kenichi Kobayashi Masami Tsugita
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.JJID.2019.411, 2020-07-22 (Released:2020-07-22)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4
A 5-year multicenter retrospective cohort study was conducted across six hospitals in Niigata, Japan. Patients (n = 179) with bacteremia due to extended-spectrum β-lactamase (ESBL)producing organisms were included in the study. The rates of appropriate carbapenem prescription were 61% (n = 41) in patients aged 65–84 years and 89% (n = 31) in those aged ≥ 85 years. Patients aged ≥ 85 years were significantly more likely to receive carbapenem than their younger counterparts. After propensity score matching, 65 patients were assigned to two groups based on age (65–84 years or ≥ 85 years). Multivariate regression analysis showed that other sites of infection had a positive association with 30-day mortality (odds ratio [OR], 27.50; 95% confidence interval [CI], 2.90–260.00) and biliary tract infection tended to have a positive association with 30-day mortality (OR, 8.90; 95% CI, 0.88– 89.90) compared with urinary tract infection. However, an age ≥ 85 years was not associated with 30-day mortality. Elderly patients aged ≥ 85 years were more likely to be treated with carbapenem; however, old age was not associated with 30-day mortality when bacteremia was caused by ESBLproducing organisms. These results may help clinicians justify withholding carbapenem in patients aged ≥ 85 years.
1 0 0 0 OA 韓国語の助詞-에と-를/-을の接点に関する研究
1 0 0 0 OA 東京府勢概要
- 著者
- 東京府総務部調査課 編
- 出版者
- 東京府総務部調査課
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和12年, 1937
1 0 0 0 OA 憲政回顧録
- 著者
- 岡崎邦輔 著
- 出版者
- 福岡日日新聞社東京聯絡部
- 巻号頁・発行日
- 1935
1 0 0 0 OA 胡麻豆腐の物理的性質と構造に及ぼす調製条件の影響
- 著者
- 佐藤 恵美子 三木 英三 合谷 祥一 山野 善正
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.10, pp.737-747, 1995-10-15 (Released:2009-05-26)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 8 6
「煮つめ法」,「滴下法」を用いて調製した胡麻豆腐の調製時における攪拌速度と加熱時間の影響について,テクスチャー測定,クリープ測定,走査型電子顕微鏡による構造観察を行って検討したところ,次のような結果が得られた.(1) 「煮つめ法」により調製した胡麻豆腐のクリープ曲線は四要素モデル(E0, E1, ηN, η1)として解析可能であった.硬さおよび瞬間弾性率,フォークト体弾性率(E0, E1)は,どの攪拌速度においても加熱25分(谷の部分)で最も軟らかくなり,その後加熱時間の増加とともに硬くなった.また,その加熱25分の調製条件が構造的にも均一な蜂の巣状構造を形成した.「滴下法」によるテクスチャーと加熱時間における一次式の傾きは,加熱45分までの時間依存性を示すもので,攪拌速度が高くなる程,大きくなり,付着性には攪拌速度による依存性が認められた.ニュートン体粘性率,フォークト体粘性率(ηN, η1)は加熱時間にともなう変化がテクスチャーの付着性と類似していた.(2) 走査型顕微鏡観察の結果,加熱15分では不均一な部分があり,加熱25分で均一な空胞が形成され蜂の巣状を示した.さらに加熱攪拌を続けると蜂の巣状構造は崩壊し始めた,250rpm 25minの試料が空胞の形成がよく,最も均一な蜂の巣状の空胞の集合体が観察された.(3) 胡麻豆腐は葛澱粉を主体とするゲルであり,胡麻の蛋白質と脂質が関与している相分離モデルであると推察される.