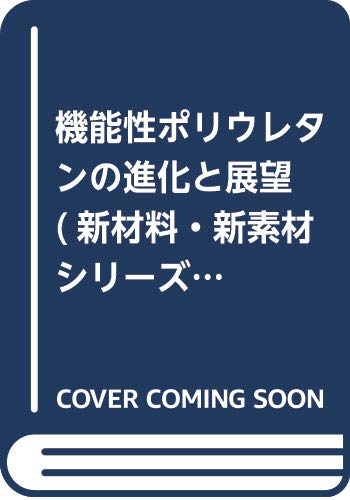1 0 0 0 OA 精米の賞味期限の設定 (第1報) : 貯蔵中の理化学特性の変化
- 著者
- 横江 未央 川村 周三
- 出版者
- 農業食料工学会
- 雑誌
- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.55-62, 2008
本研究は, 市販の普通精米と無洗米を用いて貯蔵試験を実施し, 理化学測定と官能試験を行い, 精米の賞味期限を設定することを目的とした。本報では特に貯蔵中の精米の理化学特性の変化について検討した。貯蔵試験は-20℃, -5℃, 5℃, 15℃, 25℃の温度で1年間行った。さらに翌年-20℃, 5℃, 15℃, 20℃, 25℃で6ヵ月の貯蔵試験を行った。その結果, 脂肪酸度は貯蔵に伴い貯蔵温度が高いほど大きく増加したが, 多くの理化学測定項目において普通精米, 無洗米ともに, 温度15℃以下では貯蔵終了時まで変化が認められなかった。炊飯米外観および米飯粘弾性では, 貯蔵前の品質が良い米は貯蔵中の品質劣化が小さく, 貯蔵前の品質が悪い米は貯蔵中の品質劣化が大きかった。
1 0 0 0 OA 中年および老年者における血清LDH分画と血清ビタミンCの相関
- 著者
- 今木 雅英 三好 保 吉村 武 棚田 成紀 松本 和興
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.87-91, 1988-07-30 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 13
健康な中年および老年者における血清LDH活性値およびアイソザイム分画比と血清ビタミンCの関連性について検討した。対象者は、漁村住民男性87名, 女性83名 (年令45-84才) である。男女とも各年令グループ (45-59才グループ, 60-69才グループ, 70才以上グループ) において血清LDH総活性値と血清ビタミンCは、統計的に有意な関係はみとめられなかった。しかし、男女とも血清LDH-4分画比, 血清LDH-5分画比と血清ビタミンCはすべての年令グループにおいて統計的に有意な負の相関関係が認められた。
1 0 0 0 IR 司法制度改革批判補遺(7)検察審査会による強制起訴制度の問題点
- 著者
- 西野 喜一
- 出版者
- 新潟大学法学会
- 雑誌
- 法政理論 (ISSN:02861577)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.105-114, 2014-02
- 著者
- 織田 信夫
- 出版者
- 新潟大学法学会
- 雑誌
- 法政理論 (ISSN:02861577)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.69-92, 2014-04
1 0 0 0 IR 訴追過程の市民参加 : 検察審査会制度の意義と課題についての予備的考察
- 著者
- 岡田 悦典
- 出版者
- 南山大学法学会
- 雑誌
- 南山法学 (ISSN:03871592)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.27-55, 2014-09
1 0 0 0 OA 北海道のお菓子メーカーの経営戦略とそれを支える要因について
- 著者
- 池田 幸代 イケダ ユキヨ Yukiyo Ikeda
- 雑誌
- 東京情報大学研究論集
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.62-90, 2011-09-30
本研究では、地域に密着した経営を行う企業が成長していくために必要な要因について明らかにすることを目的としている。そのために北海道札幌の代表的な菓子メーカーである「(株)きのとや」を事例として取り上げている。そしてこの企業の成長プロセスをいくつかの時期に分け、経営戦略の様々な視点から分析を行っている。この企業は創業時より、店舗の立地上の不利益や限定された販売エリア、厳しい競争環境といった様々な困難に直面してきた。しかし、この企業は、成長過程のそれぞれの時期において、戦略上の対応を変えることで成長を続けてきた。企業の成長の過程では、戦略ポジショニングの変更と製品開発を行うとともに、戦略ポジショニングを支える組織能力の構築がすすめられていた。このように、本研究は、企業がいかにしてこうした直面する問題を克服してきたかについて明らかにするものである。
1 0 0 0 検察審査会問答2015
- 著者
- 田中 輝和
- 出版者
- 東北学院大学法学政治学研究所
- 雑誌
- 東北学院大学法学政治学研究所紀要 (ISSN:09194347)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.23-37, 2016-03
1 0 0 0 検察審査会の機能の変化と問題点 : 米国の大陪審制度を参考に
- 著者
- 篠原 亘
- 出版者
- 中央大学法学会 ; 1891-
- 雑誌
- 法学新報 (ISSN:00096296)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.7, pp.145-171, 2017-12
1 0 0 0 IR 検察審査員の判断を規定する要因 : 大学生を対象とした模擬検察審査会実験の結果から
- 著者
- 山崎 優子
- 出版者
- 立命館地域情報研究所
- 雑誌
- 地域情報研究 : 立命館大学地域情報研究所紀要 (ISSN:24240923)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.73-89, 2018-03
1 0 0 0 OA 音韻処理障害のメカニズム
- 著者
- 大槻 美佳
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.197-203, 2018-06-30 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 10
非定型な症状を呈した患者を通して, 音韻処理について考察した。本患者は, 言語表出は, 自発話のみでなく, 呼称, 復唱, 書字など全ての表出で, 音韻性錯語, 新造語, 音韻性ジャルゴンが中心であったが, 一方, 言語理解は, 聴覚的には単語レベル, 視覚的には (文字呈示) , 文レベルでも可能であるという乖離を示した。また, 「1 音を聞いて, 該当する仮名文字を選択する」課題も全くできなかったが, 詳細に調べると「1 音」の弁別・認知は可能で, かつ, 「仮名文字」の弁別・認知も可能であることが明らかになった。本患者の症候から, いわゆる ‘音韻処理障害’ には, これまで言及されてきたような, 音韻の認知・喚起・選択・把持・配列などの障害のみでなく, 記号としての役割はある程度果たせるものの, 音響的な表出や文字表出という次のステップに利用できないという壊れかたもある可能性が推測される。
1 0 0 0 OA 小型電子器機のワイヤレス充電に関する一検討
- 著者
- 内山 直美 山田 博仁
- 出版者
- 科学・技術研究会
- 雑誌
- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.71-76, 2020 (Released:2020-06-30)
近年、さまざまな種類の小型電子機器の普及に伴いワイヤレス充電(給電)の研究が盛んにおこなわれているが、新規手法として光ワイヤレス充電の研究が進められている。光ワイヤレス充電は、主に送信器にレーザーやLEDのような光源、受光器に太陽電池のような受光素子を用いる方式である。安全面に制約のないLEDの研究事例は少ない。本研究では、室内でよく使われる赤外線リモコンの光ワイヤレス充電の方式について検討した。その結果、小型の結晶Si太陽電池セルと蓄電デバイスを内蔵すれば、近赤外LEDからの光により室内においても動作可能となる十分な電力量が蓄電され、乾電池レスにできることがわかった。
1 0 0 0 OA 【画像応用技術専門委員会】ViEWとアルコン—IAIP最新活動報告—
- 著者
- 梅田 和昇 寺田 賢治 野口 稔
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.10, pp.841-845, 2016-10-05 (Released:2016-10-05)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 機能性ポリウレタンの進化と展望
- 著者
- 古川睦久 和田浩志監修
- 出版者
- シーエムシー出版
- 巻号頁・発行日
- 2018
- 著者
- 児玉 徳美
- 出版者
- 立命館大学人文学会
- 雑誌
- 立命館文學 (ISSN:02877015)
- 巻号頁・発行日
- no.596, pp.202-183, 2006-11
1 0 0 0 OA インスリン抵抗性と糖代謝
1 0 0 0 OA とろろ昆布を用いた,生体関連物質に関する実験(定番!化学実験(高校版)60:生命と物質)
- 著者
- 小林 邦佳
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.96-97, 2009-02-20 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 価格規制撤廃後の航空運賃設定についての統計的分析
1 0 0 0 OA Building a Low-cost Standalone Electrochemical Instrument Based on a Credit Card-sized Computer
- 著者
- Toshi NAGATA Kentaro SUZUKI
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.10, pp.1213-1216, 2018-10-10 (Released:2018-10-10)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3
A low-cost, standalone electrochemical instrument was built from a credit card-sized computer and inexpensive A/D and D/A converter chips. The instrument is capable of cyclic voltammetry and constant potential electrolysis, with the potential range of –4 to +4 V and the current range of 1 μA to 20 mA.
1 0 0 0 OA 肩関節初期屈曲・外転角度での僧帽筋の機能について
- 著者
- 福島 秀晃 三浦 雄一郎 布谷 美樹 田中 伸幸 山本 栄里 鈴木 俊明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0635, 2005 (Released:2005-04-27)
【はじめに】我々は、肩関節疾患患者の肩甲上腕リズムの乱れに関して、肩関節屈曲に伴い肩甲骨には力学的に前傾方向へのモーメントが加わり、これを制動できない場合は、肩甲骨の安定した円滑な上方回旋に支障が生ずるのではないかと考えている。そこで、第44回近畿理学療法学術集会にて、屈曲30°位において僧帽筋下部線維は上部・中部線維と比較して有意に筋活動が増大したことから、この前傾モーメントを制動するには解剖学的に僧帽筋下部線維が有効であると報告した。このことから、上肢の運動に伴い肩甲骨には力学的なモーメントが生じ、また運動方向の違いによって肩甲骨にかかるモーメントも異なることが示唆された。今回、肩関節外転運動に着目し、肩関節屈曲運動と比較して肩甲骨に生じるモーメントが異なると仮定し、肩関節初期屈曲・外転角度における僧帽筋の肩甲骨安定化機能を筋電図学的に比較・検証したので報告する。【対象と方法】対象は健常男性7名(平均年齢28.7±4.2歳)、両上肢(14肢)とした。運動課題は端座位姿勢での上肢下垂位、屈曲30°位および外転30°位をそれぞれ5秒間保持し、それを3回施行した。測定筋は僧帽筋上部・中部・下部線維とし筋電計myosystem1200(Noraxon社製)を用いて測定した。分析方法は下垂位の筋積分値を基準に屈曲30°位と外転30°位の筋積分値相対値を算出し、各線維ごとに対応のあるt検定を行った。なお、対象者には本研究の目的・方法を説明し、了解を得た。【結果と考察】僧帽筋上部・中部線維の筋積分値相対値は、屈曲位と比較して外転位において有意に増大した(p<0.01)。一方、下部線維の筋積分値相対値は屈曲位と比較して外転位において減少傾向となった。肩甲上腕リズムでは屈曲60°、外転30°までは肩甲骨の運動なしに肩甲上腕関節固有の運動でなされるsetting phaseの時期である。本研究における運動課題もsetting phaseの時期であり、この時期での僧帽筋の活動は肩甲骨と体幹を固定するための活動であると考える。山本らは正常な肩甲骨の動きは胸鎖関節を支点として三次元的に制動方向が導かれることとなるが、その動的な制御は肩甲骨と胸郭を連結している筋群のバランスと肩鎖関節の安定性により決定されるとしている。僧帽筋上部・中部線維については解剖学的に鎖骨外側1/3・肩峰・肩甲棘上縁に付着しており上肢の外転運動に伴う肩甲骨の下方回旋モーメントへの制御に機能したと考える。一方、下部線維については解剖学的に肩甲棘内側下部(肩甲棘三角)に付着しており上肢の屈曲運動に伴う肩甲骨の前傾モーメントへの制御により機能したと考える。以上より、上肢の運動方向が異なれば肩甲骨に生じる力学的なモーメントも異なり、そのモーメントに応じて選択的に僧帽筋の各線維がより活動し肩甲骨を制御することが示唆された。
1 0 0 0 IR 自治体における人事異動の実証分析 : 岡山県幹部職員を事例として
- 著者
- 前田 貴洋
- 出版者
- 首都大学東京都市教養学部法学系
- 雑誌
- 法学会雑誌 (ISSN:18807615)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.343-391, 2016-01