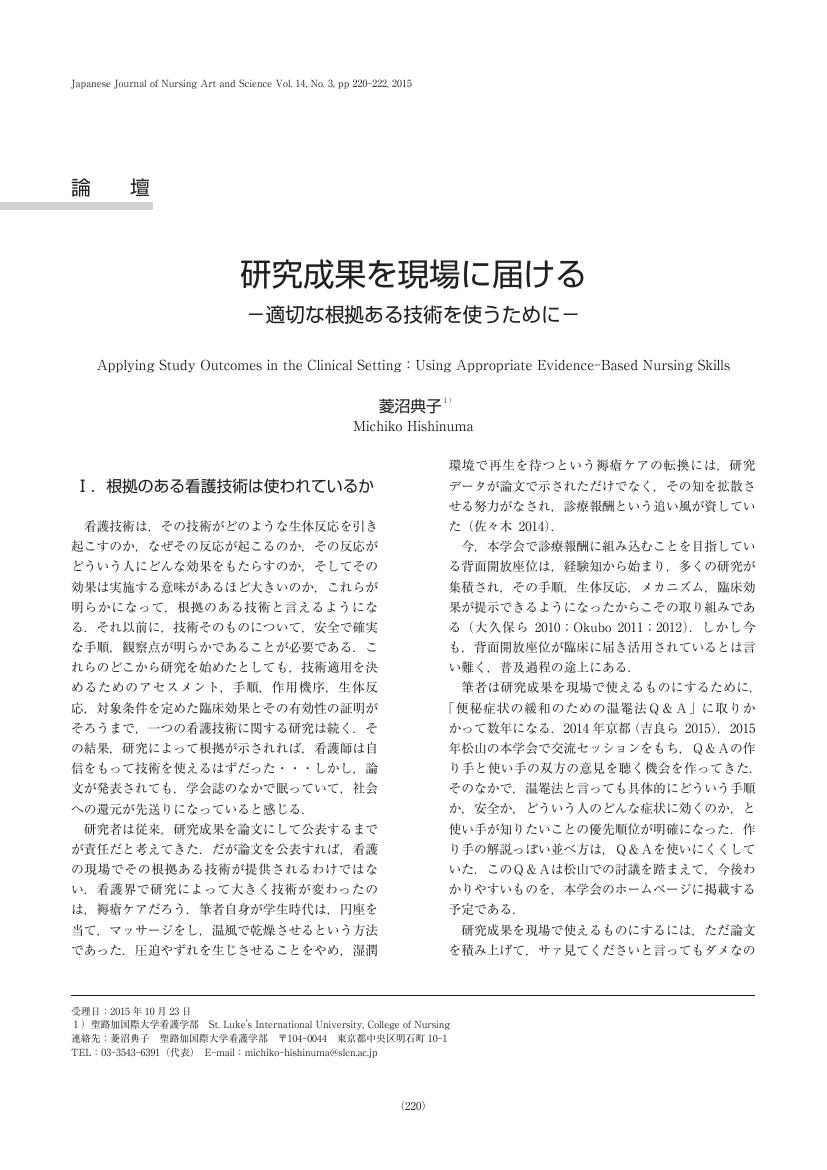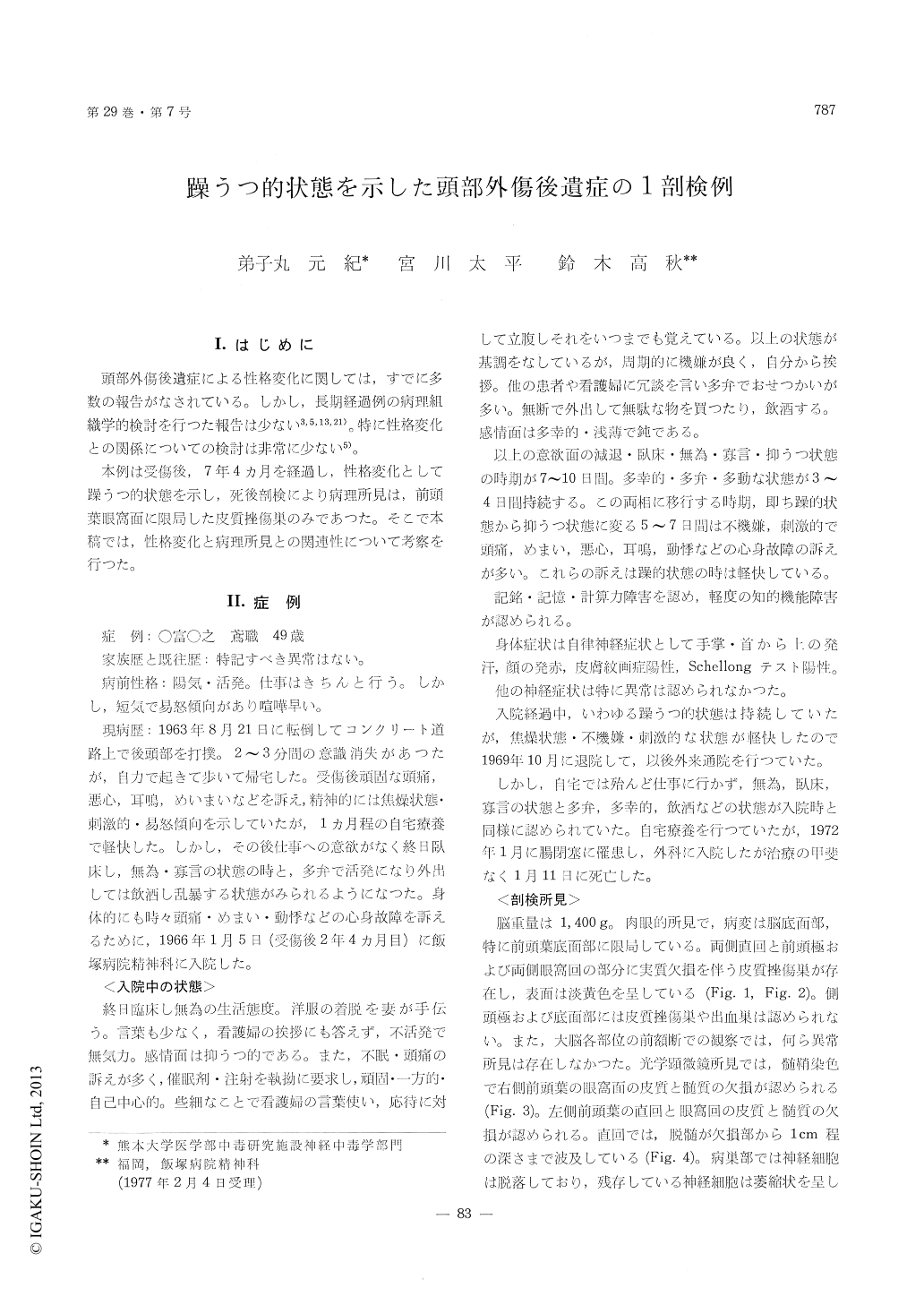- 著者
- 青木 信之 鈴木 繁夫 渡辺 智恵 池上 真人 松原 緑 榎田 一路 寺嶋 健史 汪 曙東 高橋 英也 阪上 辰也 江村 健介
- 出版者
- 広島市立大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2017-04-01
2018年度(平成30年度)については、本科研の最大課題について大きな知見が得られた年度となった。まず学生に実施したアンケート結果については、多くの大学生は長期休暇期間後の英語力低下は感じている、学習不足も感じている、しかし休暇期間中の学習機会の大学による提供については積極的ではなく、学習を管理されることについてはほとんど望まないということであった。一方、少人数ではあったが、長期休暇期間中に英語e-ラーニングを実施した大学では、学習量は学期中よりかなり少なかったものの、それでも受講しなかった学生達に比べて、英語力が向上あるいは維持されるという結果が示された。本研究で取り組もうとしてきたのは、英語力を向上させるには(特にある程度の基礎力をもった大学生の場合は)、集中的に大量の学習をさせることが必要であり、そしてそれをe-ラーニングによって実施することが可能であるということであった。本科研では、それに加えて、教養教育期間中にしっかりと英語力を上げ、そしてそれを維持させるには、長期休暇期間中の学習不足を克服する必要があり、それこそe-ラーニングの出番であることを証明するということで主目的であった。つまり、本科研の最大のポイントは、長期休暇中の英語力低下を防ぐという点であり、そういった意味では大きな前進があったと考えている。
1 0 0 0 OA 固体電解質LixLa(1-x)/3NbO3のバルク単結晶
- 著者
- 藤原 靖幸 太子 敏則 干川 圭吾 小浜 恵一 胡 肖兵 小林 俊介 幾原 裕美 Craig Fisher 幾原 雄一 射場 英紀
- 出版者
- 日本結晶成長学会
- 雑誌
- 日本結晶成長学会誌 (ISSN:03856275)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.46-1-04, 2019 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 22
Bulk single crystals of the perovskite LixLa(1-x)/3NbO3, which is one of the materials used as the solid electrolyte in all-solid lithium-ion batteries, have been grown for the first time by the directional solidification method. The ionic conductivity measured in the growth direction of the single crystal wafer of LixLa(1-x)/3NbO3 and the anisotropy of ionic conduction in solid electrolyte were experimentally confirmed for the first time by using LixLa(1-x)/3NbO3 single crystals. Here, the results of four experiments on LixLa(1-x)/3NbO3 bulk single crystals are presented: (1) growth of solid electrolyte LixLa(1-x)/3NbO3 bulk single crystals, (2) ionic conduction in LixLa(1-x)/3NbO3 single crystal, (3) anisotropy of ionic conduction in LixLa(1-x)/3NbO3 single crystal and (4) microstructure analysis of LixLa(1-x)/3NbO3 single crystal.
- 著者
- 宮本 直美
- 出版者
- 日本ポピュラー音楽学会
- 雑誌
- ポピュラー音楽研究 = Popular music studies (ISSN:13439251)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.33-47, 2014
1 0 0 0 カンナビノイドの睡眠調節に及ぼす作用に関する研究
- 著者
- 内山 奈穂子 有竹 浩介 マリシェフサカヤ オリガ
- 出版者
- 国立医薬品食品衛生研究所
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-01
大麻由来カンナビノイドΔ9-THC或いは合成カンナビノイド(JWH-018)を投与したマウスの脳波と自発運動量の変化を調べた.マウスにΔ9-THCを腹腔内投与すると,有意な行動量の低下が観察され,痙攣行動と痙攣脳波が誘発され,痙攣脳波は断続的に4時間以上持続して起こることが判明した.一方,JWH-018を腹腔内投与すると,Δ9-THCと比較して,行動量の抑制と痙攣がより投与から短時間に誘発されることが判明した.さらに,JWH-018によるマウスへの痙攣誘発作用が容量依存的に起こることが明らかとなった.また,CB1受容体選択的拮抗薬AM251をΔ9-THC 或いはJWH-018投与の30分前に腹腔内投与しておくと,行動量の抑制と痙攣の誘発が完全に消失することが判明した.従って,Δ9-THCやJWH-018は,CB1受容体を介してマウスに痙攣を誘発することが示された.次に,痙攣を誘発するΔ9 -THC用量の閾値を検討した結果,投与量2.5 mg/kgが痙攣を誘発する最低用量であった.さらに,脳波スペクトルの特性を視覚的に区別することができる脳波解析:スペクトログラムとエンベロープ変動係数解析を行った.さらに,Δ9-THCの反復投与により,投与3-4日後に痙攣の発生数が減少したことから,Δ9-THC連続投与により身体的な耐性が生じることが示された.また,CB1受容体拮抗薬をマウスに前投与することにより,Δ9-THCおよびJWH-018によって誘発される痙攣が抑制されたことから,これらの痙攣作用は,CB1受容体を介して起こることが示された.さらにCB1受容体KOマウスにJWH-018を腹腔投与した結果,CB1受容体KOマウスはJWH-018投与後に痙攣の脳波または痙攣行動を示さなかったことから,JWH-018の痙攣作用は,CB1受容体を介して起こることが改めて確認された.
1 0 0 0 OA リハビリテーション3.0とメルロ=ポンティの身体性
- 著者
- 稲垣 諭
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター
- 雑誌
- 神経現象学リハビリテーション研究 = Neurophenomenological rehabilitation study (ISSN:18846912)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.43-51, 2020-03
1 0 0 0 OA 海水に含まれるミネラル成分 (オリゴマリン®) の保湿ならびに肌荒れ改善効果
- 著者
- 大江 昌彦 奥村 秀信 山村 達郎 松中 浩 森岡 恒男
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.220-225, 2004-09-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
海水に含まれるミネラル成分であるオリゴマリン®について, 保湿ならびに肌荒れ改善作用に着目して検討を行った。その結果, オリゴマリン®は培養真皮線維芽細胞を活性化して, コラーゲン産生を促進した。また, 培養ケラチノサイトに対しては, 角化マーカーであるトランスグルタミナーゼ (TG-1) やインボルクリンの発現を高め, 角化を充進させることを確認した。さらに, オリゴマリン®の配合量に応じて角層水分量が増加することから, 肌表面での保湿作用が確認できた。実際に, 乾燥肌の被験者を対象とした使用試験の結果, オリゴマリン®を配合したローションの使用部位で角質水分量の増加, TEWLの減少, ならびに角質細胞形態の改善が観察された。したがって, オリゴマリン®には, 真皮マトリックス構造を強化するとともに, 表皮の角化を促してバリア機能を改善することで肌表面の水分保持能を高め, 肌荒れの予防・改善に有用であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 研究成果を現場に届ける
- 著者
- 菱沼 典子
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.220-222, 2015 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 13
- 著者
- Koji HIRAKAWA Masaaki KATAYAMA Nobuaki SOH Koji NAKANO Toshihiko IMATO
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.81-86, 2006 (Released:2006-02-24)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 6 10
A rapid and sensitive immunoassay for the determination of vitellogenin (Vg) is described. The method involves a sequential injection analysis (SIA) system equipped with an amperometric detector and a neodymium magnet. Magnetic beads, onto which an antigen (Vg) was immobilized, were used as a solid support in an immunoassay. The introduction, trapping and release of magnetic beads in an immunoreaction cell were controlled by means of the neodymium magnet and by adjusting the flow of the carrier solution. The immunoassay was based on an indirect competitive immunoreaction of an alkaline phosphatase (ALP) labeled anti-Vg monoclonal antibody between the fraction of Vg immobilized on the magnetic beads and Vg in the sample solution. The immobilization of Vg on the beads involved coupling an amino group moiety of Vg with the magnetic beads after activation of a carboxylate moiety on the surface of magnetic beads that had been coated with a polylactate film. The Vg-immobilized magnetic beads were introduced and trapped in the immunoreaction cell equipped with the neodymium magnet; a Vg sample solution containing an ALP labeled anti-Vg antibody at a constant concentration and a p-aminophenyl phosphate (PAPP) solution were sequentially introduced into the immunoreaction cell. The product of the enzyme reaction of PAPP with ALP on the antibody, p-aminophenol, was transported to an amperometric detector, the applied voltage of which was set at +0.2 V vs. an Ag/AgCl reference electrode. A sigmoid calibration curve was obtained when the logarithm of the concentration of Vg was plotted against the peak current of the amperometric detector using various concentrations of standard Vg sample solutions (0 - 500 ppb). The time required for the analysis is less than 15 min.
1 0 0 0 OA 中性子・放射光による構造物性研究, および結晶学の発展への貢献
- 著者
- 藤井 保彦
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.131-138, 2012-06-30 (Released:2012-07-03)
- 参考文献数
- 49
In this article, I have reviewed a series of research on a various phase transitions such as (1) structural phase transitions of perovskite compounds driven by soft phonons, (2) pressure-induced molecular dissociation and metallization observed in solid halogens, and (3) the “Devil's Flower” type phase diagram observed in two compounds with frustrating interactions. Also commented is on the so-called “Small Science at Large Facility” typically symbolized by neutron and synchrotron radiation experiments like the present research.
1 0 0 0 IR 講演筆録 〈近代仏教学〉と 〈仏教〉
- 著者
- 下田 正弘
- 出版者
- 大谷大学佛教学会
- 雑誌
- 佛教学セミナー (ISSN:02871556)
- 巻号頁・発行日
- no.73, pp.97-118, 2001-05
1 0 0 0 OA 練習時間の長い成長期の野球選手では尺側手根屈筋が硬くなる
- 著者
- 齊藤 明 岡田 恭司 髙橋 裕介 柴田 和幸 大沢 真志郎 佐藤 大道 木元 稔 若狭 正彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1220, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】成長期野球肘の発症には投球時の肘関節外反が関与し,その制動には前腕回内・屈筋群が作用することが知られている。成長期野球肘おいては投球側の円回内筋が硬くなることが報告されており,特に野球肘の内側障害ではこれらの硬い筋による牽引ストレスもその発症に関連すると考えられている。しかしこれらの筋が硬くなる要因は明らかにされていない。そこで本研究の目的は,成長期の野球選手における前腕屈筋群の硬さと肘関節可動域や下肢の柔軟性などの身体機能および練習時間との関係を明らかにすることである。【方法】A県野球少年団に所属し,メディカルチェックに参加した小学生25名(平均年齢10.7±0.7歳)を対象に,超音波エラストグラフィ(日立アロカメディカル社製)を用いて投球側の浅指屈筋,尺側手根屈筋の硬さを測定した。測定肢位は椅子座位で肘関節屈曲30度位,前腕回外位とし,硬さの解析には各筋のひずみ量に対する音響カプラーのひずみ量の比であるStrain Ratio(SR)を用いた。SRは値が大きいほど筋が硬いことを意味する。身体機能は投球側の肘関節屈曲・伸展可動域,前腕回内・回外可動域,両側のSLR角度,股関節内旋可動域,踵殿距離を計測し,事前に野球歴と1週間の練習時間を質問紙にて聴取した。また整形外科医が超音波診断装置を用いて肘関節内外側の骨不整像をチェックした。統計学的解析にはSPSS22.0を使用し,骨不整像の有無による各筋のSRの差異を比較するため対応のないt検定を用いた。次いで各筋のSRと各身体機能,野球歴や練習時間との関係をPearsonの相関係数またはSpearmanの順位相関係数を求めて検討した。有意水準はいずれも5%とした。【結果】参加者のうち肘関節内側に骨不整像を認めた者は4名(野球肘群),認められなかった者は21名(対照群)であった。浅指屈筋のSRは2群間で有意差を認めなかった(1.01±0.29 vs. 0.93±0.23;p=0.378)が,尺側手根屈筋のSRでは野球肘群が対照群に比べ有意に高値を示した(1.58±0.43 vs. 0.90±0.28;p<0.001)。浅指屈筋のSRと各測定値との相関では,各身体機能や野球歴,練習時間のいずれも有意な相関関係は認められなかった。尺側手根屈筋のSRも同様に各身体機能や野球歴との間には有意な相関関係を認めなかったが,1週間の練習時間との間にのみ有意な正の相関を認めた(r=0.555,p<0.01)。【結論】成長期の野球選手において浅指屈筋,尺側手根屈筋の硬さは,肘・股関節可動域や野球歴とは関連がないことが明らかとなった。一方,1週間の練習時間の増大は尺側手根屈筋を硬くし,このことが成長期野球肘の発症へとつながる可能性が示唆された。
1 0 0 0 躁うつ的状態を示した頭部外傷後遺症の1剖検例
1 0 0 0 OA サービス・エンカウンターにおける 販売員と顧客との関係性に関する研究
- 著者
- 村井 吉昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会
- 雑誌
- プロモーショナル・マーケティング研究 (ISSN:24341665)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.31-46, 2011 (Released:2019-09-02)
1 0 0 0 OA 国土交通省におけるICT,次世代社会インフラ用ロボットの導入推進の取組について
- 著者
- 新田 恭士
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.470-476, 2016-06-10 (Released:2016-06-22)
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 辻井 農亜
- 出版者
- 科学評論社
- 雑誌
- 精神科 = Psychiatry (ISSN:13474790)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.634-639, 2019-06
1 0 0 0 OA 建設会社が目指すICTの活用とロボット化
- 著者
- 古屋 弘
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.489-494, 2016-06-10 (Released:2016-06-22)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA ロボットの新たな応用の方向性について
- 著者
- 北島 明文
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.9, pp.758-759, 2011 (Released:2011-12-15)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA タスマニア先住民の動態的差別分析
- 著者
- 張能 美希子 チョウノウ ミキコ Mikiko CHONO
- 雑誌
- 千葉商大紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.47-63, 2008-03
本稿では動態的差別の定義を用いてタスマニア先住民抹消について説明した。動態的差別の定義は差別の2つの特徴,時間による差別の変化と差別の多面的な社会的機能に注目して提唱されている。従来の差別研究で,差別は画一的にネガティブな現象として提えられ,十分な検証を終えずに差別の撤廃という目的に向けて議論は進められがちであった。しかし,動態的差別の定義においては,差別が比較的無害な状態から,有害な状態へと変化するとしており,さらにそれらの変化が差別要素のスパイラルによって行われる,と説明されている。タスマニアの先住民は多くの書物で「絶滅した」とされている。しかし2001年現在,タスマニアのアボリジニの人口は15,733人居り,彼らは純血ではないものの確かにタスマニア先住民の子孫である。本稿ではタスマニア先住民のケースは,存在自体を抹消されてしまう,という差別の最悪のレベルにまで達しているとした。その上でなぜ,タスマニア先住民の存在が無視され,抹消されてしまうのか,という疑問について動態的差別の定義を用いて論じた。
1 0 0 0 東大寺「十二大会」をめぐって
- 著者
- 三輪 眞嗣
- 出版者
- 仏教史学会
- 雑誌
- 仏教史学研究 (ISSN:02886472)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.22-43, 2018-03
1 0 0 0 OA 我が国が未利用の資源植物に関する調査
- 著者
- 牧田 道夫
- 出版者
- 農林水産省農業生物資源研究所
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.103-172, 1994 (Released:2012-09-24)
I部では,まず,新資源植物に対する過去と現在の内外の取り組み及び新資源植物の重要性を調べた.すなわち,今日の主な栽培植物は古代文明の発生時に殆どが出現し,その後,今日まで重要な新栽培植物は出現しなかったのであるが,栽培植物発生地域から他地域への伝播は活発に行われ,特に16世紀以降の大航海時代とそれに続く欧州諸国の植民地統治時代に活発になり,積極的に新資源植物の探索,収集が行われた.その後もこの取り組は地道に継続されてきた.現在,新資源植物に対する関心が内外共に高まっている.それは長期的には人類の将来の食糧,産業資源問題と現代の世界規模の地域開発等による資源の滅失問題,短期的には我が国も含めた先進国の生産者,消費者ニーズへの対応と開発途上国の食糧増産のためである.新資源植物を開発の素材の面から二つに分けることができる.一つは栽培化に必要な栽培型の諸特性が,ある程度獲得されている植物と,他は野生型の特性を強く残している植物である.前者は21世紀内外の比較的短期のニーズを目標とする開発に適した素材であり,後者は21世紀以降の長期的な展望のもとの開発に向いている.次に,我が国における新資源植物の果たすべき役割,確保の方向について述べた.新資源植物は既存の栽培植物にとって換わる立場でなく,住み分けて考えるべきで,用途,機能,物質生産において新しい需要を創出するものである.将来の食糧増産の方策は,先ず第一に既存の主要栽培植物を基本の素材としてその延長上にこれらの遺伝的変異の拡大を計るべきである.一方,新資源植物の役割を次の6項目の分野の面から示した.1)生産物質の面,2)利用形態の面,3)工業用原料の面,4)生体機能の面,5)耕地環境保全の面,6)不良環境地帯の耕地利用の面.II部ではI部で述べた新資源植物の果たすべき役割の考え方を念頭に置いて,内外の単行本,論文,事典,業務資料から107種の新資源植物を選定し,それらの情報を簡潔に示し,考察を加えた.