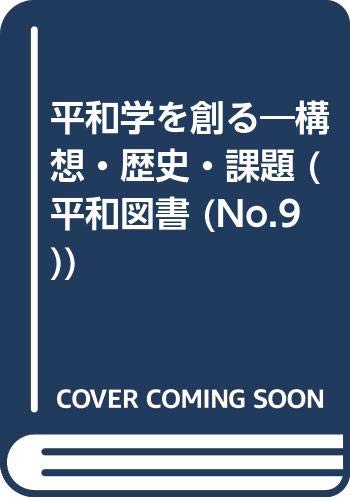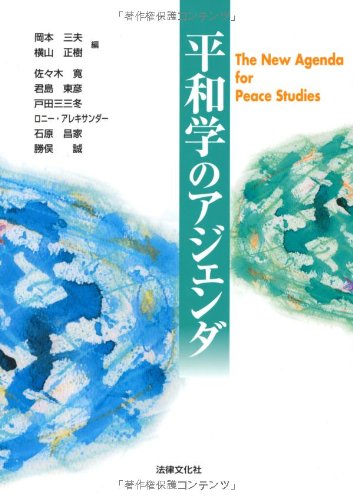1 0 0 0 OA 変形車輪を用いた段差移動ロボットの研究
- 著者
- 山田 慶太 入江 寿弘 浅見 明
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第29回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.216, 2013 (Released:2015-01-24)
低中層建築物ではエレベーターを設置している建物は少なく重量物や大型機材の搬入・搬出作業は人手で行われている。著者等は変形車輪を用いた階段昇降機構を考案し、軽量負荷での昇降実験に成功している。実用化するには有る程度の重量物を安定に運搬する必要が有り、階段で荷台を水平に保つ機構が必要である。しかし、荷物によって重量,重心位置の状態が多様に変化し、それに対応できる水平維持制御が必要がある。本研究では荷台部分の水平維持機構を考案し、その運動モデルをもとに制御系を検討する。制御を行うには荷台部の姿勢をセンサで検出し、状況に応じた適切な制御パラメータを設定する必要があるのでファジイ理論のメンバーシップ関数を用いた安定化が有効と考えられる。
1 0 0 0 OA 幕末并明治初年芝居番附
- 出版者
- [製作者不明]
- 巻号頁・発行日
- vol.第5冊(明治7年1月-11月), 1000
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.366, pp.86-89, 2004-12-24
1960年代からの急速な市街化によって失われた保水機能などを補うよう,遊水地を整備して流域の水害に対処。平常時は公園となる遊水地の運用を2003年6月から開始。2004年の台風では総貯水量の3分の1が流入して水害を防いだ。 2004年10月9日,伊豆半島に上陸した台風22号は,東海地方と関東地方南部の広い範囲に激しい雨と風をもたらした。
1 0 0 0 OA 最低賃金制度と経済成長 : 内生的貨幣供給理論に基づく分析
- 著者
- 丁 遠一 山崎 好裕 Ding Yuanyi Yamazaki Yoshihiro
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学経済学論叢 = Fukuoka University Review of Economics (ISSN:02852772)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3-4, pp.257-274, 2010-03
1 0 0 0 サラワク·ランビル国立公園における降雨と風向·風速の日周変動特性
- 著者
- 諸岡 利幸 蔵治 光一郎 鈴木 雅一
- 出版者
- 水文・水資源学会
- 雑誌
- 水文・水資源学会研究発表会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.228-229, 2002
1 0 0 0 内閣文庫「続編孝義録料」(越前・若狭関係分)について
- 著者
- 宇佐美 雅樹
- 出版者
- 福井県文書館
- 雑誌
- 福井県文書館研究紀要 (ISSN:13492160)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.47-56, 2017-03
- 著者
- 深澤 晴美
- 出版者
- 芸術至上主義文芸学会事務局
- 雑誌
- 芸術至上主義文芸 (ISSN:02876213)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.27-32, 2009-11
1 0 0 0 OA 表現の意味、真理条件、解釈の関係をめぐって
- 著者
- 西山 佑司
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.56, pp.113-129,6, 2005-04-01 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 20
The present paper considers the adequacy of an essential assumption in the philosophy of language in the twentieth century, which is that linguistic meaning is to be understood in referential/logical terms and that semantics is inherently truth conditional. Frege origi-nated this assumption. He defined Sinn (sense) as the determiner of Bedeutung (reference) . In contrast, linguistic semantics developed within the framework of the generative theory of grammar has no commitment to Frege's reference determining definition of sense. It defines sense as the determiner of sense properties and relations such as ambiguity, synonymy, analyticity, and entailment. Quine's argument that these sense properties and relations cannot be made objective sense of is critically reviewed.We claim that linguistic semantics is not truth conditional. Truth conditions are to be assigned to the proposition expressed by an utterance, which is captured by the theory of utterance interpretation, i.e., inferential pragmatics.Particular attention is paid to Yamada's argument that the content of illocutionary acts such as commands, promises, and the like cannot be identified with propositions. We claim that Yamada's argument is not convincing. We also comment on his idea of a general theory of content for illocutionary acts which generalizes Austin's theory of truth.
1 0 0 0 Union calendar
1 0 0 0 日本における地理教育の研究法
- 著者
- 朝倉 隆太郎
- 出版者
- The Geographic Education Society of Japan
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.52-55, 1982
地理教育は地理学と教育学との交界領域にあり, これまで地理学又は教育学の応用面とみなされてきたが, 1960年代以来地理教育を学問として定立させようとする機運が高まってきた。<br>地理教育の研究方法には, 理論的研究法, 歴史的研究法, 調査的研究法, 実験的研究法, 比較的研究法の5者があり, これらは相互に補完し合うものである。<br>理論的研究では, 地理教育の目標・内容構成・カリキュラム・学習過程・学習形態・評価, 地理科担当教員の養成, 児童生徒の地理的意識の発達などが対象になる。<br>歴史的研究では, 明治以後の地理科教授要目・教科書戦後の社会科学習指導要領, 地理教育思想に関する歴史的研究が多くの成果をあげている。<br>調査的研究は, 一般に実態把握調査と解決策発見調査に2分されるが, 地理教育に関しては前者が多い。国研・文部省などで全国的規模での学力 (社会科地理を含む) の調査が行われるようになったのは戦後になってからである。また, 読図力, 地名に関する知識, 好きな国と嫌いな国などについて, 小学生から高校生まで各地で多くの調査が行われてきている。しかしまだその結果を体系化するまでにはいたっていない。<br>実験的調査法は地理の指導法・学習形態・学習過程の問題に適用される。1955年ごろから実験の信頼性を高めるための手続きについての論議が積み上げられ, 現在ではさらに統計学の実験計画法が導入されて, 教育実験におけるデータの科学的処理を向上させる努力が続けられている。日本国内ユネスコ委員会『国際理解のための教育実験』の「他国の理解」は, 地理教育の実験的研究の一礎石である。<br>教育の比較研究は, 教育における各種の事象を国, 地域, 学校等の間で比較することによって, 類似性と相違性を発見し, それらの相違を生む原因を究明し, 共通に見られる原理の発見を目指すものである。<br>昭和33年度改訂の小学校学習指導要領第4学年の内容に, イギリスの Sample studies が導入され, 昭和52年度の改訂でその考え方が第5学年の内容にまで広げられた。アメリカ合衆国のHSGP, イギリスの New Geography に採用されている games and simulation の指導法は, 一部を除いてまだ普及していない。小学校低学年の合科教授の参考として西ドイツの「事実教授」, フランスの「めざまし活動」は, 比較的研究からみた目下の研究対象である。<br>国際教育情報センターの外国教科書に関するこれまでの業績は高く評価すべきであり, 教科書研究センターは, 米・英・仏・独・ソ5か国を対象に, 教育課程 (教科書を含む) の国際比較研究を進行中である。
1 0 0 0 OA 川崎軍曹渡単身大同江
- 雑誌
- 日清戦争錦絵
- 著者
- 斉藤 文彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.216-220, 2016-11-01 (Released:2018-03-15)
- 参考文献数
- 1
National Medicinal Chemistry Symposium(NMCS)は、ACS Division of Medicinal Chemistry主催で1948年より隔年で開催されている。今回の第35回シンポジウム(NMCS2016)は、2016年6月26~29日までの4日間、イリノイ州シカゴで開催された。29の国・地域から約350名の参加があり、受賞・招待講演である口頭発表が26演題、ポスター発表が109演題であった。1日目は「DMPKに関する最近の話題」と「受賞講演」、2日目は「転写因子ターゲット」、「エピジェネティック メカニズム」と「ポスターセッション」。3日目は「神経変性疾患に対する治療の最近の進歩」、4日目は「オープンイノベーション」と「アンドラッガブルからドラッガブルへ」についての講演であった。本レポートでは口頭発表のなかからいくつかの演題について報告する。
1 0 0 0 OA 三國志65卷
- 著者
- 晉陳壽撰
- 出版者
- 村上勘兵衞山本平左衞門刊
- 巻号頁・発行日
- vol.[3], 1670
1 0 0 0 OA 大東輿地図
- 著者
- [ (朝鮮) 金正浩] [作]
- 巻号頁・発行日
- vol.[19], 1800
1 0 0 0 Peace studies in the nuclear age
- 著者
- by Mitsuo Okamoto
- 出版者
- Institute for Advanced Studies, Hiroshima Shudo University
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 平和学を創る : 構想・歴史・課題
- 著者
- 岡本三夫著
- 出版者
- 広島平和文化センター
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 平和学のアジェンダ
- 著者
- 岡本三夫 横山正樹編 佐々木寛 [ほか著]
- 出版者
- 法律文化社
- 巻号頁・発行日
- 2005