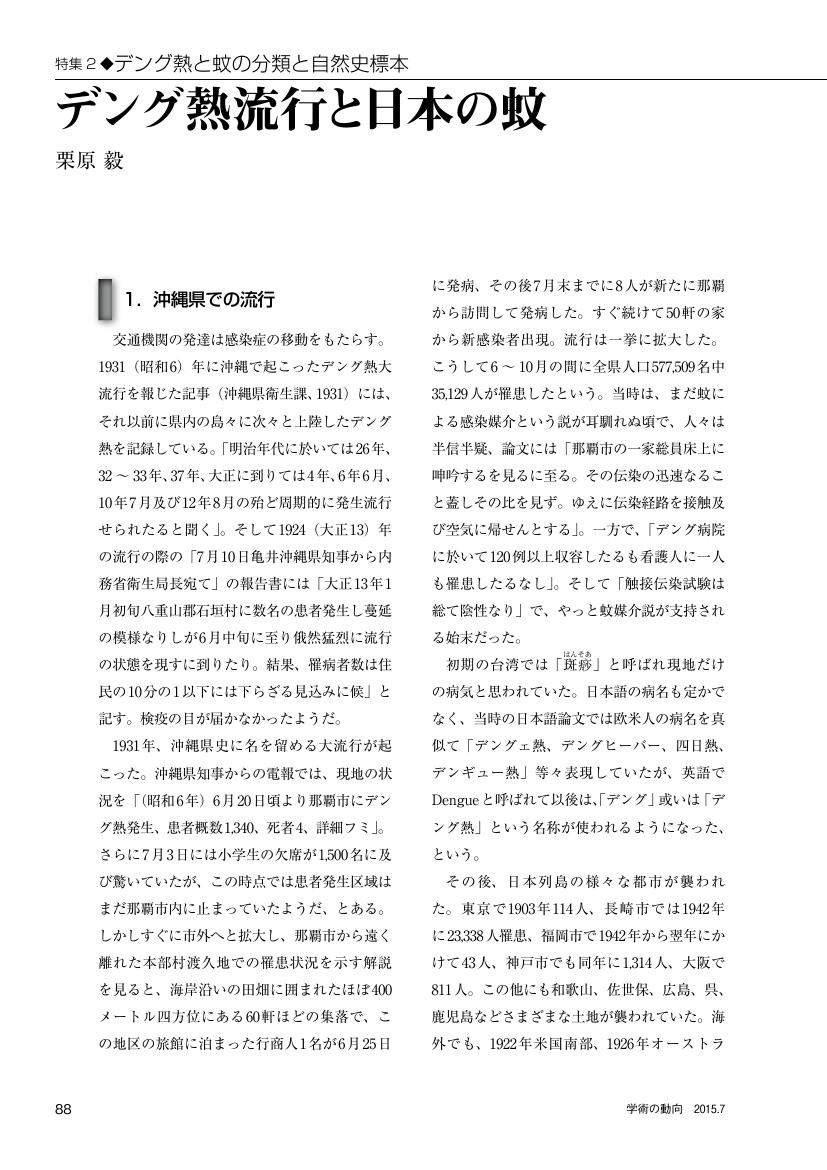1 0 0 0 OA 本邦に於ける動物崇拜追加
- 著者
- 南方 熊楠
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- 東京人類學會雜誌 (ISSN:18847641)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.296, pp.63-65, 1910-11-20 (Released:2010-06-28)
- 著者
- 平野 道代 塩沢 泰子 佐伯 林規江 吉田 真理子
- 出版者
- 一般社団法人大学英語教育学会
- 雑誌
- 大学英語教育学会紀要 (ISSN:02858673)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.1-19, 2000-03-15
- 著者
- 神保尚武 [ほか] 著
- 出版者
- 東京書籍
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 OA 建築の「巨大さ」について
- 著者
- 吉川 桃子
- 出版者
- 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系社会文化環境学専攻
- 巻号頁・発行日
- 2011-03-24
報告番号: ; 学位授与年月日: 2011-03-24 ; 学位の種別: 修士 ; 学位の種類: 修士(環境学) ; 学位記番号: 修創域第4034号 ; 研究科・専攻: 新領域創成科学研究科環境学研究系社会文化環境学専攻
1 0 0 0 OA 「少年」から少年・少女へ : 明治の子ども投稿雑誌『頴才新誌』におけるジェンダーの変容
- 著者
- 今田 絵理香
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.214-227, 2004-06-30
The purpose of this paper is to clarify how the idea of a child's gender among the middle class has changed by analyzing "Eisaishinshi", a contribution magazine for children during the Meiji Era whose publication started before the practice of gender specification. This magazine was particularly chosen due to the fact that in modern Japan, the magazine used as supplementary materials in school education have also carried out sex specification at the time when the concept of gender studies in middle school education was put into practice in 1879. The results of the analysis are as follows. From 1877 to 1882, when "Eisaishinshi" was first published, children's compositions praised the merits of studying to attain careers and abilities. Their works also represented both the boy and the girl as "Shonen (the Youth)" based on the idea that they should have the same opportunity, which perfectly reflected the meritocracy society and civilization. However, since 1882, attention has been paid to the so-called "difference in intellectual power" between men and women. This led to the separation of "Shojo (the girl)" from "Shonen (the youth)", considering that the former has different opportunity from the latter, and to the emergence of different entities "Shonen (the boy)" and "Shojo (the girl)". This transition derived from the system of the study according to sex, by which the so-called" difference between men's intellectual power and that of women" has been realized. Two things have become visible from such a transition. Firstly, the transition has demonstrated two sides of the meritocracy by learning. The ideology, on the one hand, has supported a new image for women during the 1870s and the 1880s who pursued careers through studies. On the other hand, however, it has inevitably revealed the difference in intellectual power between men and women and justified gender discrimination as a by product of this difference. Consequently, since the practice of the study according to sex, the latter idea has been strongly influenced. Secondly, it has become clear that meritocracy has created two separate entities "Shonen (the boy)"and "Shojo (the girl)'. That is, females whose education and subsequent career have been severed in relation since study according to sex, have lost continuity between their way of life as "the mother", and that as "the girl". Unlike the boyhood which has been positioned as a preparatory period for the adulthood, the girlhood has been regarded as a specific time which will be completed in itself. In conclusion, the analysis has shown that the construction of a child's gender in modernJapan has been strongly connected with the meritocracy by learning that appeared at the time.
1 0 0 0 OA 320列冠動脈CTによる無症候性糖尿病患者の冠動脈疾患のスクリーニング
- 著者
- 横田 美紀 竹内 淳 永井 聡 安藤 康博 川嶋 望 宮本 憲行 甲谷 哲郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.105-113, 2016-02-29 (Released:2016-02-29)
- 参考文献数
- 28
糖尿病患者においては冠動脈疾患の合併頻度が高く,生命予後を左右するために,早期の的確な診断が期待される.糖尿病では無症候性心筋虚血のために自覚症状が乏しく,診断時に高度に進行した病変を示す患者も少なくない.今回,我々は,合併症の精査目的に入院をした159例の無症候性糖尿病患者に対して320列冠動脈CTによる冠動脈疾患のスクリーニングを実施した.その結果,67例(42 %)に有意狭窄を認め,循環器内科医による追加検査によって20例(13 %)が虚血を有する冠動脈疾患と診断された.虚血を有する冠動脈疾患と診断された患者では,腎症の合併,降圧薬の使用,抗血小板薬あるいは抗凝固薬の使用,脳梗塞の既往が多かった.またeGFRは有意に低く,ABI,IMTにも有意な差異を認め,石灰化スコアも高値であった.
1 0 0 0 鉄道労働科学
- 著者
- 日本国有鉄道鉄道労働科学研究所
- 出版者
- 日本国有鉄道鉄道労働科学研究所
- 巻号頁・発行日
- 1952
1 0 0 0 IR 認知症の人による他害行為と民法714条責任,成年後見制度
- 著者
- 久須本 かおり
- 出版者
- 愛知大学法学会
- 雑誌
- 愛知大学法学部法経論集 = The Journal of the Faculty of Law (ISSN:09165673)
- 巻号頁・発行日
- no.203, pp.67-158, 2015-08
1 0 0 0 楕円曲線における Signcryption方式
- 著者
- 鄭 玉良 今井 秀樹
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. ISEC, 情報セキュリティ
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.380, pp.55-62, 1997-11-19
Signcryption は公開鍵暗号技術の新たなプリミティブであり、公開鍵暗号化とディジタル署名の両機能を効率的に実現する。すなわち、従来通り署名してから暗号化をするという2ステップを経て両機能を達成する場合 (signature-then-encryption方式) と比較して、コストを極めて低くすることができる。本稿では、この Signcryption を有限体の楕円曲線上で実現する方式について述べる。さらに、楕円曲線上の signature-then-encryption 方式との効率比較を行い、Signcryption によって計算コストが58%、通信オーバーヘッドが40%削減できることを示す。
1 0 0 0 OA 1960年代の国際通貨体制とOECD : 経済政策委員会第三作業部会の創設と初期の活動
- 著者
- 矢後 和彦 Kazuhiko Yago
- 雑誌
- 経済学論究 (ISSN:02868032)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.111-137, 2014-06-20
特発性大腿骨頭壊死症の病態および修復に関して、動物モデル及び疫学調査等を用いて、基礎的、臨床的研究を行った。基礎的研究として、ステロイド性骨壊死家兎モデルを用いて、ステロイドの投与経路によって薬物体内動態およびステロイド性骨壊死の発生頻度がどのように変化するについて検討を行った。臨床におけるステロイド投与法と、モデルにおける投与法は相違点があるものの、その詳細や薬物動態についてはこれまで検討されていなかった。雄日本白色家兎に対して、経静脈、経口、経筋肉内の3種の経路でステロイド剤を投与し、骨壊死発生率および血中薬物動態、血液学的変化を検討した結果、ステロイド性骨壊死発生の危険因子として、ごく短期間の高ステロイド濃度を引き起こす投与法より、一定期間一定濃度を維持する投与法がより強く関与している可能性が示唆された。臨床的研究として、記述疫学調査によって特発性大腿骨頭壊死症の詳細な記述疫学調査を行った。福岡県では過去3年間に新規認定患者は339人であり、発生率は年間10万人あたり2.26人であった。誘因はステロイドあり31%、アルコールあり37%、両方あり6%、両方なし25%であった。治療法では約半数で手術が行われており、人工関節手術が最も多かった。ステロイド性骨壊死では平均41mgの投与量、4.6年の投与期間であった。アルコール性壊死では1日あたり平均2.7合、約25年の飲酒歴であった。記述疫学結果をまとめ特発性大腿骨頭壊死症調査研究班会議にて報告した。さらに平成25年8月からは、米国テキサス州に渡航し、Texas Scottish Rite Hospital for Childrenにて、大腿骨頭壊死の病態に関する基礎的な研究を開始した。小児における大腿骨頭壊死疾患としてPerthes病が知られているが、当施設では未成熟豚を使用したPerthes病モデルを用いて、骨壊死のどのような組織変化が滑膜炎、関節炎を引き起こすかにかについて分子生物学的な検討を行っている。
1 0 0 0 OA 年間記事索引
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.index1-index5, 2016-03-01 (Released:2016-03-01)
1 0 0 0 OA 情報界のトピックス
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.946-947, 2016-03-01 (Released:2016-03-01)
1 0 0 0 OA デング熱流行と日本の蚊
- 著者
- 栗原 毅
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.7, pp.7_88-7_91, 2015-07-01 (Released:2015-11-06)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 石田 勝英 塩入 有子 石坂 泰三 岩崎 博道 藤田 博己 高田 伸弘
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.55-61, 2004 (Released:2011-07-13)
- 参考文献数
- 12
症例は88歳,女性。約2日前に自宅近くの草むらに入り,全身を多数のマダニに咬着され,平成15年5月19日に当科を受診した。当科で229匹の虫体を摘除したが,すでに脱落した虫体も含めるとさらに多くの寄生を受けていたものと思われた。虫体はタカサゴキララマダニ幼虫と同定された。塩酸ミノサイクリンを予防投与したが虫体摘除2日後に発熱・全身関節痛・両腋窩リンパ節腫脹などの全身症状が出現した。塩酸ミノサイクリンは効果がなく中止し,多種の抗生剤を用いてようやく症状は軽快した。日本系および欧州系紅斑熱やライム病など,およそマダニが媒介し得るだけの各種感染症の血清抗体検査では陰性だった。全身症状の明らかな原因は特定できなかった。