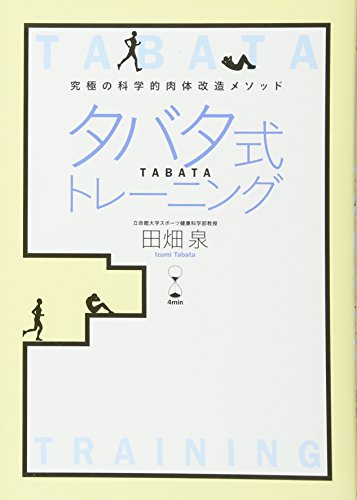1 0 0 0 OA 時系列解析における長期記憶モデルについて
- 著者
- 矢島 美寛
- 出版者
- 応用統計学会
- 雑誌
- 応用統計学 (ISSN:02850370)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.1-19, 1994-09-30 (Released:2009-06-12)
- 参考文献数
- 99
- 被引用文献数
- 1 1
長期記憶モデルは系列相関の強い定常時系列データを解析する目的で,Mandelbrot and Van Ness, Granger and Joyeux, Hosking等によって提案された.従来のポピュラーなモデル,自己回帰移動平均モデルを,補完,代替するモデルとして注目を浴び,1980年代以降理論,実証両側面に於て盛んに研究されている.本稿では長期記憶モデルの由来,現在までに得られている理論的結果,実際データへの応用を概説するとともに,今後の課題について議論する.
1 0 0 0 OA 仏教が非人倫的であると云ふ謗難に対しての仏教者の反論 : 反排仏の護法思想
- 著者
- 古田 紹欽
- 出版者
- 北海道大學文學部
- 雑誌
- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-15, 1959-03-30
1 0 0 0 OA 作用子:APL言語の特徴と設計思想
- 著者
- アイバーソン E. K 竹下 亨
- 雑誌
- 情報処理
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.9, 1979-09-15
1 0 0 0 OA 医療被曝とその影響
- 著者
- 阿部 由直
- 出版者
- 公益社団法人日本放射線技術学会
- 雑誌
- 放射線防護分科会会誌 (ISSN:13453246)
- 巻号頁・発行日
- no.17, 2003-10-10
This paper mainly handles the cases of traditional alcoholic beverage making in villages at east side of Bali. Making, circulation and drinking of these drinks are changing with the peoples living style. This research mainly aims to capture these changes with the social problems of today's Bali. Making of traditional drinking are now illegal. But this subsistence is important to the makers because, there is no other opportunity that they can take. Illegal drinks that are distilled in the villages at east side of Bali circulate to other places in the island, by using relative and local networks. Now this subsistence changed from what it used to be, and now it is able to get enough incomes from the increase of demands. A maker who uses modern style of machines to distill spirit and earn much income as they can under the strategy is less. Most makers distill spirit by cheep traditional equipment under the tactics that has limited incomes. In Bali Social changes are rapidly, so many makers take the tactics that are able to adopt changes quickly. This style of makers shows the flexibility of subsistence in the villages, and this also means the problems of tourism development, agriculture and also education.
1 0 0 0 OA インドネシアの特異な発酵食品
- 著者
- 小崎 道雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.12, pp.824-829, 1986-12-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 11
東南アジアは発酵食品の宝庫といわれるが, 中でもインドネシアはその最たる国といってよいであろう。それは, この国が地域的に広さと環境の変化に富んでいるために, 自ら沢山のバラエティーを生みだしたものと見られる。代表的なのがテンペで, この国が世界の文化に貢献しうる最高の財といわれ, 今や世界中から注目されている。その他にも数多くの地域発酵食品があるが, それらについては, 未だ余り紹介されてないものが多く, それらの中から, 特に興味ある二, 三の食品についての紹介である。
1 0 0 0 IR ジャワ島の発酵糖菓子 : ブルム
- 著者
- 小崎 道雄 飯野 久和 クスワント カプティ ラハユ Michio Kozaki Hisakazu Iino Kapti Rahayu Kuswanto Laboratory of Food biotechnology Faculty of Agricultural technology Gajah Mada University
- 雑誌
- 昭和女子大学大学院生活機構研究科紀要 = Bulletin of the Graduate School of Human Life Sciences, Showa Women's University (ISSN:09182276)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.101-106, 1997-03-31
Brem cake is a traditional fermented rice cake made from glutinous rice in east and central Java island, and eaten mainly as snack food. This cake divid into two types, one is Madium type (ash-yellow colour, sweet-sour flavour, small rectangle plate) another is Wonogiri type (white colour, solide sweet flavour, thin round block). Microorganisms concerning with fermentation was Saccharomycopsis spp. and Mucorales for degradation of rice starch. Saccharomyces is mainly concerned in alcohol fermentation.
- 著者
- 古田 定昭
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 : hoken buturi (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, 2005-12
1 0 0 0 ロックミュージックによる聴覚障害
- 著者
- 細川 智 田部 哲也 平出 文久 井上 鉄三
- 出版者
- THE JAPAN OTOLOGICAL SOCIETY
- 雑誌
- Ear Research Japan (ISSN:02889781)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.238-240, 1985
Acute sensori-neural hearing loss after exposure to loud sounds in rock music was experimently studied. With guinea pigs exposed to rock music for tour hours a day during one week, parmanent threshold shift (PTSs) were not recorded. Next, temporal threshold shifts (TTSs) were examied after exposing guinea pigs to rock music for 1-4 hours. There was a increased temporal threshold shifts (TTSs) at over two hours.<BR>Finally, with guinea pigs exposed to rock music for three hours and restricted in the bottle filled with water, temporal threshold shifts (TTSs) were greatest, but parmanent threshold shifts (PTSs) were not recorded at seven days later.
1 0 0 0 OA 原子力あるいは放射線緊急事態における各国の短期防護措置の現状
- 著者
- 木村 仁宣 本間 俊充
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 : hoken buturi (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.76-87, 2006-06
- 被引用文献数
- 1
In the event of a nuclear or radiological emergency, short-term countermeasures are implemented. This report summarizes the current status of these countermeasures, such as sheltering, evacuation and iodine prophylaxis in OECD/NEA member countries.
- 著者
- 岡崎 龍史
- 出版者
- 産業医科大学学会
- 雑誌
- 産業医科大学雑誌 (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.85-89, 2013-10-01
日本における放射線障害防止の法律は,昭和3O年に施行された「原子力基本法」が元となる.原子力の研究,開発及び利用の促進のために制定されたが,海外からの放射線同位元素の輸入の増加に伴い,昭和32年に科学技術庁所管で「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律」,つまり「放射線障害防止法(障防法)」が制定され,昭和33年に施行された.平成24年原子力規制委員会が環境省の外局として発足し,管轄している.労働基準表の面からもさらに充実した規制が生じたため,昭和34年に労働省令第11号として「電離放射線障害防止規則(電離則)」が制定された.これまでにも何度も改正が行われたが,平成23年福島原子力発電所(福島原発)事故に伴い,新たに改正されている.障防法及び電離則を解説し,労災認定について述べる.
- 著者
- 加藤 文男 野本 諭 大津山 彰 法村 俊之
- 出版者
- 公益社団法人日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, 1998-07-20
1 0 0 0 なぜ、日本が太陽光発電で世界一になれたのか
- 著者
- 「NEDO books」編集委員会編
- 出版者
- 新エネルギー・産業技術総合開発機構
- 巻号頁・発行日
- 2007
- 著者
- 倉持 史朗
- 出版者
- 天理大学学術研究委員会
- 雑誌
- 天理大学学報 (ISSN:03874311)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.87-107, 2012-02
近代日本の監獄制度や更生保護,児童保護等の領域を専門とする有力な学術雑誌に『大日本監獄協会雑誌』がある。本誌は上記分野の史的展開を理解する上で重要な資料の1つである。本研究では第1に,本誌を発行した民間団体・大日本監獄協会の組織・活動等について検討を行う。第2に19世紀末から20世紀初頭にかけて生まれた感化教育や少年行刑,少年保護事業の母胎とも言うべき監獄改良の展開とその内実の一端について,本誌上の議論から検討した。また,それらを通して本協会とその機関誌が監獄改良に果たした貢献やその限界についても考察を加えた。
1 0 0 0 片倉工業株式会社三十年誌
- 著者
- 片倉工業株式會社調査課編
- 出版者
- 片倉工業株式會社調査課
- 巻号頁・発行日
- 1951