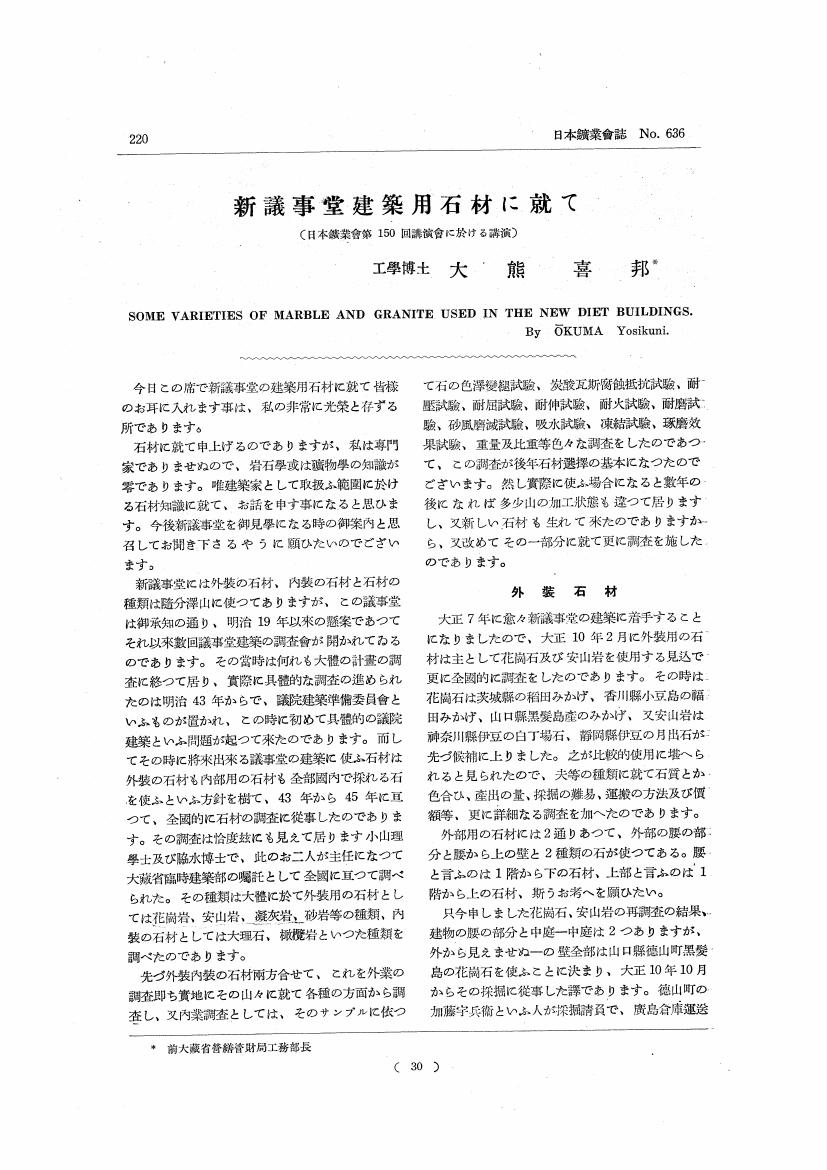- 著者
- 東京大阪養育費等研究会
- 出版者
- 判例タイムズ社
- 雑誌
- 判例タイムズ (ISSN:04385896)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.7, pp.285-315, 2003-04-01
1 0 0 0 東京都八丈島八丈町におけるタナバ(丹梛婆)の伝承
- 著者
- 山本 節
- 出版者
- [西郊民俗談話会]
- 雑誌
- 西郊民俗 (ISSN:09110291)
- 巻号頁・発行日
- no.210, pp.5-10, 2010-03
1 0 0 0 女子学研究
- 著者
- 甲南女子大学女子学研究会編
- 出版者
- 甲南女子大学女子学研究会
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 幼児の人間描画に見られる頭足人的表現形式の構造と本質
平成10〜13年度を通しての研究成果は、以下の通りである。1.学術論文「幼児の頭足人的表現形式の連続描画に見られる対象の重要度による描き分け」の複数審査制全国的学会誌への掲載…幼児は、それぞれ自分の人物描画における描画課題を独自にもっている。そして描画対象の重要度に応じて新旧の型を併用すると推察できる。2.学術論文「幼児の頭足人的表現形式に関する先行研究の問題点-W.L.Brittain(1979),鬼丸吉弘(1981),林健造(1987),長坂光彦(1977)の研究を中心にして-」の複数審査制全国的学会誌への掲載…幼児の頭足人的表現形式に関する先行研究を俯瞰し、批判的に考察した。3.学術論文「幼児の頭足人的表現形式の理論的説明における主知的見解とG.H.Luquetの描画発達説」の複数審査制全国的学会誌への掲載…有力な描画発達理論であるG.H.Luquet(1927)の学説は、幼児の描く頭足人的表現形式にも及んでいる。その理論を批判的に考察した。4.学術論文「幼児の頭足人的表現形式に関するH.Engの主知説批判」の複数審査制全国的学会誌への掲載…幼児の描画活動の縦断的事例研究者であり描画心理学の創設者でもあるH.Eng(1927)は、幼児の描く頭足人的表現形式について考察している。その理論を批判的に考察した。5.学術論文「幼児の初期人物描画の理論的説明における主知的見解への批判」の複数審査制全国的学会誌への掲載…本論では、L..S.Vygotsky(1930)、V.Lowenfeld(1947)、W.Grozinger(1952)、W.L.Brittain(1979)などの研究を取り上げ、主知説による頭足人的表現形式の説明を再吟味した。6.学術論文「幼児の人物画研究における用語問題」の複数審査制全国的学会誌への掲載…幼児の初期人物描画と頭足人的表現形式に関する学術用語は、各研究者によって使い方が違い、不統一である。本論では、先行研究を概観・整理し、新しい学術用語を提起した
1 0 0 0 外山亀太郎と明治期の蚕糸業における蚕の「種類改良」
- 著者
- 森脇 靖子
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究. 第II期 (ISSN:00227692)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.255, pp.163-173, 2010-09-24
In 1891, Silk Association of America warned Japanese vice-consul in New-York that the quality of Japanese raw silk was sub-standard. It advised both an improvement of silkworm breeds and a reduction in Japan's more than 300 silkworm breeds. In 1893, the engineers at the Institute of the Ministry of Agriculture and Trade (I.M.A.T.) began applying themselves to the task, though there was little scientific knowledge of breeding by crossing. By 1910, I.M.A.T. could not develop suitable silkworm breeds. However silkworm breeders had achieved some improvements through hybridization. When Kametaro Toyama who had known the breeder's breeding by crossing, began to interbreed in 1900, he did not know Mendelism. But Toyama had learned about the heredity and variation of hybridization, through the book, 'The Germ-Plasm' of A. Weismann. In 1901, he read the paper of H. de Vries and found out about Mendelism. From 1902 to 1905, he continued silkworm cross-experiments in Thailand (then Siam). In 1906, he confirmed that Mendel's law could be applied to silkworm in his doctoral dissertation. And he insisted on making f_1 hybrid for improvement of silkworm. In 1909, he published the book, 'Sansyuron' which he presented his method of breeding based on Mendelism. Only in 1910 did the engineers at the I.M.A.T., including S. Ishiwata, accept Mendelism and Toyama's methodology. After that, under the leadership of Toyama, I.M.A.T. began improving silkworm breeds and succeeded in producing an excellent f_1 hybrid by 1913. As a result, the Japanese raw silk was rapidly improved in quality.
- 著者
- MATSUNAGA Toshio
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- Historia scientiarum. Second series : international journal of the History of Science Society of Japan (ISSN:02854821)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.218-225, 2002-03-30
In Japan, evolutionism became popular towards the end of nineteenth century. Mendelism became popular around 1920. Mendelian genetics has become one of the important branches of Japanese biology. But evolutionism did not become an academic subject among Japanese biological researchers. Popularization of Mendelism had not changed this state of evoutionism in Japan. In this report I will describe mainly the state of evolutionism in Japan untill the 1920s, and comment briefly on the state of evolutionism arter that.
- 著者
- 秋元 ひろと
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.73-86, 2011-04
1 0 0 0 OA 中学生・高校生の男女交際と性的衝動との関係について : 横浜地域での調査をもとにして
- 著者
- 岡田 守弘 大草 正信 高安 睦美
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国立大学教育紀要 (ISSN:05135656)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.37-63, 1997-11-28 (Released:2016-09-15)
近年の中学生・高校生の1対1の男女交際・性意識・性行動の実態とその背後にある要因との関連を明らかにすることを本研究の目的として,横浜市内公立中学校22校,横浜地域の高等学校11校に在籍する中学生・高校生を対象に質問紙調査を実施した。実施時期は1995年11月,回収数は8420部,特定の学校による分布の偏りを避けるために5038人を抽出して分析した。結果は,次の通りである。(1)1対1男女交際の経験率は学年を追って高くなり,高校3年女子では30%を超える。キス経験率は中学3年女子で2割を超え,性交経験率は高校2年女子で2割を超え,女子の性に関する経験率が男子を上回っている。(2)性的衝動には「心理愛情的」と「心理生理的」の次元があり,若者文化許容には「制止」と「風潮」の次元があり,性的衝動の高さと若者文化許容度の高さが男女交際・性行動を積極的にする。(3)中学生・高校生は同世代の愛し合っている者同士のキスや性交に対する容認率は高く,1対1の男女交際や性経験が中学生・高校生にとって「あたりまえ化」し,「日常化」しているが,一部の突出した部分に幻惑されずに彼らのけじめ感覚を理解することが大切である。 This study was aimed at investigation about datings and sexual behaviors of recent junior high school and high school students, and exploration into the relation between their behaviors and the factors hidden behind. The survey was conducted through questionaires in 22 public junior high schools in Yokohama City, and 11 high schools around Yokohama City. 8420 students answered the questionaires in November 1995. 5038 questionares were sampled for analysis. Results are as follows; 1) Dating rate increases as the grade goes up. Dating rate of the third year female students is over 30%. The number of students who have experienced kissing is over 20% in the third year female students of junior high schools. The number of female students who have experienced sexual intercourse surpassed 20% in the second grade in high school. In every grade female students 'sex experiencing rate is higher than boys'. 2) Two dimentions were found in sexual urge. They are 'psycho-affectional' and 'psycho-psysiological' dementions. And permissiveness toward youth culture included dimentions of 'inhibition' and 'fashion'. The ones who showed high sexual urge and high permissiveness are comparatively active in datings and sexual behaviors. 3) Junior high school and high school students tend to think it's natural to kiss or have sex, if they love each other. Dating and having sex have become a part of every day life and nothing special for junior high and high school students. And it's important to understand that most of them have their own standards of behaviors. The number of students who show excessive behaviors are quite limited.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1932年10月05日, 1932-10-05
1 0 0 0 OA 計算機によるゲームの研究をめぐって
1 0 0 0 OA 新議事堂建築用石材に就て
- 著者
- 大熊 喜邦
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.636, pp.220-226, 1938 (Released:2011-07-13)
1 0 0 0 OA 給食管理実習の実施献立における調味および食品構成の検討
- 著者
- 三橋 洋子 小林 幸子
- 出版者
- 和洋女子大学
- 雑誌
- 和洋女子大学紀要. 家政系編 (ISSN:09160035)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.55-63, 1996-03-31
昭和58年と62年に実施された献立のうち,22献立についての塩分量の検討を行った。また平成元年から7年(前期)までの7年間に実施された132献立のうち,5回以上実施された8種類の主菜,合計53献立について同一主菜別に献立内容の分析・検討を行い,次の結果が得られた。1) 大量調理における塩分濃度は,材料の量の多さや器具の表面積の大きさ等に影響をうけ,計算値と実測値に差が生じ,その差にはバラツキがみられた。2) 同一主菜の食材料の使い方にはハンバーグやちらし寿司のように各回で個性のあるものや,チンジャオロースやクリームシチューのように毎回使用する食品がほぼ同一であるものとがあった。3) 同一主菜を副菜,汁物を含めた献立としてみた場合,たんぱく質源食品や野菜類の主菜での使用不足分は,副菜や汁物で補っていることが多いが,不足しているままの献立もあり今後の検討課題としたい。
- 著者
- 塩見 翔 Sho Shiomi
- 雑誌
- Zero Carbon Society 研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.59-72, 2012-03-30
1 0 0 0 大学鉄道サークルにおける女性メンバーたち
- 著者
- 塩見 翔
- 出版者
- 甲南女子大学女子学研究会
- 雑誌
- 女子学研究 (ISSN:21869235)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.9-12, 2013-03
1 0 0 0 OA 地域再構築における中高年女性の伝統手芸活動と民俗技術の多様化
福岡県柳川地域のひな祭り行事の際、雛人形の両側にさげられる吊るし飾り「さげもん」(毬とちりめん細工)は、自作の贈答品としてだけでなく趣味の手芸品、土産品として一年を通して制作されている。近年、さげもんが観光資源に活用され、またその需要と供給の地域的流通システムが形成されることで、中高年女性を中心に様々な目的や技術をともなう制作活動がさらに活発化し、民俗技術の持続にもつながっていた。柳川のさげもんの民俗技術はその観光資源化と多様な制作グループの自主的活動を通じて、地域社会の活性と伝統の再創造および中高年期の女性の生活の質の向上に積極的な役割を果たしていることが明らかになった。
- 著者
- 松浦 啓一
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ : 日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.5-11, 2011-08-20
Taxonomy is recognized as an important infrastructure of biodiversity research and nature conservation. However, taxonomy itself has been declining in terms of number of taxonomists and expertise covering various taxonomic groups. The animal taxonomy in Japan is not an exception. How can animal taxonomists improve this situation? This paper provides several suggestions including basic assessments on animal taxonomy in Japan (e.g., number of taxonomists and number of specialists on various animal taxa), making a nation-wide list of animals in Japan, research projects by groups of different specialists covering different animal taxa, and using biodiversity databases to implement new researches on distribution and phylogeography.