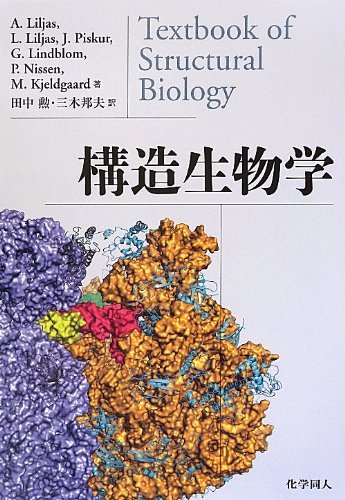1 0 0 0 OA 脱リグニンおよび水熱処理による酵素糖化複合前処理
- 著者
- 吉村 忠久 井上 誠一
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 日本エネルギー学会誌 (ISSN:09168753)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.9, pp.915-922, 2012 (Released:2012-09-28)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
Effects of delignification treatment on the enzymatic saccharification of grass biomass (rice straw and sugarcane bagasse) were investigated. The delignification treatment improved the efficiency of the enzymatic saccharification. The yields of glucose and xylose from the delignified rice straw by enzymatic saccharification at low cellulase loading (2 FPU/g-substrate) were 75 and 65 %, respectively. Furthermore, combining delignification and hot compressed water treatment at 140°C, the yields of glucose and xylose was increased to 95 and 80 %, respectively. On the other hand, the yields of glucose and xylose from the sugarcane bagasse combining delignification and hot compressed water treatment by enzymatic saccharification were 55 and 70 %, respectively. It is shown that the high cellulase loading (10 FPU/g-substrate) was needed for obtaining high monosugar yield from sugarcane bagasse.
1 0 0 0 OA タプル再分散不要の並列データベース構成法
- 著者
- 油井 誠 小島 功
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.11-33, 2011-12-28
本論文では無共有計算機設計においてデータウェアハウス処理を行ううえでタプルの再分散の問題に着目し,タプルの再分散を必要としない並列データベース構成法を述べる.特にΦハッシュ分割と呼ぶ,タプルの再分散を必要としないテーブル分割手法を提案する.Φハッシュ分割ではノード数に対するスケーラビリティを維持しながら,TPC-Hなどの複雑なデータ分析問合せを並列処理することができる.TPC-HのSF=100による評価実験で,提案手法がMapReduceに基づく競合システムHiveに対して顕著な性能面での優越(3.1倍~19.9倍)があることを示すとともに,我々の問合せ処理手法の現実装における有効範囲と制限に考察を与える.
1 0 0 0 伯林オリムピック大觀
- 出版者
- 滿州日日新聞社
- 巻号頁・発行日
- 1936
1 0 0 0 開発の鉄人--多喜義彦 現場をゆく 水中可視光通信
- 著者
- 多喜 義彦
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ものづくり (ISSN:13492772)
- 巻号頁・発行日
- no.678, pp.97-100, 2011-03
どこまでも青い海─。沖縄の第一印象は、とにかく海だ(図1)。サンゴの里海ともいわれる、サンゴ礁に囲まれた島の景観は、まさに南国の趣。ここで生まれたサンゴの卵は、沖縄本島や周辺の島はもちろんのこと、遠く本土にまで供給されているという。 そんな、どこまでも青く透き通った海とサンゴ、さまざまな熱帯魚に魅せられ、沖縄には年間589万人もの観光客が訪れている*。
1 0 0 0 全国飲食料品仕入案内
- 著者
- 日本和洋酒缶詰新聞社 編
- 出版者
- 日本和洋酒缶詰新聞社
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和5年度版, 1929
- 著者
- Serdal Ugurlu Erkan Caglar Tijen Erdem Yesim Eda Tanrikulu Gunay Can Pinar Kadioglu
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.205-209, 2008 (Released:2008-02-15)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 3 8
Objective To determine the characteristics of thyroid nodules by using fine needle aspiration (FNA) biopsy and ultrasonography. Patients and Methods FNAs of 1,004 patients with thyroid nodules between 2000 and 2007 were evaluated retrospectively. The surgical records of 101 of the patients were available and reviewed. The Odds ratios for nodule characteristics were calculated individually. Results The sensitivity of FNA was 66.7% and the specifity was 95.2%. Positive predictive value was 72.7% and negative predictive value was 93.7%. Our diagnostic accuracy was 90.5%. Solitary nodules, irregular margins and microcalcifications were associated with increased risk of malignancy with Odds ratios 3.61 (95% CI: 1.25-10.42; p= 0,017); 5.44 (95% CI: 1.76-16.78; p= 0,003) and 39.29 (95% CI 8.32-185.47; p< 0.001) respectively. Macrocalcification, age, gender and thyroid status were not associated with increased risk of malignancy. Conclusion Our data suggest that FNA is a reliable, reproducible and valid method to evaluate thyroid nodules and ultrasonographic features, especially microcalcification is a very important predictor of malignancy.
1 0 0 0 IR 甲状腺癌に関する疫学的研究-1-長野県中・南信地方抽出9地区における実態調査成績
- 著者
- 丸地 信弘
- 出版者
- 長野県医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.255-265, 1967-02
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 IR 生活環境要素としてのヨード 人類生態的側面よりの省察
- 著者
- 丸地 信弘
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.7-13, 1973-04
1 0 0 0 IR 甲状腺癌に関する疫学的研究 : 第2報:長野県東・北信地方抽出4地区における実態調査成績
- 著者
- ODA JIRO NAGAMASU HIDETOSHI
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- Acta phytotaxonomica et geobotanica : APG (ISSN:13467565)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.145-150, 2011-02-21
Carex noguchii J. Oda & Nagam. is described as new to science. It is similar to C. biwensis Franch. in having irregularly trigonous to pentagonous culms, many-flowered (ca. 30) spikes, and short (1.8-2.0mm long) perigynia. Carex noguchii is distinguished from the latter, however, by the dark brown basal leaf sheaths, wider and longer leaves, orbicular-ovoid perigynia, and achenes loosely enclosed by the perigynia, and micromorphologically by the absence of satellite bodies.
- 著者
- 榎田 翼 若槻 尚斗 水谷 孝一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.5, pp.197-204, 2013-05-01
本論文は,金管楽器において吹鳴圧力に加え唇のアパチュアを変化させたときの吹鳴音高を計測することで,吹鳴圧力とアパチュアが吹鳴音の音高に与える影響を明らかにすることを目的とする.具体的にはアンブシュア可変機構を有する人工吹鳴装置を用いて,吹鳴圧力とアパチュアの大きさを制御しながら吹鳴音の計測を行った.結果として吹鳴圧力とアパチュアの相互関係により励起される吹鳴音の周波数が決定されることを確認した.また,アパチュアの大きさを徐々に大きくしていく場合と小さくしていく場合では吹鳴音の周波数が遷移するアパチュアの大きさが異なるという結果が得られた.更に,アパチュアを小さくすれば吹鳴音の周波数が高くなるという奏者の見解とは逆に,人工吹鳴においてアパチュアを大きくしたときに吹鳴音の周波数が高くなるという興味深い結果が得られた.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1921年05月07日, 1921-05-07
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1916年08月16日, 1916-08-16
1 0 0 0 OA フィリピン語辞典編纂のためのコーパス構築と携帯端末用アプリの開発研究
1 0 0 0 する河湾地域の地震時地殻上下変動
- 著者
- 石橋 克彦
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.105-110, 1984
- 被引用文献数
- 2 17
The coseismic vertical crustal movements in the Suruga Bay region, the Philippine Sea coast of central Japan, during three historical large earthquakes are briefly reviewed with special reference to the late Quaternary seismic crustal movement in the region. According to abundant historical documents, at the time of the 1854 Ansei-Tokai earthquake of magnitude around 8.4, many places on the west coast of Suruga Bay were remarkably uplifted, whereas the east coast was scarcely displaced or slightly subsided. The general pattern of that crustal deformation strongly suggests that the earthquake was basically due to a large-scale thrust faulting along a plane dipping westerly from the Suruga trough running north-south in the middle of the bay so far as the eastern part of its rupture zone is concerned. The pattern of the 1854 coseismic crustal deformation is generally in good harmony with the distribution of late Quaternary tectonic landforms, submarine topography and active faults in the Suruga Bay region, which implies that the 1854-type faulting has recurred many times during the late Quaternary due to the northwestward underthrusting of the Philippine Sea plate at the Suruga trough. There is no positive record of uplift nor subsidence concerning the coseismic crustal deformation in the Suruga Bay region at the time of the 1707 Hoei earthquake of magnitude around 8.4, which is considered on the basis of macroseismic and tsunami data, to have been basically an 1854-type faulting so far as the Suruga Bay region is concerned. At the time of the 1498 Meio earthquake of magnitude around 8.6, which is also considered on the basis of macroseismic and tsunami data, to have been basically an 1854-type faulting so far as the Suruga Bay region is concerned. a point on the west coast of Suruga Bay considerably subsided. This subsidence is interpreted as deformation of the hanging-wall side of the 1854-type reverse faulting. The difference among the coseismic vertical crustal movements on the west coast of Suruga Bay in 1854, 1707, and 1498 suggests that secondary reverse or normal faults on the hanging-wall side of the main thrust contribute much to the surface deformations and that these subsidiary faultings do not always accompany the plate boundary main ruptures. These features of coseismic crustal deformations in the Suruga Bay region should be taken into account in the morphotectonic investigation of the region.
1 0 0 0 地域住民の意向に配慮した橋梁景観の定量的評価法に関する基礎的研究
- 著者
- 勇 秀憲
- 出版者
- 高知工業高等専門学校
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2011
地域における良好な景観形成のためには,その地域特性や地域住民の意向に合致した総合的な景観評価法の確立が急務である。特に橋梁景観においては,橋を含む景観の形状と色彩がその景観イメージ・感性に大きな影響を及ぼす。本研究は,橋梁景観の形状特性と色彩特性を相互に考慮し,橋梁新設・改修時や再塗装時などでの色彩評価・選定のための合理的で定量的な工学指標を含む景観評価法・設計法の確立を目標とするものである。平成25年度は,平成24年度に提案した橋梁景観を構成する背景と橋梁の形状に着目した橋梁景観評価法に関し,背景を含む橋梁景観のカラー画像・白黒画像および背景を取り除いた橋梁のみの白黒画像の3種類の画像を対象に,それぞれSDアンケート調査と因子分析の結果から,色彩の有無と背景の有無によるイメージの変化を多変量解析により定量的に調べた。因子分析とクラスター分析を用いてイメージの変化の分類を行い,数量化II類を用いてイメージの変化の分類と景観属性(構造形式,架設場所など)との相互関連性を調べた。色彩の有無や背景の有無によるイメージの変化は,ともにその景観要素(構造形式,架設場所など)に依存することが示された。また,平成23・24年度の研究で提案した色彩評価法の適用事例として,主な世界の絶景風景を対象に,それらの「美しさ」のイメージの分析を実施した。SDアンケートを実施し因子分析から,イメージ特性,主色彩および地域との相互関係を評価し,本色彩評価法の妥当性を示した。なお,主色彩は本経費によるカラーイメージ分析ソフトウェアと色彩色差計により測色し定量化した。本研究提案の色彩評価法,カラーイメージ評価法およびフラクタル解析を連携させることで,本研究を基にして,各種景観に対し色彩特性と形状特性を総合的に配慮できる新しい定量的な景観設計システムの構築を目指すことがきるものと考える。
1 0 0 0 構造生物学
- 著者
- A. Liljas [ほか] 著 田中勲 三木邦夫訳
- 出版者
- 化学同人
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 OA イオン選択性液膜界面における電位発生機構の分子レベルでの解釈
- 著者
- 遠田 浩司
- 出版者
- 公益社団法人日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.641-657, 1996-07-05
- 被引用文献数
- 1
レーザー光第二高調波発生(SHG)及び分子プロ-ブを用いる新しい手法によって, イオン選択性電極(ISE)液膜界面における電位応答機構を分子レベルで解釈する研究を行った.イオノフォア含有ISE液膜/試料水溶液界面にレーザー光を照射することによりSHGが発生し, その強度が試料水溶液中の目的イオン濃度が増加するに従って増加することを見いだした.この結果は, 生成した陽イオン-イオノフォア錯体がISE液膜界面で配向しSHG活性種となっていることを示唆している.又, ISE液膜の目的イオンに対するSHG強度変化と膜電位変化との相関より, 膜界面で配向したSHG活性な錯体陽イオン種が主に膜電位を支配していることを明らかにし, SHG強度より見積もった界面電荷密度に基づいて解析した.更に, 膜電位と界面電荷密度の関係を定量的に調べるために, 光照射によって膜の状態を一切変えることなく, 膜中のイオノフォア濃度及びそのイオノフォアに配位するイオンとの間の結合力(錯体安定度定数)を変化させることができる光応答性イオノフォアを分子プローブとして利用し, 光で誘起された膜電位の絶対値及び電位応答勾配の変化量を, 液膜界面での錯形成平衡を考慮した拡散電気二重層に基づく界面モデルを用いて定量的に説明した.
1 0 0 0 IR 紀行文作家・田山花袋(2)明治四三年、伊勢・奈良・京都の旅
- 著者
- 光石 亜由美
- 出版者
- 奈良大学
- 雑誌
- 奈良大学紀要 (ISSN:03892204)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.348-327, 2013-03
一九一〇〔明治四三〕年三月、田山花袋、蒲原有明、前田晁、窪田空穂、吉江孤雁の五名が、伊勢・奈良・京都をめぐった七日間の旅程を明らかにした。まず、この五人の関係を年譜や伝記を参照して概略し、次に、五人が一九一〇〔明治四三〕年三月の旅に関して書き残した紀行文、小品、回顧録などの資料を探索した。そして、その資料により、旅の動機、そして旅程をできるかぎり復元することを試みた。
1 0 0 0 IR 橘広相考(2)
- 著者
- 滝川 幸司
- 出版者
- 奈良大学
- 雑誌
- 奈良大学紀要 (ISSN:03892204)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.364-350, 2013-03