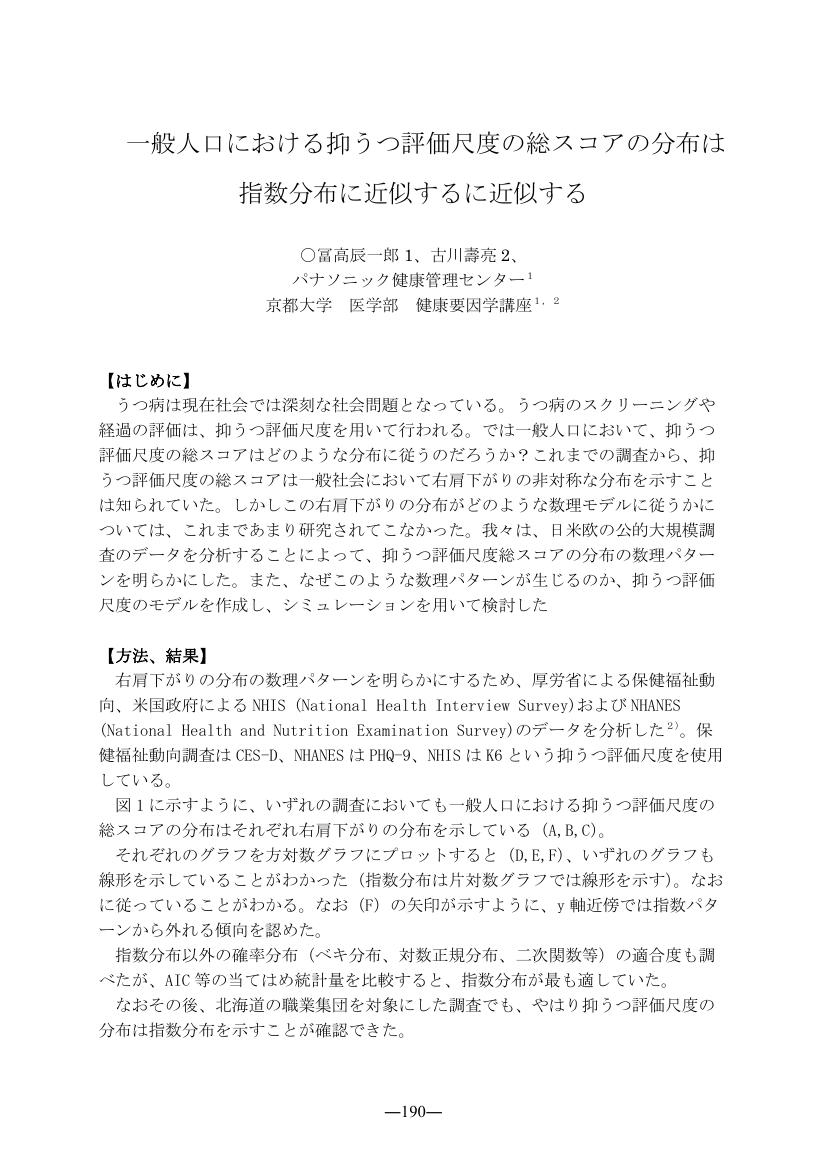- 著者
- Kyoji Fujiwara Toshiyuki Suzuki Hiroyuki Motomura
- 出版者
- National Museum of Nature and Sciece
- 雑誌
- 国立科学博物館研究報告A類(動物学) (ISSN:18819052)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.229-233, 2022-11-22 (Released:2022-11-22)
- 参考文献数
- 8
A single specimen (14.9 mm in standard length) of Trimma panemorfum Winterbottom and Pyle, 2022, a species recently described on the basis of three specimens from deep coral reefs off Palau, was collected from Okinawa Island, Ryukyu Islands, southern Japan. A description of the Japanese specimen, the first Japanese record of T. panemorfum, is provided, and the new standard Japanese name “Kosumosu-benihaze” proposed for the species.
3 0 0 0 OA 機能性塗料 : 航空機用塗料の事例
- 著者
- 目加田 融
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.829, pp.1495-1499, 1987-12-05 (Released:2017-06-21)
3 0 0 0 OA ヒップホップについての諸要素 -ブロンクスからイタリアへと-
- 著者
- 谷口 眞生子
- 出版者
- 大阪音楽大学
- 雑誌
- 大阪音楽大学研究紀要 (ISSN:02862670)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, 2011-02-15
3 0 0 0 OA 日本人小児における乳歯・永久歯の萌出時期に関する調査研究II その2.永久歯について
- 著者
- 日本小児歯科学会 有田 憲司 阿部 洋子 仲野 和彦 齊藤 正人 島村 和宏 大須賀 直人 清水 武彦 尾崎 正雄 石通 宏行 松村 誠士 石谷 徳人 濱田 義彦 渥美 信子 小平 裕恵 高風 亜由美 長谷川 大子 林 文子 藤岡 万里 茂木 瑞穂 八若 保孝 田中 光郎 福本 敏 早﨑 治明 関本 恒夫 渡部 茂 新谷 誠康 井上 美津子 白川 哲夫 宮新 美智世 苅部 洋行 朝田 芳信 木本 茂成 福田 理 飯沼 光生 仲野 道代 香西 克之 岩本 勉 野中 和明 牧 憲司 藤原 卓 山﨑 要一
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.363-373, 2019-06-25 (Released:2020-01-31)
- 参考文献数
- 17
要旨:日本人永久歯の萌出時期,萌出順序および第一大臼歯と中切歯の萌出パターンを明らかにし,約30 年前と比べて永久歯の萌出に変化があるか否かを検討する目的で,4 歳0 か月から18 歳11 か月の小児30,825 人を調査し,以下の結果を得た。1 .男子の萌出は,1 が5 歳6 か月-7 歳0 か月,6 が5 歳10 か月-7 歳6 か月,1 が6 歳6 か月-7 歳10 か月,2 が6 歳3 か月-8 歳3 か月,6 が5 歳11 か月-8 歳7 か月,2 が7 歳6 か月-9 歳2 か月,3 が9 歳2 か月-11 歳3 か月,4 が9 歳1 か月-11 歳7 か月,4 が9 歳5 か月-11 歳6 か月,3 が9 歳10 か月-12 歳1 か月,5 が10 歳4 か月-13 歳0 か月,5 が10 歳3 か月-13 歳2 か月,7 が11 歳3 か月-13 歳 10 か月,7 が12 歳1 か月-14 歳5 か月の順であった。2 .女子の萌出は,1 が5 歳5 か月-6 歳7 か月,6 が5 歳6 か月-7 歳0 か月,1 が6 歳3 か月-7 歳7 か月,2 が6 歳3 か月-7 歳8 か月,6 が5 歳10 か月-8 歳4 か月,2 が7 歳2 か月-8 歳8 か月,3 が8 歳 8 か月-10 歳5 か月,4 が8 歳11 か月-11 歳0 か月,4 が9 歳1 か月-11 歳1 か月,3 が9 歳2 か月- 11 歳4 か月,5 が10 歳1 か月-12 歳11 か月,5 が10 歳2 か月-13 歳1 か月,7 が11 歳2 か月-13 歳 10 か月,7 が11 歳9 か月-14 歳3 か月の順であった。3 .萌出順序は,男女ともに上顎が6≒1 →2 →4 →3 →5 →7 で,下顎が1 →6 →2 →3 →4 →5 → 7 であった。4 .第一大臼歯と中切歯の萌出パターンは,男子では上顎がM 型77.2%,I 型22.8%で,下顎がM 型29.2%,I 型70.8%であった。女子では上顎がM 型73.4%,I 型26.6%で,下顎がM 型36.7%,I 型63.3%であった。5 .萌出時期の性差は,すべての歯種で女子が早く萌出しており,上下顎1, 2, 3, 4 および6 に有意差が認められた。6.約30 年前に比べて,男子は上下顎4, 5, 6 が,女子は3,上下顎の4, 5, 6, 7 の萌出時期が有意に遅くなっていた。
3 0 0 0 出水の歴史と物語
- 著者
- 出水郷土誌編集委員会 編
- 出版者
- 出水市
- 巻号頁・発行日
- 1967
- 著者
- 松永 裕太 佐伯 高明 高道 慎之介 猿渡 洋
- 雑誌
- 研究報告音声言語情報処理(SLP) (ISSN:21888663)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-SLP-140, no.31, pp.1-6, 2022-02-22
本論文では,個人性を再現する自発的な音声合成の実現に向けて,言語学的知識に基づいた包括的な実験的調査を行う.近年発展している音声クローニングは流暢な朗読発話に限定され,より人間らしい自発的な音声合成のための新たな音声クローニングの手法が求められている.そこで本論文は,声色の個人性のみならず非流暢性の個人性を再現可能な自発音声合成に取り組む.具体的には,主要な非流暢性であり,心理学や言語学の研究により発話生成やコミュニケーションにおいて重要な役割を果たすことが知られている,フィラーを扱う.本論文では,話者依存と話者非依存のフィラー予測手法を比較評価するため,多話者コーパスで学習した話者非依存のフィラー予測モデルを用いた音声合成手法を提案する.実験的評価により,フィラーの位置と種類の関連,自然性と個人性のトレードオフを明らかにし,人間らしい音声合成の実現への方向性を示す.
3 0 0 0 OA 日本歌学全書
- 著者
- 佐々木弘綱, 佐々木信綱 共編並標註
- 出版者
- 博文館
- 巻号頁・発行日
- vol.第4編 後拾遺和歌集 第1−20(藤原通俊奉勅編) 相模集(相模) 経信卿母集(源経信母) 高陽院歌合 源経信判−寛治8年, 1891
3 0 0 0 OA 耳硬化症におけるCT所見と術後成績の検討 ─CT所見と術後成績の予測─
- 著者
- 力武 正浩 小島 博己 山本 和央 田中 康広 森山 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳科学会
- 雑誌
- Otology Japan (ISSN:09172025)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.125-130, 2013 (Released:2015-04-16)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 8
画像診断の進歩により高分解能側頭骨CTにおいて耳硬化症病変の有無や進展範囲を評価することが可能となりつつあるが、耳硬化症症例における術前CT所見と術後成績について検討した。側頭骨CTを施行し耳硬化症と診断され、初回アブミ骨手術を行った67人81耳を対象とした。術前CTにて卵円窓前方および蝸牛周囲の脱灰の有無を判断した。術後成績はAAO-HNSの基準案に準じ術後気骨導差が10dB以下に収まるものを成功とした。CTにてfenestral typeと診断されたものが59.3%、蝸牛にも脱灰像を認めたretrofenestral typeと診断されたものが9.9%、所見なし30.9%であった。卵円窓の狭小化例が9.9%あり、アブミ骨底板の肥厚例が22.2%であった。全症例における手術成績は79.0%であった。CT上、卵円窓の狭小化が認められた例の成功率は42.9%、アブミ骨底板の肥厚が認められた例では66.7%であった。病態が進行したと考えられる卵円窓狭小化、アブミ骨底板肥厚が認められた症例では手術成功率が低かった。
3 0 0 0 OA プライシングの系譜
- 著者
- 兼子 良久 上田 隆穂
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.6-17, 2022-01-07 (Released:2022-01-07)
- 参考文献数
- 34
1990年代後期以降,インターネットの普及,デジタル財の増加,収集可能な情報の増加,AI技術の発展など,情報技術の急速な進歩によって企業を取り巻くマーケティング環境は大きく変化した。これら環境変化を一つの背景に,企業が採用する価格戦略にも変化が生じた。この結果,近年ではダイナミック・プライシングとサブスクリプションが価格戦略の二大潮流になっている。本稿の目的は,情報技術が進歩する1990年代後期以降に採用されるようになった主要な価格戦略を整理し,Tellis(1986)によって示された価格戦略を起点としたプライシングの系譜を示すことにある。本稿では,近年の各価格戦略が採用されるようになった背景とプライシングの系譜に基づき,今後の価格戦略の行く末について述べる。
3 0 0 0 OA CA8-1 一般人口における抑うつ評価尺度の総スコアの分布は指数分布に近似するに近似する
- 著者
- 冨高 辰一郎 古川 壽亮
- 出版者
- 日本行動計量学会
- 雑誌
- 日本行動計量学会大会抄録集 49 (ISSN:21897484)
- 巻号頁・発行日
- pp.190-193, 2021-08-30 (Released:2021-11-17)
- 著者
- 小谷 眞男
- 出版者
- Japan Society of Family Sociology
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.201-207, 2009
3 0 0 0 OA 建築土木資料集覧
- 著者
- 建築土木資料集覧刊行会 編
- 出版者
- 建築土木資料集覧刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和16年版, 1941
3 0 0 0 OA 人工内耳小児のハビリテーション
- 著者
- 諸頭 三郎 内藤 泰
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.494-508, 2020-12-28 (Released:2021-01-16)
- 参考文献数
- 72
要旨: 人工内耳小児のマッピングや言語ハビリテーション, 心理的及び社会適応上の課題と対応などの術後ハビリテーションの概要を述べた。 人工内耳による聴覚入力と音声表出とは密接な関係にあり, 小児ではマッピングの結果が聴覚による言語学習や構音の発達に大きく影響する。従って, 小児での人工内耳マッピングでは, 強すぎる電荷量での刺激を避け, 適切な電荷量のマップで, 人工内耳を安定して継続的に装用できることが基本となる。個々の難聴原因や合併症などを勘案し, 最適な言語モダリティや言語ハビリテーションの方法や内容を検討することが重要である。また, 小児から成人に至るまで, すべてのライフステージで人工内耳での聴こえの限界に起因する心理的及び社会適応上の課題が起きることを想定し, 人工内耳の補聴援助システムを活用するなどの対応や指導が必要である。そして, 人工内耳小児自身が自分本来の人生を歩んでいけるよう, 人工内耳小児に関わる医師や言語聴覚士, 聴覚特別支援学校の教諭といった多職種による, 長期的視点にたった継続的なハビリテーションと支援が必須であると考える。
3 0 0 0 OA 拡張タンデムラーニングの実践と展開――ファシリテーターの役割を中心に
- 著者
- 寺尾 智史
- 出版者
- 九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会リポジトリ部会
- 雑誌
- 九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 = The Joint Journal of the National Universities in Kyushu. Education and Humanities (ISSN:18828728)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.No.7, 2021-10-30
宮崎大学では、一般の大学では外国語教育の対象とされていない言語を母語とする留学生が、複数の日本人学生、自分以外の留学生に対して、自らの母語とそれをとりまく文化を日本語で教えるクラスを正規授業科目として開講している。「拡張型タンデムラーニング」の実践ともいうべきこのクラスのコーディネーションおよびファシリテーション担当者としての参与観察を通して、学ぶ側、そしてなによりレクチャーする留学生側にどのような異文化理解の互恵的深化が見られるかをまとめ、今後のさらなる展開の指針とする。
3 0 0 0 OA 社会意味ネットワーク分析とテキストマイニングの混合法による知識創造型学習の評価の提案
- 著者
- 大﨑 理乃 大島 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.13-29, 2019-07-10 (Released:2019-07-10)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4
本研究は,アクティブラーニングとして今後発展が期待される知識創造型学習に焦点をあて,新たな評価方法を提案するものである.提案方法では,知識創造型学習のデザイン原則に対して,CSCL 研究をはじめとして成果を挙げつつある社会意味ネットワーク分析と,テキストマイニングの混合法による可視化に基づく評価を行なった.具体的には,知識創造型学習を目指して設計された課題解決型学習(Project Based Learning)で利用されたCSCL システム上の学習者による書き込み内容を分析し,最終成果物の質が異なるグループの知識創造プロセスの違いが評価できることを確認した.その上で,提案した評価方法の有用性と限界を検討した.
3 0 0 0 OA 本草綱目啓蒙 48巻
- 著者
- 蘭山小野先生 口授
- 出版者
- 須原屋善五郎 [ほか2名]
- 巻号頁・発行日
- vol.[14], 1805
3 0 0 0 OA 明治時代以降の「〜川」の連濁と非連濁について
- 著者
- 城岡 啓二
- 出版者
- 静岡大学人文社会科学部
- 雑誌
- 人文論集 (ISSN:02872013)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1-2, pp.A159-A185, 2014-01-31
3 0 0 0 IR 明治十四年の政変の真相 (1)
- 著者
- 木曽 朗生
- 出版者
- 長崎大学教育学部政治学研究室
- 雑誌
- 架橋 = KAKYO
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.31-210, 2005-03
本誌未刊
3 0 0 0 OA 佐賀郡誌
- 著者
- 私立佐賀郡教育会 編
- 出版者
- 佐賀牧川書店
- 巻号頁・発行日
- 1916