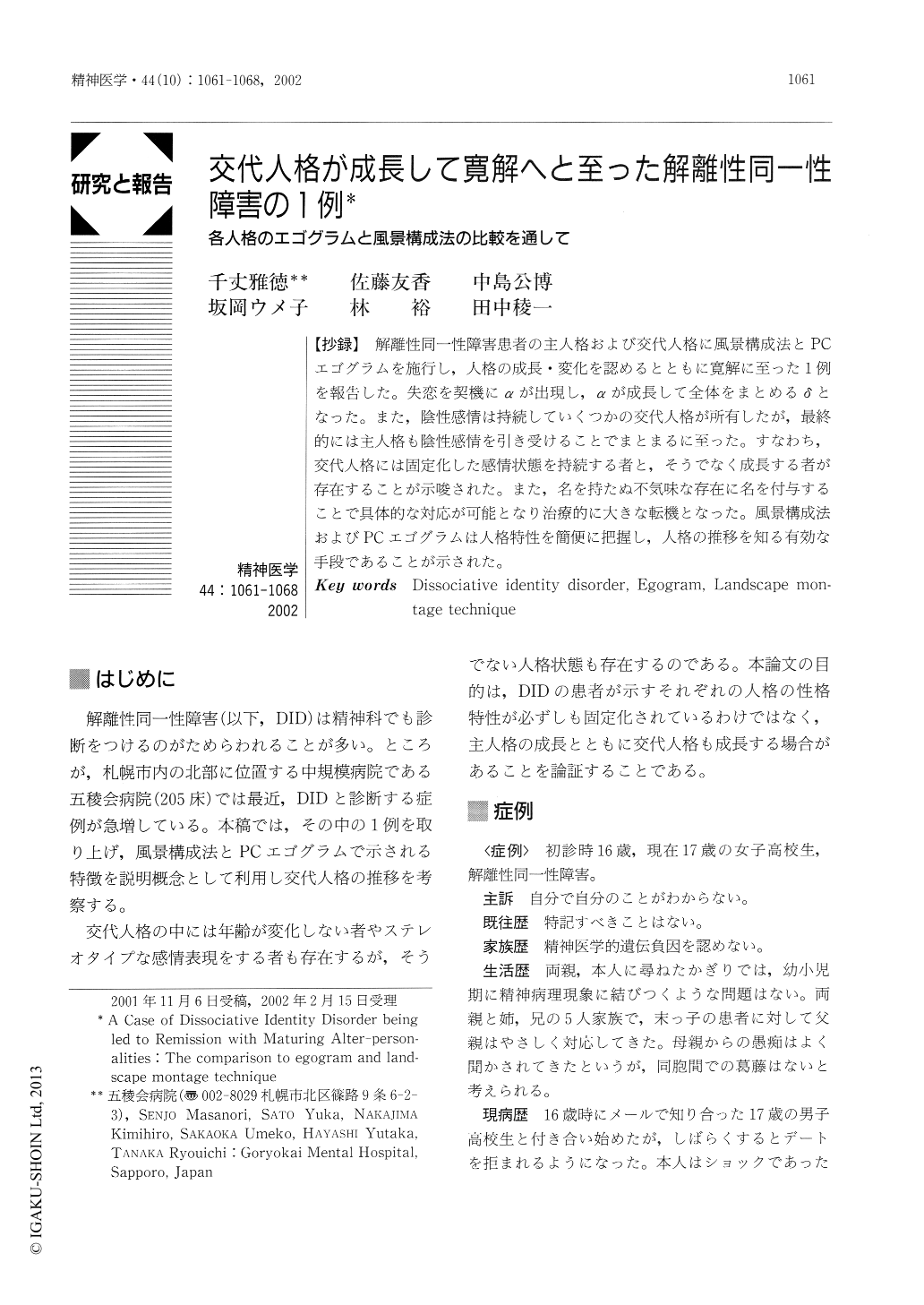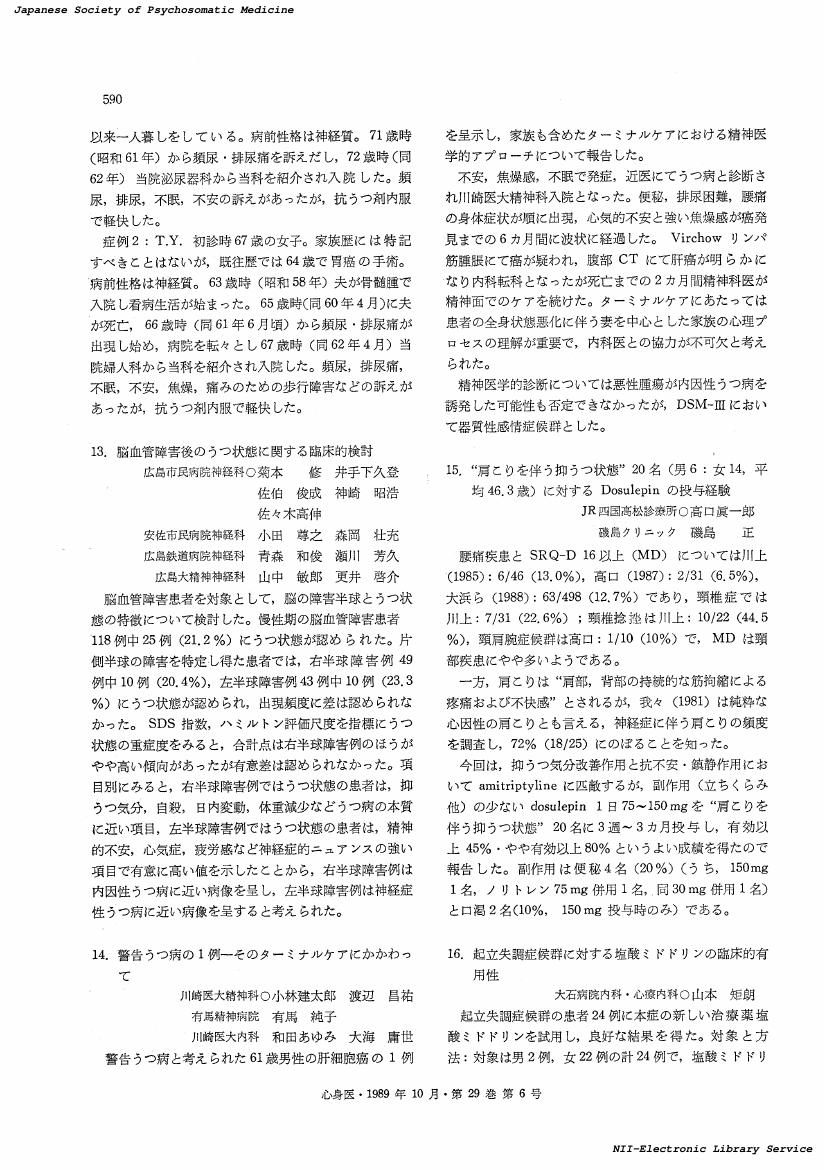3 0 0 0 OA トロポノイド化学の育つまで
- 著者
- 野副 鉄男
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.9, pp.610-616, 1984-09-25 (Released:2009-05-25)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 障害者総合情報ネットワークのアーカイヴィング・メソッド
- 著者
- 塩野 麻子
- 出版者
- 立命館大学生存学研究センター
- 雑誌
- 立命館生存学研究 = 立命館生存学研究 (ISSN:24337811)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.219-223, 2019
- 著者
- 伊東 香純
- 出版者
- 立命館大学生存学研究センター
- 雑誌
- 立命館生存学研究 = 立命館生存学研究 (ISSN:24337811)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.225-229, 2019
3 0 0 0 OA 社会基盤としての電子認証と電子署名
- 著者
- 松本 泰
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.324-329, 2006 (Released:2009-10-15)
- 参考文献数
- 4
An authentication platform for electronic signature and electronic authentication, which is applied to electronic government, is utilized as the social infrastructures. In this paper, I explain such an authentication platform from technical, legal and business view with internal and external situation. Then, I present future problems.
3 0 0 0 IR 「聖者」と「自然児」 : 大正時代の和辻哲郎の思想
- 著者
- 藤村 安芸子 フジムラ アキコ Akiko Fujimura
- 雑誌
- 駿河台大学論叢
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.63-77, 2020
3 0 0 0 リクルートスーツのシャツの色が印象形成に及ぼす影響
- 著者
- 庄山 茂子 浦川 理加 江田 雅美
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.87-94, 2004-03-31
- 被引用文献数
- 1
本研究は、女子学生のリクルートスーツにおいて、シャツの色彩の違いが、服装メッセージにどのような影響を及ぼすかを明らかにすることを目的とした。調査に用いた試料は、ベーシックなdark Grayのスーツにオープンカラーのシャツである。12色のシャツの色について調査した(ペールトーン10色と無彩色2色)。調査対象者は、就職活動中の女子学生166名と採用者側の銀行員157名とした。女子学生が着たい色、採用者側が好感を持つ色について回答を求めた。それぞれの色について、25対の形容詞を用いてSD法によるイメージ評価をしてもらった。その結果、女子学生が着たい色および採用者側が好感を持つ色の上位は、White、Blueであった。因子分析の結果、女子学生は、着たい色に「洗練」や「知性」を求め、採用者側は交換を持つ色に「誠実さ」を感じている事が明らかとなった。シャツの色彩の違いにより異なる服装メッセージが認められた。
- 著者
- 斎藤 徹 白波瀨 龍一 砂川 裕亮 松下 祐也 髙橋 耕一 牧野 秀樹 山崎 裕 栂安 秀樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.233-239, 2020-12-31 (Released:2021-01-28)
- 参考文献数
- 15
当院の高齢者に対する歯科訪問診療を評価することを目的として,高齢者の歯科訪問診療症例と外来診療症例の年齢分布および歯科治療の内訳を比較した。当院が2011年1月~2019年12月の間に歯科訪問診療および外来診療を施行した新患症例はそれぞれ6,303例,10,014例であった。これらの症例中,65歳以上の高齢者の訪問診療および外来診療症例はそれぞれ5,753例(91.3%),1,806例(18.0%)であった。訪問診療では外来診療と比較して,歯周治療(60.7% vs 88.1%),義歯新製(28.0% vs 46.7%),抜歯(20.3% vs 45.6%),歯冠補綴(4.4% vs 50.6%),インレー修復(0.5% vs 17.4%),レジン・グラスアイオノマー充塡(21.9% vs 56.1%),抜髄(2.0% vs 18.9%)および感染根管処置(1.7% vs 20.5%)を行った症例の割合が有意(p<0.001)に低かった(歯科治療内容の重複症例あり)。他方,義歯調整・修理(32.5% vs 16.7%)および摂食機能療法(18.5% vs 2.0%)を施行した症例の割合は訪問診療では外来診療と比較して有意(p<0.001)に高かった。 高齢者に対する歯科訪問診療でも多様な歯科治療が行われており,外来診療と比較して義歯調整・修理および摂食機能療法を施行した症例の比率が高く,咀嚼や摂食嚥下機能に問題がある症例が多かった。しかし,その他の治療を行った症例の割合は歯科訪問診療では外来診療と比較して低かった。
3 0 0 0 IR 『インタビューの社会学』を読み直す ― 書評とリプライを手がかりに ―
3 0 0 0 OA (4)單螺船の伴流係数の推算法(昭和24年春季講演會論文梗概)
- 著者
- 松藤 龍一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会雑纂 (ISSN:24331023)
- 巻号頁・発行日
- vol.278, pp.13-14, 1949-05-25 (Released:2018-04-21)
- 著者
- 千丈 雅徳 佐藤 友香 中島 公博 坂岡 ウメ子 林 裕 田中 稜一
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.10, pp.1061-1068, 2002-10-15
【抄録】 解離性同一性障害患者の主人格および交代人格に風景構成法とPCエゴグラムを施行し,人格の成長・変化を認めるとともに寛解に至った1例を報告した。失恋を契機にαが出現し,αが成長して全体をまとめるδとなった。また,陰性感情は持続していくつかの交代人格が所有したが,最終的には主人格も陰性感情を引き受けることでまとまるに至った。すなわち,交代人格には固定化した感情状態を持続する者と,そうでなく成長する者が存在することが示唆された。また,名を持たぬ不気味な存在に名を付与することで具体的な対応が可能となり治療的に大きな転機となった。風景構成法およびPCエゴグラムは人格特性を簡便に把握し,人格の推移を知る有効な手段であることが示された。
3 0 0 0 OA ボランティア女性教育情報センターだよりNo.92
- 著者
- 国立女性教育会館情報ボランティア
- 巻号頁・発行日
- 2021-03-26
- 著者
- 片山 卓也
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.3_33-3_46, 2019
<p>国民年金法の述語論理による記述と定理自動証明システムZ3Pyによる検証に関するケーススタディついて述べた.法令の作成は伝統的に人手により行われて来たが,近年法令が大量に作られるようになり,その品質の維持には計算機科学,特にソフトウェア工学や人工知能で培われた技術を応用することが有効であると考えられる.本稿では,法令を意図した通りに正しく作る上で,法令の形式的記述と自動検証技術が有効であることを確認する目的で,国民年金法の基本的条文の述語論理による記述と,そのSMTソルバーZ3Pyによる検証を試行した結果を報告する.法令の文章上の複雑さは別にすると,その論理的深度は深くなく,このような方法が誤りの無い法令を作る上で有効な方法になり得ることが分かった.</p>
3 0 0 0 OA 自己愛傾向が援助行動に及ぼす影響
- 著者
- 阿部 晋吾 高木 修
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.65-73, 2011-02
In this study, we examined the relationship between the level of narcissism and helping behavior. Participants, 108 students, were asked to rate the Narcissistic Personality Inventory-Short Version (NPI-S), the normative attitude toward helping, helping ability, and daily helping behaviors. Results indicated that the higher the sense of superiority and competence, which was an aspect of the narcissistic personality, the higher they rated their helping ability. On the other hand, the higher the need for attention and praise, another aspect of the narcissistic personality, the more they rated positively on their normative attitude. Moreover, helping ability and the normative attitude were positively related to the daily helping behaviors. These results suggested that there would be two processes in the influences of narcissism on helping behavior.本研究では、対象者(108名の学生)に自己愛人格目録短縮版(NPI-S)と、援助規範意識、援助能力評価、援助行動について回答してもらい、自己愛傾向の程度によって援助行動に差異が見られるかどうかを検討した。その結果,自己愛傾向のうち、優越感・有能感が高いほど、援助能力評価が高いことが明らかとなった。また、注目・賞賛欲求が高いほど、肯定的な援助規範意識を持ちやすいことも明らかとなった。さらに、援助規範意識、援助能力評価は、援助行動に対して正の影響を及ぼしていた。これらの結果は、自己愛傾向は2つのプロセスを通じて援助行動に影響を及ぼしていることを示唆している。
3 0 0 0 慶応SFCのテクニカルライティング講座
- 著者
- 君島 浩
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. コンピュータと教育研究会報告 (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.29, pp.17-24, 1998-03-20
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4
私は慶応義塾大学藤沢湘南校舎のテクニカルライティング講座の講師陣の一人として講座を設計し, 実施した.私の講座は世界標準のテクニカルライティング講座の日本語版である.文書工学手法と段落作成法とを合体させた.本講座は教育を効率化し, 作文も効率化する.このような世界標準の作文教育は翻訳や国際教育を容易にする.
- 著者
- 高橋 遼平 タカハシ リョウヘイ Ryohei TAKAHASHI
- 出版者
- 総合研究大学院大学
- 巻号頁・発行日
- 2012-09-28
現在の琉球列島の食文化に家畜ブタは必要不可欠な存在だが、その起源は不明瞭である。文献史実では琉球列島への最古の家畜ブタ導入は14世紀頃とされ、それ以前は琉球列島に固有の野生イノシシであるリュウキュウイノシシが狩猟されていたと考えられてきた。しかし近年では琉球列島や周辺地域を対象とした考古学・動物考古学研究から、12世紀以前の先史時代にイノシシ・もしくは家畜ブタ(以下Sus属と省略)が外部諸地域から導入されていた可能性が指摘されている。本論文では先史時代の琉球列島へ外部地域からSus属が導入された時期や地域・経路を解明するため、琉球列島の現生及び先史時代遺跡から出土したSus属の歯や骨を用いて形態解析とancient DNA (aDNA) 解析を行った。本論文は全6章から構成される。第1章では家畜ブタや様々な家畜動物の起源や拡散に関する動物考古学研究や分子系統学研究を概観した。また本章では琉球列島の形成史や先史時代文化に関する研究も概観した。第2章には解析に使用した遺跡資料と現生資料、そして解析手法を記載した。琉球列島は地質学・考古学的に北部圏、中部圏、南部圏の3つに区分される。本論文ではこれらのうち中部圏と南部圏の先史時代遺跡から出土した資料を解析した。さらに本論文では現生リュウキュウイノシシの遺伝的変異の程度を確認するため、現生個体のmtDNA D-loop領域を解析した。第3章では沖縄本島の野国貝塚群(約7200 - 4400年前)を含む中部圏の遺跡から出土したSus属の歯や骨を用いて形態・aDNA解析を行った。野国貝塚群から出土した下顎第三臼歯 (M3) の計測値を現生リュウキュウイノシシや沖縄諸島の他の遺跡資料(約4800 - 1400年前)と比較した結果、野国貝塚群から出土したSus属のM3のサイズ分布は、現生リュウキュウイノシシや他の遺跡資料とは異なり小さい事が判明した。また野国貝塚群から出土した下顎骨から得られたmtDNA D-loop領域の塩基配列情報をデータベースから取得した世界のSus属と比較した結果、野国貝塚群から現生リュウキュウイノシシと遺伝的に異なる系統に属するSus属の配列タイプを検出した。第4章では琉球列島南部圏に属する石垣島の大田原遺跡(約4100 - 3800年前)と神田貝塚(約1600 - 900年前)、宮古島のアラフ遺跡(約2800 - 800年前)と長墓遺跡(約1900 - 1400年前)から出土したSus属の骨を用いてaDNA解析を実施した。この結果石垣島の遺跡から出土したSus属は全て現生リュウキュウイノシシと遺伝的に近縁であった。一方宮古島のアラフ遺跡と長墓遺跡からは、現生リュウキュウイノシシと遺伝的に異なる系統に属する個体が検出された。第5章では現生リュウキュウイノシシの遺伝的変異の程度を検討した。リュウキュウイノシシの生息する全7島のうち6島由来の113個体を用いたmtDNA解析の結果、これらは全て遺伝的に近縁であり、他のアジアのSus属系統と近縁な配列タイプは現生集団から検出されなかった。第6章では研究結果をまとめ、先史時代の琉球列島を舞台としたSus属の導入について考察した。琉球列島中部圏では約7200 - 4400年前、南部圏でも約2000年前に琉球列島の野生イノシシであるリュウキュウイノシシとは形態・遺伝的に異なる特徴を持つSus属が存在した事が判明した。この結果から1) 先史時代の琉球列島には遺伝的に異なる野生イノシシが複数系統存在した、2) 先史時代の琉球列島へ人類が近隣地域からSus属を導入していた、という2仮説が考えられた。しかし仮説1で示すように先史時代の琉球列島に複数の野生イノシシ系統が混在していた場合、a) 現在は生息地域ごとに異なるイノシシ系統が生き残っている可能性が高いが、113個体の現生リュウキュウイノシシを解析しても遺伝的に異なる系統は確認されなかった。b) また複数のイノシシ系統は、アジア大陸と琉球列島が地続きであった可能性のある約8万年前より古い時期に渡来し、遺跡が形成された時期まで多型を維持していた事になる。しかしシミュレーションによる推定の結果、複数のイノシシ系統がどちらか1系統に固定する事なく約7万5000年間維持される確率は低い(1%以下)。従って本研究では琉球列島にかつて複数系統の野生イノシシがいたという仮説1は支持されなかった。以上の結果から本研究では、先史時代の琉球列島やその周辺地域でSus属を伴う人類の移動が生じていたという仮説2が支持された。野国貝塚群が属する琉球列島中部圏とアラフ遺跡や長墓遺跡が属する南部圏の間では物質文化交流が12世紀頃まで生じていなかったとされるため、中部圏と南部圏では異なるSus属の導入経路があったと考えられる。先史時代の琉球列島中部圏は考古学的に九州との交流が指摘されている。しかし野国貝塚群から出土したSus属は、九州等のニホンイノシシやアジア大陸の野生イノシシよりも小さいM3を持つうえ、リュウキュウイノシシよりもさらに小型であるため、これらの地域の野生イノシシが直接導入されたとは考えにくい。野国貝塚群のSus属は、家畜化の影響を受けて M3が矮小化していた可能性も考えられる。アラフ遺跡や長墓遺跡が属する琉球列島南部圏の先史時代文化は、フィリピンやミクロネシア等を含む海外諸地域に影響されていた可能性がある。島嶼部東南アジアやオセアニアでは、約3300年前以降に人類が家畜ブタを伴って移動や交流をしていた事が知られているため、琉球列島南部圏のSus属の導入はこれらの先史時代人類の移動や交流による可能性も考えられる。 本論文では先史時代の琉球列島に複数のSus属の導入経路が存在した可能性を示した。また本研究成果は先史時代の東アジアや東南アジア、オセアニアにおけるSus属を伴う人類の移動や交流に琉球列島が含まれていた可能性をも示している。 Although domestic pigs play an important role in traditional food resources in the Ryukyu Islands, southern Japan, the origin of domestic pigs in the Ryukyu Islands is not clear yet. From historical evidence, the oldest date for the introduction of domestic pigs to the Ryukyu Islands was in the 14th century AD. It has been believed that there were no domestic pigs in Ryukyu before this introduction (earlier than 14th century AD), rather people hunted Ryukyu wild boar, one of the subspecies of wild boar that inhabits the Ryukyu Islands. Recent archaeological and zooarchaeological studies in the Ryukyu Islands and surrounding areas, however, suggest that there is a possibility that wild boar or domestic pigs (Sus) may have been introduced to the Ryukyu Islands in the prehistoric times, which is earlier than the 12th century AD according to archaeological chronology. In this thesis, I analyzed tooth samples and ancient DNA (aDNA) derived from bone of Sus excavated from prehistoric sites in the Ryukyu Islands as well as the modern Ryukyu wild boar samples, and investigated morphologically and molecular phylogenetically whether external introduction of Sus into the Ryukyu Islands took place during prehistoric times.This thesis consists of six chapters.Chapter one describes previous archaeological and molecular phylogenetic studies concerning the origin and dispersal over the world of various domestic animals including domestic pigs. In this chapter, I also reviewed previous studies on the formation of the Ryukyu Islands as well as prehistoric culture of the Ryukyu.Chapter two describes archaeological and modern samples, and methods of analyses used in this thesis. Based on geological and archaeological knowledge, the Ryukyu Islands can be divided into three cultural regions, North, Central, and South regions. Of these three cultural regions, for the following analyses, I used archaeological samples from prehistoric sites in Central and South cultural regions. Furthermore, nucleotide sequences of mtDNA D-loop region of modern Ryukyu wild boar were determined to investigate the extent of genetic variation among present population of Ryukyu wild boar.In Chapter three, I analyzed morphological and molecular phylogenetic characteristics of Sus tooth samples and aDNA from bones excavated from the sites in Central region, including Noguni shell middens (ca.7200 - 4400 years ago) on Okinawa main Island. Measurements of lower third molars from Noguni shell middens were compared with those of Sus remains from later sites in the Okinawa Islands (ca.4800 - 1400 years ago) as well as modern Ryukyu wild boar. Based on measurements of lower third molars, Sus samples from the Noguni shell middens were distinctly smaller than those from modern Ryukyu wild boar and other ancient sites in the Okinawa Islands. In addition to morphological analysis, nucleotide sequences of ancient mtDNA D-loop region from mandibles of the Noguni shell middens were compared with those of Sus in other parts of the world collected from a database. Phylogenetic analysis using aDNA sequence types showed that some sequence types from the Noguni shell middens made a different cluster from modern Ryukyu wild boar, suggesting a presence of the different genetic Sus lineage from modern Ryukyu wild boar at that time.In Chapter four, aDNA analysis was carried out by using Sus bone samples excavated from Ohtabaru site (ca.4100 - 3800 years ago) and Kanda shell midden (ca.1600 - 900 years ago) in Ishigaki Island, Arafu site (ca.2800 - 800 years ago) and Nagabaka site (ca.1900 - 1400 years ago) in Miyako Island, which belonged to South cultural region. All aDNA sequence types from prehistoric sites in Ishigaki Island were genetically close or identical to those of modern Ryukyu wild boar. However, sequence types from Arafu site and Nagabaka site were in different lineages from modern Ryukyu wild boar but had rather close relationship to other Asian Sus lineages: the similar situation was observed as in Noguni samples.In Chapter five, I investigated the extent of genetic variation among present population of Ryukyu wild boar to find out whether the different lineage detected from ancient samples still exist among the present populations. Ryukyu wild boar inhabits seven islands in the Ryukyu Islands. Phylogenetic studies based on the mtDNA analysis of 113 Individuals from six of the seven islands show all individuals are genetically close to each other, and no sequence type is either identical or similar to other Asian Sus lineages. Chapter six discusses the possibility of the external introduction of Sus into the prehistoric Ryukyu Islands. In the present study, some Sus samples from prehistoric sites in the Central (ca.7200 - 800 years ago) and South cultural regions (ca.2000 years ago) had different morphological / genetic characteristics from modern Ryukyu wild boar. Concerning the origin of these Sus population from the prehistoric sites in Ryukyu, I propose two possible hypotheses: first, there were at least two genetic lineages of wild boar inhabited the prehistoric Ryukyu Islands; second, introduction of Sus to the Ryukyu Islands by human took place during prehistoric times. I distinguish these hypotheses as follows.In the case of former hypothesis, a) It is very likely that some surviving population has different genetic characteristic from those of other habitats (islands). However, multiple lineages of wild boar were not found in 113 individuals from present populations. b) Furthermore, if multiple lineages of wild boar really existed in the prehistoric Ryukyu Islands, they must have migrated from Asian Continent to Ryukyu at the time when land bridge connected these regions, which is earlier than 80,000 years ago. Based on estimation using simulation, probability for coexistence of multiple Sus lineages for the period of 75,000 years was calculated and it reveals to be lower than 1%. These results indicate that it is unlikely that multiple lineages of wild boar coexisted in the prehistoric Ryukyu Islands. Thus, the latter hypothesis that prehistoric introduction of Sus into the Ryukyu Islands by human was supported by my study. It has been suggested that the South cultural region had no archaeological links with North and Central regions until historic time, ca. 12th century AD. This archaeological evidence infers a possibility of more than one introduction pathways of Sus from outside of the Ryukyu directly to the Central or South Cultural regions during prehistoric times. In the case of Noguni shell middens, some cultural factors of prehistoric Central regions were considered to be related to Jomon culture in Kyushu. This archaeological evidence suggests that Sus population was introduced from main land Japan or from the Asian Continent via Kyushu region. In this case the transported Sus cannot be hunted wild boar because the size of wild boar in both mainland Japan and Asian Continent is much larger than those of Noguni shell middens. There is a possibility that lower third molars of Sus from Noguni shell middens were reduced in size as the consequence of domestication. In contrast, prehistoric culture of South cultural region including Arafu and Nagabaka sites were considered to be related to those of Island Southeast Asia such as the Philippines as well as Micronesia. Since it is revealed that prehistoric human dispersal and peopling in Island Southeast Asia and Oceania was accompanied by domestic pigs and other animals, introduction of Sus population to South cultural region of Ryukyu might be involved in such prehistoric interaction of humans. In this thesis I conclude multiple pathways of Sus introduction to the Ryukyu Islands existed during prehistoric times. Furthermore, present study indicates the possibility that cultural interaction and movement of prehistoric human took place between the Ryukyu Islands and surrounding areas, accompanied by Sus.
3 0 0 0 IR 宮武正道の「語学道楽」--趣味人と帝国日本 (特集 民族)
- 著者
- 黒岩 康博
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.1, pp.125-153, 2011-01
奈良の言語研究者宮武正道は、従来マレー語の専門家と考えられていたが、残された旧蔵資料を見ると、彼がマレー語に至るまでに辿った「語学道楽」の跡が明らかになった。中学校時代、切手蒐集の延長として始めたエスペラントに対する熱意は、奈良エスペラント会を発足させ、機関誌『EL NARA』を生み出す。該語を飽くまで社交の道具と見倣す宮武主宰の同会には、パラオよりの留学生エラケツも参加していたが、宮武は彼からパラオ語で多くの民話を聞き取り、『南洋パラオ島の伝説と民謡』を上梓する。この一時期は土俗の研究へと傾いたが、昭和七年七月のインドネシア旅行以降、マレー語を本格的に研究し始める。当初はマレー語の新聞・雑誌を読むことを念頭に置いていたが、日本の南進政策がマレー語圏にも及ぶと、カナの普及やローマ字綴りの日本風改革を提唱するようになる。こうして書斎から出た好事家は、最後タガログ語辞書の完成を待たずに夭逝した。
- 著者
- 高口 眞一郎 磯島 正
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.590, 1989-10-01 (Released:2017-08-01)
3 0 0 0 OA 祖父、 林 愛作のこと
- 著者
- 林 裕美子
- 雑誌
- 甲子 : 武庫川女子大学生活美学研究所甲子プロジェクト報告集
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.11-29, 2018-03-31
3 0 0 0 OA イリジウム-192線源 (740GBq) についての特別形放射性物質に係る試験
- 著者
- 浜岡 進 萩原 聡昭 二ッ川 章二 松下 幹夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.83-88, 2007-02-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 5
3 0 0 0 OA 九州における噴気を利用した家庭用設備の利用実態
- 著者
- 辻原 万規彦 今村 仁美
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.41, pp.255-260, 2013-02-20 (Released:2013-02-20)
The purpose of this paper is to examine the actual use of fumarole gas fixtures in Takenoyu and Tsuetate areas, Kumamoto Prefecture; Kannawa area, Oita Prefecture; and Unagi area, Kagoshima Prefecture. Some features were discovered by conducting field investigations, interviews and questionnaires for residents in each area. The variety of geothermal energy potential and appearance causes the difference of fumarole gas use and expansion process of these areas. Investigating some features of the actual use of fumarole gas fixtures is useful for creating the low environmental load and high-quality living environments.