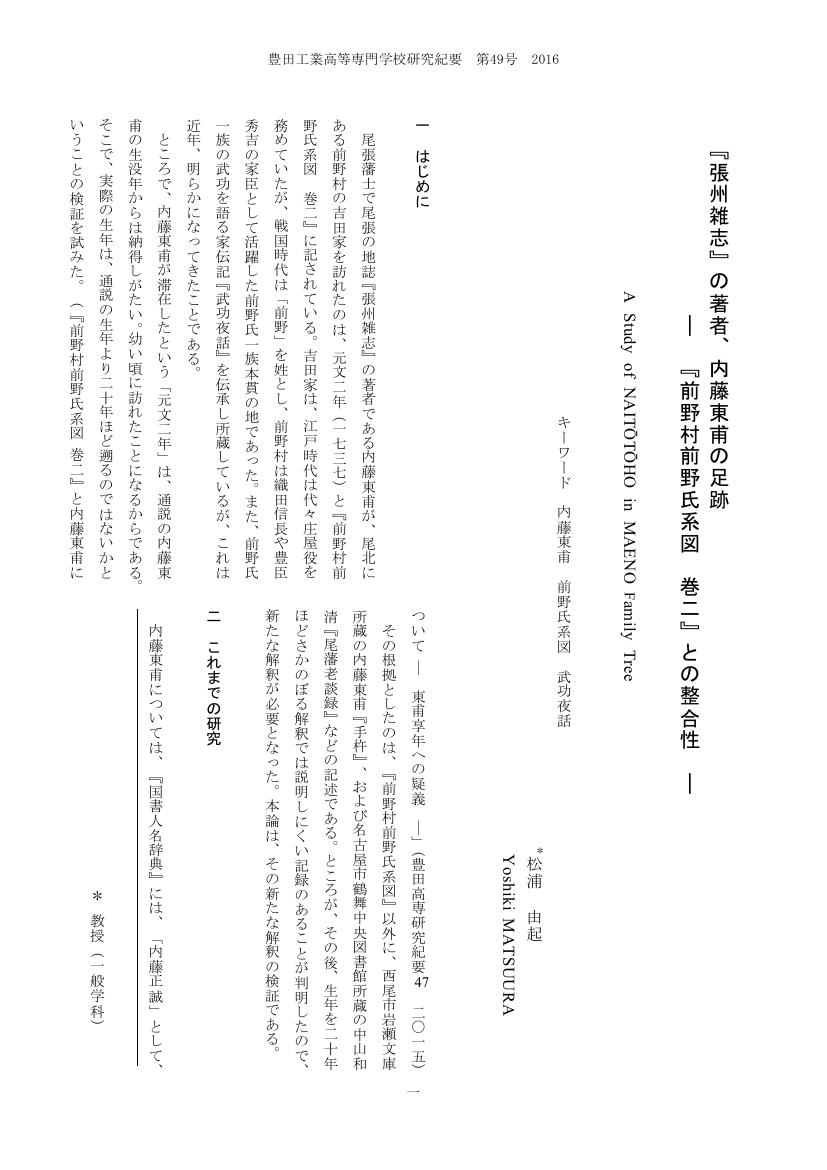3 0 0 0 OA マルコ・ポーロ写本(1) -マルコ・ポーロの東方(2-1)-
- 著者
- 高田 英樹 タカタ ヒデキ Hideki Takata
- 雑誌
- 国際研究論叢 : 大阪国際大学紀要 = OIU journal of international studies
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.131-151, 2010-03-31
- 著者
- 宮原 浩二郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.832-833, 2009-03-31
3 0 0 0 OA N.I.グロデコフ名称ハバロフスク地方博物館所蔵の永樂通寶の化学分析
- 著者
- 中村 和之 三宅 俊彦 GORSHKOV Maxim Valerievich 小林 淳哉 村串 まどか
- 出版者
- National Institute of Technology, Hakodate College
- 雑誌
- 函館工業高等専門学校紀要 (ISSN:02865491)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.39-47, 2018 (Released:2018-01-31)
- 参考文献数
- 12
This paper reports the result of the chemical analysis of the Chinese coin Yongle Tongbao owned by Khabarovsk Regional Museum named after N.I. Grodekov. It was found that this Yongle Tongbao is the officially minted coin. This coin was excavated in Krasnokurovka burial ground in the Khabarovsk Territory. The burial ground was made under the Pokrovka culture (from the 9 th to the 13 th centuries). However the Yongle Tongbao, which was first minted in 1408, was discovered in the mound No. 30 of Krasnokurovka burial ground. So, it is necessary to reconsider the end period of the Pokrovka culture.
3 0 0 0 OA NFκBデコイオリゴの臨床開発
- 著者
- 和田 和洋 森下 竜一
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.579-589, 2010 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 37
近年,核酸医薬品が次世代の分子標的薬として注目され,様々な疾患の分子レベルでの機構解明を目的とした研究に基づき,その有効性が検証され臨床応用への期待が高まっている.DDSを適用し,目的とする臓器・組織へ送達,標的分子に作用させることにより,治療できる対象疾患が拡大されうるが,核酸医薬品の開発には,安全性および品質の確保という観点で,低分子化学合成品にはない留意点があり克服しなければならない.本稿では,NFκBデコイオリゴヌクレオチドの開発を中心に,核酸医薬品の開発上の課題とDDS技術適用の試みを紹介する.
3 0 0 0 OA バイオ後続品(バイオシミラー)の開発と今後の展望
- 著者
- 高安 義行 塚本 哲治
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, no.5, pp.303-309, 2016 (Released:2016-05-13)
- 参考文献数
- 8
バイオ後続品(バイオシミラー)は,品質,安全性および有効性について,先行バイオ医薬品との比較から得られた「同等性/同質性」を示すデータ等に基づき開発される.国内では既に7剤のバイオ後続品が販売されており,バイオ後続品の開発や承認申請に関する企業側の経験も蓄積されてきている.高額な先行バイオ医薬品に比べ,薬価が低く設定されるバイオ後続品は,高騰する国民医療費の抑制策として,また,患者の医療費負担軽減策として大いに期待されており,今後,大型バイオ医薬品の特許が次々と満了することも相まって,この分野の開発競争は激化するものと予想される.一方,医療の現場におけるバイオ後続品の認知度は依然として低く,十分にその価値が発揮されるためには,国の政策に加え,開発・販売する企業がバイオ後続品に関する正しい情報を発信し,医療機関や患者と共有してくことが重要である.
3 0 0 0 OA 會津お薬手帳を用いた薬物医療情報の共有化
- 著者
- 木本 真司 河原 史明 安齊 泰裕 塩川 秀樹 鈴木 涼子 小室 幹男 市橋 淳 西郷 竹次 下山田 博久
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.563-571, 2017-08-31 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 10
目的:とくに救急医療において,地域で形式を統一したお薬手帳による薬物医療情報の共有化が必要であると考える。方法:お薬手帳に関するアンケート調査,病院薬剤師と保険薬局薬剤師が協同した協議会の発足,会津地方で統一した『會津お薬手帳』の構成検討を行った。結果:保険薬局対象のお薬手帳に関するアンケート調査では,お薬手帳のデメリットとして,「持参しない」が90.2%,「医療機関ごとに複数所持している」が85.7%であった。作成した『會津お薬手帳』は,情報共有の同意や病名等を記載する「サマリーページ」,残薬確認,医療スタッフからのメッセージ等を記載する「アセスメントページ」,過去の処方内容や変更が一目でわかる「薬歴ページ」で構成された。考察:救急医療において病名や薬剤服用歴,処方意図を把握することは重要であると考えられ,地域統一型の『會津お薬手帳』を用いての薬物医療情報の共有化が可能となることが示唆された。
- 巻号頁・発行日
- 1945-11
3 0 0 0 OA いわゆる「転形問題」についての覚え書き
- 著者
- 佐々木 隆治 ササキ リュウジ Ryuji Sasaki
- 雑誌
- 立教經濟學研究
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.89-102, 2016-07
3 0 0 0 OA 可換環論の50年
- 著者
- 永田 雅宜
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.157-163, 1984-05-10 (Released:2008-12-25)
3 0 0 0 OA 漢籍国字解全書 : 先哲遺著
- 著者
- 早稲田大学編輯部 編
- 出版者
- 早稲田大学出版部
- 巻号頁・発行日
- vol.第1巻, 1911
3 0 0 0 インタビュー形式によるカーナビ向け自由発話コーパス収集法
- 著者
- 嶋 和明 本間 健 池下 林太郎 小窪 浩明 大淵 康成 佘 錦華
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.J101-D, no.2, pp.446-455, 2018-02-01
電子機器の音声入力操作が一般的になった.音声入力操作に必要となる言語理解器開発のためのコーパスは,主にWOZで収集されてきた.WOZは,人が機械に話すときに見られる簡潔な発話スタイルの収集に向く.しかし,ユーザは,言語理解に優れる機械と対話するなかで,多様な発話をするように変化すると予測される.本研究は,機械相手の簡潔な発話だけでなく将来起こりうる多様な発話も収集することを目的とし,インタビューによるコーパス収集法を提案する.具体的には,カーナビをターゲットとして,質問者から回答者にカーナビに何と言うか質問し,回答を得る.回答者には,機械向けの発話収集であり,かつ機械は進化しているため発話の制限がないことを教示する.インタビューで得たコーパスと現製品の発話ログデータ(製品ログ)を比較したところ,コーパスが一発話あたり11.7%多く形態素を含み,多様な発話を収集できたことを確認した.また,現製品の言語理解用データとしての有用性を調べるため,コーパス,製品ログ,両者混合の3パターンで学習させた言語理解器を構築し,評価した結果,両者混合学習で最高精度となり,有用性を確認した.
3 0 0 0 OA 遺伝性痙性対麻痺の最新情報
- 著者
- 瀧山 嘉久
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.12, pp.1009-1011, 2014 (Released:2014-12-18)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 3
遺伝性痙性対麻痺(hereditary spastic paraplegia; HSP)は下肢の痙縮と筋力低下を呈する神経変性疾患群である.現時点でSPG1~72の遺伝子座と60を超す原因遺伝子が同定されているが,全国多施設共同研究体制であるJapan Spastic Paraplegia Research Consortium(JASPAC)により,本邦HSPの分子疫学が明らかになってきた.さらに,JASPACにより,はじめてC12orf65遺伝子変異やLYST遺伝子変異がHSPの表現型を呈することが判明した.今後,JASPACの活動がHSPの更なる新規原因遺伝子の同定,分子病態の解明,そして根本的治療法の開発へと繋がることが望まれる.
- 著者
- 伊達 聖伸
- 出版者
- 上智大学
- 雑誌
- 上智ヨーロッパ研究 (ISSN:18835635)
- 巻号頁・発行日
- no.5, 2013-02-28
3 0 0 0 IR エビス神の一側面 : 不具神伝承について (平山敏治郎教授退任記念)
- 著者
- 田中 宣一
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 日本常民文化紀要 (ISSN:02869071)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.169-184, 1984-12
3 0 0 0 恐山展 : みちのくの神秘 地獄と極楽
- 出版者
- 京都新聞社
- 巻号頁・発行日
- 1972
3 0 0 0 OA 『張州雑志』の著者、内藤東甫の足跡 - 『前野村前野氏系図 巻二』との整合性 -
- 著者
- 松浦 由起
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学校
- 雑誌
- 豊田工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02862603)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.18, 2017 (Released:2017-03-15)
3 0 0 0 IR 南極の地名
- 著者
- 原田 美道
- 出版者
- 国立極地研究所
- 雑誌
- 南極資料 (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.1768-1776, 1964-02
- 被引用文献数
- 1
Japanese geographic nomenclature in Antarctica was decided by Japanese Promotive Headquarters of Antarctic Research Expedition (J.P.H.A.R.E.) in 1961, based on the policy of United States Advisory Committee on Antarctic Names. Until 1963 total 98 place names were decided by Antarctic Names Committee of Japan, Ministry of Education, and authorized by J.P.H.A.R.E. Those names are classified by First class, Second class and Third class generally. The provisional gazetteer will be published in the near future, in which all official names and their descriptions are contained. Place name lists are shown in Appendices 1, 2 and 3, and new names are located in Figs. 1, 2 and 3 respectively. Exact geographical positions are shown in the topographic maps which are being compiled by Geographical Survey Institute.
3 0 0 0 OA 南極の地名
- 著者
- 原田 美道 Yoshimichi HARADA
- 雑誌
- 南極資料 (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.1768-1776, 1964-02
Japanese geographic nomenclature in Antarctica was decided by Japanese Promotive Headquarters of Antarctic Research Expedition (J.P.H.A.R.E.) in 1961, based on the policy of United States Advisory Committee on Antarctic Names. Until 1963 total 98 place names were decided by Antarctic Names Committee of Japan, Ministry of Education, and authorized by J.P.H.A.R.E. Those names are classified by First class, Second class and Third class generally. The provisional gazetteer will be published in the near future, in which all official names and their descriptions are contained. Place name lists are shown in Appendices 1, 2 and 3, and new names are located in Figs. 1, 2 and 3 respectively. Exact geographical positions are shown in the topographic maps which are being compiled by Geographical Survey Institute.
3 0 0 0 日本の神(神道の神)(鈴木達也教授退職記念号)
- 著者
- 柿山 隆
- 出版者
- 亜細亜大学
- 雑誌
- 亜細亜大学教養部紀要 (ISSN:03886603)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.132-112, 2000