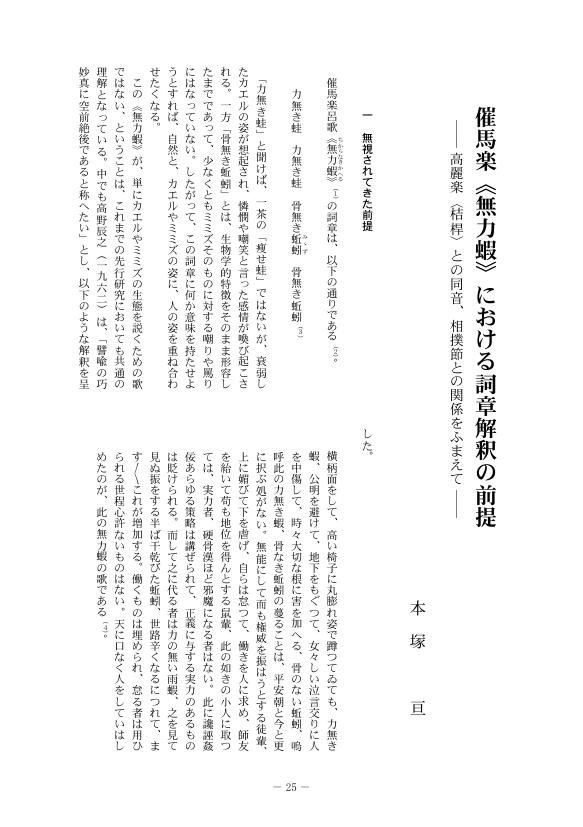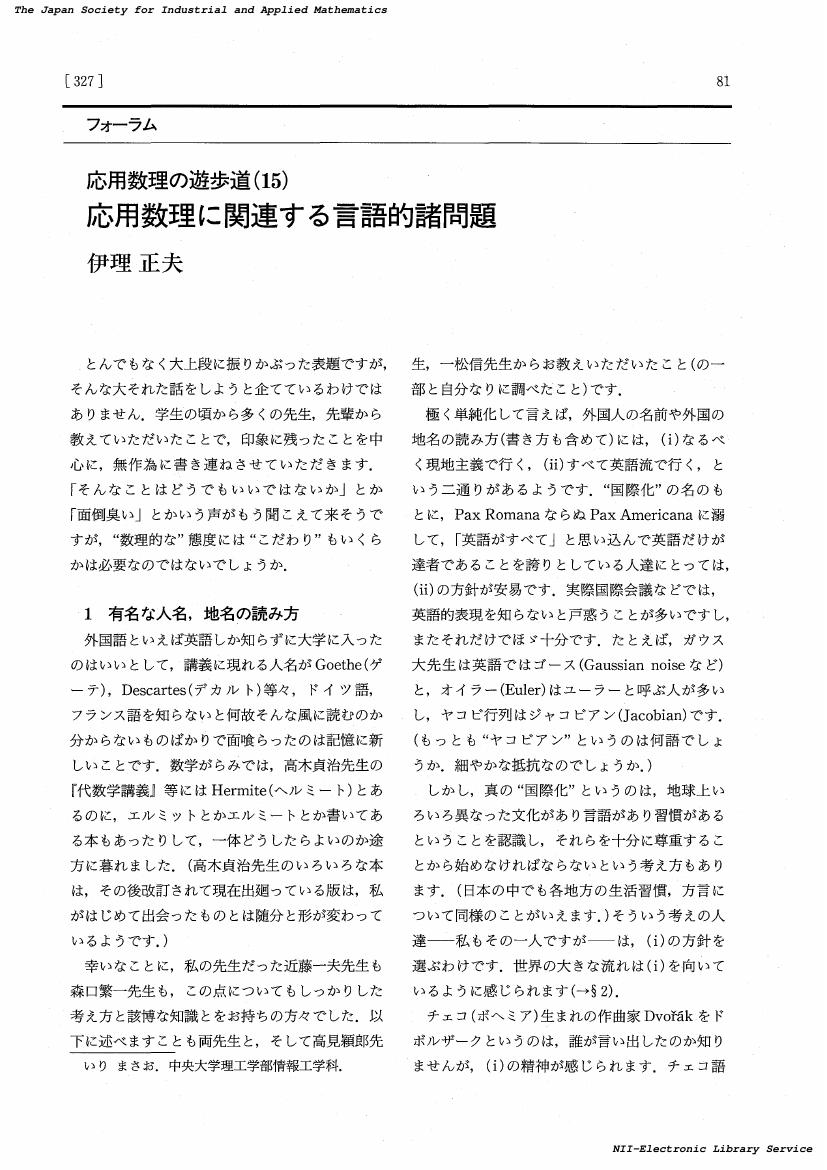2 0 0 0 OA 催馬楽《無力蝦》における詞章解釈の前提 高麗楽〈桔桿〉との同音、相撲節との関係をふまえて
- 著者
- 本塚 亘
- 出版者
- 日本歌謡学会
- 雑誌
- 日本歌謡研究 (ISSN:03873218)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.25-40, 2015-12-30 (Released:2020-08-05)
2 0 0 0 OA 保存条件の違いによるベルリン青染色試薬の染色性及び試薬凍結保存の有用性についての検討
- 著者
- 池亀 央嗣 高橋 加奈絵 川口 裕貴恵 横山 千明 諸橋 恵子 磯崎 勝 須貝 美佳 梅津 哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.117-123, 2019-01-25 (Released:2019-01-25)
- 参考文献数
- 4
3価鉄イオンを検出するベルリン青染色は,フェロシアン化カリウムに3価鉄イオンが結合しフェロシアン化鉄(ベルリン青)形成反応を利用した染色で,染色試薬の用時調製を要する。我々は,染色試薬の使用可能期間を明らかにするため,染色試薬の600 nmでの吸光度と染色性の変化を,保存条件を変え1年間まで経時的に検討した。保存条件は,室温,4℃,両者の遮光,及び−80℃(一部−20℃)凍結とした。吸光度は,凍結保存では一定値を保っていたが,それ以外では増加した。凍結保存では染色の色調,及び強度は1年後でも変化せず,共染色もなかった。それ以外では,青色から緑色調へと変化し,染色強度は減弱,共染色は増強した。凍結速度や凍結保存の温度は,染色性に影響しなかった。吸光度変化から,凍結保存以外の染色試薬では,経時的に液中に3価の第二鉄塩を生じ,フェロシアン化カリウムと反応して遊離フェロシアン化鉄を形成するため,組織中の鉄イオンと結合するフェロシアン化カリウムが減少して染色強度が低下すると考えられた。また,青色から緑色への色調変化は,ベルリン青色素の分子量が変化するためと考えられた。遮光保存の結果から,これらの反応に光が関与することが示唆された。染色試薬の凍結により反応が停止し吸光度と染色性の変化がみられなくなると考えられた。以上から,染色試薬を凍結保存することで,用時調製が不要となることが示された。
2 0 0 0 OA CWレーザー推進におけるエネルギー変換過程
- 著者
- 井上 孝祐 上原 進 小紫 公也 荒川 義博
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会論文集 (ISSN:13446460)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.627, pp.168-174, 2006 (Released:2006-05-19)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 4
An experimental study on the energy conversion process of a continuous wave (CW) laser thruster is presented. The effect of the flow parameters on two dominant loss mechanisms of a CW laser thruster was investigated by using a CW CO2 laser with output power of 700W. The laser transmission and radiation from the laser sustained-plasma (LSP) were measured for several flow velocities and pressures, which were independently controlled. CCD camera was employed in order to observe the shape and position of the LSPs. We found that the energy conversion process is optimized when the LSP is in the vicinity of the focal point of the condensing laser beam.
2 0 0 0 OA シリーズ〈地誌トピックス〉全3巻
- 著者
- 田林 明
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.191-193, 2019-05-01 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 OA 応用数理に関連する言語的諸問題(応用数理の遊歩道(15))
- 著者
- 伊理 正夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.327-336, 1998-12-15 (Released:2017-04-08)
2 0 0 0 OA カフェインが及ぼす睡眠への影響
- 著者
- 星野 未来 本村 美月 阿部 友杏 上野 古都
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第37回日本霊長類学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.54, 2021 (Released:2021-09-22)
高校生は夕食後,授業の復習や予習,課題など就寝前に活動する時間が長く,眠気を解消するためにカフェインを摂取する機会が多い。一般に,カフェインは眠気を抑制し,覚醒する作用があるため,摂取する時間によっては夜間の入眠に影響を及ぼすと言われている。本研究では,夜間の睡眠の質に影響を及ぼさないカフェイン摂取方法を検証することを目的とする。 実験は,平日5日間の夜間に設定し,カフェイン120mg を含む無糖ブラック缶コーヒーを1日目は8時間前,2日目は6時間前,3日目は4時間前,4日目は2時間前,5日目は就寝直前と摂取時間を変えて摂取する計画で行う。被験者は,実験期間中,睡眠日誌を記録し,23時から6時の7時間睡眠を確保する介入調査にする。夜間の睡眠の質として,覚醒回数と入眠後最初の徐波睡眠の長さに着目をし,Smart Sleepディープスリープヘッドバンド(Philips 社)を用いて測定し,専用アプリSleep Mapperで記録する。高校2年女子4人を被験者に実験を行った結果,覚醒回数とカフェイン摂取時間に関係があることが示された。8時間前,就寝直前では覚醒回数が2回未満であったが,2時間前,4時間前では3回以上記録され,特に,2時間前では覚醒回数が4回以上記録された。入眠後最初の徐波睡眠の長さは,4時間前,2時間前,就寝直前で短くなることが確認された。本研究の結果から,就寝直前のカフェイン摂取は覚醒回数への影響は少ないものの,深睡眠である徐波睡眠の長さに影響を与え,2時間前,4時間前のカフェイン摂取は覚醒回数及び徐波睡眠の長さに影響を与えると考えられる。夜間の睡眠の質に影響が少ない方法は就寝前4時間以上のカフェイン摂取が適すると考えられる。今後は,睡眠時間や就寝時間を設定する介入調査をせず,高校生の普段の生活リズムにおけるカフェイン摂取と睡眠の質の関係性を明らかにすることが展望である。
2 0 0 0 OA 訂正: 「デジタルアーカイブ学会誌. 2022, 6(2), p.99」の訂正
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.150, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
記事:内田朋子. 「デジタル改革」「デジタル政策」の未来を考える:フォーラム「図書館とデジタルメディア、融合の可能性」実施報告と参加感想. デジタルアーカイブ学会誌. 2022, 6(2), p.99 https://doi.org/10.24506/jsda.6.2_99以下の通り訂正します。p.99誤 共同通信社編集局の内田朋子(筆者)正 共同通信社編集局メディアセンター予定チーム委員の内田朋子(筆者)p.101誤 外務省の官僚たち正 財務省の官僚たち
2 0 0 0 OA デジタルアーカイブ学会誌 編集方針、投稿規程、査読規程
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.148-149, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
2 0 0 0 OA 学会規約
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.146-147, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
2 0 0 0 OA 活動報告
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.143-145, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
2 0 0 0 OA 第4部:ビヨンドブックのプロトタイプ制作
- 著者
- 野見山 真人 谷川 智洋
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.131-137, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
- 参考文献数
- 3
書籍やWebコンテンツの膨大なデータをもとにユーザの好奇心をサポートする知識体験プラットフォームBBのプロトタイプをUI/UX設計を重視して制作した。BBのUI/UX設計では、「知りたいことから体系的に学べる」「遊び感覚で好奇心を育める」「書籍とWebコンテンツを横断できる」という3つの知識体験を設計して、新しい知識体験の形態を模索した。BBのユーザは知りたいことをモバイルアプリで調べることで、書籍やWebコンテンツに裏付けされた知識を体系的に学びながら徐々に好奇心を育てることができる。このような知識体験のUI/UX設計は、デジタルアーカイブの利用形態全般に応用可能であり、デジタルアーカイブに含まれる知識コンテンツを楽しみながら系統的に学ぶことをサポートする。
2 0 0 0 OA 第2部:ビヨンドブックの機能要件と構成
- 著者
- 柳 与志夫 久永 一郎 前沢 克俊
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.123-126, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
- 参考文献数
- 2
ビヨンドブック(BB)の機能として、デジタル文化資源のもつオープン化・ネットワーク化・インタラクティブ性、マイクロコンテンツ化など5つの要件を可能な限り取り入れた。利用形態としては自分の専門外で仕事・趣味・生活上の有用な知識を得る手段となること、利用者としては新しい知的潮流に関心のある若いビジネスパーソンを想定した。BBの利用継続性を担保するための収益モデルの可能性についても検討した。これらの要因を満たすためのコンテンツとして講談社ブルーバックスシリーズの「お酒の科学」4冊をテキストデータ化した。最後にBBプロトタイプ制作のための制作フローを設定した。
2 0 0 0 OA 第1部:新しい本の可能性を考える―「ビヨンドブック」プロジェクトの試み
- 著者
- 柳 与志夫
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.120-122, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
- 参考文献数
- 10
書籍とインターネット情報源のメリットを最大限生かし、そのデメリットを最小化した、デジタル時代にふさわしい新しい知識構成体「ビヨンドブック(BB)」の開発に取り組んだ。そのために先ず過去の開発事例及びその問題点をレビューした。またそれを実施するための研究チームを、多様な分野からの人材で編成した。図書や資料が図書館やアーカイブの中核をなすように、デジタルアーカイブにとって、将来BBがコンテンツの中核を担うことが期待される。
2 0 0 0 OA 「Beyond Book(BB)」プロジェクトの概要
- 著者
- 渡邉 英徳
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.117-119, 2022-08-01 (Released:2022-10-05)
- 参考文献数
- 2
本特集では、デジタル環境の利点を活かして「電子書籍」を越えることを目指した「Beyond Book (BB)」プロジェクトについて解説する。1990年代から開発が開始されたeBookは「電子書籍」として普及しているとはいえ、デジタル化・ネットワーク化の利点を十分に活かすことができていない。そこで本プロジェクトでは、電子書籍の先にある新しい知識形態のプロダクトとして「BB」の開発を目指した。本特集は5部で構成される。第1〜4部においては、BBプロジェクトのコンセプト・要素技術について解説する。第5部では、BBプロジェクトの後継となる「新しい本」プロジェクトの方針と現状について述べる。
2 0 0 0 OA 異なる時間スケールでみた阿多溶結凝灰岩における遷急点の後退速度
- 著者
- 高波 紳太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.175-190, 2019-05-01 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 54
薩摩半島の川辺盆地周辺において,基盤地形に応じて階段状に堆積した阿多溶結凝灰岩に発達する遷急点群の平均後退速度を明らかにした.特に永里川における後退期間の大きく異なる2遷急点での結果から,最終氷期中の降水量減少が岩盤侵食速度を低下させたかどうかを考察した.現地露頭調査や掘削資料に基づく阿多火砕流堆積時の原地形の復元により,遷急点形成当初の位置を推定し,その現在までの後退距離および長期的な平均後退速度を求めた.短期的な後退速度の算出には人工の曲流短絡で生じた遷急点を用いた.結果,遷急点の平均後退速度は11万年間で2.0~2.6 cm/年,最近315年間では0.8~2.0cm/年と推定され,氷期を含む長期的な速度が温暖期に限られた短期的な速度をやや上回った.過去11万年間の薩摩半島では,気候変動に伴う河川流量,すなわち降水量の減少による岩盤侵食速度の極端な低下はなかったことが,地形学的に強く示唆された.
2 0 0 0 IR 日本語教育文法における「部分否定表現」の研究
2 0 0 0 OA 市民参画ジャーナリズムの国際連帯 : オーマイニュースと韓国民主化・記者クラブ解体
- 著者
- 浅野 健一 李 其珍 森 類臣 Kenichi Asano Kijin Lee Tomoomi Mori
- 出版者
- 同志社大学人文学会
- 雑誌
- 評論・社会科学 = Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) (ISSN:02862840)
- 巻号頁・発行日
- no.74, pp.1-108, 2004-12-20
"OhmyNews" is an independent Internet newspaper in the Republic of Korea, and as such it wields great influence now. It is reportedly the largest Internet newspaper in the world. Five years ago, OhmyNews was published by four professional reporters and 727 "citizen reporters." The number of OhmyNews citizen reporters has grown to more than 35,000 today. Mr. Oh Yeon-Ho, founder and chief representative of OhmyNews, gave a lecture at Doshisha University on 15 September 2004. We could hold a subject of inquiry on alternative media from Mr. Oh's lecture and could interview him. We found that, in fact, the success of OhmyNews is a remarkable accident in the world of journalism. So much so that many big media outlets in the world, such as the New York Times, Washington Post, CNN and BBC have covered Mr. Oh's experimental challenge and his success with OhmyNews. We consider one of the big achievements of OhmyNews to be the abolition of the closed system of press clubs in Korea known (in Japanese) as Kisha Clubs. We thus refer to Internet newspapers in the Republic of Korea (especially OhmyNews) and Kisha Clubs in this article. As to why "OhmyNews" succeeded, we can point to several reasons. The most important reason, however, is the existence of the "prepared citizen" in the Republic of Korea. In the Republic of Korea, through a long fight for democratization, people have come to not believe in the traditional corporate media. The corporate media is identified in the public mind as standing by the "powers that be" and not reporting the truth. Consequently, people in Korea have held high expectations for the appearance of alternative news media. Many people harbor a strong will to change their society, and they can do so by supporting OhmyNews and participating in it as "citizen reporters." OhmyNews operates on the basis of several important concepts, the most important being : "Every citizen is a reporter." Mr. Oh explained that "This concept is the most characteristic" of OhmyNews. The traditional corporate media represents journalism of the 20th century. It is a one-way stream in which professional reporters write articles and the reader only reads it. But OhmyNews is breaking that cycle of 20th century journalism. OhmyNews has made journalism a two-way stream in which the reporter is reader, and the reader is reporter. The system of Kisha Clubs is a unique system in Japan and the Republic of Korea. It is an exclusive and conservative system which excludes non-member reporters. Mr. Oh of OhmyNews had successfully sued for abolition of the Kisha Clubs in Korea, and following that, President Roh Moo-Hyon abolished the Kisha Clubs of the country's central administrative offices. This dismantling of Kisha Clubs is rapidly advancing in the Republic of Korea. Yet in Japan it is not advancing at all, rightly inviting criticism of Japan's press system. But that does not appear to faze Japanese reporters of the corporate media and some Japanese scholars, who insist that Kisha Clubs are the most proper system for Japan. By contrast, abolishing the Kisha Clubs in Korea is the result of strenuous efforts by alternative media such as OhmyNews and a large number of supporters. All of which begs the questions : What benefits do we receive from the Japanese press club system? And what needs to be done to eliminate this outdated, injurious system? We dare to envision the kind of journalism in which people take part -as with OhmyNews- and at the same time, we aim to solve the many problems of journalism in Japan, above all permanently dissolving the Kisha Club system.
2 0 0 0 OA インド・デリーのインフォーマル工業部門における産業集積の存立構造
- 著者
- 宇根 義己 友澤 和夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.153-174, 2019-05-01 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 3
インド・デリー首都圏のムスリム居住地ジャミア・ナガルに展開する繊維・縫製産業を事例に,都市インフォーマル部門における産業集積の存立構造を明らかにした.調査対象の作業場における現場労働者,経営者は主に低所得州の農村地域出身であり,当該地域における地縁・血縁関係を基盤にして人材が当地へ供給されている.作業場は卸売・輸出業者との近接性を活かした高い接触頻度により,賃加工型の受注を獲得している.また,デリーの卸売・輸出業者によるサプライチェーンの一端を担うことが当集積の存立をもたらしている.現場労働者の生活環境は良好とはいえないが,出来高制を基本とした長時間労働のため,フォーマル部門の労働者の最低賃金以上の収入を得る者もある.また,現場労働者から作業場の経営者となる経路が確認された.現場労働者による起業を可能としているのは,多額の投資を必要としないことや労働力の確保が容易な点などであった.