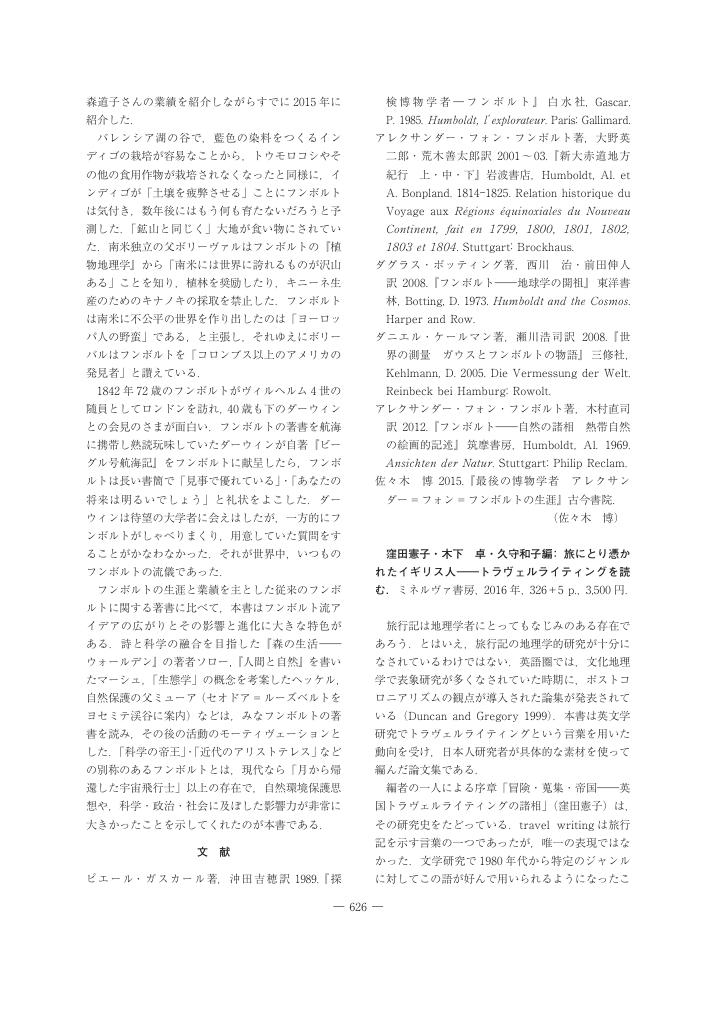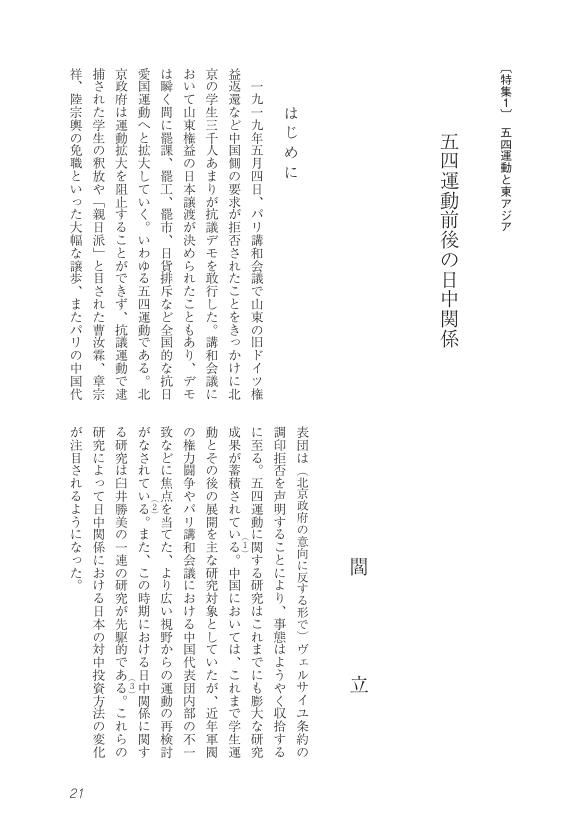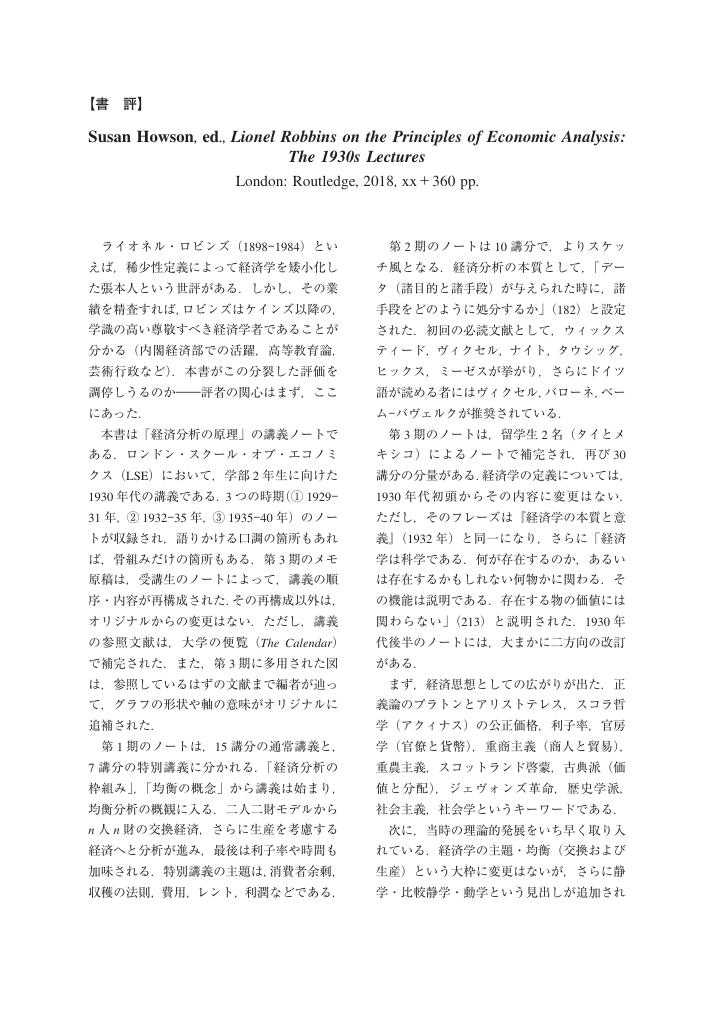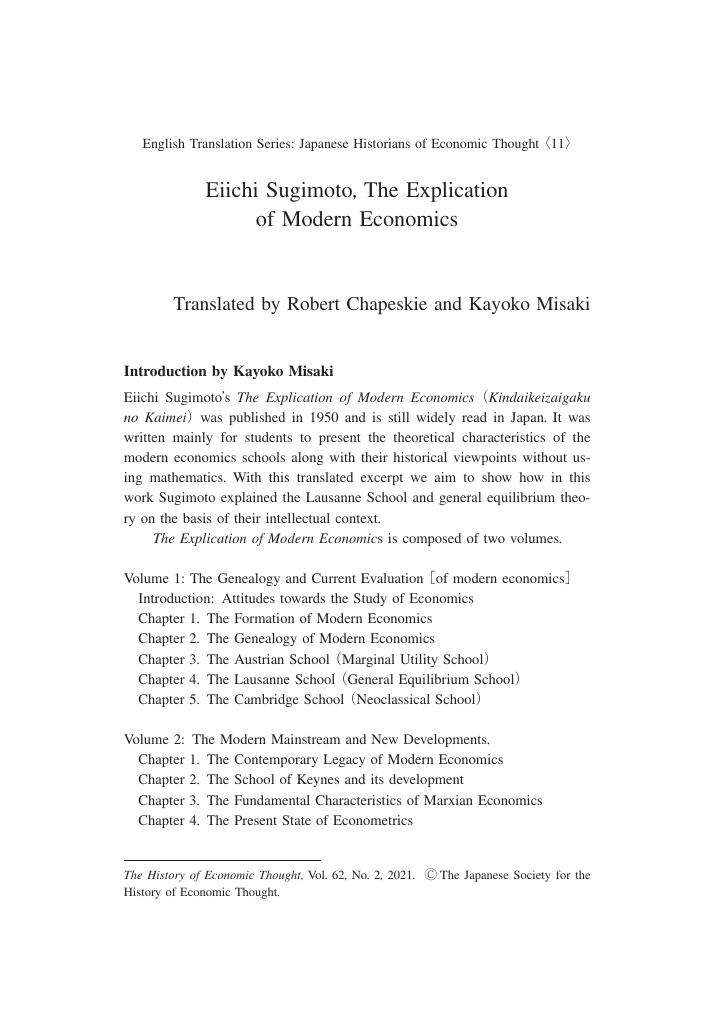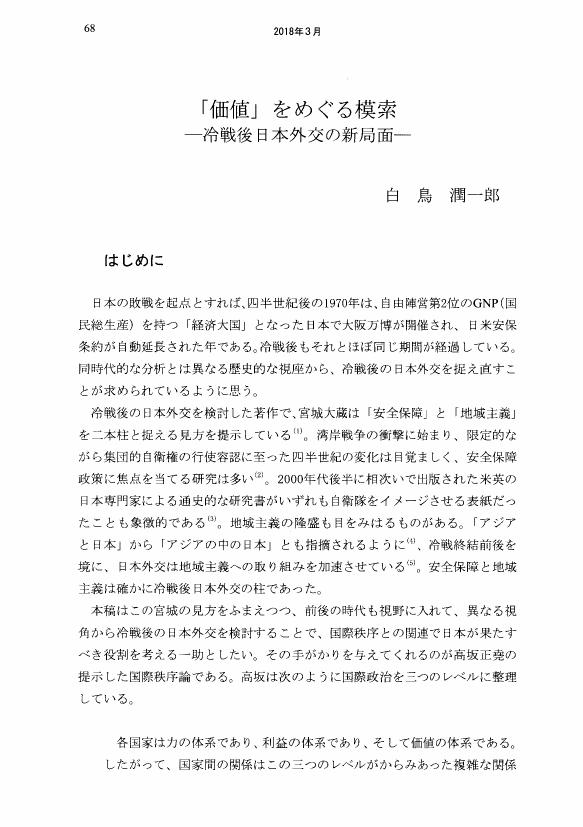- 著者
- EL-BARBARY Mohamed N. IKEDA Mariko UEKITA Yasufumi
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.2, pp.65-80, 2021-12-25 (Released:2021-12-25)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1
Historic Cairo, in Egypt, is a living urban entity that was registered by the UNESCO as a World Cultural Heritage Site in 1979. Its historic urban core is crowded with outstanding medieval buildings which overlap with the city’s modern architecture and local people’s daily life activities. Unfortunately, despite receiving several conservation interventions, since the mid-20th century, most of the historic buildings in Cairo are in constant deterioration. Therefore, the study aimed at identifying the reasons behind this controversial situation, based on theoretical and practical methodologies. Through critical review of related literature and field survey, the study identified the shortcomings in the main conservation practices, implemented in Historic Cairo after the mid-20th century, and the current challenges for its effective conservation. The research findings clarified that no significant conservation effort was made in Historic Cairo during the 1950s and 1960s. While, since the early 1970s, about 17 mega conservation projects have been conducted, by national and international organizations, most of these projects adopted inappropriate conservation approaches which ignored the living nature of Historic Cairo and undermined the active participation and needs of the local community. The ‘top-down’ strategy prevailed in most conservation projects, in which the historic buildings were either ‘restored then closed’ without adaptive reuse or conserved for ‘touristic’ purposes without monitoring after conservation. Finally, the study concluded that the ‘local community’ oriented approach is the most appropriate for the effective conservation of Historic Cairo.
- 著者
- YOSHIDA Kunimitsu
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.1, pp.31-47, 2021-07-31 (Released:2021-08-03)
- 参考文献数
- 51
This paper aims to explain the mechanism of the transfer of farming rights in Japan’s large-scale upland farming belt by focusing on the social relationships among farmers. The mechanisms of farmers’ social relationships were analyzed by applying the concept of “multiplex-uniplex” that is used in the social network approach. The study area was Omaki and Kowa settlements in central Hokkaido Prefecture. This area was newly cleared and opened for settlement in 1950. The major agricultural enterprises in this area are upland, dairy, and vegetable farming. The main findings are as follows. 1) Various social relationships among farmers were observed behind the transfer of farming rights, including territorial relations, kinship and school connections. Some official agencies were also involved in these relationships. 2) The types of social relationships varied in the way the transfer of farming rights overlapped. Almost all transfers were influenced by multiplex relationships, such as a combination of territorial relations, kinship, and school connections. On the other hand, uniplex relationships existed in the transfer of farming rights when farmers did not have these social relationships. 3) Social relationships in the transfer of farming rights expanded spatially from the scale of the neighborhood or settlement to the scale of the home district, other districts, and outside of town. Many farmers accumulated most of their farmland within their settlements, but depending on farm management conditions, some late accumulated farmland was located outside their settlements.
- 著者
- 岩嵜 博論
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第69回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.148, 2022 (Released:2022-08-30)
行政課題の複雑化や行政サービスのデジタル化に伴って行政組織においてデザイン方法論の活用が進展している。本研究は,日本の行政組織におけるデザイン方法論の実践として,ペルソナがどのように作成され,どのように政策に反映されたかを明らかにすることを目的とする。本研究では,滋賀県庁において2020年度に行われた「ポストコロナにおける滋賀県の姿を考える」ワーキンググループ(WG)で作成されたペルソナとその成果を活用した政策立案の過程を対象に事例研究を行った。事例分析を通じて,行政組織におけるペルソナ活用のメリットとして,1)住民への共感醸成,2)組織内コミュニケーション,3)未来視点での政策立案の3点が挙げられることがわかった。
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.6, pp.626-629, 2017-11-01 (Released:2022-03-02)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 OA 山下清海: 新・中華街――世界各地で「華人社会」は変貌する――
- 著者
- 杜 国慶
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.1, pp.56-58, 2017 (Released:2022-03-02)
2 0 0 0 OA 長崎県における医療情報システムの普及過程
- 著者
- 中村 努
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.2, pp.67-85, 2017-03-01 (Released:2022-03-02)
- 参考文献数
- 32
本稿は,医療供給主体間の関係から長崎県における医療情報システムの普及過程を明らかにした.大村市で構築されたシステムは,参加施設数の増加ペースをあげながら県全域に普及した.県内スケールでみると,普及促進機関による協調行動が,異なる利害をもつ主体による共通のシステムの運用を可能にした.また,普及促進機関による職能団体との協調およびコスト負担の軽減を通じて,市町の領域を超えてシステムが普及した.市町内スケールでみると,長崎市や大村市では,地域医師会や地域薬剤師会における信頼関係が,診療所や薬局のシステムの普及に重要な役割を果たしていた.システムの普及は単なる技術的な問題ではなく,地域間で異なる職能団体の特性に依存することが明らかになった.本稿の結果は,情報通信技術が社会インフラとして機能するため,その普及や効果に地域差が生じる要因をさまざまな空間スケールから解明することの必要性を示唆している.
2 0 0 0 OA 秦漢時代の人的結合と国家 『嶽麓書院藏秦簡』を手掛かりに
- 著者
- 椎名 一雄
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.8, pp.1-36, 2021 (Released:2022-08-20)
秦漢時代を対象とする歴史研究において、郷里社会における人的結合を究明することは、当該時代の特質を描きだすとともに秦漢国家形成論にもつながる重要な課題である。従来の主な議論では、任侠や爵制あるいは血縁や地縁が着目されてきた。本稿では、諸研究の成果を踏まえ、出土文献や編纂史料を分析し、犯罪者およびその犯罪者を救わんとする者の関係を構築する原理を明らかにして、秦の統一国家形成と関連づけた議論を行う。 第一章では、『睡虎地秦墓竹簡』『嶽麓書院藏秦簡』『二年律令』に抄録される法律条文から、犯罪者およびその犯罪者を救わんとする者の関係を確認し、親属と「所知」二つの人的関係を指摘する。また、犯罪者およびその親属と「所知」には強い人的結合が存在したことも確認する。 第二章では、国家が法律条文において、危機に瀕した者を救済する資格を、その親属と「所知」のみに認めていたことを指摘する。その上で、『嶽麓』で親属と「所知」を並記する構造が、『墨子』にもみえることを確認する。 第三章では、墨家の影響を受ける『呂氏春秋』や任侠を称賛する司馬父子による『史記』から、命を賭して報恩に至る人的結合に、「知」が不可欠な要素と認識されていたことを確認する。その上で『嶽麓』には、秦墨や任侠的風潮の色濃い地域への秦の進出が影響していたことを指摘する。 第四章では、秦の法律文書には、「知」にもとづく関係を国家の支配に利用する施策が内包されていたことを確認する。また、その「知縁」とも呼ぶべき人々と親属で構成される小型の集団を、国家が社会の基盤として認識していたことを指摘する。 秦の東方や南方地域の郷里社会には、親属と任侠的習俗にもとづいた「知縁」で構成される小型の集団が存在した。秦はその小型の集団を維持・再生産する施策を通し支配の正当性を獲得し、その構成員や郷里社会の維持や再生産にまで及ぶ支配構造を構築していたことを論じる。
2 0 0 0 OA 明治中・後期の皇室財政 制度と実態
- 著者
- 加藤 祐介
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.4, pp.64-92, 2021 (Released:2022-04-20)
本稿は、明治中・後期(1888~1912年)における皇室財政の制度と実態について、基礎的な検討を行うものである。 1888~1893年度においては緊縮財政路線がとられた。一方、この時期の宮内省内蔵頭の杉孫七郎は、平常の財政運営に関しても伊藤博文の指導力に依存する傾向があり、また主に元老によって構成される皇室経済会議が皇室財政を監督する体制を支持していた。 1894年度以降、皇室財政は次第に膨張へと転じていく。そうした中で内蔵頭の渡辺千秋は、御料地経営の収益を組み込んだ統一的な財政制度の確立や、借入金の完済などを提起した。また渡辺は、杉内蔵頭の時代とは異なり、平常の財政運営に関しては、宮内省は自ら問題を処理する能力=専門性を備えつつあると認識していた。 1903年以降、帝室制度調査局において皇室法の検討が活発化していった。同局および宮内省内での検討を経て、1910年に皇室財産令が、1912年に皇室会計令が制定・公布された。皇室財産令によって、皇室経済会議は宮相の「諮詢機関」である帝室経済会議へと縮小再編され、宮内省の専門分化が進展した。また皇室会計令によって、御料地経営の収益を組み込んだ統一的な財政制度が確立した。 一方で、田中光顕(宮相)・渡辺体制下の宮内省は、財政基盤強化のためのアドホックな資金獲得に走るところがあった。日清戦争賠償金の皇室財政への編入(1898年)や国庫支出の皇室費の増額(1910年)はその典型である。宮内省は、前者によって借入金の完済に成功し、後者によって日露戦後の財政逼迫に対処したが、こうした対応は議会(国民)との間に一定の緊張を生じさせた。こうした明治中・後期における宮内省の対応のあり方は、議会(国民)との間の緊張を回避するという志向が明確に見られた1920年代のそれとは、大きく異なっている。
2 0 0 0 OA 暴力の歴史の描写を目指して 中近世ドイツ犯罪史研究における動向から
- 著者
- 齋藤 敬之
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.2, pp.37-57, 2021 (Released:2022-02-20)
1990年代初頭からドイツ歴史学の中で活況を見せる歴史犯罪研究は、中近世における傷害や殺人などの暴力をはじめとする犯罪の社会史を論じている。その系譜は、ドイツ社会史研究の盛り上がりや、人類学にも接近した「新しい文化史」の台頭といった、1970年代以降の歴史学の趨勢に位置づけられる。G・シュヴェアホフやM・ディンゲス、J・アイバッハといった研究者は、犯罪社会学の概念やP・ブルデューの名誉や男性性に関する見方を積極的に摂取することで、N・エリアスの文明化論でしばしばネガティヴに描写されてきた前近代の暴力を文化史的に捉え直した。すなわち、とくに男性間での名誉をめぐる揉め事に、中傷や挑発の言動に端を発して最終的に身体的な実力行使に至るというエスカレートの規則性や儀礼化を見出すことで、感情や攻撃欲の無制限の発露、非文明的な行為としての暴力像を退けた。こうした理解はその後の研究に受け継がれつつも、P・シュスターやP・ヴェットマン=ユングブルートらは暴力と名誉の関係をより緩やかに捉えており、さらに近世の決闘の諸相を検討したU・ルートヴィヒや19-20世紀ベルンにおける暴力犯罪を分析したM・コティエーは男性の名誉と結びついた暴力を一種のゲーム、つまり自己目的化したコミュニケーション形態と理解することで、暴力の感情的次元を改めて視野に収めている。 本稿での整理から導かれる今後の課題として、18世紀フランクフルトの犯罪を分析したアイバッハの研究を決闘研究や感情史研究と接続させ、19世紀まで射程に入れて暴力の形態や行動様式、認識の変化をたどるとともに、名誉を守る必要性と暴力による負傷や命の危険との間に葛藤を抱いていたのかといった点を問うことが有意義である。このような暴力の社会的位置づけの検討を通じて、「端境期(ザッテルツァイト)」と呼ばれる18世紀から19世紀の時代的特質の解明にも貢献できると思われる。
- 著者
- 安酸 香織
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.11, pp.1-33, 2020 (Released:2021-11-20)
近世ヨーロッパ史研究では、ここ半世紀のあいだに近代化論から離れ、近世国家の特質をめぐる議論を展開してきた。この傾向は、近世アルザス史研究にも、フランス絶対王政の新たな理解に基づく再考を促した。しかし、一七世紀のアルザス譲渡以降についてフランスとの関係にのみ注目し、神聖ローマ帝国とのつながりを度外視するならば、同地域の秩序を根本的に理解することはできない。近年では両関係が考慮されつつあるが、いまだ事例研究の数は少なく、まして体系的な研究には至っていない。それゆえ本稿では、アルザス最大勢力であるシュトラースブルク司教の訴訟を事例とし、帝国、王国、アルザスの諸権力を視野に入れて同地域の秩序を描き出すことを試みた。 具体的には、第一章にて近世アルザス史を概観し、第二章にて前述の訴訟を分析し、第三章にてアルザス周辺の紛争と解決における特質を浮かび上がらせた。特質として、以下三点を指摘できる。第一に、アルザス地域諸権力は、フランス王が創設したアルザス最高評定院を、紛争解決の唯一の手段ではなく、選択肢の一つとみなしていた。第二に、彼らは神聖ローマ皇帝とフランス王の双方の封臣として、多様な紛争解決手段を利用できた。しかし第三に、手段の複数性は、裁判所間、さらには皇帝とフランス王のより大きな紛争を引き起こす危険性を孕んでいた。彼らがこの危険を避け、当事者間の示談を試みたことは、多様な選択肢の一時的な放棄を意味したが、しかし結果として彼らの自立性を高めることにもなった。 本稿では、フランスの主権確立や州の統一という従来のアルザス史像とは対照的に、また新旧制度の併存という近年の理解を発展させて、地域的・国家的枠組みを越えた柔軟な紛争解決に基づくアルザスの秩序を明らかにした。この成果は、近世ヨーロッパの政治秩序を、国家間の勢力関係や近世国家論とは異なるかたちで描き出す可能性を秘めている。
2 0 0 0 OA 消費論からみた中世菅浦
- 著者
- 橋本 道範
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.6, pp.32-48, 2020 (Released:2021-09-09)
本稿は、環境史的視野をもった消費論、環境史的消費論を構築するために、中世の近江国菅浦における産物の消費実態の考察から、生業の構造とその変化を解明したものである。 網野善彦が「湖の民」と述べたように、菅浦については内水面を対象とした二つの生業、漁撈と水運に従事したムラというイメージが流布している。しかし、まず近世菅浦研究がそのイメージを一新し、中世菅浦研究もそれに続こうとしている。それは、アブラギリ生産など、「集落とその背後などの陽当たりのよい傾斜地」を対象とした生業の重要性を提起したものと総括できる。 建武二年(一三三五)に進上を誓約したとされる供御、コイ、ムギ、ビワ、ダイズのうち、コイが長禄元年(一四五八)には代銭納化されていたのに対し、ビワは禁裏に献上され、都市領主社会内部でも分配されていた。十五世紀の王権と都市領主にとっては、菅浦はビワの名産地という位置づけであった。 一方、琵琶湖地域内での贈答をみると、菅浦産コイの贈答も確認できるものの、もっぱら菅浦から贈答されるのはビワとコウジであった。いずれも「集落とその背後などの陽当たりのよい傾斜地」の産物である。ここで注目したいのは、反対に菅浦へと贈答されるもののなかに、琵琶湖産淡水魚のフナ・ウグイ・アユがみえることで、もし菅浦の主たる生業が漁撈であれば贈答されるとは考えにくい。地域内の消費実態からも中世菅浦の生業の重心が、内水面ではなく、「集落とその背後などの陽当たりのよい傾斜地」に置かれていた可能性は高い。 中世菅浦は、多様な生業を複合的に組み合わせて生存していたが、消費論はこうした複合する生業を羅列的に明らかにするだけでなく、それらの首都や地域における価値づけなど、階層的構造とその変化を解明する可能性を秘めている。その上で、この構造と自然条件との関係が解明できれば、地域環境史にも貢献できると考える。
2 0 0 0 OA 古代中世の葬送と女性 参列参会を中心として
- 著者
- 島津 毅
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.1-36, 2020 (Released:2021-09-02)
古代中世の葬送において女性がどう関わっていたのか。これまで葬送史研究、および女性史研究でも検討されたことはなく、両者の歴史的な関係を解明する必要性があった。 そこで本稿は、八世紀から十六世紀までの葬送事例を通して、女性における葬送への参列参会の実態と歴史的な変化を検討し、その背景を葬送の性格と女性の位置という二側面から考察した。 まず十三世紀半ばまででは、次のようなことを指摘した。一に、葬送が凶事とされたため、身体を保護する必要性から幼女や妊婦は葬送の参列もできなかった。二に、女官・女房や女性親族は、故人を愛しみ遺体に触れることも可能であった。しかし、九世紀中頃から女性が公的な社会から疎外されていくなか、女性親族が会的側面をもつ葬送への参列や葬所への参会が行われなくなる。一方女官・女房は、公的立場をもった女性として、職務の一環から参列参会していた。三に、皇后・中宮はさらにその身位がもつ制約から、夫であった天皇や上皇の葬送にも参列参会できなかった。 そして、十三世紀後半以降では次のようなことを指摘した。十二世紀以降、父祖経歴の官職を嫡系が継承していく中世的な「家」の成立により、女性の位置関係にも変化が現れた。一方、禅律系寺院が境内に荼毘所・墓地を構えたことから葬所が「結縁の場」となる。こうして十三世紀後半を期に、公家・武家などの葬送では寺院で葬送が完結して葬列がなくなり、女性親族が葬所へ参会し始めるようになる。ところが十四世紀以降、后も立てられず、女房が妻妾として天皇に仕え、娘の皇女は尼となっていた。天皇家のこうした特異な状況によって、葬列が組まれ続け、平安時代以来の形態を残す天皇・上皇の葬送にも、妻妾が参列して娘とともに荼毘に参会するようになっていた。 以上のように古代中世の女性と葬送の位置関係には、九世紀半ばと十三世紀半ばの二度の画期があったことを解明した。
2 0 0 0 OA 五四運動前後の日中関係
- 著者
- 閻 立
- 出版者
- 大阪経済大学日本経済史研究所
- 雑誌
- 経済史研究 (ISSN:1344803X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.21-48, 2021-01-31 (Released:2021-03-15)
- 著者
- Robert Chapeskie Shin Kubo Naoki Mastuyama
- 出版者
- The Japanease Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.23-58, 2021 (Released:2022-01-13)
2 0 0 0 OA 板倉孝信『ポスト財政=軍事国家としての近代英国』 晃洋書房,2020 年
- 著者
- 大倉 正雄
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.66-67, 2021 (Released:2022-01-09)
- 著者
- 小峯 敦
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.64-65, 2021 (Released:2022-01-09)
- 著者
- Kayoko Misaki
- 出版者
- The Japanease Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.26-66, 2020 (Released:2021-12-02)
2 0 0 0 OA 「価値」をめぐる模索 ―冷戦後日本外交の新局面―
- 著者
- 白鳥 潤一郎
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.68-85, 2018-03-31 (Released:2022-04-01)
- 著者
- 篠田 英朗
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.110-114, 2017-03-31 (Released:2022-04-01)
2 0 0 0 OA カルギル紛争における「核の作用」に関する考察
- 著者
- 斎藤 剛
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.89-107, 2016-12-31 (Released:2022-04-01)