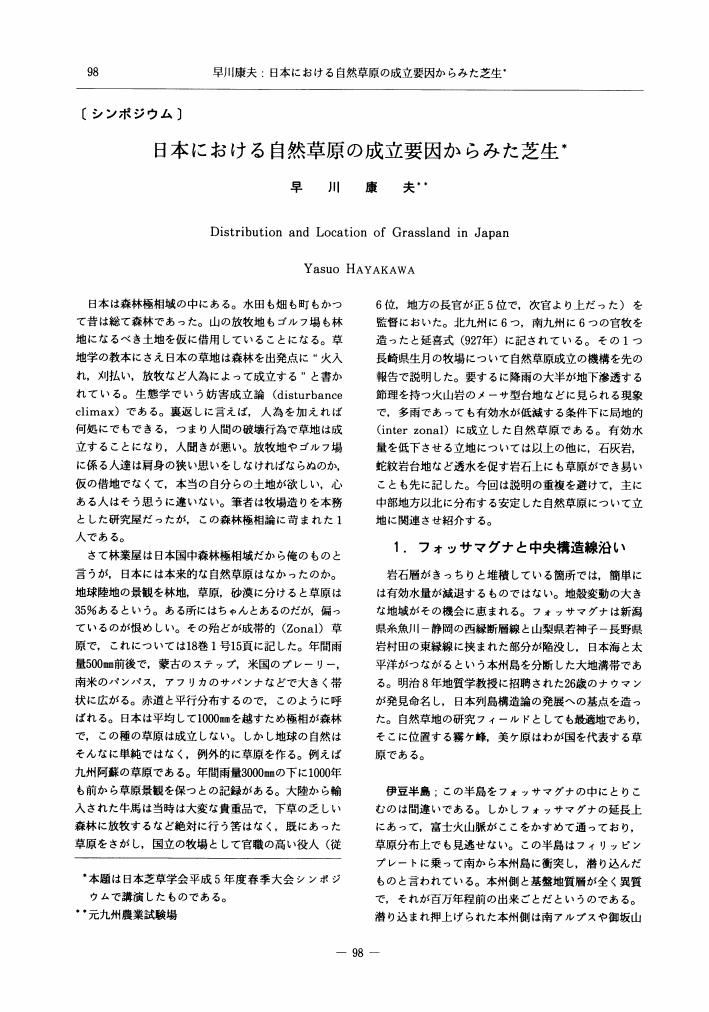- 著者
- Fumiaki Mori Tomoya Nishimura Taisuke Wakamatsu Takeshi Terada Yuki Morono
- 出版者
- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles
- 雑誌
- Microbes and Environments (ISSN:13426311)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.ME21031, 2021 (Released:2021-08-24)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3
Microbial cell counting provides essential information for the study of cell abundance profiles and biogeochemical interactions with the surrounding environments. However, it often requires labor-intensive and time-consuming processes, particularly for subseafloor sediment samples, in which non-cell particles are abundant. We developed a rapid and straightforward method for staining microbial intracellular DNA by SYBR Green I (SYBR-I) to enumerate cells by flow cytometry (FCM). We initially examined the efficiency of microbial cell staining at various dye/sediment ratios (volume ratio of SYBR-I/sediment [vSYBR/vSed]). Non-cell particles in sediment strongly and preferentially adsorbed SYBR-I dye, resulting in the unsuccessful staining of microbial cells when an insufficient ratio (<1.63 vSYBR/vSed) of SYBR-I dye was present per volume of sediment. SYBR-I dye at an abundance of 10 vSYBR/vSed successfully and stably stained microbial cells in green fluorescence, while the fluorescent color of non-cell particles red-shifted to yellow-orange with the overaccumulation of SYBR-I dye. A low vSYBR/vSed ratio was quickly recognized by a colorless supernatant after centrifugation. At the appropriate vSYBR/vSed ratio, FCM-measured cell concentrations in subseafloor sediments were consistently similar to microscopy counts (>106 cells cm–3). Samples with low cell abundance (<105 cells cm–3) still require cell separation. This modified staining allows us to efficiently process and perform the microbial cell counting of sediment samples to a depth of a few hundred meters below the seafloor with a higher throughput and capability to scale up than procedures employing microscopy-based observations.
2 0 0 0 OA 佐野鉄道の成立と展開
- 著者
- 中川 浩一 吉田 真理子
- 出版者
- 茨城大学教育学部
- 雑誌
- 茨城大学教育学部紀要 (人文・社会科学・芸術) = Bulletin of the Faculty of Education Ibaraki University (Humanities and Social Sciences) (ISSN:0386765X)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.53-64, 1993-03
2 0 0 0 OA 日本語母語話者が用いるあいづち表現―違いと用法について―
- 著者
- 吉澤 佳奈
- 出版者
- 日本女子大学国語国文学会
- 雑誌
- 国文目白 (ISSN:03898644)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.1-25, 2019-02-28
2 0 0 0 バタフライナイフを持った子供の前で文学は有効か(子午線)
- 著者
- 丹藤 博文
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.62-63, 1999
2 0 0 0 OA 当教室で経験した強酸による化学熱傷:産業医学的側面よりの検討
- 著者
- 織茂 弘志 山元 修 小林 美和 安田 浩
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.69-75, 2001-03-01 (Released:2017-04-11)
- 被引用文献数
- 2 2
平成12年6月, 当教室では強酸による化学熱傷を2例経験した. 症例1は44歳の男性. 化学工場勤務中, 防護マスクをしていたにもかかわらず, その隙間より硝酸が侵入し, 顔面に化学熱傷を受傷した. また, 作業衣を通して右上腕から肩甲部および両下腿から大腿前面にも被酸した. 症例2は26歳の男性. 化学工場勤務中, 濃硫酸を両前腕部に浴び, Ⅱ度の化学熱傷を受傷した. いずれの例も酸をホースにより充填している作業中に, 不慮の事故で酸に曝露している. 両者ともマニュアルどおり15分以上の洗浄をし, 重大な機能障害を残すことなく軽快したが, 一部深達性の損傷部位も認めた. さらなる安全対策のために, 産業医学的側面より検討を行った. 今回の曝露事故を教訓として, 作業に関して次の3つの改善点をあげた. 1)作業中の油断, 特にベテランに多い慣れに伴う強酸の危険性の軽視に対しては, 再教育あるいは啓蒙活動が必要である. 2)主な受傷部位以外にも, 被酸部位の見逃しの可能性があることに対しては, 保護衣を脱ぎ, 全身シャワーを浴びることを勧めた. 3)保護マスクをしていたにもかかわらず曝露したことに対しては, 保護マスクの改良を提案した. また, 強酸曝露時の黄色痂皮を診たときは, 過小評価することなく, 深達性潰瘍の存在を念頭におくべきであることを反省した. 事故防止のため, より質の高い安全対策が望まれる.
- 著者
- 鈴木 健司
- 出版者
- 文教大学国語研究室, 文教大学日本語日本文学科研究室, 文教大学国文学会
- 雑誌
- 文教大学国文 (ISSN:03858782)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.1-10, 2020-03
2 0 0 0 OA ヲ格とニ格の使用から見る心理動詞の語彙的特徴 : 心理動詞述語文を文を中心に
- 著者
- 趙 仲
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 言語と文化 = Language and Culture (ISSN:09147977)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.70-91, 2015-03-01
关于日语心理动词的格助词使用问题,我们知道 : “o(を)”提示对象内容,“ni(に)”提示对象或者原因。先前的研究大多止步于此,没有系统地做下去。因心理活动的格助词使用情况与其在句子中的功能和位置有关,本研究将讨论对象圈定为心理动词在陈述句中作谓语的情况。通过例句分析,本文将影响心理动词的格助词使用的因素分为句子结构和语意影响两种情况。前者指受“o(を)+表示作用接收方的ni(に)”这一句子结构制约的心理动词;后者指不受这一结构制约,单独使用“o(を)”,或单独使用“ni(に)”的心理动词。本文以后者,即格助词使用受单纯语意制约的心理动词为中心,将这类心理动词的格助词使用情况分为了“o(を)”,“o(を)”或“ni(に)”和“ni(に)”三种情况,并通过调查得出三种格助词使用情况不是互相孤立的,而是具有连续性的。具体表现为,使用格助词“o(を)”的心理动词中有一部分词的格功能开始向“ni(に)”转变,使用格助词“ni(に)”的心理动词中有一部分词的格功能开始向“o(を)”转变。由此,将格助词使用受语意制约的心理动词分成了既互相区别又相互联系的五类。此外,本文具体讨论了这种制约心理动词格助词使用的语意特征具体体现为主体性。即按照主体性由强到弱的顺序,心理动词的格助词使用情况依次为:“o(を)”、开始向“ni”发生功能转变的“o(を)”、既可用“o(を)”也可用“ni(に)”、开始向“o(を)”发生功能转变的“ni(に)”、“ni(に)”。
2 0 0 0 サブナノ白金の経口曝露後動態に関する基礎解析
- 著者
- 山口 真奈美 吉岡 靖雄 吉田 徳幸 宇治 美由紀 三里 一貴 宇高 麻子 森 宣瑛 角田 慎一 東阪 和馬 堤 康央
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- vol.40, 2013
近年,粒子径100 nm以下のナノマテリアル(NM)と共に,10 nm以下のサブナノマテリアル(sNM)の開発・実用化が進展している。その中でも,白金粒子を数nmという大きさに制御した白金ナノコロイド(サブナノ白金;snPt)は,人体の皮膚表面や腸内で発生する全ての活性酸素種の除去に有効であるとされ,既に健康食品や化粧品などに添加されている。一方で,特にsNMは,分子と同等サイズであるために,あらゆる経路から体内に吸収される可能性など,NMとも異なる特有の体内動態に起因する生体影響が懸念されている。本観点から我々は,snPtの安全性確保を目指したNano-Safety Scienceの観点から,体内動態と生体影響の連関情報(ADMET)を収集している。本検討では,一次粒子径が1 nm,8 nmのsnPt (snPt1, snPt8)を経口投与した際の血中移行性や,尾静脈内投与後の血中消失速度に関して情報を収集した。snPt1とsnPt8をマウスに経口投与し,経時的な血中Pt濃度を誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)で測定した。その結果,snPt1は少なくとも2%以上が体内へと移行するが,snPt8は体内へ殆ど吸収されないことが判明した。次に,これら素材をマウスに尾静脈内投与し,血中消失速度を検討した。その結果,snPt1の血中半減期は,snPt8の約1/8であり,snPt8とは異なる特徴的な動態を示すことが明らかとなった。本結果は,粒子径1-8 nmの間に,体内動態に関する閾値・変動点が存在する可能性を示した知見である。今後,粒子径に依存した腸管吸収や排出メカニズムを精査することで,NM・sNMの最適設計(Nano-Safety Design),さらには生体の異物認識におけるサイズ認識機構を解明する足掛かりとなることを期待する。
2 0 0 0 OA 哺乳類学者・進化学者 徳田御稔の足跡
- 著者
- 玉田 敦子
- 出版者
- 奈良女子大学文学部
- 雑誌
- 奈良女子大学文学部研究教育年報 (ISSN:13499882)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.11-18, 2016
2 0 0 0 ホワイトアウトにおける光の散乱効果
- 著者
- 竹内 政夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会/日本雪工学会
- 雑誌
- 雪氷研究大会講演要旨集 (ISSN:18830870)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
2 0 0 0 セントルイス万国博覧会における「日本」の建築物
- 著者
- 畑 智子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.532, pp.231-238, 2000
- 参考文献数
- 29
From the study of the Japanese buildings and the exhibits at the Louisiana Purchase Exposition in 1904, St. Louis, it came to clear that Japanese buildings were built in the three areas, Japanese government place, each Japanese section of the exhibition buildings by the U.S.A., and in the 'PIKE' that was an entertainment place. All Japanese buildings were traditional Japanese style, and made by Japanese carpenters like the exhibition at Philadelphia 28 years ago. But we can recognize some element of transformation in the technique and the materials in that buildings. It is one of the transitional time at the fair of St. Louis through the international exhibitions in 19-20th century.
2 0 0 0 ウクライナのKGBアーカイブ : 公開の背景とその魅力
- 著者
- 保坂 三四郎
- 出版者
- ロシア史研究会
- 雑誌
- ロシア史研究 = История России (ISSN:03869229)
- 巻号頁・発行日
- no.105, pp.78-94, 2020
2 0 0 0 OA 日本における自然草原の成立要因からみた芝生
- 著者
- 早川 康夫
- 出版者
- 日本芝草学会
- 雑誌
- 芝草研究 (ISSN:02858800)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.98-102, 1993-10-31 (Released:2010-06-08)
2 0 0 0 OA 肩関節挙上角度と肩甲下筋の筋活動の関係
- 著者
- 中山 裕子 大西 秀明 中林 美代子 大山 峰生 石川 知志
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.292-298, 2008-10-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 17
本研究の目的は,肩甲下筋の機能的な違いを明らかにすることである。対象は健常成人6名とし,運動課題は5秒間の肩関節最大等尺性内旋運動で,筋力測定器(BIODEX)を使用した。計測肢位は肩甲上腕関節回旋中間位,内旋45度位,外旋45度位で,上肢下垂位,屈曲60度・120度,肩甲骨面挙上60度・120度,外転60度・120度の計21肢位であり,肩甲下筋上部・中部・下部の筋活動をワイヤー電極にて導出した。筋電図積分値は内外旋中間位上肢下垂位の値を基に正規化した(%IEMG)。最大トルク値と%IEMG値は挙上角度による比較を行った。肩内外旋中間位・肩甲骨面挙上および外転位での内旋運動において,最大トルク値は,120度の値が下垂位および60度の値より有意に低く,運動肢位により内旋トルクの変化が見られた。また,%IEMGについては,内外旋中間位・外転において,肩甲下筋上部は,下垂位が60度および120度に比べ高い傾向が見られた。また,内外旋中間位・肩甲骨面挙上において,肩甲下筋中部は,60度の値が,下垂位および120度の値に比べ高い傾向が見られた。下部においては,120度の値は下垂位,60度に比べ高い傾向が見られた。以上より,肩甲下筋は肩内外旋中間位における挙上角度の変更により上腕骨長軸に対し垂直に近い線維が最も強く肩関節内旋運動に作用することが示唆された。
2 0 0 0 OA 3.禁煙外来
- 著者
- 三浦 伸一郎 朔 啓二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.2, pp.351-356, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 17
喫煙は,万病のもとであり,禁煙は,心・血管疾患予防・治療の第一歩である.喫煙は,喫煙者だけでなく,周囲の非喫煙者にも様々な疾患を引き起こす.現在,日本では,約3,000万人の喫煙者がいるが,その多くは「喫煙は嗜好」と捕らえている.未成年者への禁煙教育はもちろん必要であるが,すでに喫煙しているものに対する禁煙指導も重要である.2006年より「喫煙は病気」という考えにより,禁煙外来が保険適応となり,多くの病院が取り入れ始めている.ここでは,喫煙の心・血管疾患に対する影響および医療機関における環境因子の強化としての禁煙外来のあり方や重要性について述べる.
2 0 0 0 OA 道教と神話伝説 : 中国の民間信仰
2 0 0 0 OA 十二指腸におけるヘム鉄吸収に及ぼす消化の影響
2 0 0 0 OA 「落書き」資料の想像力 特高警察による戦時期日本社会の解読
- 著者
- 野上 元
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.10, pp.133-144, 1997-06-05 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 25
The aim of this paper is to elucidate a pragmatic use of imagination, focusing on that of the political police to detect latent complaint in wartime Japan. Public scribblings, collected and recorded by the police, provide a good instantiation. During the war (1931-45), they took care of them as anti-establishment political thought, and collected them in the Tokko Geppo, a monthly secret report about the social movements. At the same time, they treated them as the representation of latent complaint in the society, having nothing to do with the Left. Therefore, these documents had two aspects: 1) thought control and its crackdown, 2) research about the society the police were sworn to protect. To attain both goals, the police developed their imagination based on the memory of city riot in the Taisho era. From fragmentary graffiti, they imagined the disturbances which might grow up into riot behind the calm society under their powerful control. These compilations are the vestige of police's method to comprehend their contemporary society.