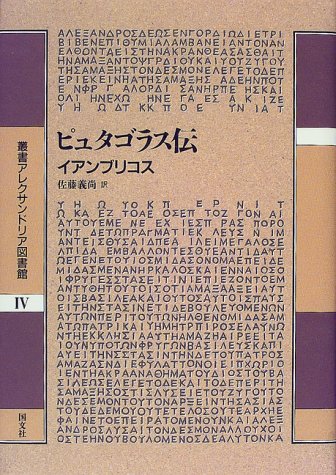- 著者
- 田中 正克 佐藤 誠 野村 健 安孫子 信明 鈴村 高幸 山下 環
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 2010 (ISSN:13431846)
- 巻号頁・発行日
- pp.15-9-1-_15-9-2_, 2010-08-31 (Released:2017-05-24)
Toward the closedown of terrestrial analogue TV broadcast on 24th July 2011, the construction of the terrestrial digital broadcasting relay stations is becoming the final stage, and it is still necessary for its costs to reduce further. As for mini-transmitting system, we are promoting the low-cost type using a gap filler system. However, there are many mini-transmitting stations that should keep frequency precision to avoid SFN interference between the other stations. So, we could not adopt conventional gap filler system, because it has only a crystal oscillator or an OCXO oscillator. Therefore we developed a gap filler system to report here, which can input 10MHz signal from an outside standard oscillator.
1 0 0 0 OA 汎用OSと専用OSを高効率に相互補完するナノカーネルの提案と実現
- 著者
- 新井 利明 関口 知己 佐藤 雅英 木村 信二 大島 訓 吉澤 康文
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.2492-2504, 2005-10-15
オペレーティングシステム(OS)はこれまでに多くのものが開発されているが,ユーザの要求が多様であり,すべての要求を満足するOS開発は不可能に近い.そこで,1台のマシン上に汎用OSと特定の目的を持つ専用OSを共存させ各々機能補完する仮想計算機機能のナノカーネルを提案し,実現した.豊富なソフトウェア資産を活用できる汎用OSと特殊機能を有する専用OSを1台のマシン上に共存させ,互いに機能補完させることができる.ナノカーネルは,上記の目的を達成するために,(1)複数OS共存オーバヘッドを削減するための資源分割機能,(2)OS間の機能補完を可能とするOS間連携機能,(3)OSの信頼性を向上させる障害監視,回復機能と擬似不揮発メモリ機能などで構成する.これらの限定した機能を実現することで,ナノカーネルは複数OSの共存を可能とし,補完環境をオーバヘッド2%以内で達成できることを確認した.また,汎用OSとリアルタイムOSの共存環境を構築し,汎用OS環境では不可能であったマイクロ秒単位の応答性を確保できることを確認し,ナノカーネルの持つOS間機能補完を実証した.さらに,専用の高信頼OSからの汎用OS障害情報の収集や汎用OSの再起動処理を実現し,システムの信頼性向上にも有効であることを確認した.
- 著者
- 佐藤 みどり 伊藤 恵子
- 出版者
- 国際武道大学
- 雑誌
- 国際武道大学研究紀要 (ISSN:09134654)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.111-120, 2000
1 0 0 0 IR 夏目漱石とチャールズ・サンダース・パース : 暗示の法則とは何か
- 著者
- 佐藤 深雪 SATO Miyuki
- 出版者
- 名古屋大学大学院文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究センター
- 雑誌
- Juncture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.52-65, 2014-03
The purpose of this article is to determine when and how Soseki NATSUME (1867-1916) had been influenced by Charles Sanders Peirce (1839-1914). Soseki had already discovered the importance of Peirce's philosophy in the early 20th century when he introduced the concept of "abduction," the essence of Pierce's philosophy, in Bungakuron (Theory of Literature), published in 1907. In this respect, I argue that Soseki possessed extraordinary foresight. In this article, I examine the concept of "suggestion" expressed in Bungakuron in order to prove the influence Soseki received from Pierce. I confirm this influence using the following two key factors; Baldwin's Dictionary of Philosophy and Psychology published in 1902 and the introduction of the concept of pragmatism to Japan in 1906. In addition, I discuss the significance of the "law of suggestion".
1 0 0 0 OA スギ花粉症とHLA抗原
- 著者
- 寺尾 彬 佐藤 靖雄
- 出版者
- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.101-105, 1978-02-20 (Released:2008-03-19)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
Thirty-five patients with cedar pollinosis were studied for clarifying the specificities of HLA antigens. Identification of HLA types was based on the result of the lymphocyte microcytotoxity test. There was a significantly high incidence of HLA-A10 and HLA-BW15 in cedar pollinosis.The incidence of HLA-A10 was 11.7% in the control group and 68.6% (X2=49. 1, p<10-6, Pc <10-5) in the patients, while that of HLA-BW 15 was 37. 1 % (X2= 12.8, p=5×10-', Pc=8 × 10-3) in the patients compared to 11.7% in the control.
- 著者
- 佐藤 圭佑
- 出版者
- 日本学校音楽教育実践学会
- 雑誌
- 学校音楽教育実践論集 (ISSN:24327743)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.100-101, 2017
1 0 0 0 現代ポリティカル・エコノミーの問題構制
- 著者
- 今東博文 折原裕 佐藤公俊編
- 出版者
- 社会評論社
- 巻号頁・発行日
- 1991
1 0 0 0 OA 水稲無代かき栽培による生育収量と土壌理化学性の改善
- 著者
- 中山 秀貴 佐藤 紀男
- 出版者
- [東北農業試験研究協議会]
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.51-52, 2001 (Released:2011-03-05)
1 0 0 0 利光春華が描く自然体の日常と幻想
- 著者
- 佐藤 恵美
- 出版者
- 美術出版社
- 雑誌
- 美術手帖 : monthly art magazine (ISSN:02872218)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1046, pp.146-149, 2016-12
- 著者
- 中澤 翔 瀧澤 一騎 厚東 芳樹 山代 幸哉 佐藤 大輔 丸山 敦夫
- 出版者
- 日本コーチング学会
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.209-217, 2018
<p> The purpose of this study was to clarify the relationship between running distance over an 8-month period and both 5000 m running performance and aerobic capacity (VO<sub>2</sub>max, VO<sub>2</sub>VT, running economy). The 8-month study period was divided into two segments of 4 months each. It was found that long-distance athletes could run 5000 m in about 15 min 30 s. The analysis also confirmed the following: (1) athletes that ran longer distances in the 8-month period had better 5000m times; (2) they had higher VO<sub>2</sub>VT; and (3) athletes whose distances were longer in the first half of the study period had better VO<sub>2</sub>VT and 5000m records in the second half of the period. The anaerobic threshold reached a higher level in runners with greater training distance, resulting in an improvement in race results. Furthermore, based on the fact that the distance run in the first four months effects on VO<sub>2</sub>VT and 5000 m running times in the latter four months, this study demonstrates the possibility of training effects occurring after a certain latency period. The results implicated that it was important to track running distances as an indicator of race performance.</p>
1 0 0 0 自動車ドア閉まり音の音質改善(<小特集>工業製品の音のデザイン)
- 著者
- 木立 純一 佐藤 利和
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.9, pp.576-582, 2008
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 ピュタゴラス伝
- 著者
- イアンブリコス [著] 佐藤義尚訳
- 出版者
- 国文社
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 OA 若年者と高齢者における体幹筋の筋厚および筋輝度の比較
- 著者
- 星 翔哉 佐藤 成登志 北村 拓也 郷津 良太 金子 千恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0076, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】加齢に伴い筋内脂肪は増加するとされている。高齢者における筋内脂肪は,身体機能と負の相関を示すと報告があることからも,わが国の高齢化社会において,体幹筋の筋内脂肪を把握することは重要であると考えられる。また,体幹筋の筋量低下は高齢者のADL低下の大きな要因であると報告もある。このことから,体幹筋の評価において,量と質を併せて検討することが必要であると考えられる。近年,筋内脂肪の評価方法として,超音波エコー輝度(以下,筋輝度)が用いられており,脂肪組織と筋輝度との関連性も報告されている。しかし,加齢による筋厚と筋輝度の変化に着目した報告の多くは,四肢筋を対象としており,体幹筋についての報告は少ない。本研究の目的は,健康な成人女性を対象に,若年者と高齢者における体幹筋の筋厚および筋輝度を比較し,加齢による量と質の変化を明らかにすることを目的とした。【方法】対象者は,健常若年女性(以下,若年群)10名(年齢20.6±0.7歳,身長159.9±5.4cm,体重51.4±4.8kg,BMI20.1±1.5)と,健常高齢女性(以下,高齢群)10名(年齢68.6±3.9歳,身長152.6±8.1cm,体重51.2±3.9kg,BMI22.4±1.7)とした。使用機器は超音波診断装置(東芝メディカルシステムズ株式会社)を使用した。測定肢位は腹臥位および背臥位。測定筋は,左右の外腹斜筋,内腹斜筋,腹横筋,多裂筋,大腰筋とした。得られた画像から各筋の筋厚を測定し,画像処理ソフト(Image J)を使用して筋輝度を算出した。なお筋厚は量,筋輝度は質の指標とした。得られたデータに統計学的解析を行い,有意水準は5%とした。また筋厚および筋輝度の信頼性は,級内相関係数(以下,ICC)を用いて,検者内信頼性を確認した。【結果】ICCの結果,筋厚と筋輝度は0.81以上の高い信頼性を得た。筋厚における若年群と高齢群の比較では,左右ともに外腹斜筋,内腹斜筋,大腰筋で高齢群が有意に小さく(p<0.05),腹横筋,多裂筋は有意な差は認めなかった。筋輝度においては,左右ともに外腹斜筋,内腹斜筋,腹横筋,多裂筋,大腰筋で高齢群が有意に高かった(p<0.05)。【結論】本研究の結果より,外腹斜筋,内腹斜筋,大腰筋は加齢に伴い筋厚は低下し,筋輝度が高かった。一方,腹横筋と多裂筋では,筋輝度は高くなるが,筋厚の低下は生じていなかった。すなわち体幹筋においては,加齢に伴い,筋厚が低下するだけではなく,筋内脂肪や結合組織の増加といった筋の組織的変化も生じていることが明らかになった。しかし,体幹深部に位置し,姿勢保持に関与している腹横筋と多裂筋は,加齢により筋厚の低下が起こりにくいと考えられる。以上のことから,加齢に伴い外腹斜筋,内腹斜筋,大腰筋は量と質がともに低下するが,腹横筋と多裂筋は質のみが低下し,量の変化は生じにくいことが示唆された。
1 0 0 0 OA Venir de infinitif 再考
- 著者
- 佐藤 正明 Sato Masaaki
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学研究部論集 A:人文科学編 = The Bulletin of Central Research Institute Fukuoka University Series A:Humanities (ISSN:13464698)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.29-40, 2005-05
1 0 0 0 音質評価の特徴 : その手順と基本メトリクス
- 著者
- 佐藤 利和 鎌田 三菜帆
- 出版者
- 社団法人 日本騒音制御工学会
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.15-19, 2002-02-01
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 佐藤 浩司
- 出版者
- 舞踊学会
- 雑誌
- 舞踊学 = Choreologia (ISSN:09114017)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.97-101, 2018
1 0 0 0 OA 黒毛和種子牛における痙攣性不全麻痺の1例
- 著者
- 三浦 萌 福田 稔彦 植木 淳史 池ヶ谷 あすか 池田 亜耶 阿南 智顕 竹鼻 一也 山口 英一郎 金 檀一 佐藤 繁 山岸 則夫
- 出版者
- 日本家畜臨床学会 ・ 大動物臨床研究会
- 雑誌
- 日本家畜臨床学会誌 (ISSN:13468464)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.8-11, 2009-04-30 (Released:2013-05-16)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 2
4ヵ月齢の黒毛和種牛が、2ヵ月齢時より発症した左後肢の跛行を主訴に来院した。症例は患肢を後方に過伸展し、蹄を着地せずに振り子状に動かす特徴的な歩様を呈していたが、疼痛反応はなく、X線所見においても異常は見られなかった。以上の所見から痙攣性不全麻痺を疑い、脛骨神経切除術を行ったところ、速やかに症状の改善が見られ、その後再発もなく治癒に至った。
1 0 0 0 OA 大学生のSNS における対人ストレス経験 : 社会的ネットワークとの関連
- 著者
- 佐藤 広英 矢島 玲
- 出版者
- 信州大学人文学部
- 雑誌
- 信州大学人文科学論集
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.53-63, 2017-03-15
- 著者
- 野田 将史 佐藤 謙次 斉藤 明子 日詰 和也 印牧 真 黒川 純 岡田 亨
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Cb0486, 2012
【目的】 ブリッジ運動は下肢筋群の筋力強化として臨床で広く活用されており,これに関する報告は散見される.しかし,両脚ブリッジ運動における股関節外転および膝関節屈曲角度の違いが下肢筋群筋活動に及ぼす影響は明らかにされていない.本研究の目的は,両脚ブリッジ運動において最も効率良く筋力強化を行う肢位を検討することである.【方法】 対象者は,下肢疾患の既往の無い健常成人15名(男性9名,女性6名,平均年齢27.4歳,平均身長166.4cm,平均体重62.7kg)であった.測定方法は,表面筋電計はマイオトレース(Noraxon社製)を用い,大殿筋・中殿筋・内側ハムストリングス・外側ハムストリングスの4筋を導出筋とした.電極貼付部位は,大殿筋は大転子と仙椎下端を結ぶ線上で外側1/3から二横指下,中殿筋は腸骨稜と大転子の中点,内側ハムストリングスは坐骨結節と脛骨内側顆の中点,外側ハムストリングスは坐骨結節と腓骨頭の中点とした.十分な皮膚処理を施行した後,各筋の筋腹に電極中心距離2cmで表面電極を貼り付け,動作時における筋電波形を導出した.アースは上前腸骨棘とした.測定値は最大随意収縮(MVC)で正規化し%MVCとした.MVCの測定はダニエルズのMMT5レベルの測定肢位において5秒間の等尺性最大収縮とした.測定条件は,MVC測定後5分間の休息を設け,次の条件における各筋の筋活動を1肢位あたり2回測定しその平均値を分析に用いた.測定時間は5秒間とし中3秒間を解析に用いた.尚,条件の測定順序は無作為とした.測定肢位は,両足部内側を揃え股関節軽度内転位とし膝関節120度屈曲位でのブリッジ運動(股内転膝屈曲120°),膝関節90度屈曲位でのブリッジ運動(股内転膝屈曲90°),膝関節60度屈曲位でのブリッジ運動(股内転膝屈曲60°),両足部を肩幅以上に開き股関節外転20度とし膝関節120度屈曲位でのブリッジ運動(股外転膝屈曲120°),膝関節90度屈曲位でのブリッジ運動(股外転膝屈曲90°),膝関節60度屈曲位でのブリッジ運動(股外転膝屈曲60°)の6肢位とした.また,運動時は股関節屈曲伸展0度になるまで挙上するよう指示し,測定前に練習を行い代償動作が出現しないよう指導した.統計学的分析にはSPSS ver.15を用い,一元配置分散分析および多重比較により筋毎に6肢位の%MVCを比較した.また,有意水準は5%とした.【倫理的配慮,説明と同意】 本研究は当院倫理委員会の承認を得た上で,各被験者に研究に対する十分な説明を行い,同意を得た上で行った.【結果】 各動作における%MVCの結果は以下の通りである.大殿筋では,股外転膝屈曲120°は股内転膝屈曲60°と股内転膝屈曲90°よりも有意に高値を示したが,その他の有意差は認められなかった.中殿筋では,すべてにおいて有意差は認められなかった.内側ハムストリングスでは,股外転膝屈曲120°は股内転膝屈曲60°と股外転膝屈曲60°と股内転膝屈曲90°と股外転膝屈曲90°よりも有意に低値を示した.股内転膝屈曲120°は股内転膝屈曲60°と股外転膝屈曲60°よりも有意に低値を示した.その他の有意差は認められなかった.外側ハムストリングスでは,股内転膝屈曲60°は股内転膝屈曲90°と股外転膝屈曲90°と股内転膝屈曲120°と股外転膝屈曲120°よりも有意に高値を示した.股外転膝屈曲60°は股内転膝屈曲90°と股外転膝屈曲90°と股内転膝屈曲120°と股外転膝屈曲120°よりも有意に高値を示した.股内転膝屈曲90°は股外転膝屈曲120°よりも有意に高値を示した.その他の有意差は認められなかった. 【考察】 今回,各動作時における%MVCの結果から,大殿筋では股関節内転位よりも外転位,膝関節軽度屈曲位よりも深屈曲位の方が有意に高値を示した.内外側ハムストリングスでは,膝関節深屈曲位よりも軽度屈曲位の方が有意に高値を示した.この結果から,ブリッジ運動を行う際は,大殿筋に対しては股関節外転位+膝関節深屈曲位,ハムストリングスに対しては内外転を問わず膝関節軽度屈曲位に設定することで効率が向上されることが示唆された.【理学療法学研究としての意義】 臨床で頻繁に処方する両脚ブリッジ運動の最も効率よい肢位が判明することで,患者への運動指導の際その肢位を活用し運動指導することができる.