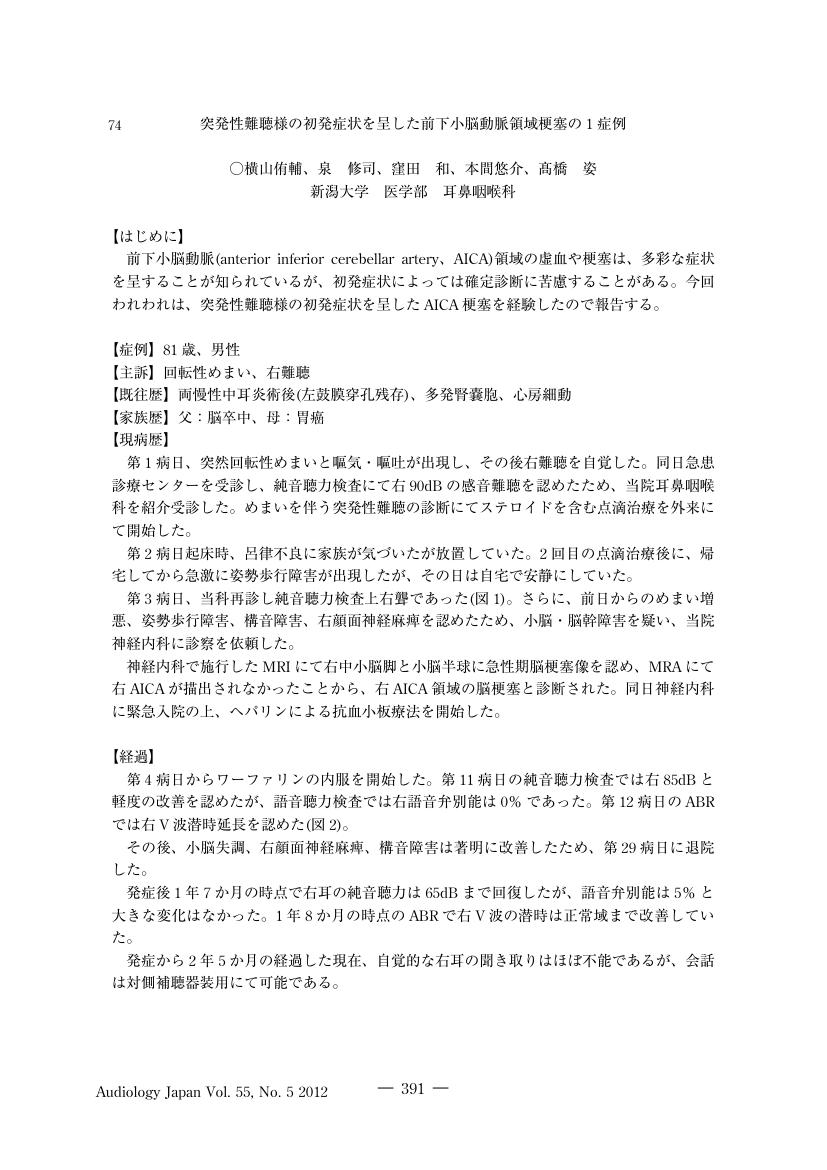3 0 0 0 OA 脳の老化に及ぼす喫煙の影響
- 著者
- 窪田 和雄 松沢 大樹 藤原 竹彦 伊藤 健吾 渡辺 弘美 小野 修一 伊藤 正敏 山浦 玄嗣 滝田 公雄 佐々木 雄一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.6, pp.503-509, 1985-11-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 21
脳は老化に伴ない, 神経細胞を減じ, 体積が減少し, 脳室, 脳溝が拡大してゆく. 我々はこの過程をCTスキャンで定量的に解析し, 脳は加齢に伴ない著明に萎縮するだけでなく, 個人差が非常に大きくなることを明らかにしてきた. 今回脳萎縮の個人差を生ずる要因を明らかにするために, 喫煙が脳萎縮に及ぼす慢性効果について調べた.神経学的に, またCTスキャン上異常のない40歳から69歳までの喫煙者159人, 非喫煙者194人について, 脳萎縮を測定した. コンピューターを使用し, CT像を構成している画素を数え, 頭蓄内の脳実質の割合を求め, 更に若い健常者の脳に比べて何%萎縮したかを示す脳体積指数 (Brain Volume Index) を求めた. BVIは加齢に伴ない低下するだけでなく, 喫煙者において, 50歳~54歳, 55歳~59歳では危険率0.1%以下で, 65歳~69歳では危険率5%で非喫煙者よりも有意に低く, これらの年代では喫煙者の脳萎縮が非喫煙者よりも進んでいることを示した. また非喫煙者では男女差は見られなかった. 喫煙量に対する依存関係を50歳代男性で調べたところ, 喫煙者各群は非喫煙者よりも有意にBVIは低下し, 喫煙指数が多くなるにつれBVIは低下する傾向があったが, 喫煙者各群に有意差はなかった. また喫煙者では血清トリグリセライド (p<0.002) 及び収縮期血圧 (p<0.05) が非喫煙者よりも有意に高かった.脳血流が喫煙者では減少しているという我々の先の報告と合わせ, 喫煙は慢性的に動脈硬化を促進し, 動脈硬化や血圧の上昇その他の要因とともに脳血流を低下させ, 加齢に伴なう神経細胞の喪失を助長し, 脳萎縮を促進させると考えた.
- 著者
- 松田 真一 深田 信幸 大石 昌仁 岡 宏明 原 良介 小島 愛 中野 駿 元吉 克明 五十嵐 繁樹 佐々木 裕子 亀山 菜つ子 窪田 和寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬剤疫学会
- 雑誌
- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.41-54, 2021-06-20 (Released:2021-07-26)
- 参考文献数
- 17
保険請求データベース(DB)や電子カルテ DB 等,日常診療の情報が記録されたリアルワールドデータ(real-world data:RWD)は,薬剤疫学研究における重要なデータ源の一つである.日本において,2018年4月より製造販売後調査の新たなカテゴリーとして,医薬品の製造販売後データベース(製販後 DB)調査が追加された.以降,医薬品リスク管理計画(risk management plan:RMP)において製販後 DB 調査が計画され,製販後 DB 調査の実践が期待されているが,現時点で結果公表まで至ったものはほとんどない.一方,海外においては RWD を用いた DB 研究成果は現時点で多数報告されている.海外と日本では,DB 自体の特性(項目・構造等)の違い,医療環境・慣習の違い等を念頭におく必要はあるが,そのような前提を踏まえて海外 DB 調査論文を精読し,研究仮説,研究デザイン,手法等を吟味することは,日本における製販後 DB 調査の計画・実行・結果の解釈を実践するうえで参考価値があると考えた.本報告の目的は,海外 DB 調査論文の批判的吟味を通じて,DB 調査の特徴や注意点を考察すること,そして,日本における製販後DB 調査の実践に役立つ提言を行うことである.本稿が,今後の製販後 DB 調査を計画・実施するうえでの一助になれば幸いである.
2 0 0 0 OA 神経内分泌腫瘍のPET・SPECT
- 著者
- 窪田 和雄
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.112-115, 2015 (Released:2015-09-02)
- 参考文献数
- 11
ソマトスタチン受容体に結合する標識オクトレオチドを用いたPET/CTおよびSPECT/CTは,膵・消化管の神経内分泌腫瘍(NET)の病巣診断・転移診断に有用である。また,ペプチド受容体放射性核種治療の適応判定や,オクトレオチド製剤の治療効果予測にも利用される。ソマトスタチン受容体イメージングがNETの高分化な特質を評価するのに対し,FDGPET/CTはNETの増殖や悪性度を評価するのに有用であり,相補的な機能画像情報を提供する。
- 著者
- 窪田 和宏
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能基礎論研究会
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.21-29, 1998-09-24
- 著者
- 金沢 弘美 窪田 和 谷口 貴哉 澤 允洋 髙橋 英里 民井 智 江洲 欣彦 吉田 尚弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.10, pp.1134-1141, 2023-10-20 (Released:2023-11-01)
- 参考文献数
- 21
一側性難聴は, 難聴側からの聴取困難だけでなく, 雑音下での聴取困難, 音源定位の困難がある. 両側性難聴者だけでなく, 一側性難聴者もマスク装用下での聞き取り困難を感じている. この困難感は, 雑音の多い学校生活で1日を過ごすことが多い学童児が特に感じていることが危惧された. 今回は, 一側性難聴児の学校生活の中での聞き取り困難感を, マスク装用生活前後で比較した調査を行った. また希望者に対しては補聴器試聴を行った. 対象は, COVID-19 流行時に当院に外来通院していた一側性難聴児31人である. コントロール群として健聴児15人をおいた. 方法はアンケート形式で, 雑音下聴取・音源定位・学業理解に関して4つの問いを設定し, VAS スケールで困難感として当てはまる程度を患児本人が記入した. 補聴器を希望した一側性難聴児は, 装用1~3カ月後に雑音下語音検査を行った. この結果, 難聴のレベルにかかわらず, 多くの一側性難聴児が, マスク装用生活後に聞き取り困難を感じていた. 11人が補聴器試聴を希望し, 9人が雑音下語音検査でその効果を認め購入に至った. 一側性難聴児は, 両側性難聴児と同様に, 学力の低下, 社会性の問題など, 年齢が上がるに連れて顕著になるケースがある. マスク装用生活が続いたことにより, 一側性難聴児が困難感を自覚するようになっている. 補聴器装用のほか, 聴取の環境調整, 心理・社会面など個別にサポートする必要がある.
1 0 0 0 OA 突発性難聴様の初発症状を呈した前下小脳動脈領域梗塞の1症例
- 著者
- 横山 侑輔 泉 修司 窪田 和 本間 悠介 髙橋 姿
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.391-392, 2012 (Released:2013-12-05)
1 0 0 0 OA 日本人労働者におけるワーカホリズムおよびワーク・エンゲイジメントとリカバリー経験との関連
- 著者
- 窪田 和巳 島津 明人 川上 憲人
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.69-76, 2014 (Released:2014-11-20)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 8
本研究では、仕事に関する積極的態度であるワーカホリズムとワーク・エンゲイジメントが、それぞれリカバリー経験(就業中のストレスフルな体験によって消費された心理社会的資源を元の水準に回復させるための活動)とどのような関連を有しているのか、 日本の労働者を対象として明らかにすることを目的とした。ワーカホリズム、ワーク・エンゲイジメント、リカバリー経験に関する各質問項目を含むインターネット調査を、調査会社である株式会社マクロミルの登録モニタを対象に行った(調査期間:2010年10月)。登録モニタから、性別、年代、居住地域が人口統計比率に合うように無作為抽出された13,564名の労働者に対して研究協力の案内が送付された。本研究では回答期間内に回答した先着2,520名を解析対象とした(男性1,257名、女性1,263名:平均年齢44.4歳、SD = 12.9)。分析は、各構成概念(ワーカホリズム、ワーク・エンゲイジメント、リカバリー経験)間の関連を明らかにするため、共分散構造分析を実施した。共分散構造分析の結果、ワーカホリズムとワーク・エンゲイジメントとは、弱い正の相関を有していた。また、ワーカホリズムは4つのリカバリー経験(心理的距離、リラックス、熟達、コントロール)と負の関連を有し、ワーク・エンゲイジメントは3つのリカバリー経験(リラックス、熟達、コントロール)と正の関連を有することが明らかになった。これらの結果は、ワーカホリズムはリカバリー経験を抑制するのに対して、ワーク・エンゲイジメントはリカバリー経験を促進することを示唆している。ワーカホリズムとワーク・エンゲイジメントは仕事に対して多くのエネルギーを費やす点では共通しているものの、リカバリー経験との関連については、それぞれ異なる影響を有することが考えられる。
1 0 0 0 OA 看護政策に携わる看護職が現在の職業・立場につくまでの経験
- 著者
- 田川 晴菜 窪田 和巳 山口 さおり 深堀 浩樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護管理学会
- 雑誌
- 日本看護管理学会誌 (ISSN:13470140)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.48-56, 2013 (Released:2018-12-28)
- 参考文献数
- 9
本研究は,看護政策に携わる看護職の現在の職業・立場につくまでの経験を明らかにし,彼らの意見から看護職の看護政策に関する興味・関心を高める方略についての示唆を得ることを目的とした.看護政策へ携わる看護職6名を対象に半構造的インタビューを実施し,質的に分析した.分析の結果,看護政策に携わる看護職の現在の職業・立場につくまでの経験として「看護政策に関心を持ったきっかけとなった経験」,「看護政策への理解を深めた体験」,「周囲の人々から対象者への反応」の3カテゴリーが,看護政策に関する興味・関心を高める方略についての意見や考えとして「看護政策への関心を高める上での障害」,「看護政策への関心を高めるために考えられる取り組み」の2カテゴリーが得られた.将来看護政策に携わりたいと考える看護職にとって,看護政策に直接携わる人との関わりが重要であるとともに,基礎教育の段階で医療・看護政策に関する内容を学び,看護以外の分野の知識や海外の医療制度・看護実践について知ることが有益であることが示唆された.また,今後より多くの看護職が看護政策に関心を持つようになるための体制を考える上で,多忙な臨床現場でも効率的に看護政策に関する情報が得られる環境整備や看護職の情報リテラシーを高める取り組み,若年層に対するアプローチが重要であることが示唆された.
- 著者
- 松田 真一 深田 信幸 大石 昌仁 岡 宏明 原 良介 小島 愛 中野 駿 元吉 克明 五十嵐 繁樹 佐々木 裕子 亀山 菜つ子 窪田 和寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬剤疫学会
- 雑誌
- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)
- 巻号頁・発行日
- pp.26.e4, (Released:2021-03-18)
- 参考文献数
- 17
保険請求データベース(DB)や電子カルテ DB 等,日常診療の情報が記録されたリアルワールドデータ(real-world data:RWD)は,薬剤疫学研究における重要なデータ源の一つである.日本において,2018年4月より製造販売後調査の新たなカテゴリーとして,医薬品の製造販売後データベース(製販後 DB)調査が追加された.以降,医薬品リスク管理計画(risk management plan:RMP)において製販後 DB 調査が計画され,製販後 DB 調査の実践が期待されているが,現時点で結果公表まで至ったものはほとんどない.一方,海外においては RWD を用いた DB 研究成果は現時点で多数報告されている.海外と日本では,DB 自体の特性(項目・構造等)の違い,医療環境・慣習の違い等を念頭におく必要はあるが,そのような前提を踏まえて海外 DB 調査論文を精読し,研究仮説,研究デザイン,手法等を吟味することは,日本における製販後 DB 調査の計画・実行・結果の解釈を実践するうえで参考価値があると考えた.本報告の目的は,海外 DB 調査論文の批判的吟味を通じて,DB 調査の特徴や注意点を考察すること,そして,日本における製販後DB 調査の実践に役立つ提言を行うことである.本稿が,今後の製販後 DB 調査を計画・実施するうえでの一助になれば幸いである.
1 0 0 0 OA 病棟看護師における感情労働とワーク・エンゲイジメントおよびストレス反応との関連
- 著者
- 加賀田 聡子 井上 彰臣 窪田 和巳 島津 明人
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.83-90, 2015 (Released:2015-11-19)
- 参考文献数
- 39
看護師を対象に、感情労働による心理学的影響を調べた近年の先行研究では、感情労働がバーンアウト/抑うつの悪化や職務満足感の向上に影響を与えることが着目されている。しかし、日本の看護師を対象に感情労働の心理学的側面に着目した先行研究は少なく、感情労働を要素別に分類し、ワーク・エンゲイジメントやストレス反応との関連を検証した研究は、我々の知る限り見当たらない。そこで本研究では、日本の看護師を対象に「看護師の感情労働測定尺度:ELIN」を用いて感情労働の要素を詳細に測定し、これらの各要素とワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との関連を検討することを目的とした。関東圏内の1つの総合病院に勤務する女性病棟看護師306名を対象に、感情労働(ELIN:「探索的理解」、「ケアの表現」、「深層適応」、「表層適応」、「表出抑制」の5下位尺度からなる)、ワーク・エンゲイジメント(The Japanese Short Version of the Utrecht Work Engagement Scale:UWES-J短縮版による)、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応(職業性ストレス簡易調査票:BJSQによる)、個人属性(年齢、診療科、同居者の有無)に関する質問項目を含めた自記式質問紙を用いて調査を実施した(調査期間:2011年8~9月)。分析は、感情労働とワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との関連を検討するため、感情労働の各下位尺度を独立変数、ワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応を従属変数、個人属性を調整因子とした重回帰分析を実施した。重回帰分析の結果、感情労働の構成要素の一つである「探索的理解」とワーク・エンゲイジメントとの間に正の関連が、「表出抑制」とワーク・エンゲイジメントとの間に負の関連が認められた。また、感情労働の構成要素の一つである「深層適応」と心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との間に正の関連が認められた。これらの結果から、「探索的理解」を高め、「表出抑制」や「深層適応」を低減させるようなアプローチによって、看護師が自身の感情をコントロールしながらも、心身の健康を保持・増進するために有効な可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 千葉市3 歳児検尿・腎エコーの先天性腎尿路異常発見における有用性
- 著者
- 松村 千恵子 倉山 英昭 安齋 未知子 金本 勝義 伊藤 秀和 久野 正貴 長 雄一 本間 澄恵 石川 信泰 金澤 正樹 重田 みどり 窪田 和子 山口 淳一 池上 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児腎臓病学会
- 雑誌
- 日本小児腎臓病学会雑誌 (ISSN:09152245)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.194-203, 2014 (Released:2014-06-14)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
千葉市3 歳児検尿システムでは,蛋白・潜血±以上,糖・白血球・亜硝酸塩+以上の1 次検尿陽性者に,2 次検尿と腎エコーを施行。1991~2011 年度154,456 名の精査陽性率は1.5%で,膀胱尿管逆流(VUR)16 名(血尿5,細菌尿11,尿単独3),アルポート症候群,ネフローゼ症候群,巣状分節状糸球体硬化症(FSGS),糸球体腎炎等が診断された。11,346 名の腎エコーで,先天性腎尿路奇形(CAKUT)92(0.8%),うちVUR 24 名(エコー単独11),両側低形成腎2,手術施行17 であった。VUR 全27 名中,VUR III 度以上の頻度は細菌尿例において非細菌尿例より有意に高かった(各々10/11,7/16,p<0.05)。10 名(7 名両側IV 度以上)は多発腎瘢痕を有し,うち7 名はエコー上腎サイズ異常を認めた。FSGS 1 名が末期腎不全に至った。千葉市3 歳児検尿システムはCAKUT 発見に有用と考えられた。
1 0 0 0 がん患者における大脳辺縁系機能抑制に関しての画像的研究
本研究は、がん患者の情動変化を客観的に脳画像として評価する方法を開発し、心理テストを補足する情動検査法を確立することを目標とする。昨年度の研究により全身ポジトロン断層検査(PET)を用いてがん診断を行った72症例の脳画像を用い、帯状回、視床下部、海馬等の大脳辺縁系における広範なブドウ糖代謝の低下を認めた。この変化が脳器質障害によるものなのか、あるいは心因性の障害なのか不明であった。そこで、ドイツのアルバート・ルートヴィヒ大学核医学科との共同研究として、ドイツでのがん患者の脳の解析を行った。年齢・性別をコントロールした正常患者10名との比較をおこない、がん患者と比較した結果、前頭前野、側頭頭頂葉皮質、前・後部帯状回、大脳基底核、などにおいて代謝の低下が確認され、東北大学データを近い結果を得ることができた。また、癌患者21名を、(1)抑鬱度、(2)不安、(3)化学療法の有無、(4)残存癌組織の有無、の四項目に関してサブグループに分け、サブグループ間解析を施行した。その結果、前頭前野、側頭頭頂葉皮質、前部帯状回における代謝低下は、抑鬱度および不安と強い負の相関を示すことがわかった。化学療法の影響が前部帯状回で、腫瘍組織の残存という因子の影響は、小脳および後頭葉において観察されたが、がん患者に観察されるこのような代謝異常は、癌組織による脳に対する生物学的影響というよりも患者の心理的な間題により引き起こされている可能性が高いという結論を得た。一連の研究結果は、スペイン、バルセロナにおけるヨーロッパ核医学会で注目すべき演題として紹介された。
1 0 0 0 OA 母親のマラリアに関する知識と子どもへの予防対策との関連
- 著者
- 沼倉 和美 窪田 和巳 徳永 瑞子
- 出版者
- 日本国際保健医療学会
- 雑誌
- 国際保健医療 (ISSN:09176543)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.261-270, 2017-12-20 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 14
目的 本研究では、カメルーン共和国において、母親のマラリアに関する知識の実態を把握した上で、母親のマラリアに関する知識と子どもへの予防対策との関連を明らかにした。方法 2014年8月から9月に、カメルーン共和国ヤウンデ市のA保健センターへ予防接種に来ていた5歳未満児の実子を養育している母親50名を対象とし、筆者らが作成した質問紙をもとに聞き取り調査を行なった(回収率:100%)。質問紙は、母親のマラリアに関する知識、母親が子どもに実施している予防対策、マラリアの情報源、および対象者の属性により構成された。母親のマラリアに関する知識の項目(全4項目)を独立変数、子どもに実施している予防対策(全1項目)を従属変数として共分散分析を行った。分析の際には、対象者の属性を共変量として投入した。母親の年齢とマラリアの原因に関する知識について、それぞれ子どもへのマラリア罹患予防対策としての蚊帳の使用状況との関連においてX2検定を行った。結果 対象のうち、マラリアの原因について「蚊の刺咬」を知っている人は40人(80.0%)、知らない人は10人(20.0%)、マラリアの情報源として「病院や診療所の医療関係者(医師、看護師、助産師)」は39人(78.0%)、「テレビ」は26人(52.0%)であった。 マラリアに関する知識の項目(全4項目)と子どもに実施している予防対策の項目(全1項目)との関連において実施した共分散分析では、すべての組み合わせにおいて有意差が認められた。 マラリアの原因に関する知識と子どもへのマラリア罹患予防対策としての蚊帳の使用状況との関連において、X2検定では有意傾向が認められた。結論 本研究から、マラリアの原因、症状、予防対策、経済的負担に関して知識のある母親は、マラリアの予防対策を実施していることが明らかになった。 これらのことから、適切な予防対策によりマラリア罹患率や5歳未満児死亡率を減少させるために、マラリアの原因や蚊の習性を含めた正しい知識の普及が重要である。
1 0 0 0 OA 肝疾患マーカー候補としての酸化型アルブミンの構造と機能解析およびその生理学的意義
- 著者
- 山田 尚之 窪田 和幸 河上 麻美 中山 聡 鈴木 榮一郎
- 出版者
- 日本電気泳動学会
- 雑誌
- 生物物理化学 (ISSN:00319082)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.25-30, 2008 (Released:2009-12-04)
- 参考文献数
- 20
Genomics and proteomics have been useful in many different areas of medicine and health science as an aid to discover new biomarker for disease diagnosis or staging and as a tool to predict or monitor treatment response or toxicity. Human serum albumin (HSA) exists in both reduced and oxidized forms, and the percentage of oxidized albumin increases in several diseases. However, little is known regarding the pathological and physiological significance of oxidation due to poor characterization of the precise structural and functional properties of oxidized HSA. Here, we characterize both the structural and functional differences between reduced and oxidized HSA. Using LC-ESI TOF MS and FT MS analysis, we determined that the major structural change in oxidized HSA in healthy human plasma is a disulfide-bonded cysteine at the thiol of Cys34 of reduced HSA. Based on this structural information, we prepared standard samples of purified HSA, e.g. non-oxidized (intact purified HSA which mainly exists in reduced form), mildly oxidized and highly oxidized HSA. Using these standards, we demonstrated several differences in functional properties of HSA including protease susceptibility, ligand-binding affinity and antioxidant activity. From these observations, we conclude that an increased level of oxidized HSA may impair HSA function in a number of pathological conditions. In addition, we determined blood and plasma sampling conditions for the accurate measurement of the oxidized albumin ratio in plasma by using EST-TOF MS screening.
- 著者
- 津野 香奈美 大島 一輝 窪田 和巳 川上 憲人
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.245-258, 2014 (Released:2014-12-20)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 2 15
目的:東日本大震災は東北から関東にかけて甚大な被害をもたらしたが,津波の被害がなかった関東地方の労働者の心理的ストレスについてはあまり注目されていない.自身の被災に加え,震災によって仮庁舎への移動が必要となり,通常業務に加え震災対応に追われた関東地方の自治体職員における困難に立ち向かう力(レジリエンス)と心的外傷後ストレス症状との関連を検討した.対象と方法:関東地方のある自治体において,震災から半年後にあたる2011年9月に全職員2,069名を対象に質問紙調査を実施し,そのうち991名から回答を得た(回収率47.9%).分析対象者は,欠損値のなかった825名(男性607名,女性218名)とした.心的外傷後ストレス症状は出来事インパクト尺度改定版(Impact Event Scale-Revised),レジリエンスはConnor-Davidson Resilience Scaleを用いて測定し高中低の3群に区分した.震災による怪我の有無(家族を含む)と自宅被害の有無をそれぞれ1項目で調査し,いずれかに「はい」と回答した者を「被災あり群」,それ以外を「被災なし群」とした.多重ロジスティック回帰分析を用いて,被災あり群における心的外傷後ストレス症状の有無(IES-R得点25点以上)のオッズ比を,レジリエンス得点の高中低群別に算出した.結果:東日本大震災によって自分ないし家族が怪我をした者は回答者のうち4.6%,自宅に被害があった者は82.3%であり,いずれかの被害があった者は全体の83.3%であった.被災あり群,慢性疾患あり群で有意に心的外傷後ストレス症状を持つ割合が高かった.基本的属性および被災の有無を調整してもレジリエンスと心的外傷後ストレス症状との間に有意な負の関連が見られた(高群に対する低群のオッズ比2.00 [95%信頼区間 1.25–3.18],基本属性,職業特性で調整後).特に被災あり群で,レジリエンスと心的外傷後ストレス症状との間に有意な関係が見られた.結論:東日本大震災で自宅等への被災を受けた自治体職員の中で,レジリエンスが低いほど心的外傷後ストレス症状を持つリスクが高いことが明らかになった.このことから,震災などの自然災害という困難の際にも,レジリエンスが心的外傷後ストレス症状発症を抑える働きをすると考えられる.
- 著者
- 窪田 和矢 橋本 禅 星野 敏 九鬼 康彰
- 出版者
- 農村計画学会
- 雑誌
- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.Special_Issue, pp.257-262, 2010-11-30 (Released:2011-11-30)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
In this study, we paid special attention to the role of inspection tours in knowledge transfer from one municipality to another. Using the city of Sasayama and its Basic Ordinance for Local Government as a case, we investigated 1) what kind of knowledge did inspectorates from other municipal governments try to obtain from Sasayama through tours, 2) commonalities and differences of knowledge looked for by inspectorates and 3) why such commonalities and differences arose. Questionnaire and interview survey were employed. Our analysis clarified that category and concreteness of questions raised by inspectorates in tours differs significantly depending on their awareness about and progresses of the draft up of ordinances because, under given time constraints, inspectorates tended to collect knowledge and information with priority which would be useful for their practices.