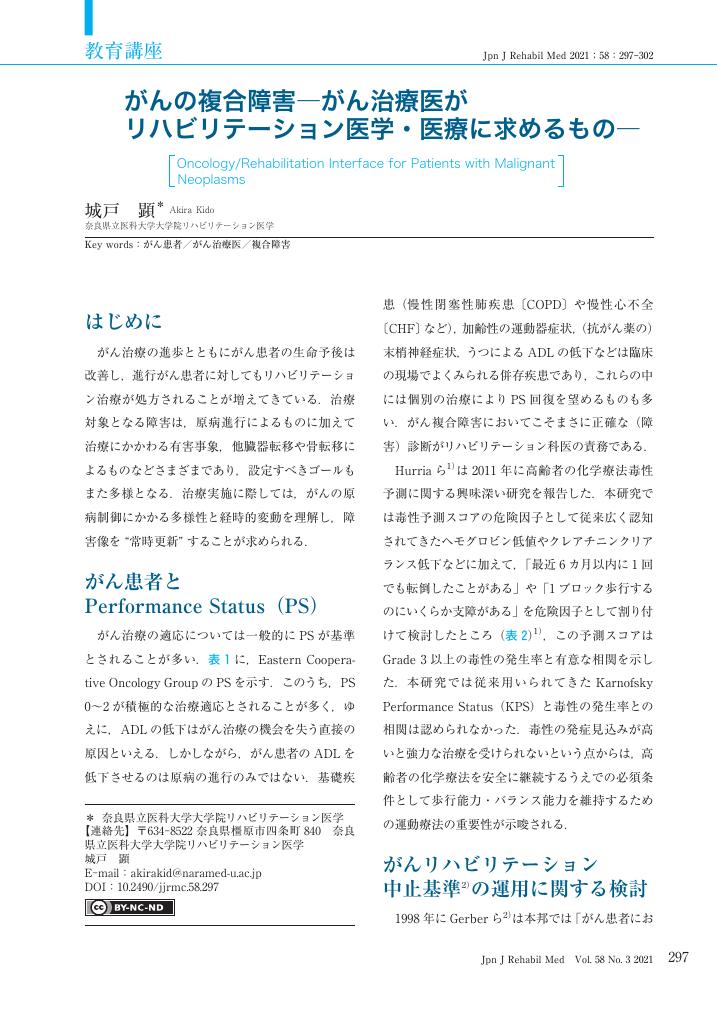- 著者
- 古賀章彦 平井 百合子 平井 啓久
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第27回日本霊長類学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.45, 2011 (Released:2011-10-08)
<目的> StSat 反復配列が形成するブロック1か所あたりの平均の大きさは、 過小に推定して、3 × 109 bp(ゲノムサイズ)× 0.001(割合の推定値)/ 24(染色体数)/ 2(両末端)= 60 kb である。異なる染色体の端部に塩基配列が均質で、かつ長大な領域が、テロメアに加えて存在していることになる。このため「StSat 反復配列の領域で非相同染色体間の組換えが頻繁に起こる」との推測が成り立つ。これを直接検出することを我々は目指している。ただし、特定の反復単位を見分ける手段はないため、マーカーのDNA断片を染色体に組み込んだうえでその挙動を追うことになり、時間を要する。そこで、短時間で可能な間接的な検証のための実験を考案し、これを行った。<方法> StSat 反復配列を含む約 30 kb のプラスミドクローン(A)と、含まない同じ大きさのクローン(B)を作り、それぞれをチンパンジーの培養細胞にリポフェクション法で導入した。クローンはサークル状であるため、染色体との間で組換えが1回起こるとクローンの全域が染色体に組み込まれる。これが起こることを可能にする時間として4世代ほど培養した後、AとBに共通する部分をプローブとして、染色体へのハイブリダイゼーションを行った。<結果> Aを導入した方でのみ、主に染色体端部にシグナルが観察された。StSat 反復配列の部分で組換えが起こってクローンが染色体に取り込まれたとの解釈が順当であり、頻繁な組換えの間接的な検証であるといえる。<考察> 一般に染色体のある場所で組換えが起こるとその近辺での組換えが抑制されることが、知られている。これを考慮すると、「チンパンジーでは StSat 反復配列があるために、隣接する領域での非相同染色体間組換え頻度は、ヒトより低い」ことが可能性として考えられる。
1 0 0 0 OA 心身医学について
- 著者
- 日野原 重明
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.11, pp.831, 2005-11-01 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 OA 沖縄県における飲料水の硬度およびケイ酸と脳血管疾患死亡率との関連
- 著者
- 仲村 薫 中田 福市 鈴木 儀弘 大城 健孝
- 出版者
- The Japanese Society of Health and Human Ecology
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.92-98, 1988-03-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 1
Environmental weather and dietary life exist within the same aspect throughout the Okinawa Prefecture. However on the farming population rates and the nature of drinking water there were regional differences. The correlations between above factors and the mortality from cerebro-vascular disease (CVD) were investigated. Interrelationships between CVD and several trace elements in drinking water were found to be strong and complex, especially water hardness and silicon seemed to make an important contribution to mortality from CVD. The mortality from CVD indicated the highest negative correlation coefficient (r=-0.86) for drinking water hardness. In our research regions, silicon concentration in drinking water was lower levels (6-14 mg/l) in Japan and correlated negatively with the mortality from CVD (r=-0.76). On the correlation with mortality from CVD, silicon concentration is considered to have a threshold value, which is presumed to about 10 mg/l. The mortality from CVD and farming population rate showed positive correlation (r=0.75). The mortality rate and Ca2+/SO4-2 are represented as the negative correlation.
1 0 0 0 OA 学校教育とホームスクール ──家庭を学習拠点とする義務教育機会の諸相
- 著者
- 宮口 誠矢
- 出版者
- 日本教育政策学会
- 雑誌
- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.25-38, 2020 (Released:2020-10-01)
Homeschooling in a broad sense implies not only educational opportunities where parents solely provide formal education for their children who do not go to school at all. In the United States, homeschools and schools are involved in various ways. The article aimed to review such homeschooling systems in the U.S. and to suggest the issues to be explored. There are some systems or programs, such as dual enrollment and assistance programs, to offer some public support for homeschools run by parents. Schools or public agencies, in some cases, run homeschools by themselves. Through examining these homeschools, I find two theoretical types of homeschooling: one as“exit”from schools, and the other as“extension”of schools. Both types of homeschools require consideration of measures to evaluate input or outcome. In addition, the“exit”type of homeschools raises the issues of what actors other than schools can properly provide compulsory education and of what tasks these providers undertake. When more than one person or institution provide compulsory education for a child, it should be made clear how they are collectively accountable for education. Finally, I offered some policy recommendations for the revision of compulsory education system in Japan.
1 0 0 0 OA 加齢による大腿四頭筋の形態的特徴および筋力の変化について ―高齢女性と若年女性との比較―
- 著者
- 池添 冬芽 浅川 康吉 島 浩人 市橋 則明
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.232-238, 2007-08-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 14
加齢に伴い,ヒト骨格筋においては筋張力が低下するだけでなく,筋厚,羽状角など筋の形態的特徴も変化する。近年では超音波法により簡便に筋の形態的特徴を調べたり,固有筋力を推定することが可能になったものの,高齢者を対象とした研究は少ない。本研究では大腿四頭筋の形態的特徴や筋力の加齢による変化について明らかにすること,ならびに高齢者の筋力低下に影響を及ぼす因子について検討を行うことを目的とした。超音波診断装置を用いて,外側広筋部での大腿四頭筋の筋厚および羽状角の測定を行った。また,大腿四頭筋の筋厚と大腿周径から筋横断面積の推定値を求め,さらに膝伸展筋力をこの筋横断面積で除した固有筋力指数を求めた。その結果,高齢女性では若年女性と比較して大腿筋厚や筋横断面積で約1/2,膝伸展筋力では約1/3に有意に減少することが確認された。また高齢女性において,膝伸展筋力と年齢との間に有意な相関がみられ,筋厚や筋横断面積と年齢との問には相関がみられなかった。これらのことから,大腿四頭筋では筋量よりも筋力の方が相対的に加齢による低下の程度が大きいことが示された。固有筋力指数も高齢者では若年者より有意に低い値を示し,加齢による筋力低下は筋量以外に神経性因子の変化が関与していることが推察された。さらに,高齢者の固有筋力指数は変動係数が56%と高く,筋力発揮に関わる神経性因子は,高齢者では個人差が拡大することが示唆された。
1 0 0 0 OA 磁石を使った簡単なβ線偏向実験 : GM計数管と霧箱での検出
- 著者
- 樋之口 仁
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.98-101, 1996-06-05 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 6
夜光塗料に含まれる^<147>Pmを線源にして,フェライト磁石を使った簡単なβ線偏向実験を行い,シャープな偏向計数率を得た。そこから得られた曲率半径から,β粒子の速度・エネルギーを求めた。さらに,拡散霧箱でβ線の偏向を受けた飛跡が観察できた。これらの実験は高等学校物理の「ローレンツ力」・「放射線の性質」の単元で演示実験や生徒の探求活動・課題研究に利用できる。
1 0 0 0 OA がんの複合障害 ―がん治療医がリハビリテーション医学・医療に求めるもの―
- 著者
- 城戸 顕
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.297-302, 2021-03-18 (Released:2021-07-03)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1905年03月08日, 1905-03-08
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1905年03月07日, 1905-03-07
1 0 0 0 OA アオリイカの多回産卵について
- 著者
- 和田 洋藏 小林 知吉
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.151-158, 1995-03-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 7 12
We reared the oval squid Sepioteuthis lessoniana in pens from June 3 to July 31 1992. The eggs spawned by these squid were reared in a tank to hatch. A female reared with a male in a pen spawned 11 times at intervals of 1-9 days from June 11 to July 30. This female laid 1, 540 egg capsules containing 7, 780 eggs in total (55 to 302 capsules containing 231 to 1, 388 eggs at one spawning). The hatchability of the eggs at each spawning ranged from 66.7 to 97.8%. Another female reared without a male in a pen spawned more than four times, but the hatchability rate of the eggs was lower than the former female. The female with a male had spermatophores when she died, while the female without a male had no spermatophores after several spawnings (both females had spermatophores at the beginning of the experiment). These results suggest that the oval squids copulated over the period from the previous spawning to the next. The number (Y) of eggs in one capsule was related to the water temperature (X, °C) on the day of spawning. This relation was expressed by the following equation. Y=15.1-0.426X.
1 0 0 0 OA 『方丈記』の受容 ―夏目漱石の『英訳方丈記』をめぐって―
- 著者
- プラダン ゴウランガ チャラン Gouranga Charan PRADHAN
- 出版者
- 総合研究大学院大学文化科学研究科
- 雑誌
- 総研大文化科学研究 = Sokendai review of cultural and social studies (ISSN:1883096X)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.99-111, 2017-03-31
『方丈記』は成立して間もないころから、様々な視点から多くの作品の中に受容され、連綿と関心が注がれ続けてきたのみならず、外国の人々からも多くの注目を集めてきた。夏目漱石が帝国大学在学中、英文学科の教授であったディクソン(James Main Dixon)の依頼により『方丈記』の最初の外国語訳として英訳を行ったことはよく知られている。また、ディクソンは、漱石の英訳を下敷きにして長明とワーズワースを対比した論文を執筆し、独自に『方丈記』の英訳も試みた。この二人の取り組みをきっかけとして、この作品は海外においても認識されるようになった。従って、『方丈記』に対する漱石とディクソンの持ったイメージは、国内外におけるこの作品の受容史を検討する上で重要な意味をもつと考えられる。本稿ではこの二人の執筆した論文を中心に、国内外の英語文献から『方丈記』に関する言説の分析を行い、その受容に関する理解を深めることを目的とする。そこから漱石の英訳以前において既に英語をはじめ外国語の文献の中でこの作品が言及されていることが判明した。漱石に英訳を依頼したディクソンは、西洋の人々の中で初めてこの作品に強い関心を持ったと言えるが、より具体的に彼は『方丈記』に描写された隠者ないし孤独さといった主題に注目したと思われる。また、ディクソンの研究発表や当時の学会議事録から、西洋の人々はキリスト教の道徳的価値観の視点から鴨長明の行動を理解しようとしたものと考えられる。さらに漱石のエッセイとディクソンの書いた論文の関係についても検討をすると、ディクソンは漱石のエッセイから多くの内容を自身の論文に取り入れたこともわかった。Kamo no Chōmei’s Hōjōki (1212) has a long history of readership. Throughout the history of Japanese literature, it continuously invited attention, not only from readers in Japan, but also from abroad. It is well known that Natsume Sōseki translated Hōjōki into English while he was a student at the request of James Main Dixon, his English literature professor at Tokyo Imperial University. Dixon, building upon Sōseki’s translation, further authored an article comparing Kamo no Chōmei with English poet William Wordsworth, and also produced his own English translation. It is owing to the endeavours of these two that Hōjōki became available to readers in the West for the first time. Hence, in order to study the history of Hōjōki’s reception, especially its circulation in the West, the insights offered by Sōseki and Dixon are particularly crucial. With this in mind, the focus in this paper is to deepen our understanding of Hōjoki’s reception through a close analysis of relevant English language resources that mention this work. We have found, from our study of late nineteenth century resources, that Hōjōki had already appeared, albeit in fragments, in English-language literature before Sōseki’s translation. Dixon was perhaps the first Westerner to show a keen interest in Hōjōki, and his primary thematic interest was the issue of reclusion and solitude. Also, the contents of Dixon’s talk on Chōmei show that the Western audience appreciated Hojoki and its author from the perspectives of the Christian cultural ethos. This paper also discusses the intertextual affinity between Sōseki’s essay and Dixon’s article. It demonstrates how the latter built his arguments based on the former’s ideas.
1 0 0 0 OA 米国の戦略核運用政策の変遷と現状 (安全保障の今日的課題)
- 著者
- 松山健二
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.696, 2009-01
1 0 0 0 OA 文化の赤十字 : ブルーシールドの現状と課題
- 著者
- 坂本博
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.694, 2008-11
1 0 0 0 OA ロシア 2020年までの発展戦略
- 著者
- 溝口修平
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 235-1), 2008-04
1 0 0 0 OA オープンソースコミュニティの組織化における行為論的アプローチ
- 著者
- 池田 達彦 酒井 直
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2002年度秋季全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.17, 2002 (Released:2003-01-17)
これまで組織論は、近代的個人を暗黙に想定して議論され、発展してきた。組織の維持は、目的(Why)に合意した人々ではなく、手段(What)に合意した人々の集まりによってなされるとされた。しかし我々の関心領域であるオープンソースコミュニティを捉えるためには、これまでの組織論のみでは言及できないという考察に至った。それは手段だけでなく、目的をも共有するような組織であるという推察によるものである。オープンソースソフトウェア開発グループに関する研究は既に様々な報告があるが、ユーザグループの組織化(Organizing)に関する研究は発展途上である。本研究では行為論的アプローチにより、一つの理解を提示するものである。
- 著者
- 村山隆雄
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.686, 2008-03
1 0 0 0 OA ブラウン新政権の首相権限改革 : イギリス憲法改革提案緑書の概要と大臣規範の改定
- 著者
- 廣瀬淳子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.684, 2008-01
1 0 0 0 OA 政府の大きさをめぐる議論
- 著者
- 西川明子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.683, 2007-12
1 0 0 0 OA 冷戦後のNATOのパートナーシップ政策の発展 : 日本とNATOの協力拡大を見据えて
- 著者
- 福田毅
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.677, 2007-06