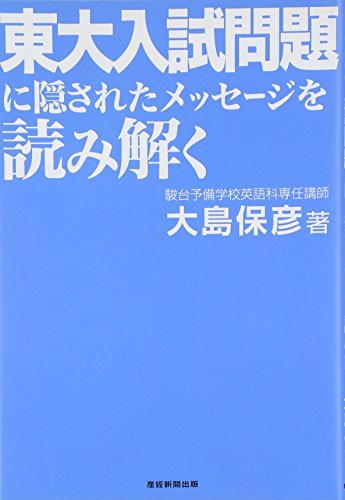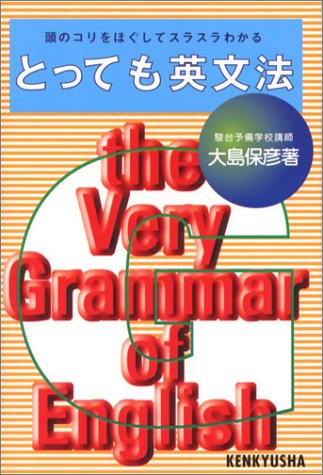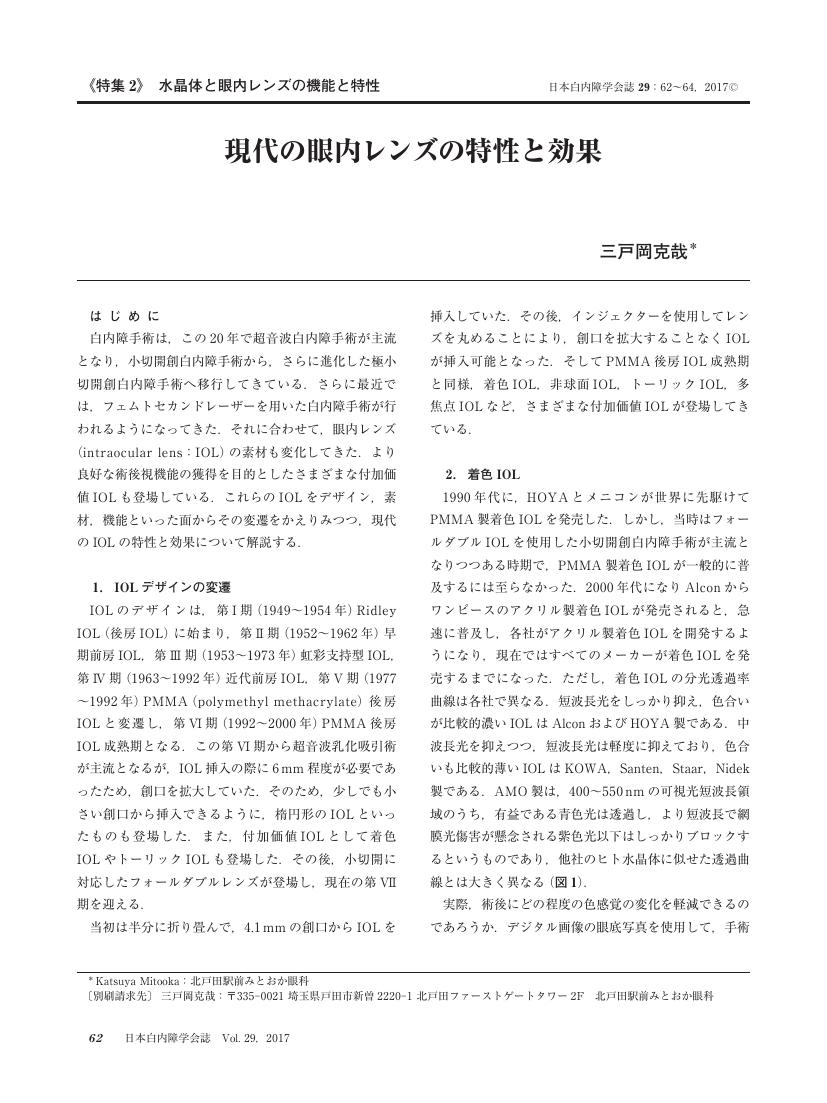1 0 0 0 OA NHK教育『できるかな』におけるナレーターの認識
- 著者
- 村野井 均 宮川 祐一
- 出版者
- 日本教育メディア学会
- 雑誌
- 教育メディア研究 (ISSN:13409352)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.28-38, 1995-12-01 (Released:2017-07-18)
『できるかな』は、NHK教育放送で21年に渡って放送された番組である。この番組には2つの映像が提示されていた。一人は男性主人公の「ノッポさん」であるが、彼は一言も話さなかった。もう一人は動物で、時々鳴き声をあげる「ゴン太くん」であった。一方、この番組には2つの音声が提示されていた。一つは「ゴン太くん」の声であり、もう一つは女性ナレーターの声である。主人公が話さない役であったため、この番組は子どもにとって音声と映像の統合が難しかった。190名の大学生の回想から、音声と映像を統合する過程に現れるつまづきを分析したところ、11.1%の学生が「ノッポさん」を女性と思ったことがあり、40.7%の学生が音声と映像の組み合わせをまちがった経験を持っていた。画面に現れないナレーターという人工的存在を認識するために、子どもは音声と映像の組み合わせを試行錯誤する経験と教育的支援が必要であることを論じた。
1 0 0 0 アングラ昭和史 : 世相裏の裏の秘事初公開
1 0 0 0 東大入試問題に隠されたメッセージを読み解く
- 著者
- 大島保彦著
- 出版者
- 日本工業新聞社 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 とっても英文法 : 頭のコリをほぐしてスラスラわかる
- 著者
- Petr Dobsak Marie Novakova Jarmila Siegelova Bohumil Fiser Jiri Vitovec Makoto Nagasaka Masahiro Kohzuki Tomoyuki Yambe Shin-ichi Nitta Jean-Christophe Eicher Jean-Eric Wolf Kou Imachi
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.75-82, 2006 (Released:2005-12-25)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 59 67
Background This study was designed to evaluate the effects of low-frequency electrical stimulation (LFES) on muscle strength and blood flow in patients with advanced chronic heart failure (CHF). Methods and Results Patients with CHF (n=15; age 56.5±5.2 years; New York Heart Association III - IV; ejection fraction 18.7±3.3%) were examined before and after 6 weeks of LFES (10 Hz) of the quadriceps and calf muscles of both legs (1 h/day, 7 days/week). Dynamometry was performed weekly to determine maximal muscle strength (Fmax; N) and isokinetic peak torque (PTmax; Nm); blood flow velocity (BFV) was measured at baseline and after 6 weeks of LFES using pulsed-wave Doppler velocimetry of the right femoral artery. Six weeks of LFES significantly increased Fmax (from 224.5±96.8 N to 340.0±99.4 N; p<0.001), and also PTmax (from 94.5±41.5 Nm to 135.3±28.8 Nm; p<0.01). BFV in the femoral artery increased after 6 weeks from 35.7±15.4 cm/s to 48.2±18.1 cm/s (p<0.05); BFV values at rest before and after 6 weeks of LFES did not differ significantly. Conclusions LFES may improve muscle strength and blood supply, and could be recommended for the treatment of patients with severe CHF. (Circ J 2006; 70: 75 - 82)
1 0 0 0 OA 風力発電のビジネスモデル ~メンテナンスで変わるリスクとバリュー~
- 著者
- 西山 裕也
- 出版者
- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会
- 雑誌
- 風力エネルギー (ISSN:03876217)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.414-419, 2014 (Released:2016-09-30)
1 0 0 0 OA 現代の眼内レンズの特性と効果
- 著者
- 三戸岡 克哉
- 出版者
- 日本白内障学会
- 雑誌
- 日本白内障学会誌 (ISSN:09154302)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.62-64, 2017 (Released:2017-07-03)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 庄谷 邦幸 並川 宏彦 種田 明 Kuniyuki Syoya Hirohiko Namikawa Akira Oita
- 雑誌
- 総合研究所紀要 = ST. ANDREW'S UNIVERSITY, BULLETIN OF RESEARCH INSTITUTE (ISSN:09187758)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.45-54, 1995-12-20
1 0 0 0 OA 近世殉国一人一首伝 : 4巻
1 0 0 0 OA メンソールタバコが原因と示唆された急性好酸球性肺炎の2例
- 著者
- 中村 和芳 須加原 一昭 一安 秀範 江崎 紀浩 堀尾 雄甲 浦本 秀志 松岡 多香子 今村 文哉 小松 太陽 天神 佑紀 松本 充博 杉本 峯晴 興梠 博次
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会
- 雑誌
- 気管支学 (ISSN:02872137)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.223-229, 2015-03-25 (Released:2016-10-29)
背景.メンソールタバコが原因と示唆された急性好酸球性肺炎(acute eosinophilic pneumonia : AEP)の2例を経験した.症例1. 16歳.男性.非メンソールタバコを2年間喫煙していたが1カ月間の禁煙後, 1カ月前からメンソールタバコの喫煙を再開した.突然の発熱と呼吸困難のため受診し,胸部X線写真およびCTにて右肺優位にすりガラス陰影,小葉間隔壁の肥厚,両側胸水貯留を認めた.症例2. 18歳男性.メンソールタバコの喫煙を開始し, 3週間後,乾性咳嗽,発熱のため受診した.胸部X線写真およびCTにて両肺にすりガラス陰影,小葉間隔壁の肥厚,両側胸水貯留を認めたため入院となった. 2症例とも気管支肺胞洗浄液(bronchoalveolar lavage fluid : BALF)中に著明な好酸球増多を認めたためAEPと診断し,ステロイド投与により解熱し,呼吸困難,すりガラス陰影は速やかに消失した.結語.メンソールタバコによると推測されるAEPの2例を経験した. AEPの原因としてメンソールタバコが考えられ,重要な症例と考えられたため文献的考察を含めて報告する.
1 0 0 0 OA 関節リウマチのリハビリテーションのエビデンスを求めて
- 著者
- 佐浦 隆一 田中 一成
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.310-314, 2010-05-18 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 〈座談会〉精密工学の25年前,今,そして未来
- 著者
- 学生編集委員会
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.165-172, 2009-01-05 (Released:2010-11-30)
1 0 0 0 OA シンボリック相互作用論とG.H.ミード ―H.ブルーマーと批判者たちの応酬をめぐって―
1 0 0 0 OA 顔の魅力度が記憶に及ぼす影響 ―異なる評定課題を用いた検討―
- 著者
- 藏口 佳奈 蘆田 宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第75回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.3AM054, 2011-09-15 (Released:2019-02-02)
1 0 0 0 OA フッ素 : 推測と発見,単離をめぐる人々(歯科とフッ素の歴史(第1回))
- 著者
- 丹羽,源男
- 出版者
- 日本歯科医史学会
- 雑誌
- 日本歯科医史学会会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, 1995-09-30
歯科をはじめ,今日の生活に広く活用されているフッ素は,発見がたいへん困難で「化学者泣かせ」だった.フッ素を人類にもたらした3人の化学者を紹介する.
1 0 0 0 OA 英語動名詞管見
- 著者
- 東 長生
- 出版者
- 大阪社会事業短期大学社会問題研究会
- 雑誌
- 社會問題研究 (ISSN:09124640)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1・2・3, pp.119-124, 1970-10-01
1 0 0 0 OA リテラシー形成理論における「批判」概念と実践構想の比較検討
- 著者
- 竹川 慎哉
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.13-24, 2004-03-31 (Released:2017-04-22)
本研究の目的は,リテラシー形成理論と実践構想の比較検討をとおして,リテラシー形成における「批判」の意味を考察することにある。ここでは,アメリカにおいて,相互に議論を交わしている批判的思考論文化的リテラシー論そして批判的リテラシー論をとりあげる。リテラシー形成理論において,「批判」という言葉は多義的である。批判的思考論において,批判的であるということは,客観的・論理的・政治的に中立的になっていくことを意味し,それを支えるスキルの獲得が何より重視される。文化的リテラシー論は,アメリカ国民として政治的・文化的に生活するために必要な選ばれた知識の獲得が,批判的な思考を可能にすると強調する。しかし,前者において,スキルの強調は,学ぶ内容の無視へとつながり,学問の境界や支配的文化に無批判になってしまっている。そして,後者においては,ナショナル・アイデンティティとしての共通知識の強調が支配的文化への同化を促すものになっている。それらと対照的に,批判的リテラシー論によれば,「批判」とは,個人の私的な問題とされるものを社会構造の公的な問題として位置づける意識を持ち,その関係を問い直すこととして理解されている。さらにそれは,文化の差異性やこれまで排除されてきた他者のF声」に対する応答も含むものである。このような政治的かつ倫理的な意味において,「批判」がリテラシー形成に組み込まれることが求められている。
- 著者
- 沼津 直樹 藤井 範久 森本 泰介 小池 関也
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム (ISSN:13487116)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.21-32, 2020 (Released:2021-07-16)
- 参考文献数
- 14
本研究ではキッカーにゴールのさまざまな地点へシュートさせ, ゴールキーパー (GK) が実際にダイビング動作によって対応した試技のシュート動作を対象に, GKがシュートの飛来する地点を予測する際に有用なキッカーやボールの動きについてバイオメカニクス的に検討することを目的とした. その結果, 右利きのキッカーが自身の左方向へシュートを行う際, 軸脚の足部や体幹の回旋角度が, 右方向へシュートする場合よりもより左方向へ向くことが明らかとなった. また, シュートがGKの近くまたは遠くに飛来するのかといったシュートの距離や飛来するシュートの高さについては, インパクト後のボールの軌道から素早く判断し, 対応しなければならないことが明らかとなった.