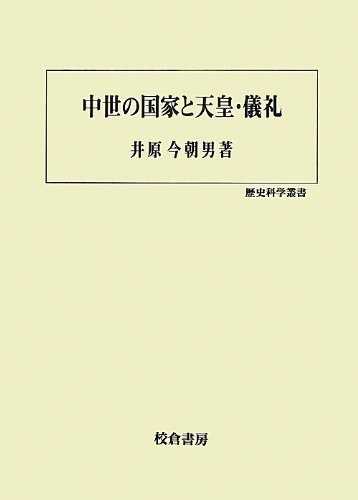1 0 0 0 OA 罪刑法定主義の中国における実践
- 著者
- 張 明楷
- 出版者
- 日本比較法研究所
- 雑誌
- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.31-56, 2015-03-30
「罪刑法定主義」について,新中国(中華人民共和国)が建国されて以来,三つの時代に分けてその変遷を捉えることができる。すなわち,⑴刑法典が存在しなかった時代,⑵旧刑法の時代,⑶新刑法の時代である。(以上Ⅰ) 「法律主義」については,犯罪とその効果を規定する法律は,全国人民代表大会及びその常務委員会しか定めることができず,各省の人民代表大会は刑法の罰則を定めることができない。これについて,慣習法,判例,命令が問題になる。(以上 Ⅱ) 「遡及処罰の禁止」については,2011年4月以前は,中国の司法機関は遡及効に対して,当時採用していた犯行時の規定あるいは刑罰が軽い規定によるという原則(刑法第12条)を遵守していたが,2011年2月25日に《刑法修正案㈧》が可決された後は,司法解釈に遡及処罰の規定が現れてきた。(以上Ⅲ) 「類推解釈」については,現行刑法が罪刑法定主義を定めて以来,中国における司法人員ができる限り類推解釈の手法を避けていることが理解できるが,それにもかかわらず,類推解釈の判決が依然として存在している。一方で,罪刑法定主義に違反することを懸念して,刑法を解釈することを差し控える現象もある。(以上Ⅳ) 「明確性」については,刑事立法に関する要請であり,立法権に加える制限だと考えられている。他の法理論においては,刑法理論のように法律の明確性を求めるものはないといえる。その意味で,罪刑法定主義の要請は,明確性の原則に最大の貢献をもたらした。(以上Ⅴ) 「残虐な刑罰の禁止」については,総合的に言えば,中国刑法で定められている法定刑は比較的厳格であり,経済犯罪においては少なくない条文に死刑が定められている。(以上Ⅵ)
1 0 0 0 OA 租特透明化法等の意義と限界 ―租税特別措置の透明性はどこまで高まったのか―
- 著者
- 田中 秀明
- 出版者
- 会計検査院
- 雑誌
- 会計検査研究 (ISSN:0915521X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.57-78, 2017-03-17 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA プロキノ研究史がかかえる問題
- 著者
- 佐藤 洋
- 出版者
- 立命館大学国際言語文化研究所
- 雑誌
- 立命館言語文化研究 = 立命館言語文化研究 (ISSN:09157816)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.99-110, 2011-01
1 0 0 0 OA 冬季の海上の層積雲の構造と反射率
- 著者
- 菊地 勝弘 遊馬 芳雄 谷口 恭 菅野 正人 田中 正之 早坂 忠裕 武田 喬男 藤吉 康志
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.715-731, 1993-12-25 (Released:2009-09-15)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 2
冬季の海上の層積雲の雲頂の構造と反射率の関係を調べるために、航空機によるステレオ写真観測法を使った観測が1989年1月から1991年1月にわたって、日本海の若狭湾沖および奄美諸島周辺の太平洋上で行われた。最初に、雲頂高度と反射率との間の関係が調べられ、両者の間にはかなりよい相関が認められた。特に奄美諸島周辺での観測では高い相関が認められた。次にCloud area ratio(雲の領域率)と雲頂の反射率との関係が調べられた。その結果、低い反射率の雲域では雲頂高度が比較的低くて雲層が薄く、また、その高度差は大きく、雲頂の形状は鋸の歯のように鋭かった。一方、高い反射率の雲域では雲頂高度が高くて雲層が厚く、そして一様で形状は平で台形のような形をしていた。しかし、奄美諸島北部の例では、雲頂高度が他の2例に比して低く、しかも最高雲頂高度と最低雲頂高度との高度差が400m以上もある層積雲であったにもかかわらず、その反射率は比較的高かった。この反射率の違いはliquid water pathの差によるものと推定される。
1 0 0 0 OA 高分子ラテックスへの限りない魅力
- 著者
- 沖倉 元治
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.5, pp.303-304, 1993 (Released:2007-07-09)
- 著者
- 岡 孝和 小山 央
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.25-31, 2012-01-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
自律訓練法は不安,抑うつ,怒りなどの陰性感情を低下させ,自己認知を積極的なものに変化させ自己受容を促すという心理的効果がある.練習中,中心後回などの手足の感覚に関連する部位に加えて,前頭前皮質や島皮質など,内部感覚や情動に関連する皮質機能の活動が亢進する.両腕が「重たい」,「温かい」という公式を裏づけるように,骨格筋の弛緩と末梢皮膚温の上昇が生じる.交感神経活動に対しては抑制的に作用する.迷走神経活動に関しては,心臓迷走神経活動を賦活する一方で,消化管を支配する迷走神経機能亢進状態に対しては抑制的に作用する.さらに視床下部-下垂体-副腎皮質系を抑制し,機械的疼痛閾値を上昇させる.
1 0 0 0 OA 天平の疫病大流行 -交通の視点から-
- 著者
- 市 大樹
- 出版者
- 公益財団法人 国際交通安全学会
- 雑誌
- IATSS Review(国際交通安全学会誌) (ISSN:03861104)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.96-104, 2021-10-31 (Released:2021-10-31)
- 参考文献数
- 21
聖武天皇の治世下にあたる735(天平7)年・737(天平9)年、深刻な被害をもたらした疫病が起こった。本稿では、この疫病の実態を多面的に浮かび上がらせることを目的として、その被害状況について確認した上で、その交通に関わる諸現象を中心に検討を行った。具体的には、疫病を退散させるための道饗祭、対外交通に伴う疫病流入の可能性、治療法を記した太政官符の伝達方法、藤原麻呂という貴族に関わる呪符木簡と奥羽連結道路の建設事業について取り上げた。
1 0 0 0 OA アメリカにおける初期精神医療と家庭小説
- 著者
- 鈴木 淑美
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.33, pp.135-150, 1999-03-25 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 65
1 0 0 0 OA 神話の現場から見た古事記 ―中国四川省大涼山彝族の神話をモデルとして―
- 著者
- 工藤 隆
- 出版者
- 一般社団法人 アジア民族文化学会
- 雑誌
- アジア民族文化研究 (ISSN:13480758)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-36, 2002-03-31 (Released:2020-04-01)
1 0 0 0 中世の国家と天皇・儀礼
1 0 0 0 OA 疼痛認知における体性感覚と情動反応の分離に着眼した慢性疼痛治療法の開発
痛みは不快な情動を生み出す感覚刺激とされるが、心の状態が痛みの感受性にも影響を与える。本研究の成果から、慢性的に痛みがあると不快な情動を生み出す脳内神経回路が活性化していることを全脳イメージングの解析から明らかにできた。また、気持ちが落ち込んでいる状態(抑うつ状態)では、些細な刺激でも痛みとして認識されることが明らかになった。特に、前帯状回皮質と呼ばれる情動に関係が深い脳領域の活動が高まっていると痛みに対して過敏になることも示すことができた。これらのことから、難治化した痛みに対しては、情動面に配慮した治療法が有効であることが提唱できる。
- 著者
- 矢萩 裕一
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.227-231, 2020 (Released:2020-08-07)
- 参考文献数
- 17
【緒言】リンパ系腫瘍では,ステロイド治療は症状緩和に加えて抗腫瘍効果も期待できる.生命予後3週間以下と見込まれた終末期リンパ系腫瘍症例ながら,ステロイドの緩和治療効果と抗腫瘍効果により,在宅療養・通院治療が可能となった2症例を報告する.【症例1】55歳女性.腸管症関連T細胞リンパ腫の患者.再発時に高ビリルビン血症とPS悪化を認めた.症状緩和目的のステロイド治療はそれのみならず抗腫瘍効果も発揮し,3カ月間の在宅療養が可能となった.【症例2】63歳男性.ATLL急性型の患者.VCAP療法を中心に化学療法を施行したが,再発再燃を繰り返したため,症状緩和目的でステロイド治療を行った.ステロイドは抗腫瘍効果も発揮し,8カ月にわたる在宅療養が可能となった.【結語】終末期リンパ系腫瘍患者において,ステロイド治療は症状緩和と抗腫瘍効果の両方を視野に入れた,強力な選択肢になり得ると考えられた.
1 0 0 0 OA 1988年ネパール・インド国境地震の災害調査
- 著者
- 藤原 悌三 佐藤 忠信 久保 哲夫 村上 ひとみ
- 出版者
- 京都大学防災研究所
- 雑誌
- 京都大学防災研究所年報. A (ISSN:0386412X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.A, pp.71-95, 1989-04-01
The earthquake we have investigated took place in the Nepal-India border region in the earlymorning on 21 August 1988. This earthquake in the southeastern zone of Nepal close to the bor-der of the State of Bihar, India registered 6.6 on the Richter Scale. Its focal depth was assumedto be 57 km. In Bihar State, India, 282 persons died, 3766 were injured and 150, 000 houses weredamaged. In Nepal, 721 persons died, more than 5000 were injured and 100, 000 houses weredamaged. Most the houses damaged had been constructed of stone cemented with mud mortar, unburnt bricks, or burnt brick masonry. There are many wooden houses and few reinforced con-crete buildings in the effected area. We did not find any serious damage to those structures.This is a survey report, in which the damage to human loss and the collapse of buildingstructures done by the earthquake are introduced and discussed. We estimated the fault zone ofthis earthquake from the post-earthquake records. The intensity of ground shaking around theeffected areas is discussed in terms of assumed fault parameters and the geological condition ofthe surface layer. We also prepared a questionnaire asking inhabitants. The intensity distribu-tion estmated from their information is compared with the intensity derived from seismographicdata. Based on our laboratory tests of sand specimens collected from riversides where liquefac-tion occurred during the earthquake, the maximum acceleration near the epi-center is also esti-mated. The strength of the structures in the effected areas is estimated and compared with theactual damage done. On the basis of our survey and analytical results we present some recom-mendations for the mitigation of earthquake disasters in these areas.
1 0 0 0 近代日本教科書史研究 : 明治期検定制度の成立と崩壊
1 0 0 0 OA 定期種痘の間隔と免疫反応の検討
1 0 0 0 OA ラトケ嚢胞
- 出版者
- 一般社団法人 日本内分泌学会
- 雑誌
- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.Suppl.HPT, pp.45-48, 2014-09-20 (Released:2014-10-07)
1 0 0 0 OA 診断と治療の難しかった症例
- 出版者
- 一般社団法人 日本内分泌学会
- 雑誌
- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.Suppl.HPT, pp.21-34, 2016-02-20 (Released:2016-04-19)
1 0 0 0 OA Rathke's Cleft Cyst with Short-Term Size Changes in Response to Glucocorticoid Replacement
- 著者
- Hiroshi MARUYAMA Yasumasa IWASAKI Makoto TSUGITA Naoko OGAMI Koichi ASABA Toshihiro TAKAO Hiromichi NAKABAYASHI Keiji SHIMIZU Kozo HASHIMOTO
- 出版者
- The Japan Endocrine Society
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.425-428, 2008 (Released:2008-05-10)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 12 13
An 81-year-old man was admitted to our hospital because of general fatigue. Hormonal examination showed that he had panhypopituitarism and central diabetes insipidus. MRI imaging revealed the presence of large cystic mass with suprasellar extension in his hypothalamo-pituitary region. Interestingly, the cystic mass shrank following the start of glucocorticoid replacement, and since then relatively high doses of cortisol administration were needed to prevent the re-enlargement of cystic size. Because of the concern over possible side effects of supraphysiological doses of glucocorticoid replacement, surgical treatment was eventually carried out, confirming the pathological feature of Rathke's cleft cyst. The present case suggests that the inflammatory nature of Rathke's cleft cyst may explain the observed short-term size changes in response to glucocorticoid administration.
1 0 0 0 OA ラトケ嚢胞の病理、画像診断と外科治療 - 最新の知見-
- 著者
- 立花 修
- 出版者
- Kinki Brain Tumor Pathology Conference
- 雑誌
- Neuro-Oncologyの進歩 (ISSN:18800742)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.12-21, 2015-09-12 (Released:2015-09-12)
- 参考文献数
- 53
Rathke cleft cysts (RCCs) are benign cystic lesions of the sella that arise from remnants of the embryonic Rathke residual pouch. RCCs are common incidental findings in 4-33% of autopsy cases and on imaging, and most remain asymptomatic. However, RCCs can become sufficiently large and rupture to cause severe headache, visual field defects and hypothalamic pituitary dysfunctions. Asymptomatic RCCs are typically followed by serial imaging, while symptomatic RCCs are managed by surgical decompression. Although a headache and the visual disturbance are improved by surgical treatment, the pituitary insufficiency is not often improved. It is thought that an irreversible disorder due to the local chronic inflammation involves the pituitary gland. MRI reveals well-demarcated homogenous lesions with variable intensity that is highly dependent on the protein concentration of cyst contents, which can range from clear, CSF-like fluid to thick, mucoid material. Rates of recurrence after surgical treatment range from 11 to 18 % in large series, and higher rates of recurrence are associated with inflammation and reactive squamous metaplasia in the cyst wall. As the natural history of RCCs remains unclear and the mechanism of progression of these cysts is not understood, it might be difficult to determine when we should do the intervention of the surgery.