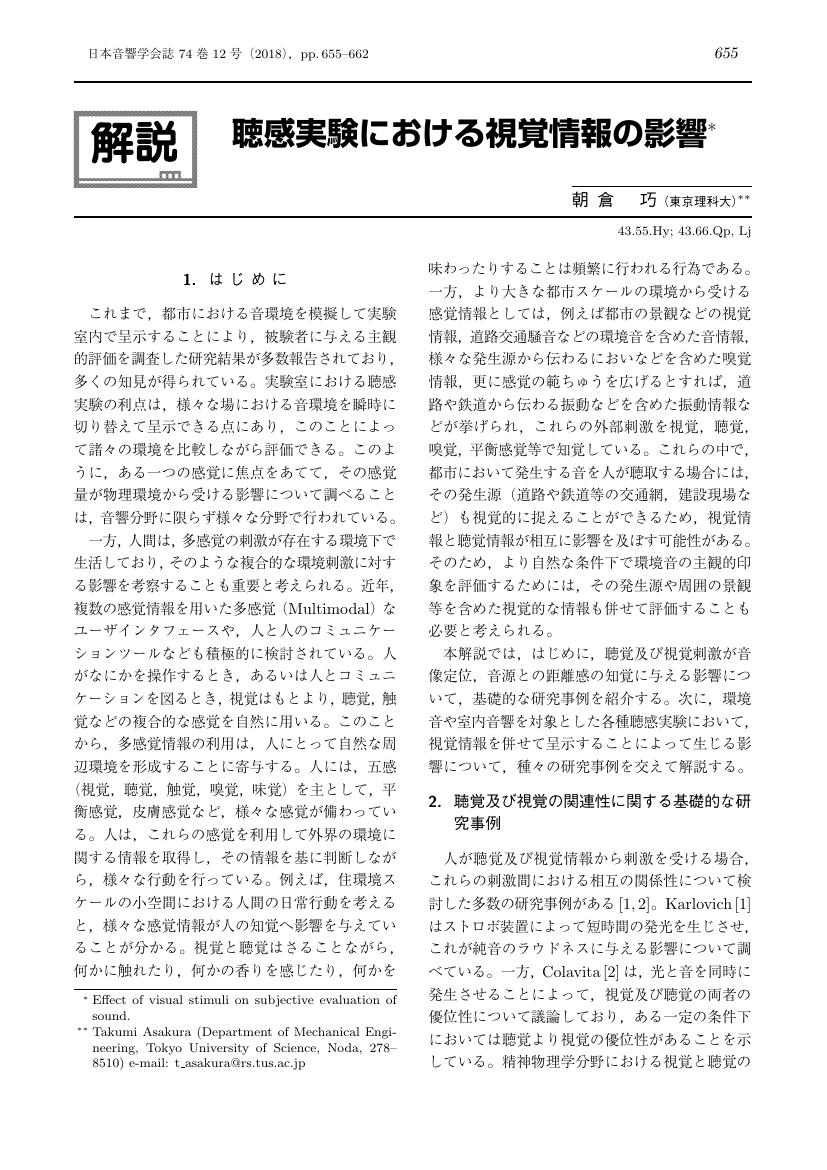1 0 0 0 OA 聴感実験における視覚情報の影響
- 著者
- 朝倉 巧
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.12, pp.655-662, 2018-12-01 (Released:2019-06-01)
- 参考文献数
- 39
- 著者
- 谷口 祐介
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.209-212, 2022 (Released:2022-04-27)
- 参考文献数
- 4
症例の概要:患者は64歳女性.上顎前歯部欠損と下顎両側遊離端欠損による咀嚼障害を主訴に来院した.咬合平面の不整や咬合崩壊を認め,これらを改善するために,上下顎欠損部のインプラント補綴を伴う咬合再構成を行った.考察:インプラント固定性補綴歯科治療により咀嚼機能が向上した.最終補綴装置装着後約4年経過したが,全顎的な補綴処置を行うことによって咬合の安定が図られたことと継続的なメインテナンスによって残存歯ならびにインプラント部が経年的に維持できたと考えられた.結論:本症例では,欠損部のインプラント補綴と残存歯の歯冠修復による咬合挙上を伴う咬合再構成を行ったことで,咀嚼障害が改善された.
1 0 0 0 OA 内視鏡によるH. pylori感染診断の注意点
- 著者
- 川村 昌司
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.2519-2529, 2018 (Released:2018-12-20)
- 参考文献数
- 14
Helicobacter pylori(H. pylori)感染は胃癌などの疾患リスクと関連しており,内視鏡観察時にはH. pylori感染状態に合わせた好発疾患・好発部位に注意する必要がある.内視鏡によるH. pylori感染診断は未感染・現感染・除菌後(自然除菌含む)の3つの状態に特徴的な胃粘膜所見を用いて行い,その局在と頻度は“胃炎の京都分類”にまとめられている.H. pylori未感染の診断は胃角までのRAC(regular arrangement of collecting venules)が有用であり,現感染診断はびまん性発赤・内視鏡的萎縮,除菌後診断には地図状発赤などの所見を用いて診断する.一方,内視鏡による感染診断の注意点として,PPI(proton pump inhibitor)などの薬剤により未感染例でもRACが不明瞭化すること,現感染例・除菌後例でも体部の集合細静脈がみられる例があること,びまん性発赤の判定が難しい例があることなどが挙げられる.内視鏡的なH. pylori感染診断は一つの所見にとらわれずに総合的に判断する必要がある.また,H. pylori感染診断のみに注視しすぎて内視鏡本来の目的である病変発見を忘れないように,バランスのとれた内視鏡観察を行う必要がある.
1 0 0 0 第二次世界大戦秘話
- 出版者
- 日本リーダーズダイジェスト社
- 巻号頁・発行日
- 1963
1 0 0 0 OA 地域研究の対象とアプローチ再考
- 著者
- 宮地 隆廣 Takahiro Miyachi
- 出版者
- 同志社大学言語文化学会
- 雑誌
- 言語文化 = Doshisha Studies in Language and Culture (ISSN:13441418)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.377-400, 2012-03-10
本稿は、地域研究の扱う範囲とアプローチについて、先行研究に対する批判的検討を通じ、その妥当なあり方を提示する。第1に、地域研究の扱う知識の範囲は特定の空間、時代、テーマおよび方法論によって制限されるべきではない。第2に、研究に値する知識は、既存の地域イメージを覆すものか、社会や学界で価値の認められるテーマに関連するものに限られる。第3に、研究のアプローチは、科学的なものと多声的なものに分けられる。
1 0 0 0 価値形態論と交換過程論
1 0 0 0 OA 教授・学習研究におけるATIパラダイムと適性理論
- 著者
- 並木 博
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.117-127, 1993-03-30 (Released:2012-12-11)
- 参考文献数
- 92
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 柏崎市史資料集
- 著者
- 柏崎市史編さん委員会 編
- 出版者
- 柏崎市史編さん室
- 巻号頁・発行日
- vol.近現代篇 2 (柏崎県史資料), 1982
1 0 0 0 OA 新生仔カニクイザルの体温変動
- 著者
- 小野 孝浩 鈴木 通弘 成田 勇人 長 文昭
- 出版者
- Japanese Association for Laboratory Animal Science
- 雑誌
- Experimental Animals (ISSN:00075124)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.293-296, 1989-10-01 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
カニクイザル新生仔の健康管理上の一指標として体温 (直腸温) を取り上げ, 新生仔における体温の変動についていくつかの基礎的検討を試みた。生後0日齢の新生仔ザルの体温は, 母ザルにより上手に哺育されていたもの183頭では33.0~37.7℃, 哺育されていなかったもの21頭では24.1~34.8℃の範囲にあった。母ザルの哺育能が良好である場合の新生仔の娩出直後からの体温変化をみると, 娩出時は約36℃と母ザルの体温に近似していたが, その後急激に下降し40~50分後に32~33℃で最低となった。その後, 新生仔の体温は上昇に転じ, 生後180~240分で36~37℃となり安定した。一方, 帝王切開術にて娩出し保温せずに個別ケージに収容された新生仔の体温は, 娩出直後37~38℃であったものが, 120分後には29~32℃にまで低下した。
1 0 0 0 OA 片脚着地動作における着地環境の違いが膝関節と体幹運動に与える影響
- 著者
- 猪股 美沙紀 桑原 亜海 石崎 裕佳 齊藤 展士 平田 恵介
- 出版者
- Saitama Physical Therapy Association
- 雑誌
- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.21-24, 2022 (Released:2022-06-04)
- 参考文献数
- 11
【はじめに】片脚着地動作における非接触型前十字靭帯損傷では膝関節外反の他に体幹側屈が危険因子と言われている。膝関節外反が生じやすい着地環境には傾斜面が想定される。本研究は,傾斜面環境での片脚着地動作において,衝撃吸収時の対応戦略を明らかにすることを目的に動作解析を行った。【方法】成人男女9名にて,傾斜面,および平坦面への片脚着地動作における膝関節と体幹関節角度の違いを比較した。【結果】膝関節外反最大角度は平坦面に比べ,傾斜面で有意に大きかった。着地により骨盤の着地脚側への傾斜,体幹の非着地脚側への側屈角度変化が生じたが,傾斜面の方が有意に小さかった。【考察】傾斜環境では膝関節外反が増大した一方,体幹の動揺を抑える対応が平坦面よりも行われていた。これは,姿勢の平衡維持や視線の安定を図る前庭と視覚の制御により体幹と頭頸部の固定性を高める課題依存的な戦略が傾斜環境で行われた可能性がある。
- 著者
- Michiko Kano Lukas Van Oudenhove Patrick Dupont Tor D. Wager Shin Fukudo
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.250, no.3, pp.137-152, 2020 (Released:2020-03-03)
- 参考文献数
- 124
- 被引用文献数
- 3 8
When patients present with persistent bodily complaints that cannot be explained by a symptom-linked organic pathology (medically unexplained symptoms), they are diagnosed with ‘functional’ somatic syndromes (FSS). Despite their prevalence, the management of FSS is notoriously challenging in clinical practice. This may be because FSS are heterogeneous disorders in terms of etiopathogenesis. They include patients with primarily peripheral dysfunction, primarily centrally driven somatic symptoms, and a mix of both. Brain-imaging studies, particularly data-driven pattern recognition methods using machine learning algorithms, could provide brain-based biomarkers for these clinical conditions. In this review, we provide an overview of our brain imaging data on brain-body interactions in one of the most well-known FSS, irritable bowel syndrome (IBS), and discuss the possible development of a brain-based biomarker for FSS. Anticipation of unpredictable pain, which commonly elicits fear in FSS patients, induced increased activity in brain areas associated with hypervigilance during rectal distention and non-distention conditions in IBS. This was coupled with dysfunctional inhibitory influence of the medial prefrontal cortex (mPFC) and pregenual anterior cingulate cortex (pACC) on stress regulation systems, resulting in the activated autonomic nervous system (ANS) and neuroendocrine system stimulated by corticotropin-releasing hormone (CRH). IBS subjects with higher alexithymia, a risk factor for FSS, showed stronger activity in the insula during rectal distention but reduced subjective sensitivity. Reduced top-down regulation of the ANS and CRH system by mPFC and pACC, discordance between the insula response to stimulation and subjective sensation of pain, and stronger threat responses in hypervigilance-related areas may be a candidate brain-based biomarker.
- 著者
- 名越 泰秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.554-559, 2019
<p>身体症状症および関連症群 (身体表現性障害) の病態は, 薬物療法の観点では, 強迫, 不安・恐怖, 怒りに分類される. </p><p>強迫に対しては, SSRIが有効である. SSRIで効果が不十分な場合は, D<sub>2</sub>受容体への親和性が高い抗精神病薬による増強療法が有効である. 早急な改善が必要な場合は, NaSSAの併用が有用である. </p><p>不安・恐怖に対しては, ベンゾジアゼピン系抗不安薬, SSRIが有効である. 効果が不十分な場合, MARTAなどの抗精神病薬の併用が考えられる. また, 不安や恐怖の中枢である扁桃体の過活動に対するα<sub>2</sub>δリガンドの併用も選択肢の1つになりうる. </p><p>怒りに対しては, 症例によっては抑肝散などの漢方薬やMARTAなどの抗精神病薬の投与を試みてもよいと思われる.</p>
1 0 0 0 OA 身体症状症および関連症群 (身体表現性障害) の薬物療法はどこまで可能になったのか?
- 著者
- 名越 泰秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.554-559, 2019 (Released:2019-09-01)
- 参考文献数
- 27
身体症状症および関連症群 (身体表現性障害) の病態は, 薬物療法の観点では, 強迫, 不安・恐怖, 怒りに分類される. 強迫に対しては, SSRIが有効である. SSRIで効果が不十分な場合は, D2受容体への親和性が高い抗精神病薬による増強療法が有効である. 早急な改善が必要な場合は, NaSSAの併用が有用である. 不安・恐怖に対しては, ベンゾジアゼピン系抗不安薬, SSRIが有効である. 効果が不十分な場合, MARTAなどの抗精神病薬の併用が考えられる. また, 不安や恐怖の中枢である扁桃体の過活動に対するα2δリガンドの併用も選択肢の1つになりうる. 怒りに対しては, 症例によっては抑肝散などの漢方薬やMARTAなどの抗精神病薬の投与を試みてもよいと思われる.
- 著者
- 宇藤 健司 小林 雅夫 佐々木 登 武川 寿 小松 攻 加賀美 武 原 寛美
- 出版者
- 社団法人日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 : 日本リハビリテーション医学会誌 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.6, 1985-11-18
1 0 0 0 不定愁訴症候群
- 著者
- 阿部 達夫
- 出版者
- 東邦大学医学会
- 雑誌
- 東邦医学会雑誌 (ISSN:00408670)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.p318-327, 1982-09
1 0 0 0 心因性視覚障害
- 著者
- 気賀沢 一輝
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.467-472, 2016
1 0 0 0 IR 特性不安とストレス負荷が記憶成績に及ぼす影響
- 著者
- 木村 浩子
- 出版者
- 日本歯科心身医学会
- 雑誌
- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.73-83, 2007
Excessive clenching of the teeth due to physical or psychological tension or stress can result in excessive air swallowing.This study sought to investigate and evaluate the characteristics of such patients in terms of both their physical condition in the head and neck region and relevant psychological and social factors.<BR>The subjects consisted of 187 patients (57males and130females) having chief complaints of aerophagia symptoms who visited the psychosomatic medicine clinic at the head and neck department of the Tokyo Medical and Dental University.52.4%were in their twenties and thirties and 69.5%were female.<BR>The principal psychological and social stress factors tended to be study and work related among younger patients, and family problems among female patients.Most of the patients exhibited depression, anxiety, neurosis and a tendency towards autonomic imbalance, and also tended to complain of neck or shoulder pain, headache, oral or pharynx paresthesia and symptoms of quasi-temporomandibular arthrosis in the head and neck region.<BR>The degree of improvement of aerophagia symptoms and a tendency to change doctors too frequently in order to find more appropriate treatment were both considered to be related to depression.<BR>The explanation of habitual teeth clenching, the existence of psychological and social stress factors, the mechanism of air swallowing, and ways to control clenching was useful in helping patients to reduce their aerophagia symptoms.