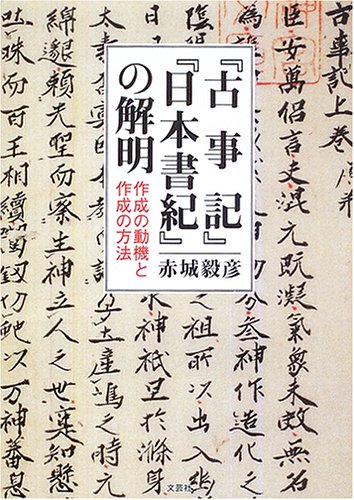- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, 1980
1 0 0 0 OA リチウムイオン二次電池の安全性と評価試験
- 著者
- 青木 雄一 河合 秀己 奥山 新
- 出版者
- 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会
- 雑誌
- マイクロエレクトロニクスシンポジウム論文集 第22回マイクロエレクトロニクスシンポジウム (ISSN:2434396X)
- 巻号頁・発行日
- pp.187-190, 2012 (Released:2020-08-12)
1 0 0 0 コモンメンタルディジーズの疫学
- 著者
- 中根 允文
- 出版者
- 一般社団法人日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, 2007-01-01
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 琵琶湖博物館研究調査報告
- 出版者
- 滋賀県立琵琶湖博物館
- 巻号頁・発行日
- 1998
1 0 0 0 『古事記』『日本書紀』の解明 : 作成の動機と作成の方法
1 0 0 0 OA 因幡の白兎説話考
- 著者
- 石破 洋 Hiroshi ISHIBA
- 雑誌
- 島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.A1-A13, 1993-03-30
1 0 0 0 OA ポール・ヴァレリーにおける「錯綜体」の概念について : 感性とのかかわりにおいて
- 著者
- 森本 淳生
- 出版者
- 京都大学フランス語学フランス文学研究会
- 雑誌
- 仏文研究 (ISSN:03851869)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.95-105, 1995-09-01
1 0 0 0 IR 時間不安,タイプA行動パターンと失敗傾向の関連性
- 著者
- 川原 正広 現代行動科学会誌編集委員会
- 出版者
- 現代行動科学会
- 雑誌
- 現代行動科学会誌 (ISSN:13418599)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.1-8, 2006
我々は仕事の期日が迫っているときや人との待ち合わせに遅れそうな時、"時間がない"や"時間が足りない"といった時間的プレッシャーを感じることがよくある。このような時間的なプレッシャーは時間的切迫感と呼ばれる。Winnubst(1988)はこの時間的切迫感を時間に対する不安の典型的な現象の一つであるとし、時間的不安と呼んでいる。生和・内田(1991)は、時間不安があらゆる不安に共通した不安であり、その傾向が強い人は時間に追い立てられ、落ち着きのない生活態度を余儀なくされると述べている。時間の経過が不安の対象となる原因は、時間と課題の難易度が結びつくことによる情報処理量に対する時間的制約感と考えられている(生和・内田,1991)。また折原(1998)は、時間のイメージや時間的評価が時間不安と深く関連することや、不安感覚が個人の時間的評価や時間イメージによって大きく異なることを指摘している。 さて時間的切迫感を主な特徴とする時間不安は、ストレスやタイプA行動パターン、強迫神経症など精神的健康や精神障害との関連が多く検討されている。たとえばAbraham(1965)は金銭的強迫態度と時間に対する強迫態度の関連について検討を行ない、強迫神経症者の多くにお金と時間に対する強迫的態度が認められることを指摘している。またFriedman & Rosenman(1974)は、タイプA行動パターンを有する人の最も顕著な特徴として時間的切迫感をあげている。 またその一方で時間不安、タイプA行動パターンは、個人の失敗傾向との関連についての検討もいくつか行われている。Fletcher, McGeorge, Flin, Glavin & Maran(2002)は、ストレスフルな状態や、時間的に切迫した状態の中で発生する問題が能力の限界を超えたとき、状況の中に潜む潜在的なエラーと結びつき、安全についての意図しない結果につながると述べている。また、Wallace, Kass & Stanny(2002)は、失敗傾向とタイプA行動パターンの関連について、認知的失敗の傾向を測定するCognitive Failures Questionnaire(CFQ ; Broadbent, Activity Survey(JAS ; Zyzanski & Jenkins,1970)を用いて検討を行い、双方の間に関連性があること見出している。さらにRothroch & Kirlik(2003)は、熟練した作業者が、時間的に切迫した状況で、まれに起こる予測できない事象に適応することができず、エラーを起こす可能性があると指摘している。このような知見を考慮すると個人の時間不安やタイプA行動パターンと失敗傾向の間には何らかの関連が推測される。しかしHobbs(2001)は、時間的切迫感と失敗行動の関連について、物忘れなど記憶に関するエラーである「ラプス」や、適用するルールやルールの適用の仕方を知らないことによって生じる「知識ベースのミステイク」と関連すると考えられるが、その実証的な検証は全く行われていないと述べている。またWallace et al.(2002)も、認知的失敗とタイプA行動パターンの関連は今日まであまり深く検討されていないと述べている。HobbsやWallace et al.の知見は、時間的切迫感やタイプA行動パターンと失敗傾向の関連についての検討が不十分であることを指摘しているものと考えられ、双方の関連についてはさらなる実証的な検討が必要と言えるであろう。そこで、本研究では時間不安、タイプA行動パターン、失敗傾向に関する質問紙調査を用い、双方の関連性について検討を行った。
1 0 0 0 視聴者不在の「NHK常時同時配信を巡る議論」
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ニューメディア = Nikkei new media (ISSN:02885026)
- 巻号頁・発行日
- no.1689, pp.6-7, 2020-01-20
「放送を巡る諸課題に関する検討会」のメンバーからすると、まさか総務省がこのタイミングで手のひら返しをするとは思っていなかったのだろう。総務省の考え方に対して、厳しい批判も行われたという。むしろ、受信料を財源とする以上、受信料の支払者に全く…
1 0 0 0 OA チーターAcinonyx jubatusの性成熟に伴う行動と鳴き声の変化
- 著者
- 井門 彩織
- 出版者
- 動物の行動と管理学会
- 雑誌
- 動物の行動と管理学会誌 (ISSN:24350397)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.125-133, 2019-09-30 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 21
チーターの発情周期は個体関係や飼育環境によって変化することから,繁殖を効率よく進めていくためには,生理学的だけでなく行動学的モニタリングも重要である。しかしながら,性成熟に伴う発情指標行動や鳴き声の発現時期に関する研究は乏しい。このことから,行動学的モニタリングの開始時期の明確化と個体の行動特徴を正確に把握するために必要な発情指標行動の基礎的データを得ることを目的とした。2009年から2013年にかけて多摩動物公園で飼育されていた22頭のチーターを観察対象とし,発情指標行動と鳴き声の頻度,発現時期と鳴き声の変化の分析を行った。その結果,性成熟とされる生後24ヵ月に向かって行動,鳴き声共に変化することが明らかとなった。「匂いをかぐ」「グルーミング」は生後6ヵ月以内の早期から発現し,最も遅く発現した行動は,雌の「尿をかける」で3歳以降であった。その他の行動と鳴き声は,親離れが始まる生後15~17ヵ月から発現又は変化し始めると考えられた。しかし,成熟個体の行動発現頻度をみると4項目で個体差が見られた。このことから,雌雄の行動特徴と発現状況を生後15~17ヵ月以降から継続的に把握し,個体ごとの発情指標を選出する必要があると考えられる。
1 0 0 0 大麦と米の内在性酵素が混炊中の糖生成に及ぼす影響
- 著者
- 浜守 杏奈 大倉 哲也 香西 みどり
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.31, 2019
<p>【目的】これまで大麦と米の混炊において,それぞれを単独で炊飯するよりも混炊することで糖の生成量が増加すること,炊飯中に大麦と米の酵素が互いの粒内に移動していることを確認した。しかし,両内在性酵素がどのように麦飯の糖生成に関与しているかは明らかになっていない。本研究では米と大麦から調製した粗酵素液を用いて糖生成活性の測定を行い,それぞれの粗酵素液と基質を組み合わせて実際の炊飯を想定した混炊モデル実験を行うことによって混炊における大麦と米の酵素の特性および相互作用を検討した。</p><p>【方法】90%搗精米(日本晴),75%搗精丸麦(モッチリボシ)を試料とした。米および大麦から50mMリン酸バッファーを用いて粗酵素液を調製し,基質を可溶性デンプン,米・大麦から調製したデンプンとし,糖生成活性を測定した。還元糖はソモギーネルソン法,遊離糖はHPLCにより測定した。混炊モデル実験は,基質デンプン総量に占める大麦デンプンの割合が0,10,20,30,40,50,100%となるように調整し,糊化させた米・大麦デンプン混合液に同様の割合で混合した粗酵素液を反応させ,単独の値から算出される混炊の計算値と比較した。</p><p>【結果および考察】還元糖生成活性については大麦が米よりも顕著に高く,その至適温度は大麦の方が低いことが示された。モデル実験において大麦単独ではβ-アミラーゼによるマルトースの生成量が多いが,混炊による遊離糖の増加はグルコースが顕著であり,大麦の割合が高いほどその傾向は強かった。大麦の酵素が米粒内でも作用することでマルトースが生成され,米のα-グルコシダーゼが作用しやすくなり,混炊でのグルコースの増加に影響したことが推察された。</p>
1 0 0 0 IR 夢想起とイメージ及び心的境界の関連
- 著者
- 田村 英恵 吉田 加代子
- 出版者
- 立正大学心理臨床センター
- 雑誌
- 立正大学臨床心理学研究 (ISSN:21883017)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.13-22, 2019-03-31
本研究では,夢想起とイメージ及び心的境界の関連について検討することを目的とした。イメージ想起に関わる特性として鮮明性と統御性,心的境界として境界の脆さと曖昧さ,夢想起に関わる側面として頻度,鮮明性,内容,感覚モダリティを取り上げた。 大学生にQuestionnaire upon Mental Imagery の短縮版(QMI;Sheehan, 1967),Test ofVisual Imagery Control(TVIC;Gordon, 1949),日本語版境界尺度(JBQ;児玉,2013),夢想起に関する尺度(岡田,2000)を実施し,全ての項目に回答が得られた198名のデータを分析対象とした。境界尺度に関しては,「境界の脆さ」と「意識された境界の曖昧さ」について7 項目ずつ抽出したため,因子分析を行った。結果,因子1 「意識された境界の曖昧さ」6 項目,因子2 「境界の脆さ」4 項目,計10項目を以降の分析に用いた。 分析の結果,夢想起の鮮明性はイメージの鮮明性(QMI)及び心的境界と有意な正の相関が認められた。同様に,イメージの鮮明性(QMI)はイメージの統御性(TVIC)及び心的境界と有意な正の相関が認められた。また,イメージの鮮明性の高群が低群に比べて夢想起の鮮明性が有意に高いことが示された。したがってイメージと心的境界及び夢想起の関連性,なかでも夢想起の鮮明性とイメージの鮮明性,心的境界の関連性が示唆された。
- 著者
- 入江 さやか
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.11, pp.2-27, 2018
「平成29年7月九州北部豪雨」では、線状降水帯による猛烈な雨が福岡県と大分県にかけての同じ地域で降り続けた。短時間のうちに中山間地の中小河川が氾濫、流域の集落が浸水や土砂災害に見舞われ、福岡県・大分県での死者・行方不明者は42人にのぼった。NHK放送文化研究所は、被災した福岡県朝倉市・東峰村、大分県日田市の20歳以上の男女2,000人を対象に世論調査を実施した。本稿では、この調査結果や現地取材に基づき、避難行動や情報伝達をめぐる課題を検討した。回答者のうち、自宅などから避難場所など安全な場所に「立ち退き避難」をしたのは朝倉市で20%、東峰村で29%、日田市で21%だった。「立ち退き避難」の主要な動機は、避難勧告などの「情報」よりも、激しい雨や河川の水位の上昇などの異常な現象だった。また、「立ち退き避難」をした人の半数程度は自治体の指定避難場所以外の場所に移動していた。立ち退き避難者の多くが浸水した道路を通って移動しており、指定された避難場所にたどり着けなかったケースもあった。「土砂災害警戒情報」「記録的短時間大雨情報」などの防災気象情報や「避難勧告」「避難指示(緊急)」などの避難情報を知ったのは「NHKテレビ」と「行政からのメール」が主要な手段であった。災害時の情報入手が「メール」などネットメディアにシフトする中で、「テレビ・ラジオ」の防災・減災情報はどうあるべきかが問われる時期にきている。
- 著者
- 藤本 哲也 村岡 千種 正根 優太郎
- 雑誌
- 日本薬学会第142年会(名古屋)
- 巻号頁・発行日
- 2022-02-01
- 著者
- 廣田 憲威 岡田 浩 岡村 昇
- 雑誌
- 日本薬学会第142年会(名古屋)
- 巻号頁・発行日
- 2022-02-01
- 著者
- 山﨑 健司 石川 雅之 関根 祐子
- 雑誌
- 日本薬学会第142年会(名古屋)
- 巻号頁・発行日
- 2022-02-01