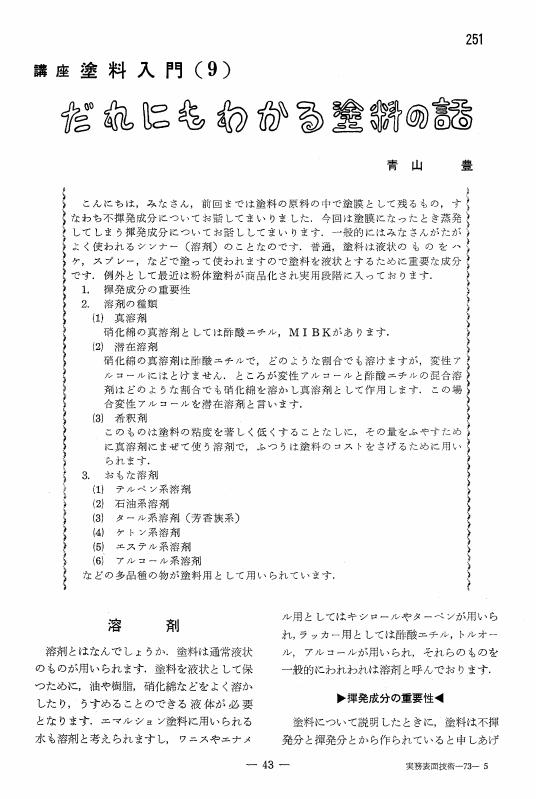1 0 0 0 OA 健康増進に寄与するルミナコイドとしてのレジスタントスターチの働き
- 著者
- 早川 享志
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.7, pp.483-493, 2013 (Released:2018-01-15)
- 参考文献数
- 42
消化管内で消化・吸収されにくく,消化管を介して健康の維持に役立つ生理作用を発現する食物成分をルミナコイドという。ルミナコイドのうちの食物繊維の整腸作用についてはよく知られているが,本報ではルミナコイドの1つであるレジスタントスターチについて解説していただいた。筆者の早川先生は平成23年度日本食物繊維学会学会賞を受賞されており,ルミナコイド研究の第一人者である。ご一読いただき,健康な食生活に生かしていただきたい。
- 著者
- 藤野真矢 中村克彦
- 雑誌
- 第76回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.1, pp.433-434, 2014-03-11
Robocup2Dシミュレーションリーグでは,コンピュータ上の仮想的なフィールドでシミュレーションによるサッカーゲームが行われる.プレイヤのエージェントには,センターフォワードやサイドバックなどのポジションが与えられるが,これまで多くのチームでは基本的な動作パラメータはポジションごとに違いがなく同じであった.本研究では,遺伝的アルゴリズムを用いてポジションごとの動作パラメータの組み合わせを最適化することによってチームの性能向上を図る.
1 0 0 0 OA 尾張藩の川船支配について(水運特集号)
- 著者
- 川名 登
- 出版者
- 日本学術会議協力学術研究団体 交通史学会
- 雑誌
- 交通史研究 (ISSN:09137300)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.21-33, 2002-02-28 (Released:2017-10-01)
1 0 0 0 OA 格闘する身体の文化社会学序説 キックボクシングのフィールドワークから
- 著者
- 山本 敦久
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.119-128,139, 2001-03-21 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 14
本稿は、キックボクサーたちの試合に備えた禁欲的な生活や厳しいトレーニングによる身体の磨き上げのプロセスに注目し、なぜ彼らが身体的危険や苦痛が伴うにもかかわらず「闘い続ける」のかを、フィールドワークをもとにしながら分析した。第1に、試合前2週間の減量や欲望の抑制に注目し、ジムの選手たちの相互監視によって、身体が自己規律化されるプロセスに注目した。第2に、キックボクサーの禁欲的な生活実践と、彼らが生きている社会的コンテクストとの結びつきを分析した。第3に、それらをふまえた上で、なぜ彼らは「格闘し続けるのか」を分析した。その結果、彼らが生きてきた (生きている) 社会的な条件のもとで繰り返される欠如 (「ハングリーの場所」) の体験を刻み込んだ身体図式が、試合に備えて減量や欲望の抑制によって欠乏感を駆り立てる身体図式のパターンときわめて一致することが明らかとなった。そして、試合前の減量の体験や欲望の抑制による禁欲的な生活実践を繰り返していくうちに、そこから生みだされる欠乏感を格闘に向けていくことなしには、自分のアイデンティティを保てないほど、彼らは格闘を欲していくことになるのである。
1 0 0 0 重度脳卒中患者に対する部分免荷トレッドミル訓練の効果
- 著者
- 鈴木 琢也 小口 和代
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.P032, 2008
【目的】近年,脳卒中患者の歩行の獲得に部分免荷トレッドミル歩行訓練(以下,BWSTT)が注目されている.しかし,BWSTT後の即時効果の報告は少ない.療養病床入院リハ中の発症後5ヶ月の重度脳卒中患者にBWSTTを施行し,訓練前後の歩行速度・歩行率・股関節伸展角度を検討した.<BR>【症例】64歳男性.脳底動脈閉塞による脳梗塞.Brunnstrom recovery stage test右上肢2・下肢2・手指2,左上肢5・下肢6・手指6.深部覚右上下肢重度鈍麻.FIM運動32点・認知30点・合計62点.<BR>【方法】BWSTTは懸荷モード12m/分で25m歩行を,5分間の休憩を挟んで2回実施した.実施前・直後・2日後に,5m平地歩行(左サイドケイン・右長下肢装具を使用し軽介助)を家庭用ハイビジョンデジタルビデオカメラ(Canon社製)で撮影した.計測の妥当性を検討するため,直後のみ三次元動作解析システムKinemaTracer(キッセイコムテック社製)で同時撮影した.歩行路の中央5歩分の右下肢イニシャルコンタクト時の左股関節伸展角度を検討した.マーカーをつけた腸骨稜と大転子の軸と大転子と膝関節外側上顆の軸で角度を計測した.統計学的処理にはANOVA(有意水準5%)を用いた.<BR>【結果】歩行速度は実施直前5.2m/分,直後5.3m/分,2日後6.5m/分.歩行率は実施前18.6歩/分,直後26.3歩/分,2日後27.4歩/分.股関節伸展角度は,実施前平均-3.6°,直後平均10.8°,2日後平均-3.8°で,直後に有意に増加していた(p<0.05).動作解析システムでの計測値でもほぼ同値であった.<BR>【考察】BWSTTについて寺西らは,膝折れや膝過伸展,股関節伸展不十分などによる歩行異常・不能症例に対して課題指向的歩行訓練実現を可能にすると述べている.多くの先行研究では,効果として歩行速度・歩行率増加が報告されている.本症例でも歩行速度・歩行率増加の効果は,2日後でも持続していた.一方で股関節伸展効果は即時的でキャリーオーバーしなかった.股関節伸展が増大した要因は,懸垂により体幹伸展を促せたことと,トレッドミルにより左下肢の踵からつま先へ重心移動がスムーズに行えたことが考えられた.以上よりBWSTTはアライメントへの効果より歩行周期への効果の方が持続的であることが推測された.<BR>【まとめ】重度脳卒中患者にBWSTTを施行し訓練効果を検討した.アライメントと歩行周期への効果を認め,後者はより持続的であった.動作解析装置のない環境でも,今回のように簡易な歩行評価項目なら,家庭用ビデオ撮影で十分検討が可能である.今後さらに慢性期・重度脳卒中症例にBWSTTを適用し,効果発現機序について検討したい.<BR>
1 0 0 0 OA 草書大字典 : 草露貫珠
1 0 0 0 OA ドイツ中世村落協同体の自治について
- 著者
- 森 正夫
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.29-45, 1952-01-31 (Released:2019-05-24)
- 著者
- 千葉 一幹
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.172-173, 2006
1 0 0 0 OA 速乾性ネールエナメルの開発
- 著者
- 金子 勝之 山崎 亮太 藪 李仁 曽山 美和 熊野 可丸 金田 勇 梁木 利男
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.8-13, 2001-03-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 9
ポイントメーキャップにおいて爪化粧料は, 口紅に次いで主要なアイテムとして使用されている。さらに近年, ネールサロンやネールアートの台頭で, その使用者はますます増加し, 重要な化粧料に位置づけられてきている。このネールエナメルに求められる特性として, 「乾きが速い」「はがれにくい」「仕上がりが均一でつやに優れる」「爪に優しい」「つやや仕上がりの持続」等が挙げられ, その中で特に「乾きの速さ」に関する要望が強く, 常に求められる機能の上位に挙げられてきた。これに対し, 溶剤の揮散により被膜を形成する速乾性タイプのものが種々上市されてきたが, 塗布後の仕上がりの美しさが損われることから, これ以上の乾燥速度の短縮は困難とされていた。今回は「エナメルが乾く」という現象をまったく新しいユニークな発想で捉え, ネールエナメルの乾燥時間を飛躍的に短縮し, 超速乾性を実現した「水で乾かすエナメル」の技術開発を例に速乾性エナメルについて概説する。
1 0 0 0 OA 塗料入門 (9) だれにもわかる塗料の話
- 著者
- 青山 豊
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 実務表面技術 (ISSN:03682358)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.5, pp.251-255, 1973-05-01 (Released:2009-10-30)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA モンティ・ホール問題における最尤法
- 著者
- 菊池 耕士
- 雑誌
- 目白大学総合科学研究 = Mejiro journal of social and natural sciences (ISSN:1349709X)
- 巻号頁・発行日
- vol.(6), pp.149-158, 2010
1 0 0 0 IR 愛宕山信仰と勝軍地蔵 : 中世のある軍神信仰についての覚書
- 著者
- 野﨑 準
- 出版者
- 東北学院大学東北文化研究所
- 雑誌
- 東北学院大学東北文化研究所紀要 (ISSN:03854116)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.1-17, 2016-12
1 0 0 0 IR 勝軍地蔵考
- 著者
- 森末 義彰
- 雑誌
- 美術研究 = The bijutsu kenkyu : the journal of art studies
- 巻号頁・発行日
- no.91, pp.1-16, 1939-07-25
1 0 0 0 OA 音響機器研究から音声信号処理研究への道 (<小特集>音声研究)
- 著者
- 永田 邦一
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.11, pp.894-897, 1989-11-01 (Released:2017-06-02)
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1415, pp.40-43, 2007-11-05
そう描かれた鉄塔が青空に向けて突き出している。仏塔ならぬ「チョコ塔」。石下の周辺だけで3カ所もあった。 石下を「聖地」と呼ぶ理由。それは、2つの有名駄菓子メーカーがこの辺りに本社を構えているからだ。リスカと菓道。社名だけではピンとこないだろうが、商品を聞けば、誰もが膝を打つ。茨城県の「駄菓子兄弟」 10円駄菓子の王様「うまい棒」。
1 0 0 0 OA 学級担任が行う健康観察に関する実態調査
- 著者
- 石山 志央子 小林 央美 新谷 ますみ
- 出版者
- 弘前大学教育学部
- 雑誌
- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.2, pp.31-36, 2016-10-14
学校において学級担任をはじめとする教職員により行われる健康観察は,日常的に子どもの健康状態を観察し,心身の健康問題を早期に発見して適切な対応を図り,学校における教育活動を円滑に進めるための重要な活動である。そこで,特に児童生徒と日常的に関わり教育活動を進める学級担任の行う健康観察に着目しその実態について質問紙調査を行った。結果,朝の健康観察は,小学校では98.8%,中学校では100.0%,高校では73.5% の割合で実施していた。校種別にみた朝の健康観察の主要な方法は,小学校では「健康状態申告方式」,中学校では「自己申告方式」,高校では「観察方式」であった。朝の健康観察は「体調不良を訴えた児童生徒の経過観察」に最も活かされていた。健康観察の機会の内,「朝の会」を小学校では特に大切にしていた。高校では,「清掃時」や「放課後」等も大切にしていた。朝の健康観察の方法は発達段階に応じて選択されており,その日一日の教育活動で行う健康観察に連動されるように活かされており,特に重点的に行う必要があることが示唆された。