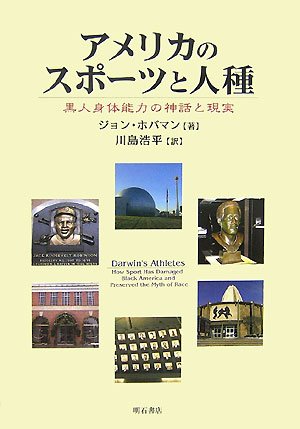2 0 0 0 OA 大阪圖書館第一回圖書展覧會列品目録
- 出版者
- 大阪圖書館
- 巻号頁・発行日
- 1904
2 0 0 0 OA アメリカ 在日米軍再編・普天間基地移設をめぐる公聴会
- 著者
- 新田紀子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 251-1), 2012-04
2 0 0 0 アメリカのスポーツと人種 : 黒人身体能力の神話と現実
2 0 0 0 人種とスポーツ : 黒人は本当に「速く」「強い」のか
2 0 0 0 OA 研究者と実務家との知識交流 : 理論と実践からの教訓
- 著者
- 吉澤 剛 田原 敬一郎
- 出版者
- 研究・技術計画学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.202-205, 2009-10-24
一般講演要旨
- 著者
- 土橋 貴
- 出版者
- 中央学院大学
- 雑誌
- 中央学院大学法学論叢 (ISSN:09164022)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.19-52, 2005-03-31
- 著者
- 松冨 哲郎
- 出版者
- 日工フォ-ラム社
- 雑誌
- エネルギ- (ISSN:02855437)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.66-69, 1999-05
- 著者
- 中川 洋子
- 出版者
- 日本コミュニケーション学会
- 雑誌
- Speech communication education (ISSN:13470663)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.83-103, 2011-03-31
2 0 0 0 IR 日本人の英語観の変容--英語コンプレックスから積極的受容への転換とその問題点
- 著者
- 中川 洋子
- 出版者
- 筑波大学人文社会科学研究科現代語・現代文化専攻
- 雑誌
- 論叢 (ISSN:18830358)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.183-212, 2010-03
- 著者
- 永野 優子
- 出版者
- 滋賀大学
- 雑誌
- 滋賀大学大学院教育学研究科論文集 (ISSN:13444042)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.71-82, 2006
- 著者
- 高橋 恒介
- 出版者
- 静岡産業大学
- 雑誌
- 静岡産業大学情報学部研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.187-219, 2008
地球温暖化で気象災害が増加しているとの報道が多い。その際に温暖化が温室効果ガスによるという解説が受け売り的である。5、6年前の温暖化の説明が繰り返されるだけである。5年前の環境測定データと今年で、どこが変化したかの解説が欠けている。気象データによる温暖化の実態の確認がもっと多くの人によって行われる必要を感じる。そこで、パソコンの使い方を教えるだけでなく、利用効果を伝える立場で、一般人でも気候変化の実態を確認できるようにパソコン(PC)による気象データの分析手法を提示する。最近は気象データが次々とネットで公開される。大量であるから、平均値を使ってグラフ分析が行なわれる。世界の平均気温上昇が100年間で0.7℃以上も上昇しているというような表現を耳にするが、静岡ではどの程度の温暖化が起こっているか具体的に示された記事は少ない。地域ごとでの気象データ分析結果があれば、公開してほしいし、分析が行なわれるなら、平均気温と共に、最高気温や最低気温が、何年前から上昇したか?季節で言えば冬か夏か、月で言えば何月の気温上昇が大きいか、朝方と昼間のどちらの上昇が大きいか、示してほしいと思う。そして、最後に、地域間の気温上昇状況の違いも知りたい。そこで、静岡の気象データを例に、グラフによる分析結果を示してみる。他都市気温変化との比較もできるようにグラフ分析を行って、日本での温暖化の状況を考察した。分析結果の概略を述べるなら、日平均気温、日最高気温や日最低気温の年平均値が1980年から2000年までにかなり急速に上昇したといえる。今後も気温上昇が続けばどのような異常気象が出現するか予想がつかない。地球環境が破滅しそうだと予言する著書が多い。本当だとすれば、気象激変のドラマが始まる。ドラマの始まる前に通常の気象特性を理解し、その後の温暖化と気象異常の因果関係を把握することが重要であると思われる。異常の発見を早めるには21世紀始めまでの通常の気象を多くの人が理解している必要がある。その一手法として、ネットから集めた気象データをファイル記憶装置の中に蓄えるだけでなく、音楽情報に変換して記録することを考えた。揺らぎの大きい気象データの中から本質的な変化をキャッチするにはコンピュータ解析だけに頼るより人間の直感が役立つように思うからである。実際に静岡など主要都市の気象データを音情報に変換して記録した。本学部のウェブページで気象データ音楽として聞けるように公開する予定である。
2 0 0 0 OA Transverse Acoustic Excitations in Liquid Ga
- 著者
- Hosokawa S. Inui M. Kajihara Y. Matsuda K. Ichitsubo T. Pilgrim W. -C. Sinn H. Gonzalez L. E. Gonzalez D. J. Tsutsui S. Baron A. Q. R.
- 出版者
- American Physical Society
- 雑誌
- PHYSICAL REVIEW LETTERS (ISSN:00319007)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.10, 2009-03
- 被引用文献数
- 125
The transverse acoustic excitation modes were detected by inelastic x-ray scattering in liquid Ga in the Q range above 9 nm-1 although liquid Ga is mostly described by a hard-sphere liquid. An ab initio molecular dynamics simulation clearly supports this finding. From the detailed analysis for the S(Q, ω) spectra with a good statistic quality, the lifetime of 0.5 ps and the propagating length of 0.4–0.5 nm can be estimated for the transverse acoustic phonon modes, which may correspond to the lifetime and size of cages formed instantaneously in liquid Ga.
2 0 0 0 IR 為替の影響を受ける図書館資料購入のリスクヘッジ
- 著者
- 松田 泰代
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 同志社大学図書館学年報. 別冊, 同志社図書館情報学 (ISSN:09168850)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.58-67, 2011
論文
2 0 0 0 OA 欧州の日本資料図書館における活動・実態調査報告 : 日本資料・情報の管理・提供・入手
- 著者
- 江上 敏哲
- 出版者
- 学術文献普及会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, pp.45-56, 2005-03
2004年9月11日から同26日まで,京都大学教育研究振興財団の事業である海外派遣助成(短期)を受け,イギリス・アイルランド・オランダの日本資料・日本研究図書館を訪問し,スペインで開かれた日本資料専門家欧州協会年次集会に参加した。各館における実態(特に,活動・運営,資料の入手・提供,目録システム,古典籍資料等)について調査した。日本からの協力・働きかけとしては,ILL受付体制の整備,NACSIS-CAT参加及び総合目録・目録システム形成へのサポート,出版物の積極的な寄贈,貴重資料電子化の支援,発表・報告等の積極的な"発信"等が考えられる。
- 著者
- 取屋 淳子
- 出版者
- 桃山学院大学
- 雑誌
- 国際文化論集 (ISSN:09170219)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.101-122, 2006-12-05
In this study of the globalization of "Miyazaki Anime", I focus on MiyazakiHayao's twin masterpieces "Spirited Away" (『千と千尋の神隠し』; 2001),which achieved astonishing box-office returns of more than 30 billion yen, and"Princess Mononoke" (『もののけ姫』; 1997), which was also a top box-officehit in Japan and became the first of Miyazaki's works to become widely popularoutside Japan. The core of the study is a comparative analysis of how thetwo works, both of which were set in Japan, were received in three differentcultures : Japan, the USA, and Taiwan.Using a comparative-culture viewpoint to investigate the true nature ofwhat is called the "globalization of Miyazaki Anime", the research indicatedthat the reception of the two movies was strongly influenced by cultural traitsin the three cultures examined. Moreover, it was found that the degree andnature of understanding of a work outside its native culture tended to bestrongly affected by things like editing and translation, resulting in images thatsometimes seemed quite different from the original. In other words, "globalization"went hand in hand with "localization", and the degree of understandingof a particular work differed according to how closely it approached local culturalnorms. Although it is natural to feel distant from a work originating inanother culture, if the work can be made to include even a small number ofelements with which local people can empathize even while they find otherelements incongruous, it will help them to understand that work. When theelement they empathize with is the core of the story, the work gains thepower of speaking to those people as strongly as it spoke to the people in theoriginal culture.Japanese people familiar with Miyazaki's works and with Miyazaki's policyof allowing audiences to make their own conclusions about the "meaning" ofa particular movie may regret the changes brought by such things as the additionof extra lines and the culturally-influenced translation introduced byDisney, the distributors of his movies in the USA. On the other hand, whateverwas lost from the original as a result of such changes it can also be arguedthat they resulted in a deeper understanding of the movies outside Japan, andMiyazaki himself seems to have concurred in this view. This is because audiencesof a particular movie originating in a culture that is not their own willinstinctively seek elements that concur with their own cultural understanding.To the degree that they find such elements, even if they continue to experiencesome elements of "strangeness", the movie will be a success, andcan then be said to have been successfully "localized", which is to say"globalized".The study found that, because of historical and geographical factors, the degreeof understanding of and empathy with Miyazaki's movies tended to bestronger in Taiwan than in the USA, particularly in the case of "SpiritedAway". For Japanese audiences, Miyazaki's movies have a timeless qualitythat resulted in their becoming such monster hits. Although, commerciallyspeaking they did not have the same success outside Japan, receipt of theAcademy Award for animation together with the high critical acclaim themovie enjoyed in both cultures (as well as in the rest of the world) indicatesthat Miyazaki's movies successfully navigated the process of "globalization" /"localization", and became movies that could be enjoyed on the world stage.
- 著者
- 井尻 正二
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科學 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.458-459, 1986-11-25
2 0 0 0 OA フランス憲法院の憲法裁判機関への進展
- 著者
- 中村 睦男
- 出版者
- 北海道大学法学部
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3-4, pp.261-291, 1977-03-30
2 0 0 0 OA 学校研究の現在(<連載>教育の実践研究の現在 第4回)
- 著者
- 古賀 正義
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.46-54, 2008-03-31
「学校が消える!」2008年の年明け、衝撃的な記事を目にした。読売新聞の調査(1月11日付)によれば、全国で今後数年間に一千校以上の公立小中学校が廃校になる見通しだという。急激な人口減少と補助金抑制の影響などで、東京都でも約50校(2.5%)が廃校になる勘定だ。教育機会の均等を実現してきた義務教育制度にあっても、社会変動の波は容赦なく地域社会を襲っている。学校選択制や中高一貫校など市場型改革の導入が進めば、一層、「生き残る学校」と「消え去る学校」とが出現する状況である。 「学校」を自明の教育機関とみなしてきた教育学者にとっても、学校とはいかなる特徴を持った教育の場で、そこで何が達成され、今後何を成し遂げることが可能なのか、いわば「学校力」(カリキュラム研究会編2006)を再度検証しなければならなくなっている。そうでなければ、教師や保護者、地域住民などを巻き込んで、学校に対して体感される不安やリスクは増大していく一方なのである。そもそも学校とは、不可思議な場である。教育学で、学校を念頭におかない研究はほとんどないし、教員養成にかかわらないことも少ない。そうでありながら、学校の内実に長けているのは現場教師であって、研究者はたいてい余所者として外側からその様子を眺め批評する立場にある。マクロレベルから教育政策や学校制度を講じることもできるし、ミクロレベルから授業実践や学級経営を論じることもできるが、学校の実像を客観的総体的に把握し切れているという実感は乏しい。 『教育学研究』を紐解いても、「学校」は学会シンポジウムのテーマに度々取り上げられてきた。「学校は子どもの危機にどう向き合うか」(1998年3月号)、「学びの空間としての学校再生」(1999年3月号)、「21世紀の学校像-規制緩和・分権化は学校をどう変えるか」(2002年3月号)など、教育病理の深刻化や教育政策の転換など、教育関係者の実感と研究者の思いが交錯する時、学校がたびたびディベートのフィールドとして選択された。今日なら、学力低下やペアレントクラシー、指導力不足、いじめ事件など、学校のガバナンスやコンプライアンスにかかわる諸問題が、個々の学校やさまざまな種別の学校、制度としての学校など、各層にもわたる「学校」について論議されることだろう。急激な改革と変化のなかで、問題言説の主題としての「学校」は隆盛であるのに、現実分析の対象としての「学校」は不十分。学校研究の10年は、こうしたねじれ状態と向き合い、その関係を現実的・臨床的にどのように再構築し、教育学の公共的使命を達成するかの試行錯誤の期間だったといえる。
2 0 0 0 Synthesis of 2-Iminoindolines via Samarium Diiodide Mediated Reductive Cyclization of Carbodiimides
- 著者
- Takayuki Ishida Chihiro Tsukano Yoshiji Takemoto
- 出版者
- (社)日本化学会
- 雑誌
- Chemistry Letters (ISSN:03667022)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.44-46, 2012-01-05 (Released:2011-12-24)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 16
A method of synthesizing 2-iminoindolines using samarium diiodide (SmI2) is reported. In the presence of tert-butyl alcohol, treatment of carbodiimides bearing α,β-unsaturated carbonyl moieties with a stoichiometric amount of SmI2 afforded 2-iminoindolines in moderate to high yields. The products were isolated after Boc protection of the amidine moieties. This reaction proved to be applicable to lactams and acyclic/cyclic esters as substrates.
2 0 0 0 金港堂の7大雑誌と帝国印刷
- 著者
- 稲岡 勝
- 出版者
- 日本出版学会
- 雑誌
- 出版研究 (ISSN:03853659)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.p171-211, 1992