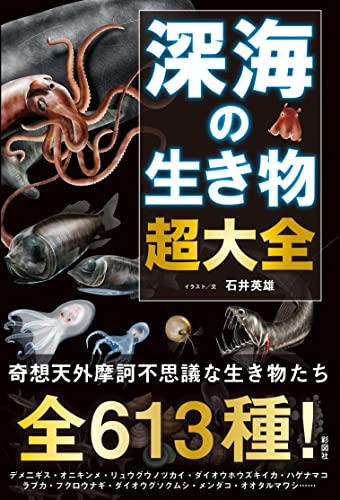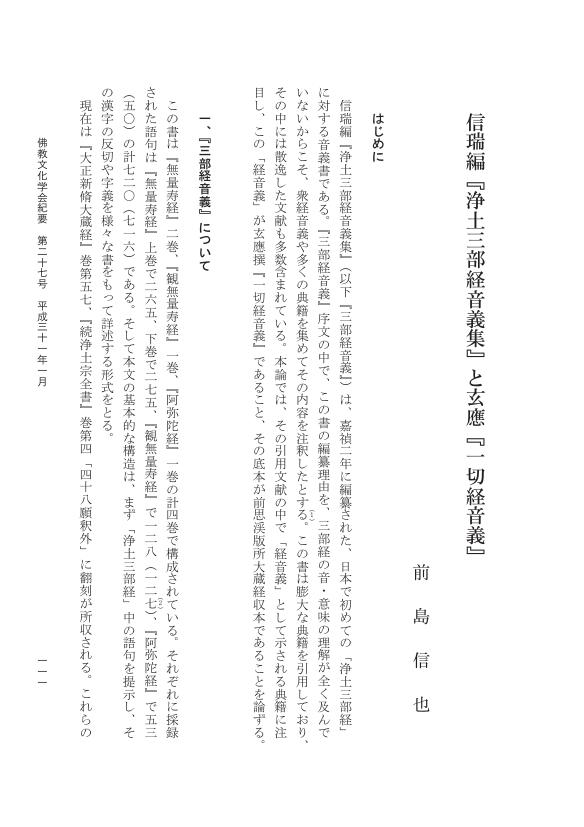- 著者
- 日本フランス語フランス文学会北海道支部 [編]
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会北海道支部
- 巻号頁・発行日
- 2008
- 著者
- 熊谷 明泰
- 出版者
- 関西大学視聴覚教室
- 雑誌
- 関西大学視聴覚教育 (ISSN:13431099)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.55-77, 2006-03-31
- 著者
- Masatomo Ogata Naoto Tominaga
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.1573-23, (Released:2023-02-22)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA M&Aに必要な本社能力に関する研究 M&A成功のための具体的な本社能力とは
- 著者
- 芳賀 裕子 立本 博文
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.1-34, 2023-02-25 (Released:2023-02-25)
- 参考文献数
- 33
M&Aの企業への効果は、先行研究から必ずしも明らかではない。M&Aで移転する経営資源に着目した多くの先行研究から明らかにされていない、M&Aの成功要因がある。それはM&Aのダイナミックケイパビリティであり、資源を評価し、再配分を実施する組織統合能力である。本研究は、企業成長の手段であるM&Aを事業成果に結びつけるために必要な本社能力とは、具体的にどの様なことかを解明した。M&Aを業績に結び付けられない要因、結び付けられる要因の両方をインタビュー調査により明らかにした上で、M&A成功に必要な七つの本社能力を抽出した。そしてこれら七つの項目は、三つのM&Aの実施各フェーズ (戦略立案、ディール実行、PMI) において横断的に実施することが重要であった。
1 0 0 0 OA 切干大根の品質に及ぼす乾燥時の光照射の影響
- 著者
- 鈴木 栄貴
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成24年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.49, 2012 (Released:2012-09-24)
【目的】大根の乾物である切干大根は近年健康食品として評価されている。著者らは農水産物に光(UV-A、青)を照射すると旨味成分である遊離アミノ酸が増加することを報告している。この研究結果を元に、光照射を行う光源を用いた機械乾燥が天日で乾燥したものと遜色がないかを検討するため、大根を様々の光を照射して乾燥して切干大根を製造し、遊離アミノ酸、GABA、抗酸化性および色彩を測定した。【方法】実験材料として、愛知県知多半島で栽培された大根を使用し、それぞれUV-A、青、非照射の3つ分けて2日間光源付き乾燥器で乾燥させ、天日干し切干大根と比較した。乾燥させた大根は前処理を行い、高速液体クロマトグラフィーで遊離アミノ酸量とGABAの分析を行い、抗酸化性は分光光度計を用いて測定した。【結果】分析の結果、遊離アミノ酸・GABA共に光照射乾燥した大根の方が増加しており、各アミノ酸では旨味成分であるグルタミン酸、甘味成分であるプロリン、苦味成分であるバリンが増加した。遊離アミノ酸総量は平均で、非照射に比べて天日干しが1.37倍、UV-A照射が1.33倍、青照射が1.09倍と増加した。GABAも非照射に比べ天日干しが2.64倍、UV-A照射が2.64倍、青照射が2.82倍増加した。このことから天日干し切干大根のおいしさはUV-Aのような太陽の波長の短い光の効果であることが判明した。
1 0 0 0 OA ダンテとイスラム文学との接点
- 著者
- 楠村 雅子
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.122-132, 1977-03-20 (Released:2017-04-05)
1 0 0 0 OA 確率モデルに基づく声質変換技術(<小特集>音声合成に関する研究の動向)
- 著者
- 戸田 智基
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.34-39, 2010-12-25 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 信瑞編『浄土三部経音義集』と玄應『一切経音義』
- 著者
- 前島 信也
- 出版者
- 佛教文化学会
- 雑誌
- 佛教文化学会紀要 (ISSN:09196943)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.27, pp.111-134, 2019 (Released:2019-12-27)
1 0 0 0 OA 信瑞纂『浄土三部経音義集』の書誌的整理 ――特に日本現存本について――
- 著者
- 前島 信也
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.634-637, 2017-03-20 (Released:2018-01-16)
- 参考文献数
- 4
The Jōdo sanbukyō ongishū 浄土三部経音義集 was written in 1237 by Kyōsaibō Shinzui 敬西房信瑞, who studied under one of Hōnen’s 法然 disciples. It contains analysis of terms in the three major sutras of Pure Land Buddhism.In Japan, there are nine kinds of manuscripts and three kinds of printed books. In this paper, I mention their bibliographic information and compare them, focusing on their marginalia. I therefore attempt to classify these sources.
1 0 0 0 OA 信瑞編『浄土三部経音義集』の書誌的整理 ―特に中国国家図書館所蔵本について―
- 著者
- 前島 信也 Shin'ya Maejima
- 出版者
- 国際仏教学大学院大学
- 雑誌
- 国際仏教学大学院大学研究紀要 = Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies (ISSN:13434128)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.71-101, 2018-03-31
1 0 0 0 OA 植物の成長調節を用いたスギ花粉症の克服に向けたアプローチ
- 著者
- 本間 環
- 出版者
- 日本植物生理学会
- 雑誌
- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集 日本植物生理学会2003年度年会および第43回シンポジウム講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.S25, 2003-03-27 (Released:2004-02-24)
現在、スギ花粉は日本の春先における代表的なアレルギー疾患となっている。これはまさに植物が他生物(動物)に対して影響を与えている例である。スギ花粉症を解決するためには医学的あるいは植物生理学的な対策が必要とされている。しかし、現在でもスギ花粉症の有効な治療や発生源の対策は実用化されていない。スギの材は建築材や家具材として価値が高い。そのために、スギは日本の有用樹木として盛んに植林されてきた。この際に必要となったのは、安定した種子の供給であった。種子生産の技術として植物ホルモンの一種であるジベレリン(GAs)を処理することで花芽形成の誘導が行われていた。しかし、植物ホルモンとスギの花芽形成のメカニズムとの関連は不明であった。そこで、スギに含まれる内生植物ホルモンの分析を行った。その結果、花芽形成の直前にGA3の含有量が著しく増加することが明らかとなった。このことから、GAsはスギの花芽形成に関与していることを示唆している可能性が示された。このことは、スギ花粉の発生源の対策としてGAsを制御すればスギの花芽形成を抑制できる可能性をも示唆していた。そこで、GAsの生合成阻害剤の処理を行った。その結果、スギの花芽形成は顕著に抑制された。ここでは、植物の成長調節を用いてスギ花粉の飛散防止を目的とした研究について、実験室レベルからフィールドレベルへの応用および実用化について紹介する。
- 著者
- 大呂 興平
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.4, pp.211-233, 2021-07-01 (Released:2023-02-19)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4
沖縄離島部の数少ない有望な農業部門として期待される肉用牛繁殖部門は,2000年代後半以降,停滞している.本稿では,多良間島における各農家の追跡調査を通じて,2000年以降の農家経営と肉用牛繁殖経営の技術的特徴の変化を分析することで,肉用牛繁殖経営群の動態を明らかにした.多良間島では農家の世代交代とともに,サトウキビと肉用牛の小規模経営を組み合わせた労働多投的な精農層が大量引退し,また,経験的技術に支えられた放牧主体の大規模経営も消滅した.これらに代わり,子牛価格の上昇を背景に,粗飼料生産を委託した労働節約的な小規模経営,近代的な施設を装備した中規模経営,採草主体の大規模経営が成立している.特に中規模経営は一般の農家にも単独で生計を立てることを可能にし,継続的な技術蓄積や再投資を誘発している.肉用牛繁殖経営は多良間島の壮年層の幅広い受け皿となっており,今後は産業の規模を維持ないし成長させる可能性が高い.
1 0 0 0 OA 説教師ベルナルディーノ・オキーノの亡命 : カトリック改革と宗教改革のはざまで
- 著者
- 高津 美和
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.96-119, 2006-10-21
La Riforma ha avuto una importante influenza sulla situazione religiosa nell' Italia del Cinquecento. L'idea venuta d'oltralpe passata attaraverso Venezia costrinse la Chiesa Romana a confermare la propria dottrina ed a mettere in ordine il sistema del controllo delle idee. Nel corso della Controriforma apparvero "gli eretici". Bernardino Ochino (1487-1564) e valutato "il piu importante dei riformatori italiani" da Delio Cantimori, autore di Eretici italiani del Cinquecento (1939). Ochino appartenne all'ordine dei Francescani Osservanti, poi a quello dei Cappuccini ed ebbe fama in tutta l'Italia come grande predicatore. Pero col tempo la Chiesa comincio a sospettare che Ochino diffondesse l'idea della Riforma mediante la sua predicazione. Nel 1542 quando Ochino fu convocato dall'Inquisizione Romana, lascio l'Italia e ando a Ginevra. Questo articolo sulla vita e la fede di Ochino e un tentative di mettere in luce una fase della storia della Chiesa in un periodo pieno di fermento. Prima della Riforma protestante ci fu il movimento riformatore cattollico, cosidetto Riforma cattolica. A partire dal pontificate di Paolo III(1534), questo movimento cambio e divenne di carattere generale la cui iniziativa fu presa dal papa e gradualmente divenne meno tollerante e piu esclusivo con i dissidenti religiosi. Fu l'Inquisizione Romana istituta nel 1542 con la bolla Licet ab initio che simbolizzo questa tendenza oppressiva della Chiesa. A quel tempo l'Italia era divisa in stati e ducati, ma dopo l'istituzione di questa organizzazione, si pote svolgere il proveddimento unificato contro gli eretici. Sembra che ci siano due ragioni perche Ochino fu convocato a Roma. Una dipende dal suo rapporto personale, soprattutto, con il mistico spagnolo, Juan de Valdes (1500-41). Valdes formo un circolo umanistico a Napoli e presento l'idea d'oltralpe agli intelettuali italiani. Nel 1536 quando Ochino predico a Napoli, conobbe Valdes. Tramite lui Ochino ebbe l' opportunita di avvicinare le opere di Erasmo, Lutero, Calvino, ecc. Per questo rapporto l'Inquisizione considero l'ortodossia di Ochino sospettosa. La seconda ragione era che Ochino era un predicatore popolare. La predicazione funzionava efficacemente come mezzo per trasmettere le nuove idee, percio, l'Inquisizione trovo il bisogno di consolidare il controllo dei predicatori. Inoltre l'influenza di alcuni prelati come il vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti o il cardinale, Gasparo Contarini che appoggiarono le riforme moderate e conobbero Ochino, ando diminuendo sotto il mutamento d'indirizzo della Chiesa e Ochino non pote contare sul loro aiuto. Cosi Ochino decise di andarsene dall'Italia. Rimangono pochi documenti delle prediche di Ochino. Pero possiamo ricostruire il suo pensiero dai suoi scritti prima e dopo la fuga. Nel Dialogi sette (1540) si trova quasi completamente la tradizione dell'idea dei Francescani invece della simpatia verso quella protestante. Tuttavia, l'idea dei Francescani ebbe una storia complicata e bisogna fare attenzione al modo di accoglierla di Ochino. Per esempio, il soggetto del "Ladrone in croce" del quarto dialogo del Dialogi e uguale a quello di Arbor Vitae Crucifixae Jesu di Ubertino da Casale, membro dei Francescani Spirituali (1305). Esaminando l'opera di Ubertino possiamo trovarci implicati due temi: la giustificazione per la fede e la predestinazione. Ochino consulto l'opera di Ubertino, ma non ne fece suo il pensiero totalmente, cioe, Ochino adopero il tema della giustificazione nella propria opera, ma si riservo su quello della predestinazione. Si puo desumere che Ochino abbia capito il pericolo di esprimere l'interesse per la dottrina dei calvinisti nella sopraddetta situazione. L'opinione di Ochino sulla Chiesa possiamo trovarla nei suoi scritti dopo la fuga dall'Italia. Ochino confesso il suo malcontento verso l'ordine dei Francescani Osservanti e quello dei Cappuccini. Alia fine manifesto la sua separazione dalla Chiesa cattolica pubblicando Imagine di Antechristo (1542) in cui identified il papa come Anticristo. Cosi si puo dire che la vita e la fede di Bernardino Ochino suggeriscano il complesso clima religiose nell'Italia del Cinquecento che ha ancora qualche punto da esaminare in future.
1 0 0 0 横浜国大国語研究
- 著者
- 横浜国立大学国語国文学会 [編集]
- 出版者
- 横浜国立大学国語国文学会
- 巻号頁・発行日
- 1983
- 著者
- 望月哲男編
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 OA 最高裁において昭和20年代中葉に確定した死刑判決の動向
- 著者
- 永田 憲史
- 出版者
- 関西大学法学研究所
- 雑誌
- ノモス = Nomos (ISSN:09172599)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.35-51, 2022-12-31