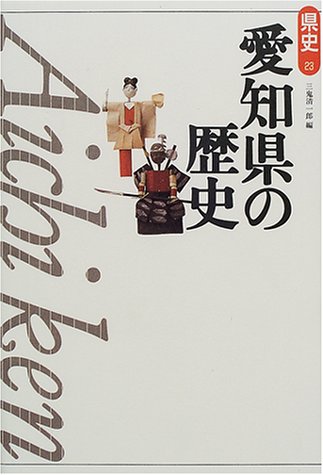1 0 0 0 OA 表現規制としての標識法とその憲法的統制 (3)
- 著者
- 平澤 卓人
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科, 北海道大学情報法政策学研究センター
- 雑誌
- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.185-231, 2018-11
- 著者
- 松本 拓真
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.186-196, 2015 (Released:2017-09-20)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2
自閉症スペクトラム障害を持つ子どもの受身性は,Wing & Gould(1979)から指摘され,思春期以降のうつやカタトニアの要因として注目され始めているが,それ以前の時期では適応の良さとして軽視されがちだった。本研究では思春期以前に受身性が固定化する要因を明確にすることを目的に,自閉症スペクトラム障害の子どもを持ち,受身性を意識している親11名に半構造化面接を行った。データを修正版グラウンデッドセオリーアプローチにより分析したところ,15概念が生成され,6カテゴリーが抽出された。【支援への受身的な状態】から「意志表出主体として認められる」ようになる間に【意志か社会性かの揺れ動き】という独特の状態が介在し,受身性の固定化への影響が示唆された。このカテゴリー内には,【やるけどやらされてる感】という特殊な状態があり,親の求めに応じられるがゆえに受身的になる特徴が見られ,自己感の問題が推測された。その状態は親に強要か適切な指導かという葛藤や子どもの人生全てを背負うかのような責任感という苦悩をもたらしていた。また,受身性から脱却する変化の前に親が深刻な悲嘆や強い後悔を体験することも見い出され,子どもの受身性により生じた親の苦悩が受身性の固定化の一因となる相互作用が示唆された。本研究で得られたモデルはサンプルの偏りなどの点で限定されたものではあるが,更なる検討により精緻化が可能だと考えられる。
- 著者
- Safi Syed Ragib
- 出版者
- 広島大学(Hiroshima University)
- 巻号頁・発行日
- 2022
1 0 0 0 OA 食品残渣のマダイ用飼料化システムの開発と事業採算性の検討
- 著者
- 池田 由起 石塚 譲 入江 正和 亀岡 俊則 石渡 卓 鈴木 孝彦 松田 行雄
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物学会論文誌 (ISSN:18831648)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.246-255, 2004-07-31 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
都市域で発生する多様な食品残渣の中から, おから, 寿司残渣, 練り製品残渣を原料として選択し, これらを気流乾燥機で乾燥した後, 回収魚アラから造られたアラミール等を添加して, マダイ用ペレット飼料を製造し, その成分を把握した。この食品残渣配合マダイ用ペレット飼料 (以下, リサイクル飼料と略す) の効果を調べるために, 63日間養殖マダイに給与して, マダイの成長等に及ぼす影響について, 市販マダイ用配合飼料と比較検討した。その結果, リサイクル飼料は, 市販配合飼料に劣らない効果を持ち, マダイの養殖に利用可能であることがわかった。食品残渣の乾燥・ペレット製造工程を最適化した食品残渣配合マダイ用ペレット飼料化システムにおける製造コストを試算し, 本システムの事業採算性を検討した。リサイクル飼料生産量6 ton/日において, IRR (Internal Rate of Return) =10%となるリサイクル飼料の販売価格は, 市販ペレット飼料と同程度となった。
1 0 0 0 OA 親鸞とルター-一向一揆とドイツ農民戦争-
- 著者
- 倉塚 平
- 出版者
- 明治大学社会科学研究所
- 雑誌
- 明治大学社会科学研究所年報 (ISSN:04656091)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.60-61, 1990-08-01
1 0 0 0 OA 蘇我石川両氏系図成立の時期について
- 著者
- 星野 良作
- 出版者
- 法政大学史学会
- 雑誌
- 法政史学 = 法政史学 (ISSN:03868893)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.37-51, 1965-03-21
1 0 0 0 OA 算数分野における小学校と就学前教育の関連性
- 著者
- 河原 聡子
- 出版者
- 京都光華女子大学京都光華女子大学短期大学部
- 雑誌
- 京都光華女子大学京都光華女子大学短期大学部研究紀要 = Research bulletin of Kyoto Koka Women's University and College (ISSN:24324841)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.165-179, 2016-12-01
- 著者
- 伊藤 久美子 河合 恒 西田 和正 江尻 愛美 大渕 修一
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-083, (Released:2023-02-10)
- 参考文献数
- 11
目的 介護保険法改正により基準緩和型サービスが創設され,地域住民が担い手として介護サービスに参加できるようになったが,その具体的な方法は示されていない。我々は通所型サービス事業所(以下,事業所)に教育機能を付加し,地域住民をサブスタッフ(介護予防の一定の知識・技術と守秘義務を持ち,職員の支援のもと自立に向けたケアを有償で提供する補助スタッフ)として養成する「サブスタッフ養成講座(以下,養成講座)」を開発した。本報告では,養成講座を自治体の介護予防事業等で実施するために,実践例の紹介と調査を通して,実現可能性と実施上の留意点を検討した。方法 養成講座は4か月間のプログラムで,介護予防等の知識の教授を目的とした講義(1時間/回,全16回)と,サービス利用者のケアプランの目標や内容を把握し職員の支援のもと介護サービスを提供する実習(半日/回,全13回)で構成した。修了後の目標は事業所での活動や地域での介護予防活動とした。2015~2017年度に東京都A市,B市,千葉県C市の14事業所にて養成講座を実施した。評価は,修了率,養成講座参加前後の活動の自信・介護予防の理解度の変化と修了後の地域活動状況,サービス利用者が受講生から介護サービス提供を受けることによる精神的影響,事業所職員の仕事量軽減の認識について,受講生,サービス利用者へのアンケート,事業所職員へのインタビューにより行った。活動内容 養成講座修了者は104人中96人(修了率92.3%)であった。受講生へのアンケートの結果,参加前後で事業所での活動の自信や介護予防の理解度が有意に向上し,65.3%が修了後に事業所での活動を含む新しい地域活動の実施に至った。サービス利用者へのアンケートの結果,受講生から介護サービス提供を受けた利用者は受けていない利用者と比べ負の精神的な影響が多くなかった。養成講座を実施した事業所の85.7%が地域住民のサービス参加により仕事量が軽減されたと回答した。結論 養成講座は受講生の活動の自信・介護予防の理解度を向上させ,半数以上が新しい地域活動への実施に至っていた。受講生の介護サービスへの参加は利用者への負の影響が少なく,事業所にとっても仕事量軽減につながることが示唆された。これらのことから,養成講座の介護予防事業等での実現可能性は高いと考えられた。
1 0 0 0 OA デシカント除湿機と用途例の紹介
- 著者
- 岡野 浩志
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第39回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.676, 2007 (Released:2008-03-17)
1 0 0 0 OA 普通鋼の局部腐食 とくに製鋼工場の湿度の影響の問題
- 著者
- 山本 洋一
- 出版者
- 社団法人 腐食防食協会
- 雑誌
- 防蝕技術 (ISSN:00109355)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.7, pp.304-307, 1962-07-15 (Released:2009-11-25)
1 0 0 0 OA 防錆技術について
- 著者
- 山本 洋一
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.11, pp.500-504, 1962-11-30 (Released:2012-11-20)
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 江村 正
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.83-86, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 4
チーム医療の推進を目的として,「特定行為に係る看護師の研修制度」(以下,本制度)が2015(平成27)年10月1日に創設された。救急領域では,研修を修了した看護師が,手順書を用いて特定行為を行うのは,入院診療と外来診療で大きく異なる。入院診療では,呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連,循環動態に係る薬剤投与関連など手順書により,看護師はさまざまな診療の補助が可能である。一方,外来診療に関しては,まだ診断がついておらず,今後の病状変化が十分予測できないので,手順書ではなく,具体的指示により,診療の補助を迅速に,かつ的確に行っていくことが現実的と思われる。
1 0 0 0 OA 欧米におけるゴースト研究(<特集>幽霊・ポルターガイスト, 第38回日本超心理学会大会)
- 著者
- 井口 博貴
- 出版者
- 日本超心理学会
- 雑誌
- 超心理学研究 (ISSN:1343926X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1-2, pp.15-22, 2005-12-09 (Released:2017-08-09)
- 参考文献数
- 5
当研究はghost研究を行うための基礎知識として広く海外の研究活動に着目し、その中で比較的進んでいると言われている欧米の研究例を分析する。まずghostの定義に触れてから、これらの現象の分析を行う。この中で、ghostの特性を抑え、次にそれらの出現例を見てゆく。また近年、高度な機械技術にともなうghost出現の変容について分析する。さらにpoltergeist時に居合せる子供と同現象の関連性を考察する。また海外で行われた一般国民のghost意識を調査、あわせて専門家による多様な考察を調査する。最後にロンドンのゴーストツアー"Ghosts by Gaslight"に自ら参加し、上記の調査と合わせて総合考察を試みる。これによれば英国ではghostに親しみを持ち平和共存しうるという考えも見られた。しかしそのメカニズムは依然として不明確であり、更なる深い研究が必要であると考える。
1 0 0 0 OA 金九の思想と行動 : 解放直後の帰国,政治情勢の中で
- 著者
- 李 景珉 リ キョンミン Kyung Min Lee
- 雑誌
- 経済と経営
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.33-47, 2015-03
- 著者
- Takehiro Numata
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.16, pp.2527-2528, 2021-08-15 (Released:2021-08-15)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 高尿酸血症患者に対するレジスタンストレーニングの影響 (パイロット試験)
- 著者
- 大山 博司 大山 恵子 諸見里 仁 高木 宜史 田代 優輝 大山 高史 山田 美紀 江戸 直樹 藤森 新
- 出版者
- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会
- 雑誌
- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.123-130, 2016-12-20 (Released:2016-12-20)
健常者3名と高尿酸血症患者6名を対象に,有酸素運動,低強度(20RMで10回を3セット)レジスタンストレーニング,高強度(10RMで10回を3セット)レジスタンストレーニングの3段階の運動を実施して血清尿酸値への影響を検討した.健常者,高尿酸血症患者とも有酸素運動では血清尿酸値は変化しなかったが,高尿酸血症患者では低強度,高強度いずれのレジスタンストレーニングでも運動翌日に血清尿酸値の有意な上昇がみられ,高強度レジスタンストレーニングでは運動直後にも血清尿酸値の有意な上昇が観察された.レジスタンストレーニングは解糖系をエネルギー源とする嫌気性運動筋である速筋を使用するトレーニングであり,運動直後の血清尿酸値の上昇には筋肉活動によって生成された乳酸による尿酸排泄障害が関与する可能性が疑われた.また,有意差はついていないが,健常者,高尿酸血症患者いずれにおいても運動翌日に血清CK値が運動前の数倍上昇しており,運動翌日の血清尿酸値の上昇には筋線維の断裂・破壊などに伴う,筋肉内に含まれているプリンヌクレオチドの溶出の影響も可能性として挙げることができるかもしれない.レジスタンストレーニングは強度によっては血清尿酸値上昇をもたらす可能性があり,その機序に関しては今後さらなる検討が必要と考えられた.レジスタンストレーニングはインスリン感受性やHDLコレステロールを上昇させる効果や筋肉量の増加,基礎代謝の亢進などにより生活習慣病の予防に有効なことが報告されており,痛風・高尿酸血症患者に運動を実施する場合は,痛風関節炎の有無や尿酸値の推移に注意しながら有酸素運動と無理のない程度の低強度レジスタンストレーニングを組み合わせた運動を推奨することが望ましいと考えられた.
1 0 0 0 OA 別宮貞雄作曲《智恵子抄》の歌唱に関する研究 [要旨]
1 0 0 0 OA 出雲大社の慶長度造営本殿について
- 著者
- 藤沢 彰
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.506, pp.149-154, 1998-04-30 (Released:2017-02-02)
- 参考文献数
- 25
I propose a reconstructed model of the main sanctuary at Izumo-Taisha Shrine in the Keicho period. It was 5 ken (35 shaku, approximately 10.605 meters) wide, 5 ken deep, a ken was equivalent to 7 shaku, and 6 jo 5 shaku 4 sun (approximately 19.816 meters) high. I presume that it didn't have a pillar that supports the ridge beam directly (manamoti-bashira), and it had a roof construction system based on one slightly curved beam (koryo) and principal rafter with king-strut (inoko-sasu).