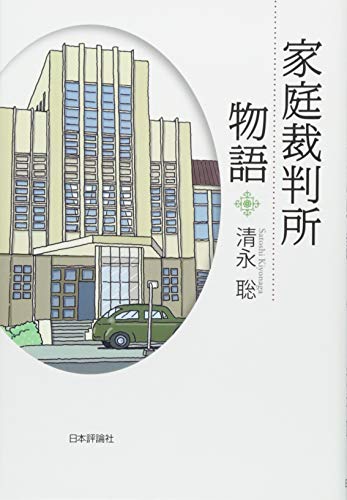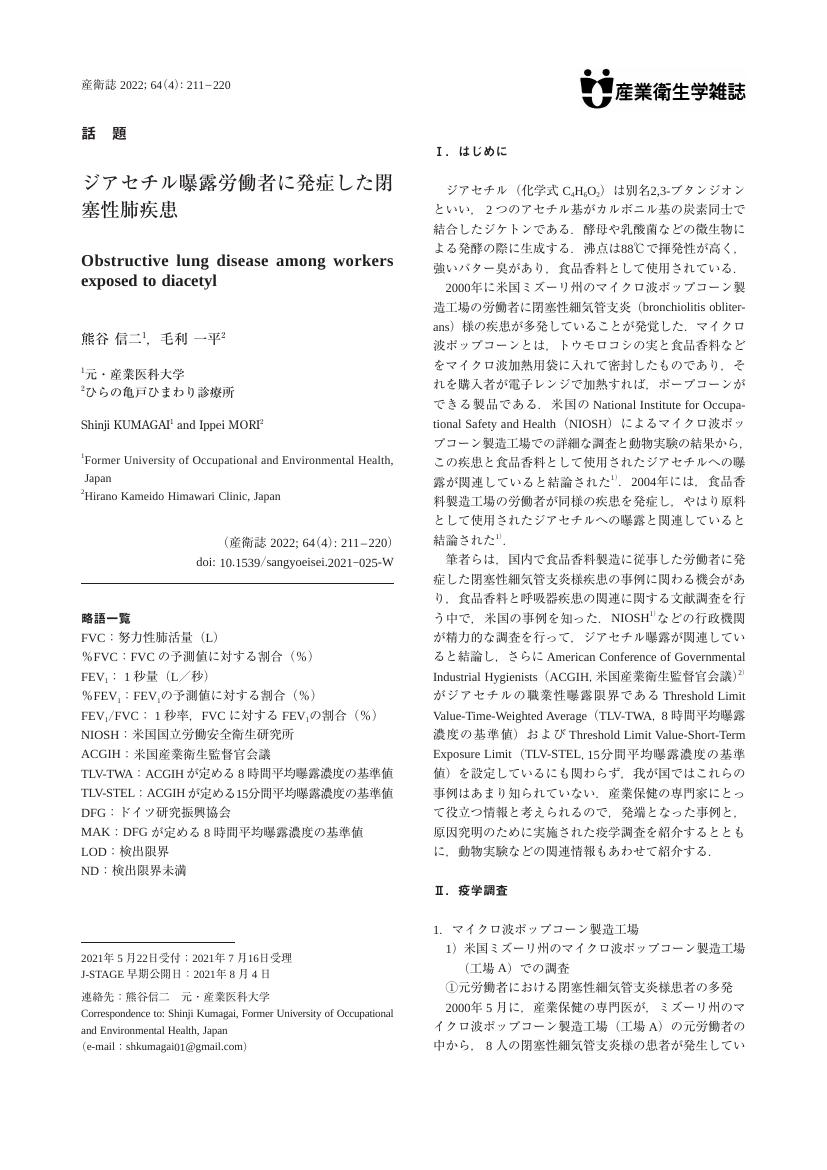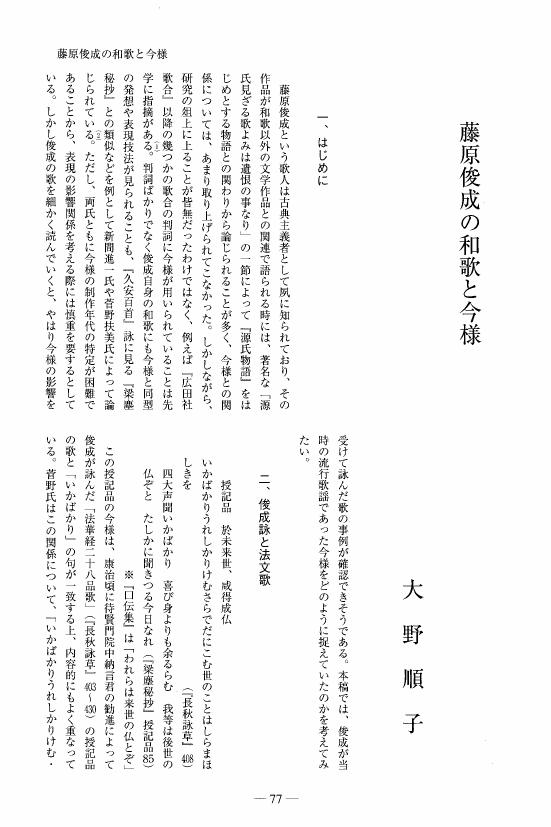1 0 0 0 インフラツーリズムの効果に関する研究
- 著者
- 野中 美貴子 阿部 貴弘
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.22-00016, 2023 (Released:2023-02-20)
- 参考文献数
- 7
近年,インフラを観光対象としたインフラツーリズムが全国で展開されはじめている.インフラツーリズムは,インフラへの理解促進とともに,周辺地域の活性化や観光振興につながる取り組みとして期待されている.本研究では,全国のインフラツーリズムを対象に,アンケート調査,ヒアリング調査,さらに現地調査に基づき,対象施設ごとの取り組み内容や発現効果を把握し,インフラツーリズムの効果を類型化するとともに,取り組みと効果との関係や,効果の相互関係について考察した.これらの成果は,インフラツーリズムの効率的かつ円滑な実践に資する研究成果であると考える.
1 0 0 0 OA 仮性結核菌とその感染症
- 著者
- 坪倉 操
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.317-323, 1987-05-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 91
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 中世期の出羽国平賀郡の領主と領域
- 著者
- 遠藤 巌
- 出版者
- 宮城教育大学
- 雑誌
- 宮城教育大学紀要 (ISSN:13461621)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.1-16, 1999
1 0 0 0 OA 我が国の生徒指導の今後の在り方について 日米比較からの考察
- 著者
- 宇田 光 岡田 順一
- 出版者
- 南山大学
- 雑誌
- アカデミア. 人文・自然科学編 = Academia. Humanities and natural sciences (ISSN:21853282)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.49-69, 2013-06-30
1 0 0 0 追想のひと三淵嘉子
- 著者
- 三淵嘉子さん追想文集刊行会編集
- 出版者
- 三淵嘉子さん追想文集刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1985
1 0 0 0 性スペクトラム研究の運営
- 著者
- 立花 誠 大久保 範聡 勝間 進 諸橋 憲一郎 菊池 潔 長尾 恒治 深見 真紀 田中 実 宮川 信一
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2017-06-30
本研究領域では「性スペクトラム」という新たな概念のもとに、性を再定義することを目指す。領域の全ての研究者が「性はこれまで言われれてきたような二項対立的なものではなく、連続的な表現型である」という視点を共有し、上記の領域目標の達成にむけて研究を推進する。このような目標のもとで、本領域では領域代表の下に総括班を置き、領域活動をサポートしていく2020年9月25日から10月23日にかけて、自己紹介を兼ねた公募班員のセミナーを開催した。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインでの発表となった。9月25日、10月2日、16日、23日の4日間で、全16名が研究発表を行った。活発な議論が交わされ、オンラインにもかかわらず大いに盛りあがった。2020年12月21日(月)から23日(水)までの3日間、東京農業大学世田谷キャンパスにて、新学術領域研究「配偶子インテグリティの構築」・「全能性プログラム:デコーディングからデザインへ」合同公開シンポジウムが開催され、立花が特別講演を行った。2021年3月25日(木)と26日(金)の2日間、第4回領域会議をオンラインにて開催した。本会議では、計画研究の研究代表者・分担者のほか、班友の3名、そして新たに公募研究班に加わった研究者1名も研究発表を行った。また、領域外からも講師1名を招き、ショウジョウバエ類の性染色体進化に関してご講演をいただいた。対面方式での会議の開催が叶わなかったが、非常に活発な議論が交わされ、各班員が順調に成果を上げていることを確認した。
1 0 0 0 OA 種々のアーベル拡大の理論と類体論との関係について
- 著者
- 河田 敬義
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.129-150, 1954-12-25 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 20
- 著者
- 川崎 弘美
- 出版者
- 日本インテリア学会
- 雑誌
- 日本インテリア学会 論文報告集 (ISSN:18824471)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.101-108, 2013 (Released:2022-06-01)
本研究の目的は,世紀末ウィーンにおいて,コロマン・モーザー(Koloman Moser/1868-1918)が提示した革新的に簡素な空間デザインについて,その展示と住宅の空間デザインの関連性を明らかにすることである。文献による当時の写真資料をもとに,まず展示を概観し,その中からモーザーによる最も簡素な空間デザインを抽出する。その後,その空間デザインに影響を与えた住宅を見出す。その際,同時期の空間デザインと比較することで,モーザーの簡素さを確認していく。さらに,彼の簡素な空間デザインの源泉を,建築家チャールズ・レニー・マッキントッシュの空間デザインに見出し,考察する。
1 0 0 0 OA ジアセチル曝露労働者に発症した閉塞性肺疾患
- 著者
- 熊谷 信二 毛利 一平
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.211-220, 2022-07-20 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA コロナ禍において主任看護師が発揮した力
- 著者
- 川口 麻衣 足立 茜 荒木 敬雄 大桑 由美 大納 英美 岡田 梨亜 金谷 妃佐子 北林 聖子 黒田 普美子 厳本 英 高田 圭美 谷元 直美 橋本 達矢 鶴亀 美幸 樋浦 絵美子 三島 準也 森岡 賢一 吉元 奈央子 斎藤 美智子 山本 和代 別府 清香
- 出版者
- 地方独立行政法人 神戸市民病院機構
- 雑誌
- 神戸市立病院紀要 (ISSN:0286455X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.41-50, 2022 (Released:2022-04-25)
- 参考文献数
- 1
神戸市立医療センター西市民病院では、2020 年4月から新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れた。コロナ専用病棟や発熱外来の開設、一般病棟の閉鎖、スタッフの異動など、すべての部署で様々な影響があった。その中で主任研修において各部署の主任看護師が、コロナ禍における自部署での経験や学びを発表する場を設けた。今回この学びをまとめることにより、主任看護師は普段から持っている力を非常事態の際にも発揮していたが、状況に合わせてその力を使い分けていることが分かった。
1 0 0 0 OA 藤原俊成の和歌と今様
- 著者
- 大野 順子
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.77-87, 2010 (Released:2018-02-09)
1 0 0 0 OA ジャワ島西部における早朝降水に伴う対流システムの伝搬と異なる北寄りの背景風
- 著者
- Erma YULIHASTIN Tri Wahyu HADI Muhammad Rais ABDILLAH Irineu Rakhmah FAUZIAH Nining Sari NINGSIH
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.1, pp.99-113, 2022 (Released:2022-02-22)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1 7
Early morning precipitation (EMP) events occur most frequently during January and February over the northern coast of West Java and are characterized by propagating systems originating from both inland and offshore. The timing of EMP is determined by the initial location, direction, and speed of the propagating precipitating system. This study explores processes that characterize such propagating precipitation systems by performing composite analysis and real-case numerical simulations of selected events using the Weather and Research Forecasting (WRF) model with a cloud-permitting horizontal resolution of 3 km. In the composite analysis, EMP events are classified according to the strength of the northerly background wind (VBG), defined as the 925 hPa meridional wind averaged over an area covering western Java and the adjacent sea. We find that under both strong northerly (SN) and weak northerly (WN) wind conditions, EMP is mainly induced by a precipitation system that propagates from sea to land. For WN cases, however, precipitating systems that propagate from inland areas to the sea also play a role. The WRF simulations suggest that mechanisms akin to cold pool propagation and advection by prevailing winds are responsible for the propagating convection that induces EMP, which also explains the dependence of EMP frequency on the strength of VBG. On the basis of the WRF simulations, we also discuss the roles of sea breeze and gravity waves in the initiation of convection.
1 0 0 0 OA 出版流通機構の変遷 ―一六〇三~一九四五―
- 著者
- 高橋 正実
- 出版者
- 日本出版学会
- 雑誌
- 出版研究 (ISSN:03853659)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.188-228, 1983-02-20 (Released:2020-03-31)
1 0 0 0 OA 大正期東京の「雑誌回読会」問題 ―雑誌のもうひとつの流通経路
- 著者
- 永嶺 重敏
- 出版者
- 日本出版学会
- 雑誌
- 出版研究 (ISSN:03853659)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.1-28, 1999-03-20 (Released:2020-03-31)
Zasshi-Kaidokukai was a commercial circulating library of magazines. This sortof library grew rapidly in Taisho Tokyo, and took readers away from magazine sellers. As a result the Tokyo Association of Magazine Sellers decided to forbid the sale of any magazine to the Zasshi-Kaidokukai. Subsequently Zasshi-Kaidokukai filed a lawsuit against the Association.This article deals with this opposition focusing on the system used by Zasshi-Kaidokukai. The system appeared about 1910 in Tokyo, and in 1922 had a membership of about 30,000. It consisted of two divisions. Sales was magazine a circulation library in Tokyo, and the other mail-order of back issues of magazines throughout the country. It played an important role in the circulation of magazines.
1 0 0 0 OA 住吉大社「御文庫」を通してみた,輝文館の出版物 ―『大阪パック』,『赤雑誌』,および絵本
- 著者
- 大橋 眞由美
- 出版者
- 日本出版学会
- 雑誌
- 出版研究 (ISSN:03853659)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.131-153, 2011-03-20 (Released:2019-03-31)
- 参考文献数
- 20
本研究では,住吉大社御文庫蔵書を主な資料として,明治から昭和にかけて大阪で活動した出版社,輝文館の出版物に焦点を当てた.大人用メディアである『大阪パック』『赤雑誌』,子ども用メディアである絵本を取り上げ,これらの比較を通して,庶民性の高い大阪という地で展開された近代化とメディアの意義を問うた.
1 0 0 0 OA グローバル化のなかの北方領土問題 : レジーム構築試案
- 著者
- 皆川 修吾
- 出版者
- 愛知淑徳大学
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集. グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科篇 (ISSN:18837573)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.65-81, 2010-03-06
1 0 0 0 音声による速度回復情報提供の交通性能改善メカニズムの実証分析
- 著者
- 和田 健太郎 金崎 圭吾 西田 匡志 平井 章ー
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.A_326-A_334, 2023-02-01 (Released:2023-02-24)
- 参考文献数
- 10
本研究は,小仏トンネルに渋滞対策として導入された音声注意喚起(速度回復情報提供)システムによって,なぜ渋滞発生時交通量,渋滞発生後捌け交通量等の交通性能の改善がもたらされたのかを考察する.具体的には,近年提案された最新の交通流理論(Jin, 2018; Wada et al., 2020)に枯づく実証分析をシステム導入前後のデータに対して行い比較する.そして,(i) 渋滞発生時/渋滞発生後捌け交通量の改善はボトルネック区間における「安全車間時間の短縮」という共通のメカニズムにより説明できること,(ii) 渋滞中のボトルネック下流の加速度向上は必ずしも捌け交通量の改善には繋がっておらずさらなる改善の余地があること,を示す.
- 著者
- 甲斐 慎一朗 和田 健太郎 堀口 良太 邢 健
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.A_280-A_287, 2023-02-01 (Released:2023-02-24)
- 参考文献数
- 9
本研究は,近年提案された連続体交通流理論に基づき,国内複数のサグ・トンネルにおける交通容量低下 (CD: Capacity Drop) 現象の分析を行ったものである.具体的には,高速道路会社が 2019 年の 1 年間で集計した渋滞イベントデータを参考に,渋滞区間(および渋滞イベント)を選定し,ETC2.0 プローブデータおよび車両感知器データを用いてモデルのキャリブレーションを行った上で,安全車間時間,ボトルネック下流端における加速度パラメータ等を推定する.そして,理論の汎用性を確認するとともに,推定されたパラメータの傾向を分析し,ボトルネック区間がサグのどこで顕在化するかはまちまちであること,安全車間時間の大小が概ね渋滞発生後捌け交通量 (QDF: Queue Discharge Flow rate) の絶対レベルを決めていること,を示す.