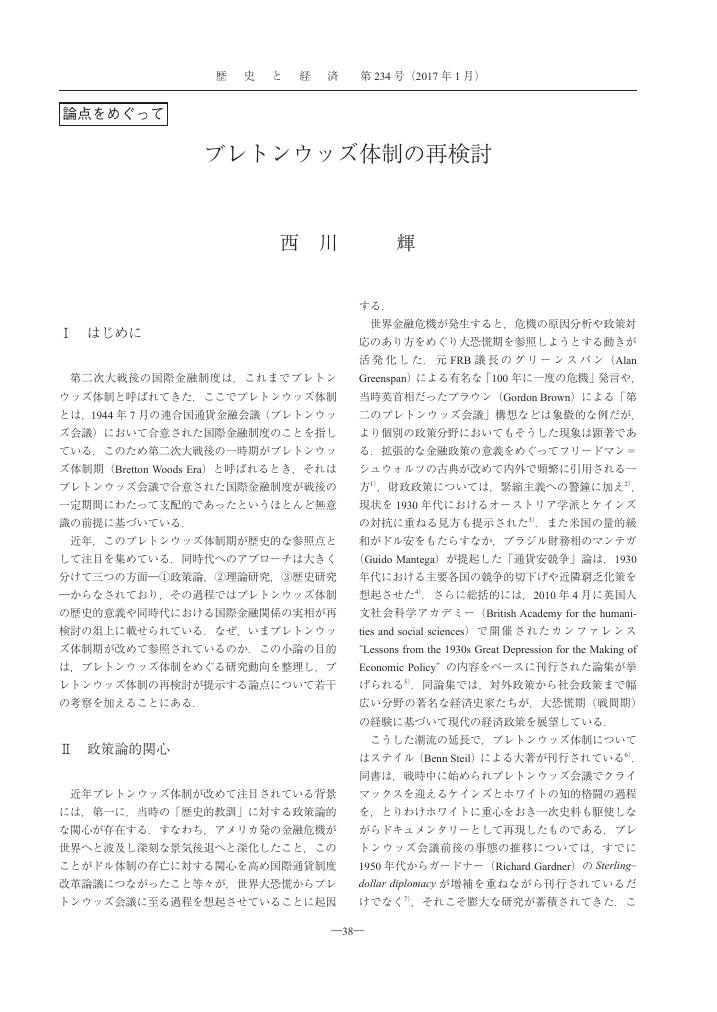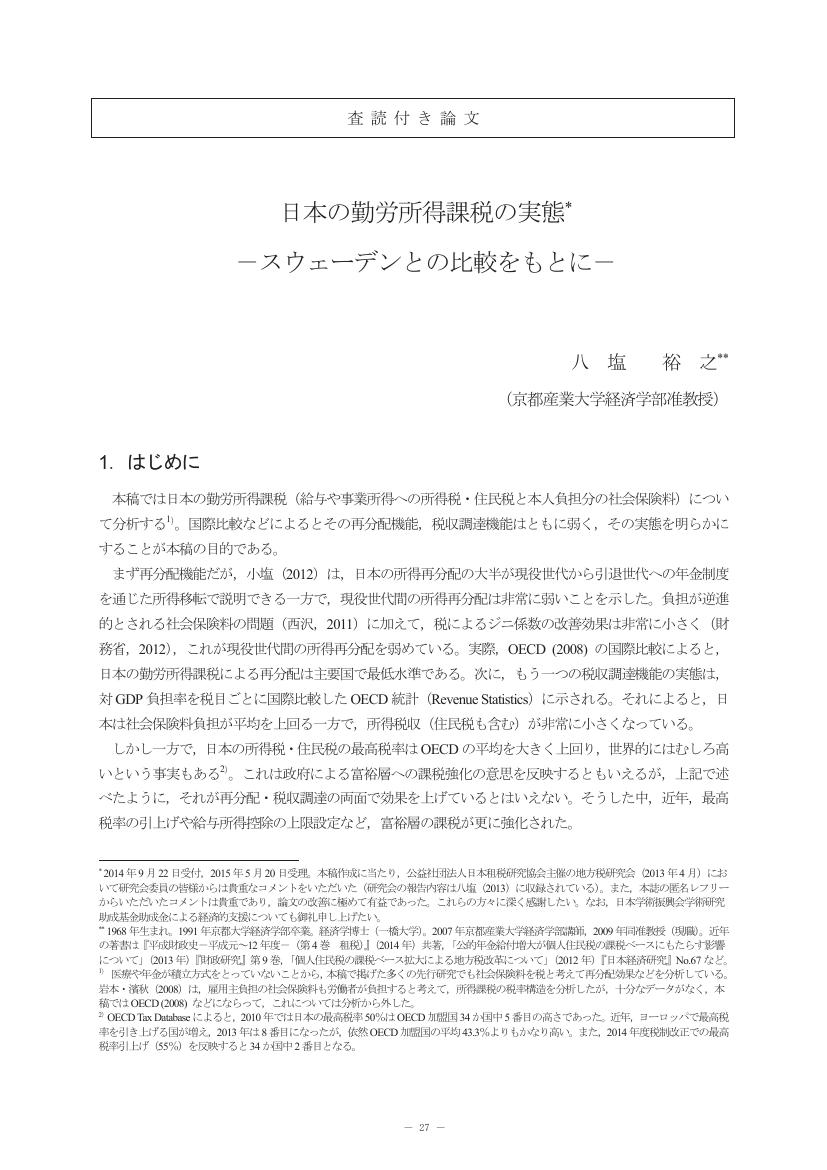1 0 0 0 OA 特集によせて
- 著者
- 米村 千代
- 出版者
- 比較家族史学会
- 雑誌
- 比較家族史研究 (ISSN:09135812)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.4-7, 2015-03-31 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 旧学制下高知県の私立中学生徒の動向 ―私立土佐中学校を事例としてー
- 著者
- 湯田 拓史
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, pp.55-56, 2018 (Released:2019-12-05)
1 0 0 0 OA 1959~1972年における丹下健三と磯崎新のサイバー計画にみる人工知能建築の特徴
- 著者
- ダニアル アフマッド 飛ヶ谷 潤一郎
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.787, pp.2358-2367, 2021-09-30 (Released:2021-09-30)
- 参考文献数
- 25
This study attempts to figure-out the characteristics of suggestive artificially intelligent architecture by case-studying the cybernetic projects and relevant theoretical discourse presented by Japanese architects Kenzo Tange and Arata Isozaki during the decade of the 1960s. First, the reason behind selecting Tange for this study is the fact that being inspired by the technological optimism of the 1960s, he presented an elaborate theoretical discourse on information and communications society and also attempted to portray this element as a significant design characteristic in the form of a central civic axis for the processing of information and communications in his projects A Plan for Tokyo (1960-61), Tsukiji Project in Tokyo (1963), Yamanashi Communications Center (1964-67), Plan for Skopje (1965) and Japan World Exposition Osaka (1967-70). This information and communications discourse led him to explore the characteristics of cybernetic environments such as tactual, auditory and visual approaches by following Norbert Wiener’s line of thought. Afterwards, he approached suggestive artificially intelligent architecture and attempted to define it through human, emotional, sensual, and technologically intelligent elements and social-communicational structure of the space. Secondly, the reason behind the selection of Isozaki is the fact that he – following in the footsteps of Tange but adopting an approach featuring arts, technology and architecture – experimented with cybernetic environments while following Norbert Wiener as his ideal in the projects of Electric Labyrinth: 14th Triennale Di Milano, Milan, Italy (1968), Arai House (1968-69), Computer Aided City, Makuhari, Chiba (1970-72) and Osaka Expo ’70 (1967-70). Computer Aided City is of particular significance as he introduced the concept of a brain of the city through this project that eliminated all the discrimination among the functions of a city hall, hospital, school, art museum, etc. and controlled the city via artificially intelligent information processing system – a concept being implemented these days through artificial intelligence. He also presented the characteristics of suggestive artificially intelligent environment as enclosed in a protective membrane, possessing interchangeable spaces, movable equipment, enjoying a man-machine symbiosis and handling a self-instructing feedback loop. Finally, both architects realized their dreams of suggestive artificially intelligent environment in the Festival Plaza of the Osaka Expo ’70. Especially Isozaki being inspired by NASA’s space missions and science-fiction based movies of the 1960s, attempted to control the entire environment via artificially intelligent brain of the Expo ’70 – that is the main control room.
1 0 0 0 柏崎に残る双頭レールの価値について
- 著者
- 田邊 洋夫
- 出版者
- 産業考古学会
- 雑誌
- 産業考古学 = Industrial archaeology (ISSN:09106731)
- 巻号頁・発行日
- no.154, pp.95-108, 2017-03
- 著者
- 飯岡 大輔
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.10, pp.647-650, 2022 (Released:2022-10-10)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA ブレトンウッズ体制の再検討
- 著者
- 西川 輝
- 出版者
- 政治経済学・経済史学会
- 雑誌
- 歴史と経済 (ISSN:13479660)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.38-44, 2017-01-30 (Released:2019-01-30)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA リン脂質膜系の凝集構造と電気的性質
- 著者
- 櫻井 郁子 川村 泰彬
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.8, pp.612-615, 1990-08-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 19
- 著者
- 清水 芳行
- 出版者
- 日本地域経済学会
- 雑誌
- 地域経済学研究 (ISSN:13462709)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.63-83, 2021-06-30 (Released:2021-11-24)
- 参考文献数
- 60
1 0 0 0 OA お吉と与兵衛の「救い」のゆくえ —近松『女殺油地獄』と親鸞—
- 著者
- 正木 ゆみ
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.7, pp.34-43, 2011-07-10 (Released:2017-05-19)
近松晩年の世話浄瑠璃『女殺油地獄』では、主人公の不良青年与兵衛が、日頃から自分に親切に接してくれていたお吉を殺害する。近松は、殺されたお吉の「救い」は保証したが、結末部分で悔悟した与兵衛の「救い」を保証することはなかった。本稿では、そのような二人の「救い」のゆくえを近松が対比して描いたところに、お吉が、深く信仰していた親鸞聖人の教えと通底するものが見出されることを指摘した。
1 0 0 0 OA 日本の勤労所得課税の実態-スウェーデンとの比較をもとに-
- 著者
- 八塩 裕之
- 出版者
- 会計検査院
- 雑誌
- 会計検査研究 (ISSN:0915521X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.27-44, 2015-09-18 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 OA 概念設計
- 著者
- 久保 正幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.645, pp.274, 2007-10-05 (Released:2019-04-22)
- 著者
- 長谷川 晃
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.1, pp.24-30, 2004 (Released:2004-06-16)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 2 4
Irradiation effects of SiC fiber reinforced SiC matrix composites were summarized. Based on studies of irradiation behavior of SiC⁄SiC composites, SiC fibers which have stoichiometric composition and highly crystallized structure are expected to have high resistance to irradiation, and advanced SiC⁄SiC composites for fusion application were developed using these advanced SiC fibers. In this paper, the mechanism of irradiation resistance and recent irradiation studies on size stability, mechanical properties and thermal diffusivity were introduced.
- 著者
- 朝倉 伸司 佐々木 廉雄 足助 雄二 渡辺 弘規 加賀 誠 清水 ひろえ 川田 松江 播磨 晋太郎 長濱 裕 松田 道生
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.12, pp.947-953, 2009-12-28 (Released:2010-01-27)
- 参考文献数
- 19
透析施行に際して動脈―静脈吻合を設置すると,その局所でのblood accessは高ずり応力の存在する動脈系から中あるいは低ずり応力が働くと考えられる吻合部遠位側(心臓側)へと移行するため,吻合部周辺での血栓形成の機序は必ずしも単純ではないと考えられる.さらにPTA(percutaneous transluminal angioplasty)による圧ストレスが血管内壁上で血液凝固線溶機構にどのように関連しているか,あるいは動脈硬化病変が血栓形成にどのように影響するか等については,十分に検討されてきていないのが現状である.今回,われわれはPTA施行前後の当該シャント部位での血液凝固線溶関連因子の変動を検討し,血栓形成の初期に形成される可溶性フィブリン(soluble fibrin, SF)が15例中4例が著明に上昇していることを見出した.また,SFとともにトロンビン―アンチトロンビン複合体(thrombin-antithrombin complex, TAT)も上昇していたが,SFとは相関を示さず,両者の上昇は異なる反応によるものと推定された.SFはフィブリンモノマー1分子に対しフィブリノゲン2分子が結合した3分子複合体であることが示されており,そのフィブリンモノマーの中央に位置するE領域に接合している1対のalpha C globuleがトロンビンにより切断,遊離されることにより,alpha鎖(96-97)に存在するRGDドメインがフィブリンモノマーのE領域表面に露呈されること,また,これが細胞膜に存在し,フィブリノゲン受容体(fibrinogen receptor)として働くα5β1インテグリンおよびビトロネクチン受容体(vitronectin receptor)であるαvβ3をも巻き込みながら細胞伸展を促進することをわれわれはすでに報告しており,SFが単に血液凝固亢進を示す分子マーカーであるだけでなく,血管壁への血小板の強力な接着に貢献することが明らかになった.SFが著明に上昇していた4例(SF著明上昇群)では動脈硬化の指標であるpulse wave velocity(PWV)がSF非上昇群に比し有意に上昇していた.またSF上昇群は非上昇群に対しシャントトラブルの年間発生率が高いことから,SFの上昇はPTA後の血行動態,ことに血栓形成機序の解明ならびにシャントトラブル発生とその予後の予想に有用な分子マーカーとなることが期待される.