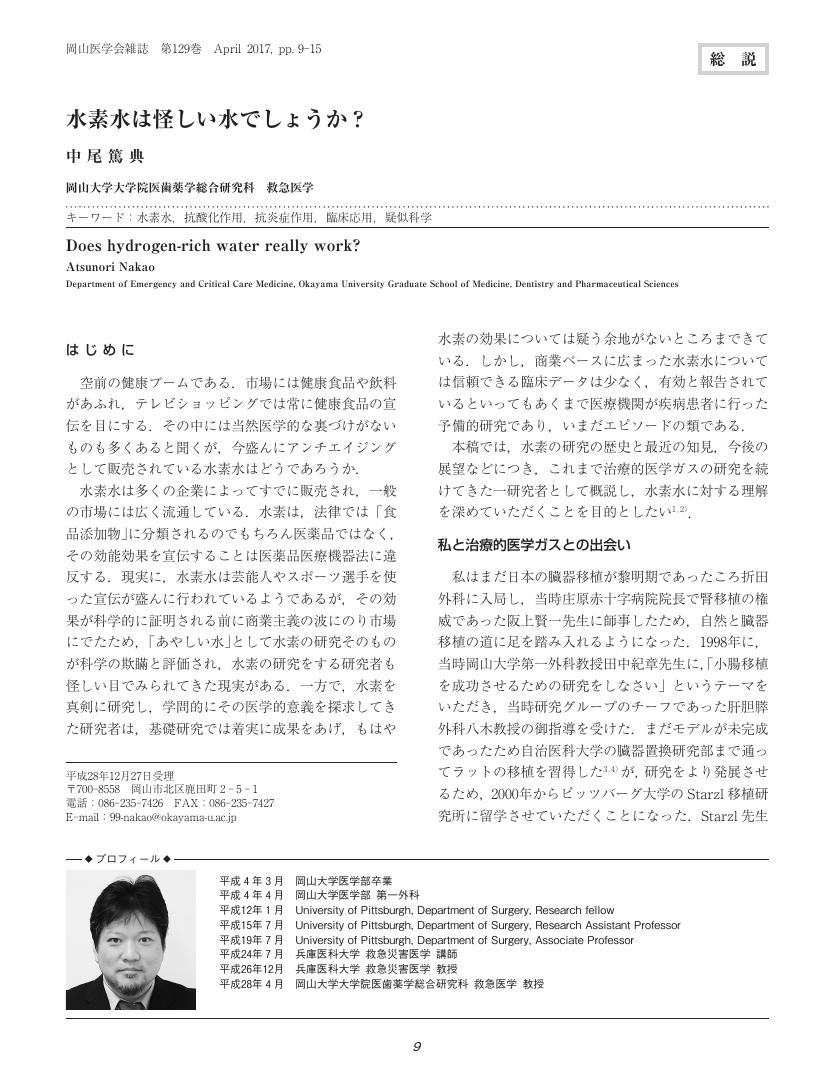9 0 0 0 OA 皇位継承の憲法政治学的考察 ―「皇室の自律の再構成」という試論―
- 著者
- 渡邊 亙
- 出版者
- 関西法政治研究会
- 雑誌
- 法政治研究 (ISSN:21894124)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.113, 2018 (Released:2018-05-28)
9 0 0 0 OA うつ病での脳由来神経栄養因子(BDNF)の血中動態
- 著者
- 吉村 玲児
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.83-87, 2011 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 26
うつ病の脳由来神経栄養因子(BDNF)の血中動態について概説した。うつ病・うつ状態では,脳でのBDNF産生および血小板からのBDNF分泌が低下しており,これが血中(血清および血漿) BDNF低下として反映されると考えられる。血清BDNF濃度の低下とうつ病重症度(ハミルトンうつ病評価尺度17項目得点)とは相関していた。血中BDNF動態はうつ病・うつ状態のバイオマーカ ーとして有用であるが,特異度に問題がある。Long-term depression やアポトーシスとの関連が指摘されているproBDNFも合わせて測定することで,BDNFのバイオマーカーとしての有用性が高まる可能性がある。
9 0 0 0 OA 水素水は怪しい水でしょうか?
9 0 0 0 OA 『グルタミン酸と精神疾患:モノアミンを超えて』 グルタミン酸トランスポーターと精神疾患
- 著者
- 田中 光一
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.6, pp.291-296, 2013 (Released:2013-12-10)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
グルタミン酸は,中枢神経系において主要な興奮性神経伝達物質であり,記憶・学習などの脳高次機能に重要な役割を果たしている.しかし,その機能的な重要性の反面,興奮毒性という概念で表されるように,過剰なグルタミン酸は神経細胞障害作用を持ち,主要な精神疾患に関与すると考えられている.我々は,グルタミン酸の細胞外濃度を制御するグリア型グルタミン酸トランスポーターの機能を阻害したマウスを作製し,そのマウスに,自閉症や統合失調症で観察される脳形成異常と似た脳発達障害や社会行動の障害,強迫性行動,統合失調症様の行動異常が観察されることを発見した.さらに,統合失調症,うつ病,強迫性障害,自閉症など主要な精神疾患において,グリア型グルタミン酸トランスポーターの異常が報告されている.これらの結果から,我々は,主要な精神疾患の中に,グルタミン酸トランスポーターの異常による興奮性と抑制性のアンバランスが原因で発症する患者が一定の割合存在し,「グルタミン酸トランスポーター機能異常症候群」として分類できると考えている.グリア型グルタミン酸トランスポーターを活性化する化合物は,新しい抗精神疾患薬として有用であると期待される.
- 著者
- 佐藤 潤司
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, pp.185-204, 2014-07-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
In this paper, I will specifically and objectively identify critical opinions on the mass media that have developed on the Internet about a report giving the real names of the Japanese victims of the hostage crisis of January 2013 in Algeria, and consider the structural factors of such criticism. The targets of this analysis are 1262 cases of opinions output from highly-ranked Web pages displayed on a search engine listing using fixed criteria. 7.1% of the opinions supported the news report, 68.5% of opinions did not support it, with other opinions accounting for 24.4%. The results of an analysis of opinions that did not support the report by using a text-mining approach did not necessarily indicate criticisms of the report that used the real names of the victims, but were an accumulation of various feelings of distrust against the mass media expressed on the Internet that were triggered by this news report. In addition, opinions that did not support the report were formed using language structures peculiar to the Internet; namely, a cyber-cascade that began at the point where people critical of the mass media became sympathetic and radicalized as unclear information spread on the Internet.
- 著者
- 中野 惟文
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, 2021
本発表では、現代カンボジア社会の呪術的実践の場において、呪術師の言葉や行為だけでなく、その場を囲んで実践を見守っているクライエントや見物人同士のコミュニケーションにも注目しながら、呪術のリアリティがどのように形成されるのかを明らかにする。
- 著者
- 三浦 麻子 小林 哲郎
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- pp.0932, (Released:2016-09-12)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3
This study focuses on “satisficing” (answering behaviors in which participants do not devote appropriate attentional resources to the survey (Krosnick, 1991)) in an online survey and aims to investigate, via various indices, to what extent these behaviors are observed among students whose participation was solicited by the researchers in their universities. This study also aims to explore effective techniques to detect individuals who show satisficing tendencies as efficiently and accurately as possible. Online surveys were carried out at nine universities. Generally speaking, the predictive capability of various types of detection indices was not high. Though direct comparison with online survey panels was impossible because of differences in measurement methodology, the satisficing tendencies of university students were generally low. Our findings show that when using university students as samples for a study, researchers need not be “too intent” on detecting satisficing tendencies, and that it was more important to control the answering environment, depending on the content of the survey.
9 0 0 0 自転車専用通行帯整備個所における交通事故分析
- 著者
- 幸坂 聡洋 宮本 和明 前川 秀和
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.5, pp.21-28, 2017-07-01 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 26
2012 年、国土交通省及び警察庁は自転車の車道通行を大原則とした「歩行者・自転車・自動車を適切に分離した自転車通行空間設計」の考え方等をとりまとめ、新たな自転車通行空間として自転車レーンが位置づけられた。自転車レーンは、自動車交通量の多い道路においても整備されるケースがある。しかし、その効果を交通事故の観点から報告している例は少ない。 そこで、本研究では、東京都区内の自動車交通量の多い道路3区間における自転車レーン整備前後の交通事故発生状況を分析した。その結果、自動車交通量の多い道路では自転車レーン整備後に自動車対自転車の交通事故件数の増加がみられた。さらに、増加した交通事故の特徴を明らかにし、これを踏まえた自転車通行空間の安全性向上に向けた改善方策の検討を課題として提示した。
9 0 0 0 OA 忍者携帯食・兵糧丸を活用した機能性保存食の検討
- 著者
- 松波 志帆 出雲 美春 川口 千遥 成木 亜衣 吉野 里奈 古市 卓也
- 出版者
- 名古屋経済大学 自然科学研究会
- 雑誌
- 名古屋経済大学自然科学研究会会誌 = Journal of Natural Sciences, Nagoya University of Economics (ISSN:24337714)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.1-5, 2019-09
9 0 0 0 OA 朝鮮総督府及所属官署職員録
- 著者
- 神嶌 敏弘 齋藤 優太 田中 一敏
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.85-88, 2023-01-01 (Released:2023-01-01)
9 0 0 0 OA 運動失調に対するアプローチ
- 著者
- 後藤 淳
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.1-9, 2014 (Released:2014-12-27)
- 参考文献数
- 10
Various motor centers reaching the spinal cord from the cerebrum are involved in smooth movement. We do not have smooth movement even if impaired wherever of this course. The cerebellum takes various parts and communication in the central nerve thickly, and the cerebellum function is important at all in conducting smooth movement. First we describe the classification of ataxia. Then, we describe rehabilitation for ataxia from the viewpoint of cerebellum function.
9 0 0 0 OA 質的研究を実施するうえで知っておきたい基本理念
- 著者
- 今福 輪太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-002, (Released:2021-01-20)
- 参考文献数
- 15
質的研究の目的は,研究対象となる当事者の視点から見える事象や人々との関わり,その人の心情などの内面的世界を理解することにあり,事実に対する「良い」「悪い」の評価基準は保留することが重要である.医療者教育の分野においても質的研究への関心が高まり,質的研究を「やってみよう」「やってみたい」と思う人が増えてきている.しかしながら,それに比例して,「どんなリサーチ・クエスチョンを立てたらいいのか」「何人からデータを収集すればいいのか」「数値に表しきれない膨大なデータが蓄積されていくだけでこの先どうすればいいのか」「分析手順がわからない」など,質的研究を始めてはみたものの壁にぶつかる人も多くいるだろう.本稿では,質的研究を実施する中でしばしば生じる疑問に答えながら,質的研究の位置づけや目指すものを整理し,その基本理念や方略について考察していく.
9 0 0 0 スポオツ随筆
- 著者
- 辰野隆, 辰野保 著
- 出版者
- 大畑書店
- 巻号頁・発行日
- 1932
9 0 0 0 OA 鮫島夏樹先生を偲んで:『養之如春』
- 著者
- 宮本 和俊
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会
- 雑誌
- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.181-182, 2020-04-20 (Released:2020-04-20)
9 0 0 0 OA ポストモダン人文地理学とモダニズム的「都市へのまなざし」
- 著者
- 加藤 政洋
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.164-182, 1999-04-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 130
- 被引用文献数
- 3 1
There has begun to develop a burgeoning new problematic in recent works in human geography addressing the debate around postmodernism and the city. David Harvey's The Condition of Postmodernity (1989) and The Urban Experience (1989), and Edward Soja's Postmodern Geographies (1989) are major works on this theme. While their contribution to 'postmodern geography' is now widely accepted, they have been criticized by some feminist geographers such as Massey (1991) and Deutsche (1991) for their suppression of difference, their failure to be aware of masculinity and their lack of recognition of feminist theories of representation in their works. There is one other matter which is important in these criticisms. As Deutsche and Gregory (1994) have acutely pointed out, Harvey and Soja read the city as a distant silhouette and both accord a particular privilege to this distant view.The purpose of the present paper is to outline a series of debates, as mentioned above, around ways of seeing the city in contemporary urban studies in general, and to undertake a critical assessment of Harvey's voyeurism in his 'Introduction' to The Urban Experience and Soja's solar Eye (looking down like a God) in 'an imaginative cruise' in particular. In addition to this purpose, I am going to suggest two directions for a postmodern geographical critique of the modernist gaze on the urban condition-the politics of representation and the politics of scale.The second section of the paper explains the change in Harvey's attitude towards the city. We can observe this change in the transfiguration of the leading figure from a 'restless analyst' (in Consciousness and the Urban Experience) to 'the voyeur' (in The Urban Experience). Harvey, as the restless analyst, places an exaggerated importance on wandering the streets, playing 'flaneur', watching people, eavesdropping on conversations and reading local newspapers. In short, he learns more about the city and its urban condition by engaging in microgeographies of everyday life and pursuing a view from the city streets. As the voyeur, however, he makes a point of ascending to a high point and looking down upon the intricate landscape of streets, built environment and human activitv. In the 'Introduction' to The Urban Experience, Harvey so obviously prefers the view from above as a voyeuristic way of seeing the city that homogenizes street life, urban life and everyday life in a desire for legibility/readability. Thus, the privileging of the high viewpoint is his particular method of conceptualizing 'the city as a whole'. For Harvey as the voyeur, therefore, the position of restless analyst in the street 'cannot help acquiring new meaning'. This goes to his modernist sensibility.In Postmodern Geographies, Soja introduces his most exciting essay on Los Angeles as an attempt to evoke a 'spiraling tour' around the city that he made with Frederic Jameson and Henri Lefebvre. This essay is not a mere field report, but he tries to recapture their travels as ';an imaginative cruise'! The third section of the paper points out that his 'imaginative cruise' is conducted from many vantage-points and so Soja's position on urban studies implies a Foucaldian panoptic gaze. For example, although Soja declares that 'only from the advantageous outlook of the center can the surveillant eye see everyone collectively, disembedded but interconnected', he climbs the high rise City Hall building and looks down on the landscape of downtown. The view from this site is especially impressive to Soja as one of surveillance.What I try to show in sections 2 and 3 is that there is a great similarity between Harvey and Soja in their ways of seeing the city.
9 0 0 0 OA 生活行為の評価と支援の実際
- 著者
- 石橋 裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年療法学会
- 雑誌
- 日本老年療法学会誌 (ISSN:2436908X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-5, 2022-11-28 (Released:2022-12-08)
- 参考文献数
- 30
生活行為とは人々が毎日行っている活動のことであり,高齢者は疾患や障害,フレイルにより日々できることが少なくなる。また,生活行為の問題は,認知症の生活障害のように,疾患の特徴として報告されることもある。生活行為には様々な方法で評価できるが,それぞれ異なった特徴を有している。具体的には,包括尺度なのか特異的尺度なのか,抽象化された質問か具体的な質問か,可否を問うのか実施状況を問うのかなどである。それらの中には,対象者に生活行為の意味や優先度を尋ねることにより,支援に生かすこともできる評価もある。生活行為の評価方法の違いは,生活行為に対する包括的支援なのか,集中支援なのかといった違いにもつながっている。一方で,最近はプログラム中に生活行為の目標を明確にするなどの取り組みも行われるようになり,双方の利点を生かしたプログラムも開発されるようになった。生活行為の評価と支援のためには専門的な知識が必要ではあるが,今後は広く社会に普及するための評価と支援方法の開発が望まれる。
9 0 0 0 OA スルガ銀行不正融資事件の事例研究(Ⅱ)
- 著者
- 樋口 晴彦
- 出版者
- 千葉商科大学国府台学会
- 雑誌
- 千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.105-150, 2021-03-31
9 0 0 0 OA コロナ禍で国際会議へ現地参加してみた!
- 著者
- 金子 正弘
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.1279-1283, 2022 (Released:2022-12-15)
- 参考文献数
- 4