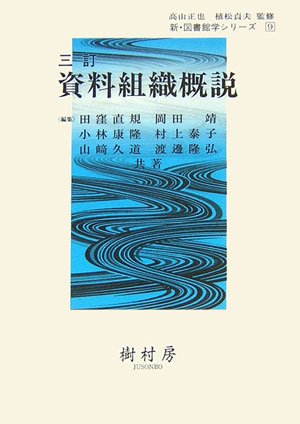Self-practice/Self-reflectionプログラム(SP/SR)とは、認知行動療法の新しいトレーニング法である。自らの問題に対して認知行動療法の技法を使って取り組み(Self-practice)、そのプロセスを振り返って記述する(Self-reflection)ことによって、スキルの知識や技法の習熟だけでなく、体験的理解が促され今後に生かすべきことを自分で見つける省察力が育まれることが明らかになっている。本研究では、SP/SRプログラムの日本語版を確定し、心理職のトレイニーの省察力がこのプログラムによって高まるかを確認する。
1 0 0 0 IR カキ料理構文の成立条件について : 文末名詞文との比較
- 著者
- 丹羽 哲也
- 出版者
- 大阪市立大学国語国文学研究室文学史研究会
- 雑誌
- 文学史研究 (ISSN:03899772)
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.56-70, 2020-03
一 カキ料理構文と非飽和名詞 : (1) a 広島がカキ料理の本場だ。 / b カキ料理は広島が本場だ。 / (1)bのように、「XはYがZだ」という二重主語構文において、「YがZだ」が指定関係にあり、かつ、「YがZだ」全体がXの属性を表す関係にあるものは、カキ料理構文と呼ばれる。この構文の成立条件について、西山(二〇〇三:276)は次のように規定する。……
- 著者
- 横田, 紘季
- 巻号頁・発行日
- 2016-03-31
1 0 0 0 IR 説明的文章の読解方略指導に関する実践研究-選択性に到達した授業に着目して-
- 著者
- 大森 康貴
- 雑誌
- 奈良教育大学教職大学院研究紀要「学校教育実践研究」 = Bulletin of School of Professional Development in Education (SPDE), Nara University of Education (ISSN:18836585)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.19-28, 2021-03-31
国語科教育研究では、自立した読み手の育成のために読解方略の概念が導入されてきた。しかし小学校段階での読解方略指導の実践研究はまだ少なく、単元全体を読解方略指導として構想した実践の有効性の検証が十分なされているとはいえない。また、読解方略の学習段階に応じた指導方法の検討についても課題が残る。そこで本研究では小学校第6学年を対象に、単元全体を読解方略指導として構想した実践を行い、その有効性の検証及び子どもの読解方略の学習を促進する指導について考察した。実践の結果、小学校第6学年において、読解方略を意識できる段階(意識性)に90%程度、読解方略を適切に選択できる段階(選択性)に70%程度の子どもが到達する等、一定の成果が見られた。また、選択性に向けた読解方略指導においては、読みの困難を明確に意識させる、子ども自身に読解方略を使わせる、考えの共有を通して読解方略の有効性を認識させる、ための指導の工夫が特に重要であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 高校生向け探究型プログラムがスキーム通り働いたか否かを検証する
- 著者
- 田村 馨 兵土 美和子 Tamura Kaoru Hyodo Miwako
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学商学論叢 = Fukuoka University Review of Commercial Sciences (ISSN:02852780)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3-4, pp.407-423, 2021-03
1 0 0 0 IR 『源氏物語』「落葉宮」試論--髪と塗籠をめぐって
- 著者
- 鈴木 温子
- 出版者
- 駒沢大学文学部国文学研究室
- 雑誌
- 駒沢国文 (ISSN:04523652)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.233-254, 2001-02
1 0 0 0 源氏物語の「塗籠」(読む)
- 著者
- 橋本 ゆかり
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.9, pp.68-73, 1999
1 0 0 0 塗籠の起源に関する一考察
- 著者
- 水谷 昌義
- 出版者
- 文化史学会
- 雑誌
- 文化史学 (ISSN:05217938)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.p105-125, 1987-11
1 0 0 0 資料組織概説
- 著者
- 田窪直規 [ほか] 共著
- 出版者
- 樹村房
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 一色直氏と秘曲伝授--手鑑と「中原芦声抄」
- 著者
- 山口 隼正
- 出版者
- 神奈川県立金沢文庫
- 雑誌
- 金沢文庫研究 (ISSN:04531949)
- 巻号頁・発行日
- no.275, pp.p17-27, 1985-09
1 0 0 0 IR ドイツにおける妊娠中絶法の改革--国際的比較法的観点において
- 著者
- Eser Albin 今井 猛嘉
- 出版者
- 北海道大学法学部
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.p1751-1777, 1994-03
1 0 0 0 IR 過疎地域における公共交通網存続の背景 : 秩父地方を事例として
- 著者
- 福留 邦洋
- 出版者
- 東京学芸大学地理学会
- 雑誌
- 学芸地理 (ISSN:09112693)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.79-98, 1996-03-31
1 0 0 0 IR 中華民国(台湾)における政治体制の移行:権力闘争と「統独」問題を中心にして
- 著者
- 村上 和也
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.303-332, 1997-10
1 0 0 0 IR 多国籍企業の法律問題--法人の国籍と裁判管轄権を中心として
- 著者
- 桜井 雅夫
- 出版者
- 慶應義塾大学法学研究会
- 雑誌
- 法学研究 (ISSN:03890538)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.p133-167, 1986-02
はじめに一 用語の分解二 TNCの定義三 TNCの現実と法の乖離四 TNCの国内法問題 1 法人の国籍 2 牴触法上の問題五 TNCの国際法問題 1 会社設立の準拠法 2 会社の準拠法 3 裁判管轄権六 TNCに対する各国の態度 1 諸規整とTNCの対処策 2 本拠地法主義と設立準拠法主義の衝突結びに代えて須藤次郎先生退職記念号
1 0 0 0 IR 大和田健樹の作文教授観
- 著者
- 岡 利道
- 出版者
- 広島文教女子大学教育学会
- 雑誌
- 広島文教教育 (ISSN:09138870)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.1-16, 1996-03-15
1 0 0 0 明治翻訳史の一断面:―大和田建樹を中心として―
- 著者
- 岡本 昌夫
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.23-33, 1961
<p> It is commonly known that the New Style Poetry of the Meiji Era, called ' Shintaishi ' in Japanese, started under the influence of Western Poetry. In point of style and metre, the translation poems of the Early Meiji Era seem to have given examples for the New Style Poetry. Ōwada's <i>Ōbeimeikashishū</i> (Selected Poems from Famous Western Authors) published in 1894, is especially considered to be among those examples by the later Meiji poets, though there are some other previous works, such as <i>Shintaishishō</i> (Selections from New Style Poetry) translated by Inoue, Takayama and Yatabe.</p><p> In <i>Ōbeimeikashishū</i> Ōwada translated more than one hundred Western poems into Japanese in seven-and-five syllable metre verse, just as Inoue and two others had done in their <i>Shintaishishō</i>. But his selection of seven-and-five syllable metre in his translation was the result of deliberate consideration and experiments of the translator, not because of his imitative instinct. Ōwada composed various styles of poems previous to his <i>Ōbei- meikashishū</i> and found seven-and-five syllable metre fittest for the New Style Poetry.</p><p> Thus after many experiments by such translators, as Ōwada, the form of the New Style Poems of the Meiji Era was established, which was brought to its perfection by such poets as Shimazaki Tōson and Tsuchii. Bansui</p>
1 0 0 0 IR 古今東西の土間と板敷の生活
- 著者
- 土田 充義
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 南太平洋海域調査研究報告=Occasional papers (ISSN:02892707)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.163-172,
1 0 0 0 IR 南極・北極に見る地球温暖化の現状と将来 : 南極・北極は本当に温暖化しているのか?
- 著者
- 山内 恭
- 出版者
- 京都大学ヒマラヤ研究会・総合地球環境学研究所「高所プロジェクト」
- 雑誌
- ヒマラヤ学誌 : Himalayan Study Monographs (ISSN:09148620)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.212-220, 2009-05-01
この30 年地球全体は温暖化の兆候にあるが, 氷の世界である南極, 北極の極地もやはり温暖化しているのだろうか. 極地の氷はどうなるのだろうか. 最近の研究成果から迫ってみた.
1 0 0 0 OA 南極・北極に見る地球温暖化の現状と将来 : 南極・北極は本当に温暖化しているのか?
- 著者
- 山内 恭
- 出版者
- 京都大学ヒマラヤ研究会・総合地球環境学研究所「高所プロジェクト」
- 雑誌
- ヒマラヤ学誌 : Himalayan Study Monographs (ISSN:09148620)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.212-220, 2009-05-01
この30 年地球全体は温暖化の兆候にあるが, 氷の世界である南極, 北極の極地もやはり温暖化しているのだろうか. 極地の氷はどうなるのだろうか. 最近の研究成果から迫ってみた.