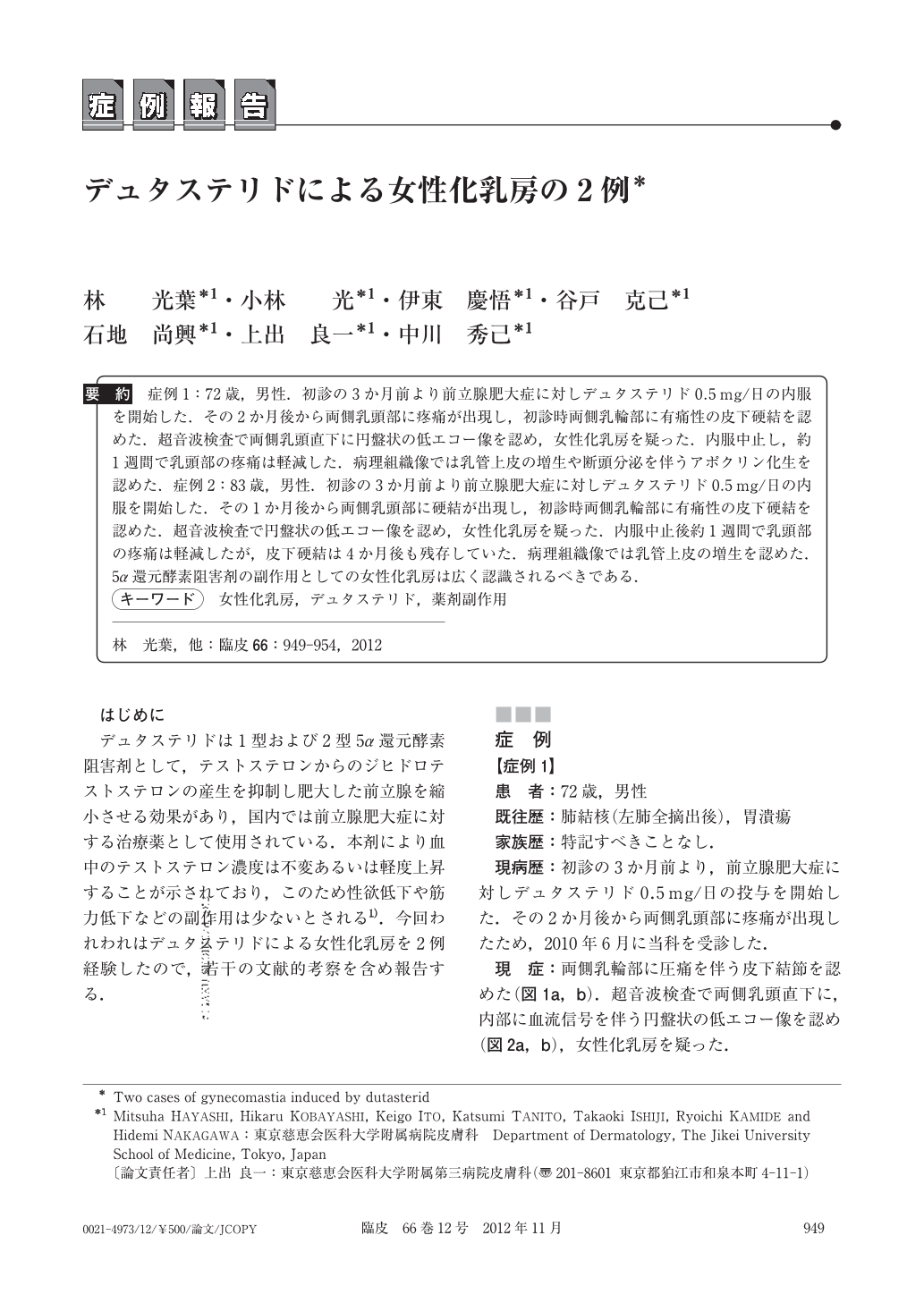1 0 0 0 バイオインフォマティクス
- 著者
- 阿久津 達也
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.247-251, 2021-06-01 (Released:2021-06-01)
バイオインフォマティクスは生物学と情報学の学際領域であり,1990年代から2000年代前半にかけて実施されたヒトゲノム計画や,他のゲノム計画の進展に伴い大きく発展した。本稿ではバイオインフォマティクスにおける代表的な研究課題を紹介する。具体的には,配列アラインメント,配列検索,遺伝子発見,進化系統樹推定,ゲノムワイド関連解析,タンパク質立体構造予測,遺伝子発現データ解析,生体ネットワーク解析などについて簡潔に説明する。日本におけるバイオインフォマティクス研究の歴史や発展についても紹介するとともに,近年における新たな展開や今後の展望について議論する。
- 著者
- 北本 朝展
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.240-246, 2021-06-01 (Released:2021-06-01)
第四パラダイムとは,実験・観測科学,理論科学,計算科学に続く第四の科学研究の枠組みであるデータ中心科学を指す言葉である。大規模データを集約したデータベースの構築から始まり,データ駆動型分析を通して新しい知見を得るという科学研究の方法論が様々な分野に浸透し,X-インフォマティクスと呼ばれる新しい分野群を形成しつつある。本論文はX-インフォマティクスの特徴を概観するとともに,いくつかの分野における事例をもとに,その強みと弱みをまとめる。さらにX-インフォマティクスが引き起こす研究方法の変化についても,測定者と解析者の分離と信頼などの点から論じる。
1 0 0 0 特集:「X-インフォマティクス」の編集にあたって
- 著者
- 炭山 宜也
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.239, 2021-06-01 (Released:2021-06-01)
2021年6月号の特集は「X-インフォマティクス」です。情報科学と生物科学を融合した情報生物科学がバイオインフォマティクスという言葉で広く知られるようになってきましたが,「バイオ」以外の「X-インフォマティクス」という言葉もよく耳にするようになってきました。蓄積された膨大なデータに情報学的アプローチを適用することで新しい発見を狙うX-インフォマティクスは,自然科学分野を中心に広がりを見せています。本特集では,X-インフォマティクスの特徴や事例について5人の方々から解説をいただきました総論では国立情報学研究所の北本朝展氏に,科学研究のパラダイムシフトにおいて第四パラダイムという概念から,X-インフォマティクスについて,自然科学,人文学,社会科学等の各分野の状況と今後の進展について解説していただきました。京都大学の阿久津達也氏には,1990年に始まったヒトゲノム計画をきっかけにX-インフォマティクスの中で先行してきたバイオインフォマティクスについて,代表的な研究課題を紹介していただくとともに,国内における研究の歴史や発展について解説していただきました。物質・材料研究機構(NIMS)の出村雅彦氏には,データ駆動型の材料開発手法として最近注目されているマテリアルズ・インフォマティクスについて,NIMSで行っているデータ駆動研究とこれを支えるデータインフラについて解説していただきました。MI-6株式会社の入江満氏には,自然科学分野の代表的なX-インフォマティクスの比較及びX-インフォマティクスと計算科学や人工知能との関りについて解説していただきました。東京大学の加納信吾氏には,医療分野におけるテキスト情報によるデータを活用した分析事例として,助成金データベースを利用した先端医療技術のトレンド分析について解説していただきました。近年の第三次AIブームも相まって自然科学分野でのデータ駆動型研究が活発化しています。人文学や社会科学の分野ではデジタル-Xやコンピュテーショナル-Xとも呼ばれ,今後データを活用した研究の発展が期待されています。本特集が情報やデータを扱うインフォプロの業務の参考になれば幸いです。(会誌編集担当委員:炭山宜也(主査),野村紀匡,水野澄子,南山泰之)
1 0 0 0 OA 肝癌スクリーニングと肝腫瘍診断のための超音波所見の標準化
- 著者
- 西村 貴士 飯島 尋子
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.240-250, 2021-05-01 (Released:2021-05-14)
- 参考文献数
- 26
肝腫瘍に対して,米国を中心として画像診断レポートの標準化が行われている.CT/MRIに続いて超音波判定システムであるUS/CEUS LI-RADSは,American College of Radiology(ACR)によって提唱された肝癌診断アルゴリズムであり,American Institute of Ultrasound in Medicine(AIUM)やAmerican Association for the Study of Liver Diseases(AASLD)でも推奨され用いられている.今後わが国でも,US/CEUS LI-RADSに基づいた肝腫瘍のカテゴリー分類,レポートの標準化に向かう方向と考えられ,米国のCEUS LI-RADSとわが国の肝癌診療ガイドラインを併せてSonazoidⓇによる診断を追記し概説する.
1 0 0 0 OA 大都市圏郊外の鉄道駅周辺における居住と通勤の特性 ―近鉄大和西大寺駅を事例に―
- 著者
- 稲垣 稜
- 出版者
- 日本都市地理学会
- 雑誌
- 都市地理学 (ISSN:18809499)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.11-22, 2016 (Released:2019-05-31)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1
本研究では,近鉄大和西大寺駅周辺において実施したアンケート調査をもとに,郊外の鉄道駅周辺居住者の居住,通勤特性を明らかにした.一戸建て住宅には1970 年代以前に入居した高齢者が多く,分譲マンションには2000 年代に入居した30 〜40 歳代の者が多い.また,大部分が一戸建て住宅で占められている地域に比べ,本対象地域では,人口の郊外化以前からの居住者割合が高い.通勤先をみると,分譲マンション居住者は大阪市,賃貸・借家や一戸建て住宅居住者は郊外内での就業率が高い.一戸建て住宅居住者の中には自営業者が多く,本対象地域が市街化した1970 年代までに,当地域で商店などを開業した人々が含まれると考えられる.奈良県出身者は,県外出身者に比べ,ローカルな労働市場の存在ゆえに,比較的近隣での就業率が高い.本研究を通じて,大部分が一戸建て住宅で占められている地域とは異なる郊外の鉄道駅周辺の居住,通勤特性の一端を明らかにすることができた.
1 0 0 0 OA パルサーグリッチ理論の新展開 : 中性子星内部の原子核構造と超流動との関わり
- 著者
- 望月 優子 伊豆山 健夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.316-325, 2001-05-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 17
中性子星にグリッチと呼ばれる現象がある.正確に一定の割合で自転の速度が遅くなっていた中性子星が,あるとき,突然スピンアップする現象である.グリッチが初めて観測されてから30年あまり経つが,その起源はあまりよくわかっていない.私たちは,「渦糸のなだれ的ピンはずれ」がその原因であると考える.渦糸の芯のところに『核の棒』ができ,そこに渦糸が捉えられる,ということを示し,しだいに押し寄せてくる渦糸によって,捉えられていた渦糸が雪崩のようにはずれるのがグリッチである,という理論を提唱する.
1 0 0 0 OA マックス・ヴェーバーにおける「教養(ビルドゥング)」
- 著者
- 山室 信高
- 出版者
- 東洋大学人間科学総合研究所
- 雑誌
- 東洋大学人間科学総合研究所紀要 = The Bulletin of the Institute of Human Sciences,Toyo University (ISSN:13492276)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.151-166, 2017-03
1 0 0 0 OA 東京大都市圏における近郊都市,八王子・町田両都市の都心部の変化
- 著者
- 山下 博樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.280-295, 1991-04-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
The cities of Hachioji and Machida, located in the western suburb of Tokyo, have developed with the expansion of the Tokyo metropolitan area. But the two cities have different histories. Hachioji city was a stage town (shuhubamachi) in the late feudal period, and developed into a central city in the Tama area after the Meiji Restoration. Machida does not have such a long history; it deve-loped as an urban area only after the opening of the national railways' Yokohama Line and the private Odakyu Line in the late. The author analyzed the processes of change in the central business district (CBD) structure of the two cities, using such indicators as the change in functional accu-mulation, location of multi-storied buildings, and change in floor use for each function, with the comparison being made between 1981 and 1987. The following are a few results in the differences of changes of CBDs in the two cities. 1) The differences in the function of CBDs in the two cities can be explained by differences in the process of accumulation. Hachioji has experienced a shift of the core of its CBD from Koshu-kaido highway to Hachioji station, and its CBD has been differentiated functionally. But in Machida, because the CBD developedd near the station of the Odakyu Line, various functions already existed there. The survey also shows a reductive tendency in the area which serves some functions of the CBD (Figs. 1-3, Tables 1-4). 2) The differences in shape between the two CBDs can also be observed from a survey of the locations of multi-storied buildings. In Hachioji, the density of those buildings which were located on the three main streets stretching away from the station in 1981 has increased since 1981, and there is now a cluster of them in front of the station. In Machida, the number of multi-storied buildings which could be seen in the core of the CBD has increased in area surrounding it. The difference in the process of forming the CBD in the two cities reflects the differences in building use in the two CBDs (Fig. 4, Table 5). 3) The cluster analysis for changes in floor use reveals the degree of the functional areal differ-entiation in each of the CBDs. In Hachioji, three kinds of clusters can be recognized separately: offices, personal services, and parking and vacant lots. In Machida, the cluster which changed to office use is dominant. The comparison between present and previous functions of each floor in the buildings of the two CBDs shows the difference in the CBD development processes (Fig. 5). Those differences can be explained by both the historical background and the CBD development processes. Hachioji experienced functional areal differentiation in the shift of its CBD core. But Machida developed into a satellite city after the railroads opened in the Meiji period. As a result, the functions in the CBD have accumulated differently.
1 0 0 0 OA 聴神経腫瘍定位放射線治療後の長期聴力変化
- 著者
- 鴫原 俊太郎 野村 泰之 平井 良冶 増田 毅 野口 雄五 浅川 剛志 亀井 知春 池田 稔
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.575-576, 2011 (Released:2013-12-05)
1 0 0 0 視覚障害者用文字認識システムにおけるレイアウト/論理情報抽出法
視覚障害者が簡単に操作でき、日常的な印刷情報にアクセスすることのできる文字認識システムの開発を行なっている。出力は合成音声によるので、文書の内容に素早くアクセスするには文書の論理構造に基づいた構造化が必要となる。また、表題や、ページ番号などは本文と独立にヘッダ、フッタなどに記載されているのでこれらの主に物理的配置に基づいた構造の抽出及びそれへのアクセスが問題となる。本稿では再帰的X-Yカットを用いた文字列の物理的配置の解析手法によるヘッダ、フッタなどの物理的情報の抽出、及び行の端点の並びからのパラグラフ、見出しなどの論理構造の抽出について報告する。
- 著者
- 箸本 健二 駒木 伸比古
- 出版者
- 日本都市地理学会
- 雑誌
- 都市地理学 (ISSN:18809499)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.1-19, 2009-03-15 (Released:2020-04-08)
- 参考文献数
- 22
本稿は,1都7県に立地する287 店舗のコンビニエンスストアを,POS データに基づく販売特性からタイプ分類した上で,平日と週末での販売特性の差異を把握し,その背景にある地理的要因を検討する.分析の結果,287 店舗のコンビニエンスストアは7つの店舗類型に区分できる.各店舗類型を規定する因子は,主として外出先因子(昼間人口),家庭内因子(夜間人口),他業態代替因子(競合状況)の3因子である.また7つの店舗類型は,国道16 号線の内側に卓越する5類型と,外側に卓越する2類型に大別され,国道16 号線を挟んで店舗類型が大きく変化している.次にPOS データを平日・週末に分け,各別に店舗類型を作成すると,含まれる店舗は変化するものの,店舗類型そのものは平日と週末とでほぼ共通している.平日と週末とで属する類型が異なる店舗は,来街者の数や質が平日と週末で大きく異なるオフィス街や学校・駅周辺に多く分布する.
1 0 0 0 OA テナガザルの進化はどこまでわかっているか?
- 著者
- 國松 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.65-85, 2003 (Released:2005-03-24)
- 参考文献数
- 94
- 被引用文献数
- 2 1
The extant hylobatids are relatively small primates, and often called lesser apes. The body weight is 5-8 kg for the majority of the hylobatid species, and 10-12 kg for the largest species, Hylobates syndactylus. Recent taxonomy classifies the hylobatids into a single genus Hylobates with four subgenera (Hylobates, Nomascus, Bunopithecus, & Symphalangus) (Groves, 2001).The present geographical distributions of the subgenera are almost perfectly bordered by three (or possibly four) huge rivers in Eastern Eurasia, that is, the Brahmaputra, Salween, Mekong (and Yangtze) Rivers. All these rivers originate from the Tibetan Plateau. Although van Gulik (1967) reconstructed the historical distribution of gibbons in China as being expanded northwards over the Yangtze River up to the Yellow River, the Pleistocene fossil evidence suggests that the northern limit of the gibbon distribution in China was probably the Yangtze River.Recent genetic studies suggest that these subgenera began to diversify around several to ten million years ago. In this period, the Tibetan Plateau reached a considerable altitude. The uplift of the Plateau probably influenced the development of the above mentioned huge rivers, strengthening the function of these rivers as zoogeographical barriers. It seems likely that the proto-hylobatid populations were then isolated from each other, and evolved into recent subgenera, though the diversification between the subgenera Hylobates and Symphalangus needs another explanation.At present, the fossil record of the hylobatids is very poor. There are some Pleistocene gibbon fossils discovered from southern China and Southeast Asia, but no Neogene fossil catarrhines, small or large, are thought to be the direct ancestor of extant gibbons. In Southeast Asian countries, except for a few findings such as the Chiang Muan hominoids discovered from Thailand by the Thai and Japanese scientists, we know nothing about the Neogene fossils of both large and small hominoids. No doubt further field works are necessary to reveal the evolutionary history of gibbons.
1 0 0 0 OA 東北地方の聴覚障害特別支援学校における 乳幼児教育相談に関する調査報告
- 著者
- 佐藤 大地 庭野 賀津子
- 出版者
- 東北福祉大学教育・教職センター特別支援教育研究室
- 雑誌
- 東北福祉大学教育・教職センター特別支援教育研究年報 (ISSN:21850275)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.49-65, 2021-03-31
聴覚障害は新生児聴覚スクリーニング検査にて早期に発見され、早期からの適切な支援が行われることによって、有効な音声言語の発達を促すことが可能であると指摘されている。その早期支援の重要な役割を担っているのが、聴覚障害特別支援学校における乳幼児教育相談である。 本稿では、東北地方の聴覚障害特別支援学校14校の乳幼児教育相談を対象に実施した質問紙調査の結果より、乳幼児教育相談における支援活動と関係機関との連携に関する現状と今後の課題について検討することを目的とした。1955年代から制度的な裏付けがないまま継続されてきた聴覚障害特別支援学校における乳幼児教育相談は、担当教員による工夫や努力と関係機関との連携のうえで、教育相談が継続されてきているものの、今後検討されていくべき課題が多いことが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 過敏性腸症候群に対する認知行動療法の実際
- 著者
- 船場 美佐子 河西 ひとみ 藤井 靖 富田 吉敏 関口 敦 安藤 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.330-334, 2021 (Released:2021-05-01)
- 参考文献数
- 24
難治性の過敏性腸症候群 (IBS) に対する心理療法の1つとして, コクラン・レビューでは認知行動療法 (CBT) の有効性が示されている. 本稿では, 近年日本で臨床研究が実施されている, IBSに対する 「内部感覚曝露を用いた認知行動療法 (CBT-IE)」 とその構成要素, CBT-IEの臨床研究の動向を紹介する.
1 0 0 0 音声テンプレート統合法
テンプレートを用いる音声認識ではその良否が直接認識結果に反映される。テンプレートの最も簡単な作成法は、ある一つの発声をもってテンプレートとする方法である。しかしこの方法は一つの発声のみに頼るので偏りが避けられないし、発声の変動が大きくなったり、テンプレートを適応化させようとした時にはうまくいかない。これらの問題点を解決するためにテンプレートを複数個使う方式(マルチ・テンプレート法)があるが、与えられた学習用発声全部をそのままテンプレートとして持つのでは記憶域及び計算量が大きくなってしまい、得策ではない。そこで、与えられたテンプレートから一つあるいは少数のテンプレートを作りだす方法が要求される。本稿ではその方法の一つとして、「重み付きDPマッチング」を利用した新しいテンプレート作成法(AWDP法:Average by Weighted DP)を示す。
1 0 0 0 視覚障害者用OCRシステムの設計
1 0 0 0 デュタステリドによる女性化乳房の2例
要約 症例1:72歳,男性.初診の3か月前より前立腺肥大症に対しデュタステリド0.5mg/日の内服を開始した.その2か月後から両側乳頭部に疼痛が出現し,初診時両側乳輪部に有痛性の皮下硬結を認めた.超音波検査で両側乳頭直下に円盤状の低エコー像を認め,女性化乳房を疑った.内服中止し,約1週間で乳頭部の疼痛は軽減した.病理組織像では乳管上皮の増生や断頭分泌を伴うアポクリン化生を認めた.症例2:83歳,男性.初診の3か月前より前立腺肥大症に対しデュタステリド0.5mg/日の内服を開始した.その1か月後から両側乳頭部に硬結が出現し,初診時両側乳輪部に有痛性の皮下硬結を認めた.超音波検査で円盤状の低エコー像を認め,女性化乳房を疑った.内服中止後約1週間で乳頭部の疼痛は軽減したが,皮下硬結は4か月後も残存していた.病理組織像では乳管上皮の増生を認めた.5α還元酵素阻害剤の副作用としての女性化乳房は広く認識されるべきである.
1 0 0 0 泡鳴「断橋」 : その成立と創作主体
- 著者
- 鎌倉 芳信
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.10, pp.62-70, 1987
「断橋」は、作者が北海道内を巡歴した時の記事をもとに構成されている。小説では、この記事の上に現実崩壊や存在基底喪失の幻影風景を重ねている。幻影風景は北海道放浪当時の作者の存在の不安や恐怖の変形したものと考えられる。樺太での事業の企ては、自己の哲学の実践であると考えながらも、もしかしたら狂気の沙汰に過ぎないかもしれないというアイデンティティーの危機意識が幻影風景となって表われたものである。
1 0 0 0 OA 既婚女性看護師のワーク・ライフ・バランスの満足感とその関連要因
- 著者
- 本島 茉那美 冨樫 千秋 土井 徹 境 俊子
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.7-16, 2017-04-30 (Released:2017-08-14)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2
本研究では,関東圏内200床以上を持つ病院46施設に勤務する既婚女性看護師632名を対象に,既婚女性看護師のワーク・ライフ・バランス(WLB)の満足感とその関連要因を明らかにするために,質問紙調査を実施した。分析にはχ 2乗検定,Mann WhitneyのU検定を行った。WLBの満足感の関連要因は,「所属部署」,「超過勤務時間」,「運動習慣の有無」,「家族とのコミュニケーションの有無」,「研修への参加の有無」,「ロールモデルの有無」,「目標の有無」,「キャリアプランの実施の有無」,「職業継続意思の有無」,「制度利用の有無」,「職務満足度」とその下位尺度(職業的地位,給料,看護管理,医師と看護師間の関係,看護師間相互の影響,専門職としての自律性,看護業務),「主観的幸福感」,職業性ストレス調査票の下位尺度「職場の社会的支援」とその構成要素(上司からの支援,同僚からの支援),「ソーシャルサポート」,「精神的健康度」であった。WLBの満足感は,「WLBに満足していますか」という質問で,「満足している」「満足していない」という回答で測定できることが明らかになった。これらの結果は,WLBに満足するためには,運動習慣をもつこと,家族とのコミュニケーションをとること,ロールモデルを持つこと,キャリアプランを実施すること,社会資源を利用することが必要であることが示唆された。また,看護管理者は,職場の社会的支援や職務満足度がWLBの満足感に影響していることを念頭におき,これらを支えていくことが必要であることが示唆された。