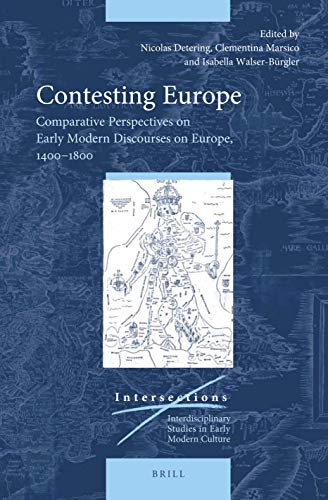1 0 0 0 近代皇室特別展 : 明治百年記念
- 出版者
- [松坂屋]
- 巻号頁・発行日
- 1968
1 0 0 0 Contesting Europe : comparative perspectives on early modern discourses on Europe, 1400-1800
- 著者
- edited by Nicolas Detering Clementina Marsico Isabella Walser-Bürgler
- 出版者
- Brill
- 巻号頁・発行日
- 2020
1 0 0 0 朝型人間と夜型人間
- 著者
- 柴田 収一
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- からだの科学 (ISSN:04533038)
- 巻号頁・発行日
- no.133, pp.p85-88, 1987-03
1 0 0 0 OA Clinical Characteristics and Prognostic Factors in Dogs with Histiocytic Sarcomas in Japan
- 著者
- Masashi TAKAHASHI Hirotaka TOMIYASU Eri HOTTA Hajime ASADA Kenjiro FUKUSHIMA Hideyuki KANEMOTO Yasuhito FUJINO Koichi OHNO Kazuyuki UCHIDA Hiroyuki NAKAYAMA Hajime TSUJIMOTO
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.5, pp.661-666, 2014 (Released:2014-06-02)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 24 40
Canine histiocytic sarcoma (HS) is a rare neoplasm that originates from dendritic cells or macrophages, and there have been a number of cases experienced in Japan. To identify the characteristics and prognostic variables that determine outcome in dogs with HS in Japan, medical records of 73 dogs with HS were retrospectively analyzed. Signalment, clinical signs, complete blood count (CBC), blood chemistry profiles, treatment, response to treatment and overall survival (OS) were analyzed. Diagnosis of HS was determined histologically in 44 cases and cytologically in 29 cases. The most frequently diagnosed breeds were Flat-Coated Retrievers (n=16, odds ratio [OR] 62.0), Pembroke Welsh corgis (n=15, OR 9.7) and Bernese Mountain dogs (n=14, OR 45.0). Median survival time for all dogs in this study was 43 days. In the dogs that received no treatment or only symptomatic treatment, the median OS was 12 days (range 2–254 days) compared with that of dogs that received surgical treatment and/or chemotherapy (85 days, range 4–360 days). Univariate analysis identified anemia, thrombocytopenia, hypoalbuminemia, hypoproteinemia and not receiving antitumor treatment (chemotherapy and/or surgery) as factors significantly associated with shorter OS. Multivariate analysis confirmed that platelet counts, localized/disseminated lesional pattern and whether the dog received antitumor treatment were significantly predictive of survival.
1 0 0 0 家庭・生活環境からみる支援方法について―Aさんのケース報告―
- 著者
- 畑野 容子 中口 潤一 原田 敦史 内田 まり子
- 出版者
- 視覚障害リハビリテーション協会
- 雑誌
- 視覚障害リハビリテーション研究発表大会プログラム・抄録集
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.42, 2010
【はじめに】 2009年度から日本盲導犬協会 島根あさひ訓練センター(以下、当協会)では、中四国地方在住の視覚障がい者を対象に1週間の入所生活訓練を行う「視覚障がい短期リハビリテーション」(以下、短期リハ)を開始した。事業を利用したAさんの支援を香川県視覚障害者福祉センター(以下、福祉センター)と連携して行い、生活に変化をもたらすこととなった。その経過を報告する。【ケース】ケース:Aさん、右)0 左)光覚、30代女性、未婚、6人家族、自宅は中山間地域。生活状況:中学から盲学校に入学し、保健理療科へ進学したが免許取得はならず就職できなかった。卒後、現在に至るまで外出の機会は少なく、昼夜逆転の生活となり、一日の大半は自宅で録音図書を聞いて過ごしていた。障害基礎年金受給中。家計に余裕はない。【経過】・数年前に家族の意向で免許取得に向け福祉センターの在宅訓練を受けたが、モチベーションが保てず中断となった。・昨秋、福祉センターの訓練士が短期リハを勧めたことで参加。その後は、生活改善の意欲が高まり、更生施設への入所希望が聞かれるようになった。・当協会と福祉センターが自宅を訪問し、家族を含め希望・目標を確認。現在は福祉センターで歩行・点字の通所訓練を行い、秋には施設見学に行く調整を行っている。【考察】 Aさんの訓練を行ったことで10年間の引きこもり生活の要因が浮かび上がってきた。第1に地域的な要因である。10年前は福祉センターの在宅訓練はなかった。盲学校卒業後、近隣に相談できる場所がなく、適切な支援が受けられるような環境になかった。このためAさんの積極性が徐々に低下したと推測できる。第2に、Aさんの障害年金が家計の一部を補っているという要因である。就職して家計を助けたいという気持ちはあるが、自宅を出ることで家族に負担がかかると心配する面もあり、なかなか具体的な動きを取らなかった。第3に家族関係の要因である。Aさんの自立を応援する意思を示してきたが、経済的なことを懸念しているためか、現実的な話になるとあまり積極的ではない印象を受ける。現在はAさんの歩行・点字技術の向上とモチベーションの維持を目的に相談支援専門員にも経過を報告し、連携して継続的な支援を行っている。居住地域・生活状況によって本人の意向を汲み取るような適切なサービスが受けられない視覚障がい者の存在を改めて感じたケースとなった。
1 0 0 0 OA 三大意 : 附・祗順天命及代師之説
1 0 0 0 OA グローバル・ストラテジストの競争優位性の研究
- 著者
- 山本 尚利
- 出版者
- 早稲田大学WBS研究センター
- 雑誌
- 早稲田国際経営研究 (ISSN:18826423)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.75-85, 2011-03-31
1 0 0 0 OA 屋内化学物質による健康被害
- 著者
- 八木 正博
- 出版者
- 日本マイコトキシン学会
- 雑誌
- マイコトキシン (ISSN:02851466)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.69-74, 2002 (Released:2009-01-08)
- 参考文献数
- 12
化学物質過敏症やシックハウス症候群といった室内空気中の化学物質による健康被害について社会的関心が高まっており,厚生労働省の⌈シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会⌉は既にホルムアルデヒド,トルエン,キシレンなど12物質の室内濃度指針値案及び暫定指針値案を策定し,総揮発性有機化合物(TVOC)の暫定目標値を定めた1).個別の指針値案はリスク評価に基づいた値であり,その濃度以下であれば通常の場合はその化学物質は健康への悪影響を及ぼさないと推定された値である.上記検討会は今後も引き続き他の化学物質の指針値案を策定していく予定である.しかし,実際の室内空気には複数の化学物質が存在すること,リスク評価を行うためのデータが不足していること及び指針値を決めていない化学物質による汚染の進行を未然に防ぐ目的からTVOCの暫定目標値も定められた1).ところで,最近の室内空気問題というのは新建材の開発や建築技術の発展などに伴い,種々の化学物質が用いられ,それらが室内空気中に揮散され,さらに住居の気密化が進んだことにより室内空気中の有機化学物質濃度が高まったために問題が生じてきたと考えられている.家具や電気製品などの家庭用品についても種々の化学物質が用いられており,これらも有機化学物質の発生源になっていると推定されている.今回,室内空気中化学物質の濃度指針値案が策定されたことにより,建築物や家庭用品等の関係者が室内空気中化学物質の濃度を下げる工夫をすることが期待され,今まで原因がわからず,健康被害があった人々の多くが健康を取り戻すことができると思われる.さらに調査研究が進み,有害な化学物質の発生の少ない,地域の風土に適した21世紀型住居が建てられ,その住居に適した住み方が検証されることにより,室内空気中化学物質による健康被害で悩む人が減ることが期待される.
1 0 0 0 IR バージニア大学図書館における電子テキストセンター
- 著者
- Seaman David Stubbs Kendon 杉本 重雄 (訳)
- 出版者
- ディジタル図書館編集委員会
- 雑誌
- ディジタル図書館 (ISSN:13407287)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.63-67, 1997-03-05
1 0 0 0 OA 日本警察の沿革 : 維新から終戦まで
- 出版者
- 内務省警保局
- 巻号頁・発行日
- 1946
1 0 0 0 OA 害虫行動を制御する黄色ランプ
- 著者
- 田澤 信二
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.3, pp.217-221, 2001-03-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 小林多喜二における「歪曲の言説」
1 0 0 0 OA 伊藤仁斎における「恕」の意義
- 著者
- 木村 純二
- 出版者
- 国士舘大学哲学会
- 雑誌
- 国士舘哲学 (ISSN:13432389)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, 2003-03
1 0 0 0 OA 我が国の温泉医学振興のあり方に関する研究 —温泉医科学研究と入湯税(2018)—
- 著者
- 合田 純人 P. J. バロン 三友 紀男
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.76-79, 2018-08-31 (Released:2018-09-26)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 IR 入湯税の概要と法解釈 (玉巻弘光教授 退職記念論文集)
- 著者
- 藤中 敏弘
- 出版者
- 東海大学法学部
- 雑誌
- 東海法学 = Tokai law review (ISSN:09134441)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.21-53, 2017
- 著者
- 合田 純人 P. J. バロン 三友 紀男
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.76-79, 2018
1 0 0 0 OA 訪日外国人旅行者に向けた災害情報提供のあり方
- 著者
- 相引 梨沙 義澤 宣明 山口 健太郎 下村 徹 氷川 珠恵 瀧 陽一郎 山添 真喜子 栗山 章
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.182-188, 2016-06-15 (Released:2016-06-29)
- 参考文献数
- 20
日本を訪れる外国人旅行者(以下,訪日外国人旅行者)は,2015 年に過去最高の1 973 万人を記録し,今後も増加が見込まれている.観光立国実現に向け,災害時における訪日外国人旅行者の安全確保の重要性が高まっている. そのため,例えば観光庁では,訪日外国人旅行者の受入れを担う地域や民間事業者による災害時の安全確保のための環境整備やICT(情報通信技術)を活用して災害情報を提供するプッシュ型情報発信アプリ「Safety tips」の提供を行っている. 本稿では,訪日外国人旅行者に向けた災害時の情報提供の取り組みを紹介するとともに,災害時に情報弱者となりうる人々に向けた今後の災害情報提供のあり方についても考察する.
- 著者
- 柏田 良樹 森田 益史 野中 源一郎 西岡 五夫
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.856-860, 1990-04-25 (Released:2008-03-31)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 11 15
A chemical examination of the polyphenolic constituents of the fern, Dicranopteris pedata HOUTT., has led to the isolation of eight new proanthocyanidins possessing a doubly-linked (A-type) unit, together with known flavan-3-ols and proanthocyanidins. On the basis of chemical and spectroscopic evidence, they are characterized as epiafzelechin-(4β→8, 2β→O→7)-eniafzelechin-(4α→8)-epiafzelechin(8), epicatechin-(4β→8, 2β→O→7)-epiafzelechin-(4α→8)-epiafzelechin(9), epiafzelechin-(4β→8, 2β→O→7)-epizfzelechin-(4α→8)-epicatechin(10), epiafzelechin-(4β→8, 2β→O→7)-epicatechin-(4α→8)-epicatechin (11), epicatechin-(4β→8, 2β→O→7)-epiafzelechin-(4α→8)-epicatechin (12), epicatechin-(4β→8, 2β→O→7)-epicatechin-(4α→8)-epiafzelechin (13), epicatechin-(4β→8, 2β→O→7)-epicatechin-(4α→8)-epigallocatechin (14) and epiafzelechin-(4β→8)epicatechin-(4β→8, 2β→O→β→7)-epicatechin-(4α→8)-epicatechin (15).
- 著者
- 杉田 悠子
- 巻号頁・発行日
- pp.1-107, 2020-03-25
北海道大学. 修士(文学)