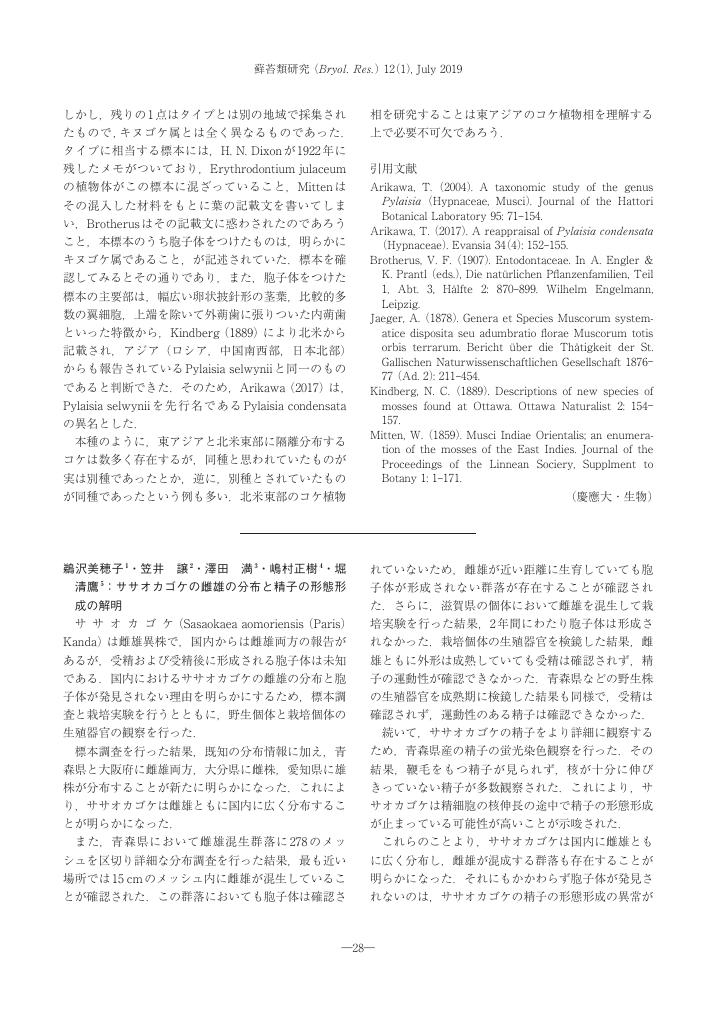1 0 0 0 OA 心理物理測定法
- 著者
- 中野 靖久
- 出版者
- 日本視覚学会
- 雑誌
- VISION (ISSN:09171142)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.17-27, 1995 (Released:2019-04-19)
- 著者
- 今井 洋子
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.74-90, 2006-03
漱石とコルタサルの作品の比較を始めたきっかけとなった『草枕』『石蹴り遊び』の中に見られる“オフェリアコンプレックス”“女性読者蔑視”を出発点として,これら作品の女性像についてフェミニズムの視点から分析する。 本論では『草枕』の那美さん,『石蹴り遊び』のラ・マガに代表される宿命の女たちはなぜ殺されたかを考察した。二人はこれまで男を惹きつけてやまない宿命の女として解釈されてきたが,近年フェミニズム批評によって,オフェリアコンプレックスの分析とともに,男の側の女性嫌悪が暴かれてきた。那美さんもラ・マガもその魔性によって抹消されたのではない。自我を持とうとしたゆえに男の共同体からの排除されねばならなかった。これが,彼女たちが殺された理由の一つである。漱石とコルタサルが生きた時代と場所と文化のコンテクストを考慮すれば,性の描写の違いは当然のことである。しかし,アジアとラテンアメリカからヨーロッパにやってきた知識人の疎外という意味では時代を超えた相似形を示す。つまり,漱石が産業革命後のロンドンに行き,その機械文明に疑問を抱いたように,ポストコロニアルのラテンアメリカからパリに行ったコルタサルは,西欧の論理に疑問を抱くのである。那美さんも,ラ・マガも,西欧の文明に対する“自然”を象徴する。しかし,その自然は西欧文明に“あさはかに”かぶれてしまっていた。これが彼女たちが殺されなければならなったもうひとつの理由である。
1 0 0 0 OA ササオカゴケの雌雄の分布と精子の形態形成の解明
- 著者
- 山田 栄 ヤマダ サカエ Sakae Yamada
- 雑誌
- 立教ビジネスレビュー = Rikkyo business review
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.62-77, 2014-07
1 0 0 0 OA 衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書
- 出版者
- 衆議院
- 巻号頁・発行日
- 2006-10
1 0 0 0 岡山県版レッドデータブック : 絶滅のおそれのある野生生物
- 著者
- 岡山県生活環境部自然環境課制作
- 出版者
- 岡山県環境保全事業団
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 まもりたい静岡県の野生生物 : 静岡県レッドデータブック
- 著者
- 静岡県くらし・環境部環境局自然保護課編集
- 出版者
- [静岡県くらし・環境部環境局自然保護課]
- 巻号頁・発行日
- 2019
- 著者
- 茨城県生活環境部環境政策課編
- 出版者
- 茨城県生活環境部環境政策課
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 千葉県の保護上重要な野生生物 : 千葉県レッドデータブック
- 著者
- 千葉県レッドデータブック改訂委員会編
- 出版者
- 千葉県環境生活部自然保護課
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 OA 交叉率と突然変異率を自動調整する改良遺伝的アルゴリズム
- 著者
- 王 超陽 賈 墨林 陳 奎廷 馬場 孝明
- 出版者
- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会
- 雑誌
- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成24年度電気関係学会九州支部連合大会(第65回連合大会)講演論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.349, 2012-09-14 (Released:2014-12-17)
近年、最適問題を高速に解く方法の一つに、遺伝的アルゴリズムは提案されてから、多くの応用分野において幅広く使われている。しかし、この手法は収束速度が遅いという問題がある。これを解決するため、本研究ではパラメータを自動調整する手法を用いた改良遺伝的アルゴリズムを提案する。この改良遺伝的アルゴリズムは、交叉率と突然変異率のパラメータを自動調整させることにより、収束速度を上げるという新しい手法である。さらに、例として一般的な遺伝的アルゴリズムとこの改良遺伝的アルゴリズムで実現したそれぞれのFIRフィルタを比較し、提案手法による結果がより良いことを示す。
1 0 0 0 OA ケータイを用いたコミュニケーションが対人関係の親密性に及ぼす影響 : 高校生に対する調査
- 著者
- 木内 泰 鈴木 佳苗 大貫 和則
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.Suppl., pp.169-172, 2008-12-20 (Released:2016-08-05)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
本研究では,高校3年生男女199名を分析対象とし,高校生のケータイ通話およびメールの利用が青少年の対人関係の親密性に及ぼし得る影響とその影響過程における媒介要因としての自己開示の役割を検討した.その結果,ケータイ通話については,ケータイ通話が多いほど,ネットでの自己開示,対面上の自己開示が多くなり,親密性が高まるというモデルの適合がもっともよいことが示唆された.さらに,ケータイメールの使用については,ケータイメールの使用が多いほどネットでの自己開示,対面上の自己開示が多くなり,親密性が高まる,あるいは,ネットでの自己開示から直接親密性が高まること,さらに,親密性が高いほどケータイメールをよく使用するようになる,という循環モデルの適合がもっともよいことが示唆された.
- 著者
- 大喜多 紀明
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.26, pp.518-528, 2016
<p> 近年,宮崎によるいくつかのアニメーション映画作品に裏返し構造が使用されていることが確認された.アニメ版『風の谷のナウシカ』は,合計6対の対応を持つ裏返し構造からなる<sup>[1]</sup>.本稿では,宮崎駿がアニメーション映画を創作する際に駆使した表現技法を明らかにすることを目的とし,[1]で示されたアニメ版『風の谷のナウシカ』の裏返し構造に関する知見に基づき,アニメ版の原作に相当する漫画版『風の谷のナウシカ』との対比を行った.その結果,アニメ版の裏返し構造は,漫画版がアニメ化される際に生成されたものであることが確認できた.</p>
1 0 0 0 女性犯罪の研究(1)ジェンダ-犯罪学への試み
- 著者
- 細井 洋子
- 出版者
- 日立みらい財団
- 雑誌
- 犯罪と非行 (ISSN:03856518)
- 巻号頁・発行日
- no.115, pp.220-256, 1998-02
1 0 0 0 犯罪学への招待(15)ジェンダ-と犯罪
- 著者
- 西村 春夫 守山 正
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナ- (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- no.522, pp.113-116, 1998-06
- 著者
- 矢野 恵美
- 出版者
- 日立みらい財団
- 雑誌
- 犯罪と非行 (ISSN:03856518)
- 巻号頁・発行日
- no.176, pp.153-176, 2013-09
1 0 0 0 都市空間における若年女性の犯罪不安:質的アプローチの導入
- 著者
- 齊藤 知範 根岸 千悠
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.10, 2011
<B>1.はじめに</B><BR><BR> 本報告では、若年女性の犯罪不安について、質的アプローチを導入することによる新たな枠組みを提示した上で、犯罪不安と都市空間における行動制約や防犯対策との関係について、試論的に考察を加えるものである。<BR> 犯罪不安がどのような社会的属性の人々に集中しやすいかは社会によって異なりうるが、重要な特徴のひとつとして、男女差の存在を挙げることができる。すなわち、他の諸要因を統計的にコントロールした上でも、女性のほうが男性よりも犯罪不安が高い傾向にあることが知られている(Ferraro 1995)。こうした男女差は、先進諸国において、比較的共通して観察されるパターンである。<BR> 一方で、犯罪不安は、主観的で多面的なものであり、生活世界を含めてその内実を深く知ろうとするほど、計量的手法だけでは、構造を解明する上で一定の限界があると考えられる。このため、質的手法が適する場合があり、諸外国においても、質的アプローチによる研究が行われてきた(若林 2009)。他方、吉田(2006)は、地理学におけるジェンダー研究を包括的に検討しつつ、育児等の再生産の舞台である郊外の住宅地における防犯のための監視性の高まりについて、ジェンダーの観点から考察を加えている。<BR><BR><B>2.先行研究</B><BR><BR> 犯罪学においては、犯罪や非行を犯す人間の心理や社会的環境要因に着目する犯罪原因論と、犯罪が起きやすい状況(場所、時間帯など)を生む条件や環境に着目する環境犯罪学の2つが、主要な説明理論として挙げられる。犯罪原因論はもとより、環境犯罪学においても、犯罪の被害に遭いうるターゲットが抱える犯罪不安や選択する防犯対策については、それほど考察がなされているとはいえない。<BR> 他方、小学生の防犯教育に関する実践的研究は比較的多くなされており、大西(2007)のレビューに詳しい。また、根岸(2011)は、公立高校の3年生(21名)を対象とする防犯の実験授業を実施しており、犯罪に関するリスクの情報を生徒に対して適切に伝達したり犯罪統計に関するリテラシーを身につけさせたりすることや犯罪不安の緩和などを目的とした、高校生の防犯に関するカリキュラム開発を行い、授業実践上の課題について明らかにしている。一方で、成人の犯罪不安や被害防止のためになされる防犯行動を空間との関わりにおいて検討した研究は、比較的少ないのが実状である。<BR><BR><B>3.研究の方法</B><BR><BR> 以上のような問題関心にもとづき、報告者は、大都市および郊外地域に居住する若年女性を対象として、質的調査を実施した。具体的な内容としては、つきまといや声かけなどのヒヤリハット事案への遭遇経験、犯罪不安の状況や背景、防犯情報への接触、防犯のために講じている対策や行動などについて尋ねるものであり、これを半構造化面接によって実施した。この安全・安心に関する質的調査は、犯罪不安と若年女性の社会生活との関係などについても、把握しようとする内容であった。<BR> 本報告では、この調査について予備的な分析を行い、第1節で提示した問いに関して若干の考察を加えることとしたい。<BR><BR><B>参考文献</B><BR><BR>Ferraro, Kenneth F., 1995. Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk, State Univ of New York Press.<BR>根岸千悠, 2011, 「「犯罪について考える」授業の開発 ―犯罪の実態と認識の乖離および環境犯罪学に着目して―」『授業実践開発研究』4, 37-43.<BR> 大西宏治, 2007, 「子どものための地域安全マップへの地理学からの貢献の可能性」『E-Journal GEO』2, 1, 25-33.<BR> 齊藤知範, 2011, 「犯罪学にもとづく子どもの被害防止」『ヒューマンインタフェース学会誌』13, 2, 123-126. <BR>若林芳樹, 2009, 「犯罪の地理学-研究の系譜と課題-」金沢大学文学部地理学教室編『自然・社会・ひと-地理学を学ぶ』古今書院, 281-298. <BR>吉田容子, 2006, 「地理学におけるジェンダー研究-空間に潜むジェンダー関係への着目-」『E-Journal GEO』1, 22-29. <BR>
1 0 0 0 OA ヒトはなぜ甘いものや脂肪分に富む食物を好むのか
- 著者
- 松村 康生
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.185-189, 1995-08-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 ダンダラテントウ鞘翅斑紋多型における地理的変異
1 0 0 0 OA 子宮頸がんワクチン接種後の副反応:わが国の現状
- 著者
- 池田 修一
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.303-314, 2018-08