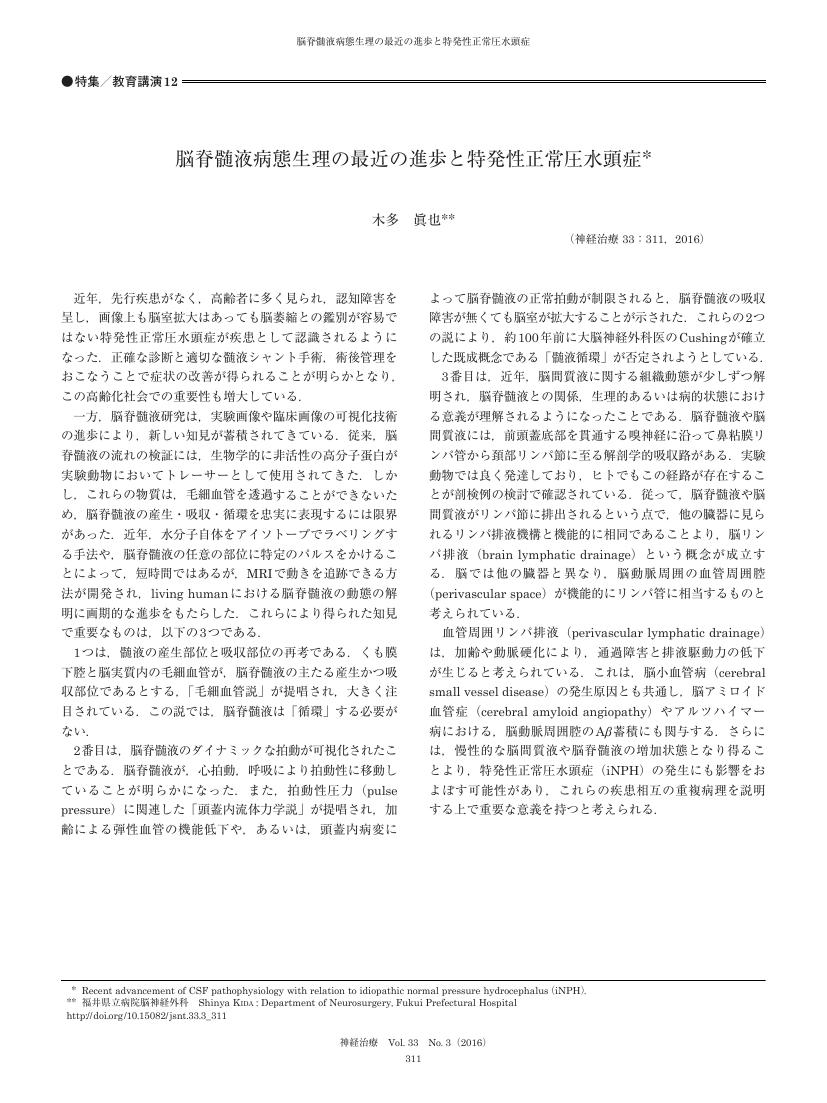1 0 0 0 OA 人血液凝固第XIII因子の血清学的研究
- 著者
- 増田 和茂
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血学会雑誌 (ISSN:05461448)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.219-229, 1980 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 32
A screening test method for human blood-clotting Factor XIII was devised in which agglutination of Factor XIII-coated latex particles by its specific antibody is specifically inhibited by the Factor XIII contained in the test material. The antigenicity is absent in human serum, but is well retained in its activation process.Decrease in Factor XIII antigenic level was observed in liver diseases, cancer and post-operative cases. The results in latex agglutination inhibition test were generally in agreement with the Factor XIII activity in MDC incorporation or fibrin clot lysis tests as well as with the results of rocket immunoelectrophoresis. An attempt was made to devise latex agglutination test by coating latex particles with IgG fraction isolated from specific anti-subunit A serum.
1 0 0 0 IR ある障害の重い子どもの言葉の世界の発見とその展開--三瓶はるなさんとの関わり合い
- 著者
- 柴田 保之
- 出版者
- 國學院大學人間開発学会
- 雑誌
- 國學院大學人間開発学研究 (ISSN:18849423)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.39-53, 2009
1 0 0 0 OA 地方改良運動と模範村・稲取村
1 0 0 0 OA 脳脊髄液病態生理の最近の進歩と特発性正常圧水頭症
- 著者
- 木多 眞也
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.311, 2016 (Released:2016-11-10)
1 0 0 0 スポーツ庁長官からの審議依頼の手交について
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.1_10, 2019
1 0 0 0 ファッション店が挑む 売り場のデジタル改革
- 著者
- 鈴木 慶太
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.1004, pp.48-51, 2019-11-28
独自開発したスマートフォンアプリを店舗の販売スタッフが活用し販売方法を変革しているのが、靴小売り最大手のエービーシー・マートだ。同社は2018年12月に、靴専門店「ABCマート」やスポーツシューズ専門店「ABCマートスポーツ」など全国約1000店舗の販売スタ…
1 0 0 0 OA 東芝砂町工場におけるタングステン精錬
- 著者
- 加瀬 薫
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.822, pp.915-918, 1956-12-25 (Released:2011-07-13)
The operation at Sunamachi plant was commenced from 1944, and the output of the metallic tungsten was 7 t per month. The plant was severely destroyed by bombing in March, 1945, but it was reconstructed soon after the war. The present production of metallic tungsten is about 3.5-4.5t per month.The raw material is wolframite and tungsten in it is leached as paratungstic ammonia. The leached solution is thickened to crystallize out the parasalt, and the salt is reduced by the two steps of heating with hydrogen gas. At first it is reduced to blue oxide (W4O11) at the temperature of 410-450°C and then is reduced to metallic state at more higher temperature .
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- D&M日経メカニカル
- 巻号頁・発行日
- no.584, pp.21-24, 2003-05
「うーん高過ぎる。とても買えない」。こうつぶやきながら出てくる人たち。鉄腕アトムの誕生日である2003年4月7日を目前に開催したパーソナルロボットの展示会「ROBODEX2003」会場での光景だ(図1,2)。いや,否定的な意味ではない。前回の「ROBODEX2002」まで,人間の手伝いができる水準のロボットは非売品,見るものであって買うものではなかった。
1 0 0 0 OA 技術者倫理教育はなぜ必要か
- 著者
- 石原 孝二
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.10, pp.626-629, 2004-10-01 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 3 3
- 著者
- 青木 美和 山本 淳一
- 出版者
- 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.106-117, 1997-03-20
- 被引用文献数
- 1 7
4名の発達障害生徒が、家庭生活スキル(学校の持ち物の準備、登校前の身じたく、帰宅後の手洗い・うがい、家庭学習)を写真カードを用いて自発的に遂行できることを目的とした。研究は全て対象生徒の家庭で実施された。対象生徒が写真カード冊子を1枚ずつめくりながら、行動連鎖を遂行してゆくことが標的とされた。ベースライン期において4名の対象生徒とも、家庭生活スキルの自発的反応の生起率は安定しなかった。家庭介入期において母親に写真カードの呈示方法と、一定時間経過後に適切な反応が出現しなかったら言語指示・身体的介助を与えることなどを教示し、それを家庭で毎日実施してもらった。その結果、家庭介入期において家庭生活スキルの自発的反応の生起率が上昇した。また、これらの介入では効果がみられなかった生徒には、写真カードや強化刺激の変更といった操作を行うことによって自発的反応が安定して生起するようになった。これらの結果について、家庭生活スキルの形成に及ぼす視覚的プロンプトと親指導の効果の点から考察した。
- 著者
- 野地 秩嘉
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.74-77, 2011-01-04
靴の小売りチェーン、ABCマートは現在、国内に572店舗ある。すべて直営で、2010年2月期の売上高は1135億円、純利益は144億円。売上高は前期比で16・6%増、純利益は30・5%も増えている。業績絶好調とは、同社のような企業を言うのだろう。ABCマートは他のチェーンに比べて売上高営業利益率がずば抜けて高い。ある同業他社が2%程度なのに、20%を超える数字となっている。
1 0 0 0 OA 自動車部品企業の生産現場能力に関する日韓比較
- 著者
- 銭 佑錫
- 雑誌
- 中京経営研究 = CHUKYO KEIEI KENKYU
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1・2, pp.19-32, 2012-03-15
1 0 0 0 OA ≪私≫という偶然をめぐって(春季公開講演会講演録)
- 著者
- 脇坂 真弥
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 = THE OTANI GAKUHO (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.1, pp.49-71, 2017-11-20
1 0 0 0 IR 第4の統語的複合動詞「終わる」 : 統語的複合動詞の分類再考
- 著者
- 大野 公裕
- 出版者
- 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院
- 雑誌
- メディア・コミュニケーション研究 (ISSN:18825303)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.95-110, 2018
- 著者
- 大谷 清伸 中川 敦寛 沼田 大樹 合田 圭介 荒船 龍彦 鷲尾 利克 古川 宗 Mark Richardson 早瀬 敏幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- バイオエンジニアリング講演会講演論文集 2014.26 (ISSN:24242829)
- 巻号頁・発行日
- pp.33-34, 2014-01-10 (Released:2017-06-19)
- 著者
- 杉本 弘幸
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌 = Journal of Ohara Institute for Social Research (ISSN:09129421)
- 巻号頁・発行日
- vol.740, pp.4-27, 2020-06-01
1 0 0 0 IR ヴィジュアル系ロックのグローバル化とその現状
- 著者
- 齋藤 宗昭
- 出版者
- 関西大学大学院社会学研究科院生協議会
- 雑誌
- 関西大学大学院人間科学 : 社会学・心理学研究 (ISSN:02892472)
- 巻号頁・発行日
- no.81, pp.19-38, 2014-09-30
- 著者
- ハーランド 泰代 植野 拓 渡辺 恵都子 青木 尚子 豊田 文俊 高畠 由隆 舟越 光彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.DbPI2348, 2011
【目的】心疾患を有する患者は、長期間運動を継続し、運動耐容能を維持・向上することが望ましく、運動を継続することが生命予後に関係するとされている。しかし、社会背景や身体的問題などの影響から、中には継続困難となり中断してしまう患者も経験する。そこで今回、外来通院による心臓リハビリテーション(以下、心リハ)の参加者を対象に、継続および非継続に関わる因子を調査および検討したため報告する。<BR>【方法】対象は、当院にて2008年1月から2009年11月の間に、外来通院型心リハプログラムに参加した心疾患患者63名(男性52名、女性11名、平均年齢69.9±10.4)である。疾患内訳は狭心症29名、心筋梗塞5名、慢性心不全12名、閉塞性動脈硬化症11名、開胸術後4名、大血管疾患2名である。公的医療保険給付の心リハ期限である150日以上の継続可能であった群を継続群、150日未満であった群を非継続群に分けて比較検討を行った。グループの内訳は、継続群30名(男性22名、女性8名)および非継続群33名(男性30名、女性3名)であり、検討内容は年齢、性別、疾患名、家庭環境(同居、独居)、冠危険因子数、費用負担、通院手段、通院距離、参加期間、NYHAの重症度分類の各値を診療録情報より調査し、後方視的に比較検討した。統計処理方法はX2検定、t検定を用いて統計学的検討を行い、危険率5%未満を有意差ありとした。さらに費用負担の有無に区分し、カプランマイヤー曲線により心リハ継続群の比較、およびコックス比例ハザードモデルにより費用負担有無による非継続群のハザード比を求めた。<BR>【説明と同意】対象者には研究の趣旨を説明し、同意を得た。<BR>【結果】今回の結果、継続群は30名(47.6%)であった。NYHAの分類のclassIIおよびclassIIIの継続群は有意に相関が高く、非継続群は低い結果となった(P<0.05)。性別では相関は認められなかったが、男性に比べて女性の継続率が高い傾向があった(P=0.1)。家族形態(同居ありおよび独居)の結果では、継続群と非継続群において有意な相関は認められなかった(P=0.7)。通院距離(遠方または近隣)においても有意な相関は見られなかったが、非継続群に比べて継続群は高い傾向にあり、近隣に比べて遠方の方が継続しやすい傾向であった(P=0.2)。また費用負担ありについても両群で相関は認められなかったが、継続群に対して非継続群は高い傾向があり、費用負担があると心リハ実施の継続率が低下しやすい傾向があった(P=0.1)。さらに、費用負担ありと非継続の年齢等を調整したハザード比では、1.67(95%CI 1.01-2.52)と有意に高く、自己負担があると継続が難しいという結果となった。<BR>【考察】重症度が低く、リスクファクターが少ない参加者が非継続の傾向が示唆された。おそらく重症度が低ければ自覚症状が少なく、意欲も低下するため継続困難であったのではないかと考えた。そのため、介入時から心リハの必要性や効果について十分な説明を行い、疾患を自己管理できるように教育などの介入を十分に行っていく必要がある。また重症度が高いと継続率は高い傾向があるが、急性増悪などを起こす可能性も高いため、増悪予防やセルフコントロールの徹底が必要である。社会的な面では、独居の方が継続率が高いと予想していたが、結果的に家族形態には違いは見られなかった。また通院距離では、近隣の対象者に比べて、遠方の対象者の方が継続しやすい結果となった。これは交通機関を利用して来院される方が多く、近隣の徒歩や自転車での通院に比べて、時間的スケジュールが確立されている事や運動負荷が少ない事などが上げられる。また加えて、医療費の自己負担がある対象者の方が、非継続の傾向が強い結果であった。このことにより、自己負担の有無が心リハの継続に影響を与える因子の一つになることが分かった。このような結果を踏まえて、心リハ開始時の情報収集では十分な社会的な特性を考慮し、必要な援助を行う必要があると考える。また心リハの通院期間や終了時期を明確に設定し、その後負担の少ない民間のスポーツジムや市町村の運動教室などへ繋げて、運動を継続するなどの配慮が必要である。また今後さらに症例を増やし、詳細な分析を行う必要がある。<BR>【理学療法学研究としての意義】患者の社会的な背景や重症度の違いにより、心リハ継続に影響を及ぼす一要因になることが示唆された。情報収集の際に社会的な背景に問題がある方に対しては、民間の施設への斡旋や連携を強化し、運動を継続していく必要がある。<BR>
- 著者
- 松本 和明
- 出版者
- 大阪歴史学会
- 雑誌
- ヒストリア (ISSN:04392787)
- 巻号頁・発行日
- no.215, pp.56-82, 2009-06