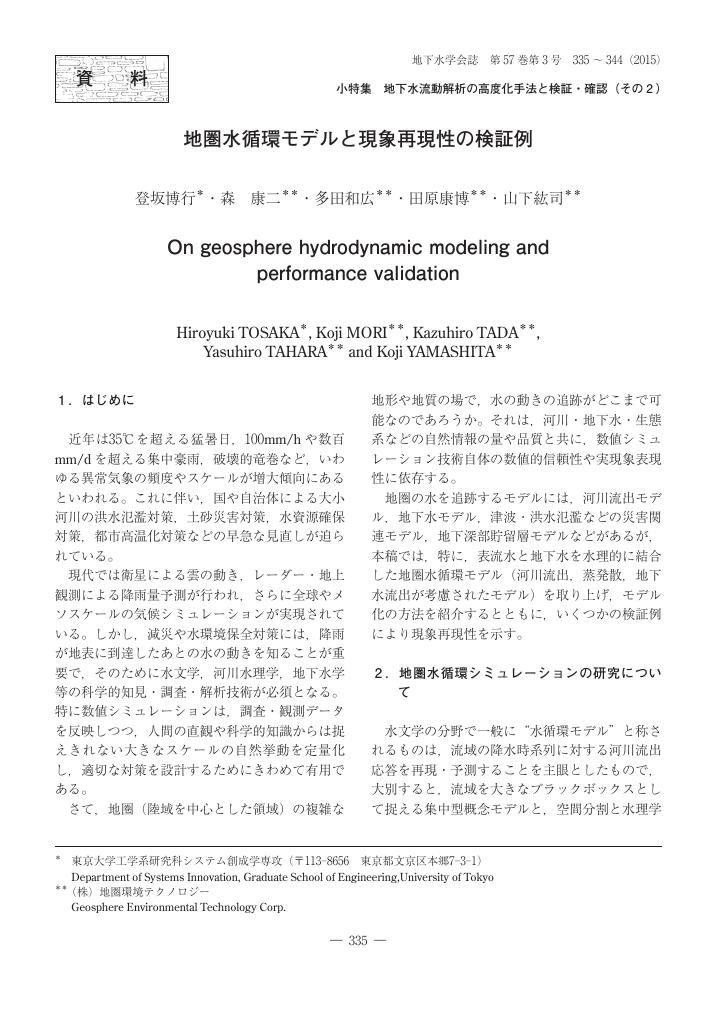- 著者
- 小田中 瞳 下地 伸司 竹生 寛恵 大嶌 理紗 菅谷 勉 藤澤 俊明 川浪 雅光
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.9-21, 2016 (Released:2016-02-29)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
目的 : 歯科治療に対して恐怖心を有している患者は多く, そのなかでも局所麻酔は全身的偶発症の発生頻度が高いため, 局所麻酔時の恐怖心や不安感を軽減させることは, 安心・安全な歯科治療を行うために重要である. そのための簡便な方法の一つとして音楽鎮静法があるが, 歯科領域ではまだ十分には検討されていない. 本研究の目的は, 健全な若年成人に対して局所麻酔を行った際の音楽鎮静法の効果について, 筆者らが開発したモニターシステムを用いて自律神経機能の変化によって評価することである. 対象と方法 : 22名 (26.5±1.9歳) の健全な若年成人ボランティアを対象とした. 同一被験者に対して, 音楽鎮静法を行わない非音楽鎮静群と音楽鎮静法を行う音楽鎮静群を設けた. 非音楽鎮静群と音楽鎮静群の順序は, 中央割付法でランダム化して決定した. 最初に, 質問票 (DAS) を用いて歯科治療に対する恐怖心を評価した. 次に非音楽鎮静群では, 麻酔前座位 (5分間), 麻酔前仰臥位 (5分間), 局所麻酔 (1/80,000エピネフリン添加塩酸リドカイン, 2分間), 麻酔後仰臥位 (5分間) を順に行った際の血圧・心拍数および自律神経機能について, 本モニターシステムを用いて評価した. 音楽鎮静群では音楽鎮静開始後に同様の評価を行った. また, 麻酔前後の不安感についてVASによる評価を行った. 自律神経機能は, 心電図のR-R間隔を高周波成分 (HF) と低周波成分 (LF) に周波数解析することで, 交感神経機能 (LF/HF) を評価した. 統計学的分析は, Friedman test, Wilcoxon signed-rank testを用いて行った (p<0.05). 結果 : 血圧, 心拍数およびVASは, 各段階でほとんど変化がなく, 有意な差は認められなかった. LF/HFは, 両群ともに局所麻酔薬注入時に麻酔前座位時よりも有意に低い値を示した. また, 麻酔前座位時および麻酔前仰臥位時に非音楽鎮静群よりも音楽鎮静群で有意に低い値を示した. 結論 : 健全な若年成人では, 音楽鎮静法を行った際は, 音楽鎮静法を行わなかった際と比較して局所麻酔前の座位時および仰臥位時において交感神経機能が低下する.
1 0 0 0 マイナーだけどおもしろいニゲラン分解酵素
- 著者
- 上地 敬子
- 出版者
- 公益社団法人 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.3, pp.135, 2021
1 0 0 0 茨城県から得られた熱帯・亜熱帯性ボラ科魚類4種の北限記録
- 著者
- 外山 太一郎 福地 伊芙映 山崎 和哉
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.54-65, 2021
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.308, pp.166-167, 2001-12
●特集1:「旨い」素材が蘇る●特集2:友人3人からのカジュアル同窓会を狙え!●特集3:ニューヨーク発 メニュートレンド●NEW OPEN:お台場の「小香港」6店、日之出食堂、大かまど飯寅福、黒毛和牛料理一頭や、Kunpuu●話題の震源地:楽雅、アジアンカフェ ホアン タム、あら田、蘭びっく●ザ・消費者:Voice Hunter/母娘ツーショットが増殖中!、データの玉手箱/不安を感じてい…
1 0 0 0 OA 細胞力学研究を振り返って
- 著者
- 佐藤 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4-5, pp.105-112, 2019-09-10 (Released:2019-12-19)
- 参考文献数
- 49
The author has continued to research on cytomechanics since 1983 when he visited Professor Nerem’s laboratory, University of Houston, Texas, USA as a visiting scholar. In those days the effects of shear stress on functions of endothelial cells (EC) are focused from the point of view of atherogenesis. In this review, progress of cytomechanics on EC is mainly summarized. First, the definition and the significance of cytomechanics are introduced. EC are located at the innermost layer of vascular wall and always exposed to three different external forces (i.e. shear stress, cyclic stretch and hydrostatic pressure). These mechanical forces affect the configuration and functions of EC and the cells finally adapt a physical environment. Cultured EC elongates and aligns to direction of flow and the degree of shape change depends on many factors such as animal and cell species, magnitude of shear stress, duration of stimulation, material of substrate and so on. Cytoskeletal structure is also changed prior to change of cell shape. Cyclic stretch induces cell elongation and the orientation transversely to the strain direction. Pressured EC exhibit multilayered structure and marked elongation and orientation with the random direction, together with development of centrally located, thick stress fibers. Mechanical forces stimulate signal transduction, gene regulation, protein synthesis and so on. The details of the time course of responses is summarized in the text. Recent progresses on cytomechanics are two topics as follows. One is an effect of substrate elasticity on differentiation of stem cells. Human mesenchymal stem cells are cultured on three different elastic substrate (i.e. soft, moderate and stiff matrices), and then respectively differentiated into neuron, muscle and bone. Another is discovery of mechanosensing molecule called mechanosensor. Living cells respond to external and internal forces, however, the sensing mechanism is not elucidated yet. Mechanosensors such as stretch-activated channel in cell membrane, p130Cas, α-catenin, talin at cell junctions and stress fiber itself are explained as the typical examples.
- 出版者
- 大日本海軍省水路局
- 巻号頁・発行日
- 1881
1 0 0 0 OA ドストエーフスキイ全集
- 出版者
- 新潮社
- 巻号頁・発行日
- vol.第8, 1920
1 0 0 0 OA 地圏水循環モデルと現象再現性の検証例
- 著者
- 登坂 博行 森 康二 多田 和広 田原 康博 山下 紘司
- 出版者
- 公益社団法人 日本地下水学会
- 雑誌
- 地下水学会誌 (ISSN:09134182)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.335-344, 2015-08-31 (Released:2015-10-30)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 北川 泰久
- 出版者
- 医歯薬出版
- 雑誌
- 医学のあゆみ (ISSN:00392359)
- 巻号頁・発行日
- vol.215, no.14, pp.1132-1136, 2005-12-31
1 0 0 0 群発頭痛の臨床現場の実際
- 著者
- 大和田 潔
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.11, pp.1134-1135, 2013
群発頭痛の治療は,診断するところからすべてが始まる.本講演では,群発頭痛と診断されるまでに苦労された患者さんの男女例を示した.治療においては,激しい群発頭痛の疼痛の制御の面から,予防薬の方が発作治療薬よりも重要でさえある.ステロイドは必須ではない.バルプロ酸,ガバペンチン,アミトリプチリン併用療法を紹介し,予防薬だけで発作が軽く終わった例も提示した.激しい発作にはスマトリプタン自己皮下注キットがもちいられるが,当クリニックのエキスパート看護師たちの主導による講習会も紹介した.群発頭痛の治療には,適切な診断と予防薬と発作治療薬の組み合わせが必須である.
1 0 0 0 頭痛: 診断と治療の進歩 II. 頭痛の疫学
- 著者
- 下村 登規夫 古和 久典 高橋 和郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.8-13, 1993
- 被引用文献数
- 3
頭痛は一般の外来診療で多く認められる訴えの一つである.しかし,日本においてはその実態はほとんど把握されていないが,日常診療において,頭痛の疫学的特徴を知っておくことは重要であると考えられる.片頭痛,緊張型頭痛は機能性頭痛の中でも頻度の高いものであり,片頭痛は若年から壮年にかけての女性に多く,緊張型頭痛は中年以後に多く認められる.群発頭痛は中年の男性に認められることが多い.片頭痛は40%以上に家族歴が認められているが,緊張型頭痛でも30%程度の家族歴があり,緊張型頭痛の発症に関してもある種の素因が関与している可能性が示唆される.
1 0 0 0 OA 私の考えるコーチング論:科学的コーチング実践をめざして
- 著者
- 結城 匡啓
- 出版者
- The Japan Journal of Coaching Studies
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.13-20, 2011-11-20 (Released:2019-09-02)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 白島 孝治
- 出版者
- 千葉県農業試験場
- 雑誌
- 千葉県農業試験場特別報告 (ISSN:03864278)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.1-49, 1972-10
1 0 0 0 銅欠乏症による種々の血球減少症を併発した透析患者の5例
- 著者
- 池田 弘 櫻間 教文 黒住 順子 大森 一慶 荒木 俊江 真鍋 康二 福島 正樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.115-122, 2019
- 被引用文献数
- 1
<p>銅欠乏症による種々の血球減少症を併発した透析患者5例を経験した. 男女比は1 : 4, 平均年齢は76歳, 平均透析歴は5.2年, 原疾患は糖尿病2例, 多発性囊胞腎1例, 腎硬化症1例, 不明1例, 併存症は誤嚥性肺炎3例, 脳神経障害2例, アクセス感染2例, 大腸癌術後の低栄養状態1例, 化膿性脊椎炎1例であった. 1例で経腸栄養, 4例で亜鉛製剤投与が行われていた. 診断時の血中銅, セルロプラスミンの平均濃度は26.6μg/dL, 12.6mg/dLで, 汎血球減少症2例, 貧血+血小板減少2例, 貧血のみ1例であった. 3例に硫酸銅, 1例に純ココア, 1例に銅サプリ投与を行い, 全例, 血球減少が改善した. 透析患者ではリン制限に伴う銅摂取量減少, 亜鉛補充による腸管での銅吸収抑制から健常人より銅欠乏をきたしやすいと考えられる. ESA抵抗性の貧血や複数系統にわたる血球減少症をみたときは, 銅欠乏も念頭において診療を行う必要があると考えられた.</p>
- 著者
- 本岡 里英子 山本 真士
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.10, pp.690-693, 2016
- 被引用文献数
- 6
<p>症例は39歳女性.1年前より下肢痙性,上下肢異常感覚が出現し,痙性による歩行障害が進行した.神経学的に両下肢痙性,両下肢深部感覚障害,四肢異常感覚を認めた.各種自己抗体,HTLV-1を含むウイルス抗体,腫瘍マーカー,ビタミンに異常を認めず,髄液細胞数,蛋白は正常で,OCB,MBPは陰性であった.頭部MRIは異常なく,頸胸髄MRIで,後索にT<sub>2</sub>WI高信号を認めた.血清銅,セルロプラスミンが低値であり,銅欠乏性ミエロパチーと診断した.生活歴を再聴取した結果,5年以上前から牡蠣を毎日15~20個摂取するという極端な食生活が判明し,亜鉛過剰摂取が原因と考えた.亜鉛過剰摂取による銅欠乏症の原因として本例のような食餌性は稀である.</p>
- 著者
- 湧上 聖 末永 英文 江頭 有朋 平 敏裕 渡嘉敷 崇 山崎 富浩 前原 愛和 上地 和美
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.304-308, 2000
- 被引用文献数
- 5
長期経腸栄養患者に銅欠乏が出現することが時々報告され, 貧血及び好中球減少症を伴うことがある. ある種の経腸栄養剤の銅含量が少ないことが原因で, 治療は硫酸銅や銅含量が多い経腸栄養剤で行われている. 今回, 食品である銅含量の多いココアを用いて銅欠乏の治療を行い, 銅の必要量を検討してみた. 当院に平成10年に入院していた経腸栄養患者86人を対象とした. 男性40人, 女性46人, 平均年齢69歳であった. 基礎疾患は脳卒中71人, 神経疾患5人, その他10人であった. CBC, 電解質, 腎・肝機能, 総蛋白, コレステロール, 血清銅 (正常値78~136μg/d<i>l</i>) を全症例に検査した. まず, 血清銅が20μg/d<i>l</i>以下の8症例に対して, ココアを一日30~45g (銅1.14~1.71mg), 血清銅が77μg/d<i>l</i>以下の31症例に対してはココアを一日10g (銅0.38mg) 経腸栄養剤に混注して1~2カ月間投与した. ココアの量が30~459の8症例の内, 2例が嘔吐と下痢で中断した. 残り6症例は血清銅が平均8.7±6.2から99.0±25.4μg/d<i>l</i>と有意に改善した. ココアの量が10gの31症例は血清銅が平均50.5±19.3から89.0±12.9μg/d<i>l</i>と有意に改善した. 銅欠乏に伴う貧血及び好中球減少も改善傾向がみられた. その後ココア10gで改善した23例についてココアを5g (銅0.19mg) に減量したところ, 平均98±36日で血清銅は90.7±10.4から100.6±17.1μg/d<i>l</i>へ有意に上昇した. これまで成人の一日銅必要量は1.28~2.5mgとされていたが, 今回の結果から銅欠乏の治療に関してはココア一日10g, 銅として0.6mg (ココアの銅含量0.38mgと栄養剤の平均銅含量0.22mg), 維持についてはココア5g, 銅として0.37mg (ココアの銅含量0.19mgと栄養剤の平均銅含量0.18mg) で十分だと示唆され, 経腸栄養剤開発における銅含量の参考になると思われる.