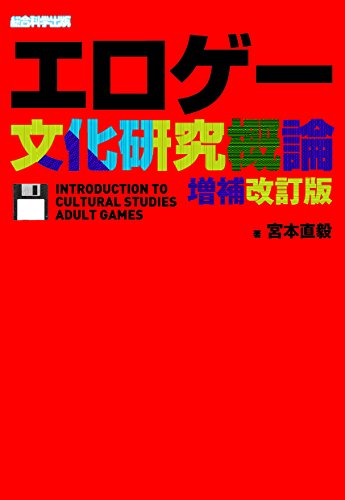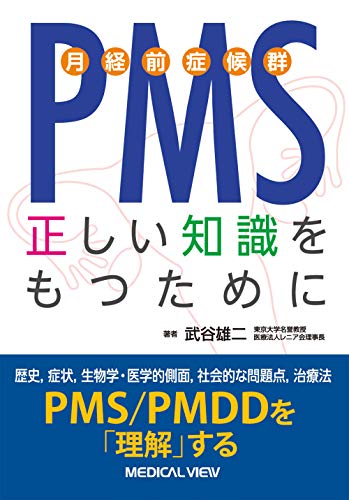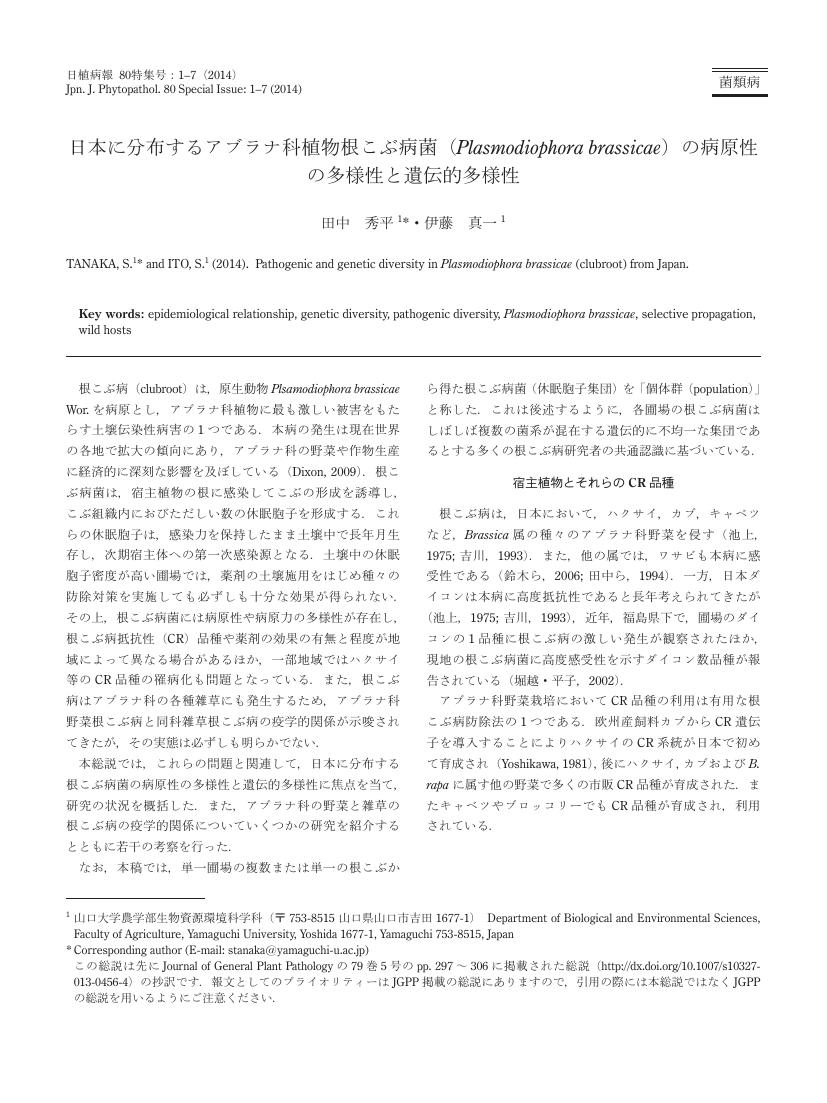- 著者
- 川原﨑 知洋
- 出版者
- 静岡大学教育学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 静岡大学教育実践総合センター紀要 (ISSN:13480707)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.179-186, 2021-03-31
1 0 0 0 IR 林達夫論 : 関東大震災への応答
1 0 0 0 OA おむつ形状の違いによる母子のおむつ交換負荷の差異
- 著者
- 菅 文美 丹下 明子 石川 浩樹 浦口 真喜 大平 英樹
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- pp.TJSKE-D-16-00092, (Released:2017-03-21)
- 参考文献数
- 15
When infants are in their crawling stage, both mothers and infants experience difficulties while changing diapers. We evaluated the effects of pull-up type diaper on physical and psychological burden in comparison to the nappy-type diaper. Twenty-four mother-infant dyads participated in this study. According to the behavioral observation analysis, negative behaviors of mothers and infants while changing pull-up type diapers were significantly lesser than while changing the nappy-type. Pull-up type diapers took mothers 30% lesser time to change, while allowing infants more physical movements than the nappy-type. A spectral analysis of infants' heart rate variability showed that low-high frequency ratio and the change in normalized unit percentage (Nu%) were significantly lower when pull-up type diapers were changed. Negative emotion-related behaviors of both mothers and infants significantly correlated with change in Nu% of infants. Lower physical and psychological burden while changing diapers was associated with pull-up type diapers.
1 0 0 0 OA 肩関節屈曲動作に伴う外腹斜筋の機能
- 著者
- 三浦 雄一郎 福島 秀晃 布谷 美樹 田中 伸幸 山本 栄里 鈴木 俊明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0634, 2005 (Released:2005-04-27)
【はじめに】我々はNgらによる腹筋群の解剖学的研究を参照とし、歩行時における個々の体幹筋の機能について報告してきた。内腹斜筋単独部位は立脚期に筋活動が増大し、骨盤の安定化に作用していることが示された。今回、上肢の運動に伴う体幹筋の機能に着目した。上肢の運動に伴う体幹筋の筋電図学的研究では、Hodgeらによると一側上肢を挙上運動させた時に反対側の腹横筋が三角筋の筋活動よりも先行して活動すると報告している。しかし、上肢挙上時における同側体幹筋の筋電図学的報告は少ない。そこで肩関節屈曲時の同側の体幹筋に着目し、その機能について検討したので報告する。【方 法】対象は健常者5名(男性3名、女性2名、平均年齢32±5歳)両側10肢とした。筋電計はマイオシステム(NORAXON社製)を用いた。運動課題は端座位での肩関節屈曲位保持とし、屈曲角度は下垂位、30°、60°、90°、120°、150°、180°とした。各屈曲肢位における上肢への負荷は体重の5%の重錘を持たせることとした。測定筋は運動側の三角筋前部線維、前鋸筋、腹直筋、外腹斜筋とした。サンプリングタイムは3秒間、測定回数は3回とし、平均値をもって個人のデータとした。下垂位における各筋の筋積分値を基準値とし、各角度における筋積分値相対値を求めた。各筋に対し角度間における一元配置の分散分析および多重比較検定を実施した。対象者には本研究の目的・方法を説明し、了解を得た。【結 果】三角筋の筋積分値相対値は肩関節屈曲120°まで徐々に増大し、それ以上では変化を認めなかった。前鋸筋の筋積分値相対値は屈曲角度増大に伴い漸増的に増大した。腹直筋の筋積分値相対値は屈曲角度に関係なく変化が認められなかった。外腹斜筋の筋積分値相対値は肩関節屈曲60°で増大し、屈曲角度60°以上で漸増的にが増大した。【考 察】 肩関節を屈曲させる際、上腕骨の運動に伴って肩甲骨の上方回旋運動が生ずる。前鋸筋は肩甲骨を上方回旋させる作用があり、肩甲骨の外転方向の柔軟性と前鋸筋の求心性収縮が必要となる。しかし、前鋸筋は起始部が第1肋骨から第8肋骨の前鋸筋粗面(肋骨の外側面)であることから前鋸筋のみ求心性収縮が生じた場合、肋骨外側面を肩甲骨内側縁にひきつける力が生ずる。結果として体幹の反対側への回旋運動が生ずることになる。また、座位姿勢は骨盤上で脊柱を介して胸郭がのっている状態であり、きわめて不安定な状態であることから、この反対側の体幹回旋は容易に生じやすいことが考えられる。運動側の外腹斜筋はこの体幹の反対側への回旋を制御し、体幹安定化に作用していることが推察される。
1 0 0 0 オガサワラヒゲヨトウの同定について
Dasythorax ogasawarae Matsumuraオガサワラヒゲヨトウは, 松村(1931, 日本昆虫大図鑑 : 786)によつて図説されたが模式標本は失われたらしく, その正体はかつて不明の蛾であつた.しかし, その図とほぼ一致する蛾が岩手県各地に少なからず産することは岡野磨瑳郎氏によつて発見され, 現在この蛾は上記の学名に同定されている.ただ一つの疑問は, Dasythorax ogasawaraeの原産地が, 小笠原島(父島)と記されていることであるが, 松村博士はしばしば"ogasawarae"という種名を岩手県でとれた蛾に命名しており, それらは標本提供者の名に因むものであつて, 地名を示すものではない.おそらく本種の場合も, その原産地は岩手県であつたものを, 松村博士が誤記したものと推定される.この蛾は, 実はDasythoraxではなく, 属Dasypoliaに属するもので, 中央アジアや蒙古などに産するD.lama Staudinger, 1896と同種であることが判つたので, ここに再記載し, 雄交尾器を図示した.ウスリーから1♀のみで記載されたD. fani Staudinger, 1892は, 上記の種と同種とされているが, 正確には明らかでない.日本における既知産地は, 岩手県(浄法寺, 沼宮内, 盛岡)と長野県(松本市中山, 山形村)の数力所のみで, 11, 12月に出現し, 3月にも1♀が得られている.
- 著者
- Gertraud Maskarinec Phyllis Raquinio Bruce S. Kristal Adrian A. Franke Steven D. Buchthal Thomas M. Ernst Kristine R. Monroe John A. Shepherd Yurii B. Shvetsov Loïc Le Marchand Unhee Lim
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20200538, (Released:2021-02-27)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 7
Aims. As the proportion of visceral (VAT) to subcutaneous adipose tissue (SAT) may contribute to type 2 diabetes (T2D) development, we examined this relation in a cross-sectional design within the Multiethnic Cohort that includes Japanese Americans known to have high VAT. The aim was to understand how ectopic fat accumulation differs by glycemic status across ethnic groups with disparate rates of obesity, T2D, and propensity to accumulate VAT.Methods. In 2013-16, 1,746 participants aged 69.2 (2.7) years from five ethnic groups completed questionnaires, blood collections, and whole-body DXA and abdominal MRI scans. Participants with self-reported T2D and/or medication were classified as T2D, those with fasting glucose >125 and 100-125 mg/dL as undiagnosed cases (UT2D) and prediabetes (PT2D), respectively. Using linear regression, we estimated adjusted means of adiposity measures by T2D status.Results. Overall, 315 (18%) participants were classified as T2D, 158 (9%) as UT2D, 518 (30%) as PT2D, and 755 (43%) as normoglycemic (NG) with significant ethnic differences (p<0.0001). In fully adjusted models, VAT, VAT/SAT, and percent liver fat increased significantly from NG, PT2D, UT2D, to T2D (p<0.001). Across ethnic groups, the VAT/SAT ratio was lowest for NG participants and highest for T2D cases. Positive trends were observed in all groups except African Americans, with highest VAT/SAT in Japanese Americans.Conclusions. These findings indicate that VAT plays an important role in T2D etiology, in particular among Japanese Americans with high levels of ectopic adipose tissue, which drives the development of T2D to a greater degree than in other ethnic groups.
1 0 0 0 OA 小児の病的近視
- 著者
- 五十嵐 多恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.7-12, 2018 (Released:2021-02-06)
- 参考文献数
- 15
近視は、遺伝要因と環境要因の相互作用が原因となり発症し進行する。近代化に伴う環境変化によって小児の近視患者が急増加する一方で、近視が強度で病的であるほどMendel遺伝疾患や稀な影響力の大きい遺伝子変異が関与する傾向が知られており、幼少期からの強度近視患者には、遺伝要因が近視の発症と進行の主因と考えられる患者の割合が高い。近年は学童近視に対しては近視進行予防治療が行われ、単一遺伝性の網膜疾患に対しては遺伝子治療が行われるようになった。今後、近視診療従事者は、個々の近視患者の発症と進行の原因を正しく理解し、適切な医療情報の提示を行うことが重要になると予測される。また病的近視患者の視機能を生涯に渡り良好に維持するためには、小児期の早期に病的患者を同定し、適切な合併症管理に結びつけることが重要である。眼底写真で視神経乳頭周囲のびまん性萎縮の形成を確認するとともに、脈絡膜厚をモニタリングすることや、広角OCTを用いて後部ぶどう腫の初期病変を同定することは、早期診断のための有用な指標と考えらえる。
- 著者
- 重茂 浩美 蒲生 秀典 科学技術・学術政策研究所科学技術予測センター
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 雑誌
- 調査資料 (Research Material)
- 巻号頁・発行日
- vol.303,
プラセボ効果は薬の効果に対する期待と過去に薬が効いたという条件付けが働くことに基づく効果であり、脳の認知機能を司る部位に関連がある。この部位は脳の前頭前野に位置し、近赤外線分光法(NIRS)を使用することでその活性度を非侵襲的に測定できる。また最近10年で、脳内化学伝達物質の遺伝子多型でプラセボレスポンダーとノンレスポンダーを区別するプラセボーム研究が台頭している。本研究では、脳内化学伝達物質の中でも5-hydroxitryptamine transporter ( 5-HTT ) 、Catechol-O-methyltransferase ( COMT )の遺伝子多型に注目し、プラセボ効果との関連性を検討することを目的としている。主観的指標として Stanford Sleepiness Scale( SSS )と Visual Analog Scale ( VAS )による眠気度調査を行い、客観的指標として近赤外分光法( NIRS )による脳血流量変化を測定した。また、5-HTT遺伝子多型 ( L/L、S/L、S/S ) とCOMT 遺伝子多型( Val/Val、Val/Met、Met/Met )を行なった。プラセボ投与前に比べ投与後で SSS と VAS ともに有意に眠気が改善された。NIRS では、認知を司る部位の脳血流量が投与後で有意に増加した。SSSとVASではVal/Met 群の方が Val/Val 群より大きな眠気改善傾向が見られた。またNIRS左脳での脳血流量は Met/Met 群が Val/Val 群と比較して増加傾向が見られた。有意差は見られないものの、Metアレルは Val アレルよりもプラセボ効果との強い関連性が示唆された。この結果は、78th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences(英国・Glasgow、2018年9月)にて学会発表した。
1 0 0 0 OA アクリルアミド(AAM)の毒性
- 著者
- 橋本 和夫
- 出版者
- 社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業医学 (ISSN:00471879)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.233-248, 1980-07-20 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 95
- 被引用文献数
- 2 11
Acute and chronic toxicities of acrylamide (AAM) are reviewed with special reference to its dose-response relationship from literature concerning the general toxicology and industrial hygiene. Although the total doses of AAM for producing chronic neuropathy in animals showed considerable variation among literature sources, estimated mean concentrations of the compound in the nervous tissues do not seem to differ very much at any stage of the poisoning. Reports of human poisoning, most of them being due to occupational exposure, are referred and symptoms of the poisoning are summarized from these cases.
1 0 0 0 エロゲー文化研究概論
- 著者
- 白木 善尚
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.160-163, 2013
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 種々のセンサを併用した集中度センシング法の検討
- 著者
- 濱谷 尚志 内山 彰 東野 輝夫
- 雑誌
- 研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) (ISSN:21888965)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015-ITS-63, no.10, pp.1-6, 2015-11-25
近年,スマートフォンや装着型センサの普及により,人々の活動量や心拍数といったライフスタイルに関する情報の収集が容易になりつつある.このような生体情報を含む様々なセンサー情報を利用すれば,人々の集中度を推定できる可能性があるが,未だ十分な検討は成されていない.そこで本研究では,スマートフォン内蔵センサや市販の装着型センサから得られる加速度,心拍数などを併用して人の集中度合いを推定する方式について検討を行った.本稿では学生を対象にデータの収集を行い,様々な集中行動におけるセンサデータの関係を分析した結果について報告する.
1 0 0 0 月経前症候群PMS正しい知識をもつために
1 0 0 0 OA 霊長類におけるホルモン分析の現在
- 著者
- 木下 こづえ
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.5-15, 2018-06-20 (Released:2018-08-22)
- 参考文献数
- 96
- 被引用文献数
- 4
The animal is connected to the external environment (e.g., social environment, habitat environment) via their brain, and the hormone plays an important role as its transmitter substance. In other words, when the external environment changes, hormones are secreted to adjust the internal environment in response. Therefore, hormone analysis is a useful tool that enables researchers to know animal's physiological state under various environments.Since the measurement of hormone concentration can be carried out at a relatively low cost and does not require advanced technique, it is applied to a wide research field. For example, many relations between behaviors and hormones were clarified, such as behaviors in estrus and rut, infant rearing, attacking behaviors, intra/inter-species communications, and response to the change of habitat environment. Recently noninvasive samples are often used for the hormone analysis in both captive and wild animals (e.g., urine, feces, and hair). However, when excrement is used as a sample, it should be noted that there is a species specificity in the excretion route of hormones and the time taken for excretion. Also, depending on hormones, it is necessary to thoroughly examine the sampling frequency according to the change of hormonal concentration. As Beach (1948) summarized, no behavior depends only on one type of hormone, and conversely, no hormone has only one kind of physiological function. Not one but multiple mechanisms are involved in the hormonal control of behavior. Therefore, focusing on multiple hormones and evaluating results from various aspects are also important keys to capturing their invisible physiological state accurately.
近年文化製品の国際展開は、国家戦略となるほどにまで活発化し、その拡大に示唆を与える研究は、社会から強く求められつつある。本研究では、日本におけるワインという成功事例を基に、文化製品の大衆品化メカニズムの解明を試みる。研究領域の細分化と専門化が進展する経営学において、本研究では複合領域的な視角を採用する。具体的には、製品開発論、生産管理論、サプライチェーンマネジメント、マーケティング、国際経営論、社会学(文化論)を活用して分析を行う。一方、最終目的に関しては、特定仮説の実証研究による短編論文が主流の中、「メカニズムの全体像を描く仮説群の提示」自体を目的に掲げ、著書による最終成果物公表を目指す。
有機レドックスポリマーの高速な電荷交換反応に基づく電荷輸送・貯蔵能を起点に、水素(プロトン)交換反応への拡張によって同じ原理で水素が輸送・貯蔵されることを明らかにする。具体的には、 (1) 水素(プロトン)交換反応の解明と(2) 高い質量密度で水素貯蔵可能な有機レドックスポリマーの創出により水素の輸送・貯蔵が可能な分子・ポリマーを開拓する。分子設計・水素発生条件などの工夫から(3) 高速な水素輸送を可能とする分子要件を解明、最大限に引き出すことで、(4) 斬新な水素輸送・貯蔵材料の創出へと繋げ、基礎化学の確立とエネルギー輸送・貯蔵材料への展開を狙う。