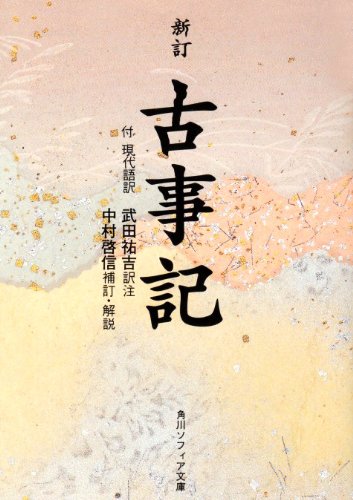1 0 0 0 OA Notes on Ulota in Japan
- 著者
- Tadashi Suzuki Zennoske Iwatsuki
- 出版者
- Hattori Botanical Laboratory
- 雑誌
- Hattoria (ISSN:21858241)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.99-106, 2013 (Released:2017-03-03)
Three species of Ulota, U. curvifolia (Wahlenb.) Lilj., U. megalospora Venturi, and U. morissonensis Horik. & Nog. are additions to the moss flora of Japan. Ulota longifolia Dixon & Sakurai, previously considered a synonym of U. crispa (Hedw.) Brid., is recognized as a good species.
1 0 0 0 OA ヨモギエキスの抗炎症効果の検討
- 著者
- 渡辺 真理奈 中田 功二 門司 和美 苗代 英一 牧野 武利
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.178-182, 1994-09-15 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
Recently, it was reported that the topical application of H2O extract of mugwort [Artemisia princeps P.] effectively prevents the itching and the inflammatory responses. However, its pharmacological mechanism is unclear. In order to clarify some of the active ingredients and their pharmacological effects, we examined in vitro and in vivo anti-inflammatory effects of the H2O extract and its fractionated parts of mugwort. The fractionation was carried out on a method of liquid-liquid partition with H2O-n-BuOH, and further reprecipitation on the concentrated H2O layer from H2O-EtOH. The fraction obtained as a precipitate significantly inhibited histamine release from rat peritoneal mast cells induced by compound 48/80. The topical application of this fraction also significantly inhibited (1) the hind paw edema induced by compound 48/80 and (2) the vascular permeability enhanced by the intradermal injection of histamine and serotonin. These results demonstrated that the anti-histamine components obtained in the fraction of water soluble and ethanol insoluble phase showed an anti-inflammatory effect.
1 0 0 0 OA Inflow and outflow loads of 484 daily-use chemicals in wastewater treatment plants across Japan
- 著者
- Kiwao KADOKAMI Takashi MIYAWAKI Katsumi IWABUCHI Sokichi TAKAGI Fumie ADACHI Haruka IIDA Kimiyo WATANABE Yuki KOSUGI Toshinari SUZUKI Shinichiro NAGAHORA Ruriko TAHARA Tomoaki ORIHARA Akifumi EGUCHI
- 出版者
- Japan Society for Environmental Chemistry
- 雑誌
- Environmental Monitoring and Contaminants Research (ISSN:24357685)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-16, 2021 (Released:2021-03-05)
- 参考文献数
- 58
- 被引用文献数
- 6
With the increasing number and volume of chemicals used in modern life, their adverse effects on human health and aquatic organisms have increased concerns as well. To formulate appropriate management plans, the amounts/volumes used and emitted of these chemicals must be regulated. However, no data are available on the use of most chemicals, particularly daily-use chemicals such as pharmaceuticals and personal care products (PPCPs). Herein, we tested eight activated sludge wastewater treatment plants (WWTPs) across Japan, each servicing populations of over 200,000, to investigate the emissions of 484 chemicals including 162 PPCPs. Twenty-four-hour composite samples were collected before and after the activated sludge component of treatment in each season of 2017. Targeted substances were solid-phase extracted and subsequently measured by LC-QTOF-MS-Sequential Window Acquisition of All Theoretical Fragment-Ion Spectra Acquisition. The mean number of the detected substances and their mean total concentrations in inflows (n=32) and outflows (n=32) were 87 and 92 and 108,517 and 31,537 ng L−1, respectively. Pharmaceuticals comprised 50% of the screened chemicals in the inflow. The median removal efficiency was 31.3%: 29.2% for pharmaceuticals and 20.2% for pesticides, which were similar to those in the literature. Cluster analysis showed that spatial differences among the WWTPs are larger than seasonal differences in the same WWTP. Regardless, we detected seasonal differences in the amounts of substances in the inflows: the amounts of sucralose, UV-filters, and insecticides were larger in summer than in winter, whereas those of ibuprofen and chlorpheniramine were larger in winter than in summer. The total inflow and outflow population equivalent loads estimated using wastewater volume, detected concentrations, and populations were 44.7 and 13.0 g 1,000 capita−1 d−1, respectively. The extrapolated total annual Japan-wide inflow and outflow loads were 2,079 and 671 tons y−1, respectively. Using the data obtained in this study, we identified 13 candidates of marker substances for estimating real-time population in a sewage treatment area and 22 candidates of marker substances for sewage contamination.
1 0 0 0 OA 奈良県生駒郡平城村是
- 出版者
- 奈良県生駒郡農会
- 巻号頁・発行日
- vol.明治41年9月調査, 1912
1 0 0 0 IR 「イナバノシロウサギ」異伝考
- 著者
- 石破 洋
- 出版者
- 島根県立大学短期大学部
- 雑誌
- 島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.1-11, 1996
1 0 0 0 IR 「八上比売」考
- 著者
- 石破 洋
- 出版者
- 島根県立大学短期大学部
- 雑誌
- 島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.1-18, 1997
1 0 0 0 IR 兎神考
- 著者
- 石破 洋
- 出版者
- 島根県立大学短期大学部
- 雑誌
- 島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.A1-A11, 1995-03-30
1 0 0 0 子どもに語る世界昔ばなし201話
1 0 0 0 OA 寫眞解説
- 著者
- 細野 善熈
- 出版者
- 日本蜘蛛学会
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.99-101, 1940-07-30 (Released:2008-12-19)
1 0 0 0 OA ローマ法学に鍛えられて : 中世教会法学のbona fidesについて
- 著者
- 小川 浩三
- 出版者
- 桐蔭法学会
- 雑誌
- 桐蔭法学 = Toin law review (ISSN:13413791)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1-37, 2009-09
1 0 0 0 OA 奈良県生駒郡片桐村是
- 出版者
- 奈良県生駒郡農会
- 巻号頁・発行日
- vol.明治42年1月調査, 1912
- 著者
- HELLSING G.
- 雑誌
- Scand. J. Dent. Res.
- 巻号頁・発行日
- vol.86, pp.486-494, 1978
- 被引用文献数
- 4 2
1 0 0 0 駐車場利用者の徒歩距離からみた駐車場の集約化の影響分析
- 著者
- 櫻井 和輝 小早川 悟 菊池 浩紀 田部井 優也
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.A_151-A_159, 2021-02-01 (Released:2021-02-20)
- 参考文献数
- 15
わが国では、高度経済成長を機にバブル経済期に至るまで駐車場不足が顕在化し、路上における違法駐車問題が発生した。この問題を解決するため、路外の駐車場整備のための制度が整えられ、次第に都市における普通乗用車のための駐車スペースは整備が進み、都心部では路外駐車施設の利用率が低下するようになった。そのため、駐車場の配置適正化や集約化の議論がされ始めたが、駐車場の集約化が駐車場利用者に与える影響については解明されていない。そこで本研究では、駐車場の利用者の駐車場選択行動を明らかにすることで、駐車場集約後の駐車場利用者の歩行距離に与える影響について分析を行った。その結果、各駐車場の利用者の利用実態を考慮して駐車場を組み合わせて集約することで利用者の徒歩距離に与える影響を小さくできることが明らかになった。
1 0 0 0 交通事故多発交差点における右折自動車と横断者の危険事象の詳細分析
- 著者
- 石田 翔平 小早川 悟 菊池 浩紀 田部井 優也
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.A_78-A_85, 2021-02-01 (Released:2021-02-20)
- 参考文献数
- 13
交通事故が多発する交差点では、事故データ等の分析に基づいて様々な交通事故対策が実施されている。しかし、対策の検討に用いられる交通事故データやヒヤリハットデータでは危険事象発生時の全ての状況を把握できるわけではない。例えば、交通事故やヒヤリ事象の発生時における信号現示の状況等は主観的なデータしか記録されない。また、交通事故は偶発的事象であるため、特定の交差点部の事故件数だけで定量的な分析を行うことは困難である。そこで本研究では、右折自動車と横断者の交通事故が多発する交差点を対象に、危険事象を定量的に抽出する交通コンフリクト指標の PET を用いて危険事象の発生状況を分析した。その結果、車群の中の右折車や単独横断の歩行者・自転車は危険性が高く、青開始から時間が経過するほど危険であることがわかった。
- 著者
- 佐藤 拓郎 小早川 悟 小柳 純也 菊池 浩紀 田部井 優也
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.A_142-A_150, 2021-02-01 (Released:2021-02-20)
- 参考文献数
- 15
自転車の車道通行促進のため車道上に自転車通行空間整備が進められている。しかし、自転車専用の空間は幅員が確保できない等の理由でネットワーク化が進んでいない。その中で、ニュータウンは計画的に道路が整備されたため、自転車専用空間のネットワーク化を図るための幅員確保が可能と考える。本研究は千葉ニュータウンを対象に道路幅員構成の調査を行った結果、現状において車道上の自転車専用通行帯として必要な幅員である1.5m以上の確保が可能な道路延長は3割程度であることを確認した。また、通行実態として、自転車利用者の多くが歩道通行し、属性によらず歩道を徐行しない傾向があることがわかった。さらに、構造改変を伴わず車線や側帯の修正のみの道路再配分を提案し、その結果7割の道路において自転車専用通行帯が確保できることを示した。
1 0 0 0 OA 食物由来水溶性抗酸化物質エルゴチオネインによる物体認識記憶の向上と海馬神経細胞の成熟促進
- 著者
- 中尾 駿介 中道 範隆 増尾 友佑 竹田 有花 松本 聡 鈴木 真 加藤 将夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学会年会要旨集 第92回日本薬理学会年会 (ISSN:24354953)
- 巻号頁・発行日
- pp.2-YIA-03, 2019 (Released:2020-03-20)
The aim of the present study was to examine enhancement of learning and memory by oral administration of ergothioneine (ERGO), which is a hydrophilic antioxidant highly contained in golden oyster mushrooms and other foods, and systemically absorbed by its specific transporter OCTN1/SLC22A4 in daily life, with an aim to clarify its possible role as a neurotropic compound. After oral administration of ERGO in normal mice, the novel object test revealed a longer exploration time for the novel object than for the familiar object. Similar result was also confirmed in mice ingested with ERGO-free diet. Dietary-derived ERGO is present in the body without the administration, but the ERGO administration led to modest (3~4 times) increase in its concentration in plasma and hippocampus. Exposure of cultured hippocampal neurons to ERGO elevated the expression of the synapse formation marker, synapsin I, and neurotrophin-3 and -5. The elevation of synapsin I was inhibited by tropomyosin receptor kinase inhibitor K252a. Thus, oral intake of ERGO may enhance object recognition memory, and this could occur at least partially through promotion of neuronal maturation in the hippocampus.
1 0 0 0 ドライフィルムの低スラッジ化技術
- 著者
- 小西 亨 高橋 亨
- 出版者
- 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
- 雑誌
- エレクトロニクス実装学術講演大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.71, 2002
ドライフィルム中に含まれる成分が現像機中に付着堆積する, いわゆるスラッジを低減すべく、従来の分散剤等を添加して改善する方法とは異なり, 汚染物を発生させないような材料を, 米国デュポン社と共同で開発をおこなった。本報ではその効果と実際のドライフィルムフォトレジスト製品への適用例を紹介する。スラッジの発生は本件を適用することにより80%以上低減することができた。
- 著者
- 大村 明雄 太田 陽子
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.313-327, 1992-12-30 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 8 4
琉球列島の喜界島・波照間島・与那国島および大東諸島の南・北両大東島に発達する更新世サンゴ礁段丘の地形層序と段丘構成物の生相および岩相解析, さらにサンゴ化石のウラン系列 (α-spectrometric 230Th/234U) 年代測定結果を総括した. それによって, 各島々で後期更新世における高海水準期 (酸素同位体ステージ7, ステージ5およびステージ3) の汀線を認定し, それらの現在の高度と Chappell and Shackleton (1986) による古海面変化との比較から, 例えば島の誕生時期・その後の隆起量および速度・傾動の方向などを含めた地殻変動史の点で, 5島それぞれが極めて個性的なことが明確になった.
1 0 0 0 OA 人工知能による医薬品副作用情報の自動抽出に関する動向
- 著者
- 荒牧 英治
- 出版者
- Japanese Society of Drug Informatics
- 雑誌
- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.N5-N7, 2018 (Released:2018-06-16)
- 参考文献数
- 3